ルッキズムに関連して――瞳と瞳が見つめ合うということ(4,095字)
はじめに
ルッキズムが話題だ。至るところで議論を巻き起こしている。
特に最近ではフェミニズムの文脈で取り沙汰されることが多く、様々な要素が絡み議論の焦点がぼやけ、皆が前提をすり合わせないまま異なるレイヤーで意見を述べ合い噛みつき合っていることも多い。そのような現象は昨今“炎上”と呼ばれ、そうなると「〇〇って炎上したよね」という事実だけがその後ひとり歩きし、なんとなく世間では「どうやら××って言うとダメらしい」「〇〇について言及する際は表現に注意しなきゃ」という空気が共有され、単なる言葉狩りに終始してしまって本質的な議論が喚起されないまま終わってしまう。私たちは、何度もそのような現場を見てきた。
「ルッキズム=外見至上主義による差別」と訳されることが多いが、実は外見を至上のものと捉えない人たちの間でも外見というものは(無意識的に)何かの判断軸になっていることが多く、知らず知らずのうちに差別は起こってしまっているのだろう。当事者が気づかないくらいのレベルで行われてしまっているからこそ、ルッキズムか否かを正確に判別することは難しい。
*
「見る」ことの難しさ
とは言え、ルッキズムの反動で外見が悪として捉えられ人の内面ばかりが重視されることも、避けなければならない。我々は外見による差別をなくしていく一方で、(逆説的かもしれないが)もっと人の外見を見ていってもよいのではないだろうか。「内面を見るべき」という声は良く聞くが、「外見を見るべき」という声は聞こえてこない。しかし、「見る」ということは相当に難しい行為である。一本の映画や一枚の絵画を見ることに対して多大なる喜びと苦労を見出し、それに人生を賭けてきた人がたくさんいることと同じように、「外見を見る」という行為にはそれ相応の経験とセンスが必要である。目を凝らしてみると、多くのことが見えてくる――造形美的な物差しでは分からない神秘的な魅力と、深まる謎。外見を丁寧に見ることを怠ったまま世の中が安易な内面至上主義に流れていくのは、それはそれで、視覚の敗北と言えないだろうか。
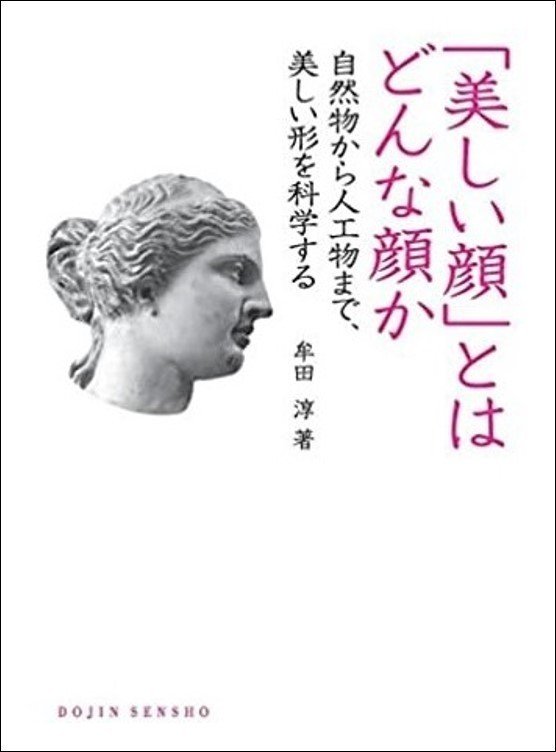
画像出典:amazonより
そもそも、人はまだ、外見について何も分かっていない。例えば、試しに『美しい顔とはどんな顔か』(弁田淳著、DOJIN選書)という書籍を開いてみよう。本書では190ページに渡り黄金比やシンメトリーなどの顔の美しさを決めるかもしれない要素が延々と分析された結果、最終的な結論として以下のように結ばれる。
人間の顔の美しさについては簡単ではないこともわかりました。たとえば左右対称な顔が美しいとは限りません。女性の顔の場合、「子供っぽくなくて可愛い」「子供っぽくなくて面長」など、より複雑な要素が加わっていることもわかりました。しかしながら美の要素は、本書で挙げた要素以外にも調べていくといろいろあるかもしれません。(192ページ)
著者の苦悩が垣間見える結びだが、実際のところ、外見について分かっていることなんてそんなものだろう。皆が薄々気付いていることだが、造形美として美しいとされる顔は必ずしも魅力的というわけではないし、多少バランスを逸脱した顔に魅力を感じてしまうことだってある。何でもない顔に対して、ある日たまたま映画やドラマを観て突然魅力を感じ始めることもある。メディアがその人を「かっこいい/かわいい」とラベリングしたことで、急に「かっこいい/かわいい」錯覚に陥ってしまうことだってある。そうなると「雰囲気美人こそが美人で雰囲気イケメンこそが真のイケメンである」ということすら成り立つのであって、そもそも真のイケメンと雰囲気イケメンなんていう関係性も常に逆転するものだ。
私たちは、何か分かったような気になってはいないだろうか。摩訶不思議な、捉えどころのない、顔というものに対して。
*
脱・映画化する視線

映画『ラ・ラ・ランド』(2016年/アメリカ/デイミアン・チャゼル監督)の切り返しショット。本シーンは、“瞳と瞳が見つめ合うこと”と“顔が変容すること”について、雄弁に語り得る材料を揃えている。(画像出典:https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli/rom-com-moments-that-are-equal-parts-sad-and-disturbing)
顔とは、本来ライブ感を持ち合わせたものである。
顔は、変容する。気候によって、疲労によって、精神状態によって、あらゆるコンディションによって。私たちがイメージするあの人の“顔”とは、私たちの間で、決して完全に一致することはない。だからこそ、顔はインタラクティブなものであると言える。愛する人の前で、愛する人の顔の前で、私の顔は愛おしい表情を見せる。困難にぶちあたった時、私の顔は気難しい表情を見せる。顔はつかみどころのないものだ。あなたが今日いつもと同じようにセットした髪型がなぜか昨日とは違うニュアンスを見せるように、ふと走らせた筆がなぜかいつになく整って見えるように、弾いたピアノの音が突然いつもとは異なる表情を纏っているように、それらと同様に顔はいつだって生命力を持って転がり続ける。
しかし私たちは、ライブ感を持ち合わせた転がり続ける顔に、向き合うことが少なくなってきている。今そこかしこで、「たった一側面でしかない顔」が、切り取られ評論されている。不特定多数に向けた顔が、静止画で、動画で、インターネットの海の中を漂っている。皆が公人になり、顔が公のものになっている。誰かの目の前でインタラクティブに変化・変容する顔ではない、ある一つの定められた顔に対して、多くの人がとやかく分析している。それはたった一つの、限られた顔の断片でしかない。多彩な表情を形作る、ほんの一ピース。だいたい、二次元に無理やり押し込められのっぺりと窮屈になってしまった、“顔のような”もの。
*
顔を見るということは、見つめ合うことである。
ライブ感を持った本当の顔を見るには、私たちは見つめ合わなければいけない。しかしこの時代に、瞳をそらさずに見つめ合うということは、重々しく難しい儀式となってきている。ZOOMで何時間会話しようと、私たちは画面の向こうの瞳と視線を交わすことができない。大人数の会議で、講義で、誰かと誰かが話しても視線の交錯は起こり得ず、人が人の顔をこっそりと、ぼんやりと、窃視しているだけである。そこに、人と人が照れと恥ずかしさと緊張感に耐えながら瞳をとらえ、見つめ合うという覚悟は介在していない。

だからこそ、ジャルジャルの作品『リモート面接でめっちゃふざける奴』(2020年5月1日YouTubeジャルジャル公式チャンネル公開)は画期的だった。「見る―見られる」関係の中で緊張感を生むコミュニケーションの代表とも言える面接だが、たとえその面接であっても、リモート環境下では決して視線が合うことはない。瞳を合わさずにその人となりを見なければならないという、そもそもその状況が「めっちゃふざけて」いる。(画像出典:YouTubeより)
それはつまり、脱・映画化する視線、と言ってもよいだろう。映画とは常に、盗み見ることと見つめ合うことによる緊張が生むドラマであった。ゆえに映画史とは、決して交わっていない視線をいかに交わっているかのように見せるか、という歴史である。カメラは見つめ合う二人の瞳をとらえることはできないからこそ、視線の交錯を演出する作法に映画的力点が置かれてきた。“視線の映画”は、近年も多く撮られている。例えば、トッド・ヘインズ監督『キャロル』(2016年/アメリカ)において、女性同士の秘められた愛の帰結としてドラマティックな視線の交錯が描かれたように。ロバート・ゼメキス監督『マリアンヌ』(2017年/アメリカ)において、ブラッド・ピットとマリオン・コティヤールが繰り返す窃視と視線劇によって大きなドラマが生まれたように。濱口竜介監督『寝ても覚めても』(2018年/日本)において、高低差とともに交わされる多くの視線が不穏な空気を醸し、唐突に開ける視界=ロングショットに大きな力を与えているように。
しかし最近の私たちはと言うと、視線をかわす機会を失い、ますます脱・映画化が進行している。私たちの世界にはもう、瞳と瞳が見つめ合うという、あの緊張感はない。

視線劇のお手本のような作品『キャロル』(画像出典:公式twitterより)

マリオン・コティヤールの窃視が効果的に配されている『マリアンヌ』(画像出典:https://www.pinterest.jp/pin/583497695453829356/より)

階段に代表される高低差のある視線劇から始まり、唐田えりかの不穏な視線が作品を支配する怪作『寝ても覚めても』(画像出典:https://www.huffingtonpost.jp/hotaka-sugimoto/movie-201808312_a_23509085/より)
*
終わりに
あなたが見ている顔は、物申そうとしている顔は、本当の顔ではない。本当の顔は、あなたが覚悟と照れと恥ずかしさを持って見つめた先にある、変化する表情にしかない。誰も分かりえない「顔」というものに対して目を凝らし動きをとらえた先にしか真実はないのであり、だからこそ見ることとはそれほどまでに難しく、そして尊いものである。
ルッキズムとは、見ることの難しさと尊さを人が失ってしまった先にある、脱・映画化とも言える状況での安易なランク付けが生む差別である。私たちはまず、オフラインの場で人と顔を突き合わせる際には覚悟を持って瞳を見つめ合わなければならず、目の前で変わり続ける表情を捉えながら、言いたいことがあるのならば瞳を逸らさないままにそっと告げるべきだろう。その言葉は例え批判であったとしても、差別というものに回収されることなく、人の心を大きな力で突き動かし瞳を輝かせることだろう。(まるで『ラ・ラ・ランド』でエマ・ストーンが見せた美しい瞳のように!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
