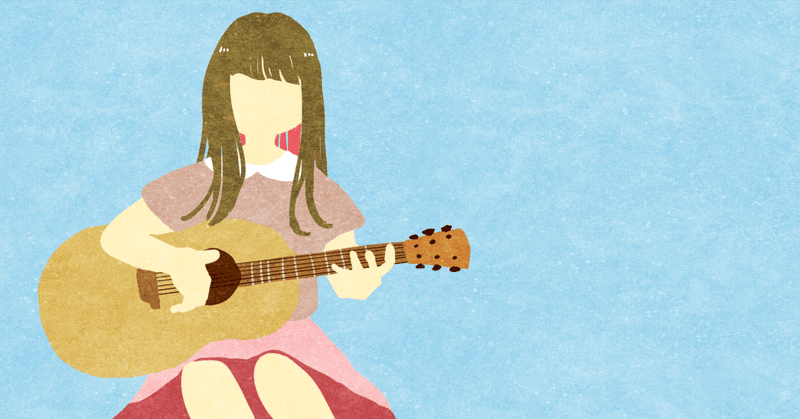
ちょっと爪を伸ばせば届いていたのかな
「今週末、東京行くことになったからさ、空いてたら飲みに行こうよ。」
その通知がスマホの上部にひょいと顔をのぞかせたのは、ちょうど12時ごろ。
僕が午前中の仕事をひと段落を終えて、春に向けて少しずつ暖かくなってきた街中を休憩がてら散歩している時だった。
3年ぶりに見るそのアイコンは、僕の心臓を雑巾で絞るかの如くキューっと締め付けた。
僕が大学時代にずっと片想いをしていた先輩だった。
彼女と僕は、同じ学科の先輩後輩の間柄。
たまたま僕の所属していた学部は、部室が用意されている珍しい学部だった。学年の垣根を超えた交流を活性化したいという狙いがあるらしかった。
彼女は僕の一つ上の学年の先輩。
お互い暇さえあれば部室に立ち寄った。勉強したり漫画を読んだり昼寝をしたり。
そんなこともあって、他の先輩よりも会話をする機会が多かった。
ある日、僕が顔を伏せて昼寝をしていたら「また寝てるやん〜」って言いながら僕の髪の毛を優しく引っ張ってきた。
「何してるんですか、思ってるより痛いんですよそれ。」
「将来ハゲるかもね笑」
イタズラっこのような笑顔でケラケラ笑う彼女の笑顔が、僕は好きだった。
いつだかの、いつも通りの飲み会終わり。
僕と彼女だけがたまたま帰り道が一緒になることがあった。
他のみんなは、朝まで飲むぞーなんて騒いでトリキに向かって行ったが、僕はたまたま次の日が部活の遠征で朝早かったのと、彼女も何かしらの予定があったみたいだったみたいで、そんな訳で二人で終電で帰ることになった。
お互い、だいぶ酔いが回っていて、彼女なんかは足取りがフラフラとしていた。
「電車くるまであと何分〜?」
「あと7分くらいですね。」
「7分もあるんや〜。もう一杯は飲めたな〜。」
「何いうてるんですか。すでにベロベロでしょ。」
たわいもない会話をしながら電車を待っていたその時、ふと肩になにかが乗っかった感覚がした。
横を一瞬だけ見ると、彼女の小さい頭が僕の肩にちょこんと乗っかっていた。
僕はなんだか見ちゃいけないものを見た気がしてすぐに目を逸らした。
心臓の鼓動がドクドクと大きく音を立てた。
僕はどうしたらいいかわからずに。
緊張していることを隠そうとして、全く気にしてないふりをした。
「先輩、今日何杯飲んだんですか?」
「わかんない〜。」
あの時の彼女のあの行動は、いったいどんな意図があったのだろう。
ただただ飲み過ぎて立つこともやっとだったためにただ支えとして使っただけだろうか。それとも彼女にはそれなりの好意があってのことだったのだろうか。
彼女が大学4年、僕が大学3年になったタイミングで僕らは接点がなくなった。
彼女は、研究室に配属され、研究をしながらその傍で就職活動も両立していたためとても忙しそうにしていた。
彼女は卒業と同時に大阪の大手企業に就職した。僕はその1年後、東京の会社に就職した。
お互いにそれまで一言もやりとりをせずに実に3年が立った今日、彼女から久々のメッセージが届いたのであった。
その通知を見て一番最初に思ったのは、何かあったのかな、ということ。
なんとなくではあるが、彼女が4年になったタイミングで部室に来なくなったその時から、もう彼女とちゃんと話す機会はないんだろうなと心のどこかでそう思っていたためだ。
彼女とは渋谷で飲むことになった。
道玄坂の路地裏にある個人経営の居酒屋。彼女がどうしてもそこがいいというので、そこに決めたのだ。
飲む前日の夜、僕は遠足の前日の小学生のようになかなか寝付くことができずにソワソワしていた。
息が臭いとまずいからなと意味もなく歯を3回磨いた。眉毛も入念に切り揃えて、鼻毛もしっかりとシェーバーで剃り上げた。万が一のことがあったら困るしな、なんていいながらこれでもかと言わんばかりに爪まで切って、深爪が10本できあがった。
当日、仕事を真っ先に終わらせて約束していた居酒屋へと向かった。
週末だから混んでいるかななんて心配していたが、その居酒屋だけは、東京からそこだけ一部切り取られたかのようにひっそりとしていて、店内ではくるりの『ばらの花』が流れていた。
3年ぶりに会った彼女は少しばかり大人びていた。
3年前はショートカットだった髪の毛は、今では胸にかかる程度まで伸びていた。薄手のニットを着ていて、ニットの上からうっすらと分かる体のラインに少しドキッとしてしまう。
東京の人混みの多さはどうしても好きになれない、と彼女はいった。
泊まるための大きなスーツケースを持って乗る山手線はもう勘弁してくれ、なんて言いながらケラケラ笑う彼女の笑顔は3年前と変わらず輝いていた。
久しぶりの先輩との会話。
彼女との会話のラリーの一つ一つが懐かしく、そして愛おしかった。
僕は先輩の笑顔をもっと見たくて、頑張ってボケては先輩を笑かす。僕のこの気持ちなんて、とっくに気づいているのだろうに、全く知らないふりをしてケラケラ笑う。
お互いに話さなかった期間が3年もあったとは到底思えないほどに時間は刻々と過ぎていった。まるで今まで止まっていた時計のネジを、再び巻き直したかのように。当たり前に。刻々と。
気づけばスマホの時計は22:54を示していた。
パーマを当てて髭を生やした気さくな店員が僕らの卓に来て、すみませんもう閉店ですので、と言い告げる。
お互いにただなんとなく流れるがままに店を出て、会話ひとつせずに少しだけ肌寒い渋谷をぶらぶらと歩く。まだもう少し、春は先のようだ。
人通りが多くなってきてスクランブル交差点付近にまで差し掛かる。このあとどうします?なんていう間もなく先に口を開いたのは彼女の方だった。
「このあと私、彼氏の家泊まるから。東京でも元気にがんばってな。」
そうだよな、と僕は思う。
こんな可愛い先輩に彼氏が居ないはずないのだもの。
そっか、彼氏に会うために東京に来たのね。そらそうだ。でなきゃ、仕事でもない限り東京には来ないよな。ましてや僕に会うなんてなおさら。
そうだよな、と僕は思う。
互いに会話をしなかった3年間はただ時計の針が止まっていたのではなかったのだ。互いが互いの人生において時が流れていて、たまたま今日それが交わっただけなのだ。そして明日からもまた当たり前のように時は流れていく。
たったそれだけのことなのだ。
また今度飲もうね、と彼女は言う。
僕はなんとなく、その"また今度"は来ない気がした。
ケラケラと笑いながら大きく手を振る彼女を見送る。僕も負けじと満面の笑顔で彼女に向かって大きく手を振る。
切り過ぎた深爪が、まだ春になりきらない冷気に触れて、少しだけ痛んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

