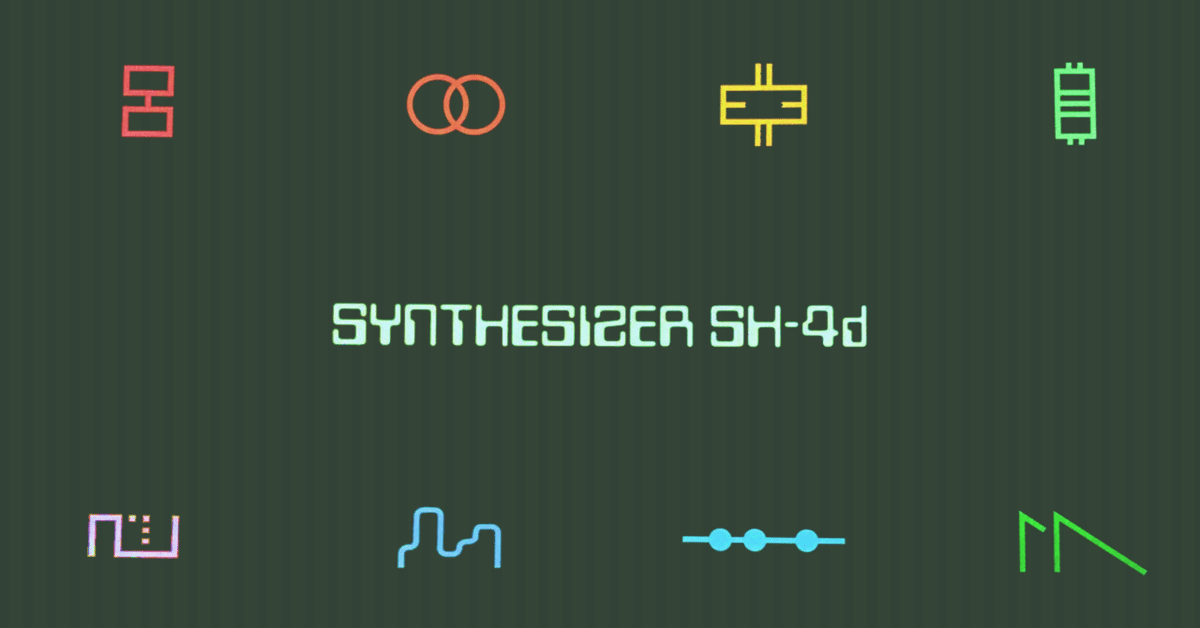
Roland SH-4d習得中。
Rolandから久々に登場した新しいシンセサイザーSH-4d。
伝統のSHの名を冠したばかりか、マルチティンバーシーケンサー、本体の傾きで音色やフレーズが変化するD-Motionなど最新機能も話題です。
非常に多機能で魅力あるマシンですが、実際に曲作りまでの工程を実践してみたので、レポートしてみます。
漢は黙ってスタンドアロン
SH-4dの機能を大きく分けると、11タイプあるオシレーターをノブやスライダーで加工できるシンセサイザーと、4つのシンセパート+ひとつのリズムパートで楽曲を作成できるシーケンサーのふたつ。
これらに加え、Zen-Core音源ゆずりの豊富なエフェクトやアルペジエイター、D-Motionといった機能が搭載されています。
あたかもAIRA以降ローランドが生み出した機能の集大成といった感もあります。
もちろんマルチティンバー音源としてDTMに組み込むこともできますが、テクノ系についてはエフェクトも含めて1台でほとんど完成してしまう上、フィジカルに操作できるインターフェースからスタンドアロンでの使用がおススメです。
ノブの感触もよく筺体も堅牢で、店頭で触った時よりずっしり感じました。
足の上に落とすとかなり痛そうです。
電池込みでだいたい2キロと、シンセサイザーとしては軽い方ですが、グループボックスとして見るとやや重め。
片手でホールドしての操作はお勧めしません。
足の上に落とすと(以下略)
時間が溶けるオシレーター選び
音源は、2019年以来Roland製品にデフォルトで搭載されてきたZen-Coreが使われているようで、最大4つの波形を重ねられます。
ただしSYNC、リングモジュレーションなど目的別にオシレータタイプをカスタマイズして独立させているために、互換性はないとのこと。
なんでもできそうだけど、あまりに複雑なZenology(プラグインシンセ)で音作りを躊躇した身からすると、非常にわかりやすい構成です。
おそらくModel Expansionから流用されたと思しき、ビンテージモデルのSH-101とJUNO-106。
同じように見える波形ですが、フィルターが共通なので、それぞれのニュアンスの違いがよくわかります。
本機ではSH-101もポリフォニックでも鳴らせますが、同じ矩形波でもJUNOはコードが綺麗に馴染むんですね。
単音での存在感はSHほど大きくありませんが、パッドにファンが多いのが改めてわかった次第です。
メインとなるオシレーターSH-4dとSH-3dは、波形間のファインも微調整でき、スラブなどの分厚いサウンドが作りやすいモデルです。
RINGやCROSS FMなど出たとこ勝負みたいなモデルもあり、オシレーター選びだけでも1時間溶けてしまいます。
ドローイングは特にヤバいです。
なおPCMモデルは波形が少ないことやウェーブテーブルモデルの充実ぶりを見るに「あえて90年代風に使ってみる」という選択肢だと思いました。
PCMは質量ともにZen-Core組の得意分野ですし、VAの操作性については圧倒的にSH-4d優勝なので、既存商品との差別化はしっかり図られている印象です。
フィルターが予想外に面白い
オシレーターはバリエーションも豊富ですが、フィルターは共通の仕様です。
レゾナンスなどを設定した後にオシレータータイプを変えていくと、逆に音源ごとの違いがよくわかります。
このフィルターが思っていた以上に面白いです。

特筆すべきは右下のDRIVEパラメーター。
これまでアンプの最終段で歪みを加える機能という印象でしたが、本機では珍しくフィルターに搭載されています。
レゾナンスとの併用は効果絶大で、高域ではピーキーな成分を抑え、低域では太くノイジーに変化させる効果があります。
たまに「オシレーター関係ないやん」というほどの威力を発揮します。
そして切り替え式のカットオフですが、これまでSH-5などにあったBPFについては「EQみたいなもの」との先入観からほとんど使ったことがありません。
それがDRIVEと組み合わせたら、繊細な加工が楽しめるようになりました。
残念ながら自己発振はしませんが、レゾナンスの存在感が強いので、オシレーター次第で口笛やザップ音もしっかり鳴らせます。
シーケンサーには慣れが必須?
ここからは、やや苦言というか愚痴モードになります。

ボタンが多数並ぶパネルの下半分は、本機の売りのひとつ、シーケンサーパートです。
入力方式は非常によくできています。
TR-808発祥の入力法としておなじみの”TR-REC”は、AIRA商品をはじめ近年の機種でも採用されていて、安心感抜群。
さらにシンセパートのステップ入力も、シーケンサーとキーボードのセクションが分かれているおかげで、MC-101より断然入力しやすくなりました。
しかし、まさにこのシーケンサー周りで苦戦したのです。
多機能ゆえSHIFTボタンとの組み合わせが多いのも本機の特徴ですが、パートとパターンの混同には注意が必要です。
パートを弄るつもりが、操作ミスでうっかり他のパターンを選択してしまうと、作成中のデータを失ってしまうのです。

僕は50代のシンセおじさんなので、操作ミスは加齢によるものかもしれませんが、本機には他にも多くのシンセおじさんも注目しているようなので、老人会的にはリスクを共有すべきかと。
データ消失を回避するには、パラメータを弄ったり何かを入力した後、必ずセーブ(WRITE)するのを心掛けることしかありません。
課題曲「CUE」YMO
もちろん操作の慣れも重要です。
そこで、実際に音を作りつつ、一連のシーケンス操作を習得することにしました。
新しい機材でいきなりオリジナル曲にトライするのはストレスが募ります。
こういう時は、過去に試したことある楽曲をコピーするのが一番です。
パート数から逆算して完コピできそうだったのは、YMOの名曲のひとつ「CUE」。
独特のドラムエフェクト、装飾を拝した楽器構成など、エフェクトやミックスの練習にもなります。
4年前にMC-101を買ったばかりの時にも、この曲にトライしたことがあります。
まあ完コピとは言いつつも、深夜に思いついてしまったのと、習得目的だったので1コーラスですけどね。
楽器の構成はドラムと4パート(パーカッション、ベース、コード、オブリガート)なので、音色込みで基本パターンをひとつ作り、それを弄っては別パターンへセーブしていく、という流れで作っていきました。
冒頭から最後まで流れる16音符のパーカッションは、リズムトラックで作ってもよかったんですが、フランジャーをかけたかったのでシンセパートを割きました。
後で「やっぱりリズムでもいいか」と考え直したんですけども、結局登場するのはベース、雅楽の笙みたいなコード音、ビブラートのかかった裏メロの3音なので全部収まりました。
他のパートを鳴らしながら直感的に音作りできるのもSH-4dの利点ですが、単体で原曲を真似て作り込んでも、他の音を重ねると印象が変わってしまうことがあり、シンセの奥深さと己の未熟さを味わってしまいました。
それとパターンモードでひとつ気になったのは、MFXのオンオフ設定が外れちゃうこと。
コピーの仕方に問題があるかもしれないので、今後研究します。
ということで、思い立ってから4時間でこうなりました。
SH-4dをPCに繋ぎ、Studio Oneを起動するとオーディオインターフェイスとして認識します。
LRのツーミックスを録音したついでに、「Piapro Studio」を立ち上げ、MEIKOさんにボーカルをとってもらいました。
ホントはゲートリバーブを通したスネアだけ別トラックに録音して、残響をノイズゲートで切りたかったんですけど、本体だけで作るのが目的だったのでやめました。
ともかく、シーケンス周りはなんとかマスターしたかなという感じです。
この手の機材をマスターするには鍛錬あるのみですので、今は音をいじりつつフルコーラスにトライしています。
デフォルト設定を弄る
ちなみに「CUE」を作る間に、本体の設定をひとつ変えてみました。

デフォルトでは電源を入れるとパターン01-01を読み込む設定です。
この01-01はSH-4dを代表するパターン"Do Synths Dream?”ですが、そのまま音作りを始めると、パート1のエフェクト設定を引き継ぐことになります。
ベース音だと残業系のセンドを全部オフったりするのが煩わしかったんですよね。
そこで、電源を入れた時に読み込むパターンを最後のパターン08-16に変更しました。
シンセパートはすべてイニシャルボイスに変え、リズムパートは[044 TR-909 Kit]にしてあります。
今はこの状態からエフェクトの設定まで含めてイチから作り、別のパターンに保存するというルーティンにしています。
いちいち前のデータをクリアする必要もないので、パターン作成も捗ります。
好みの問題もありますけど、ひとまずおススメ。
ラジオ局勤務の赤味噌原理主義者。シンセ 、テルミン 、特撮フィギュアなど、先入観たっぷりのバカ丸出しレビューを投下してます。
