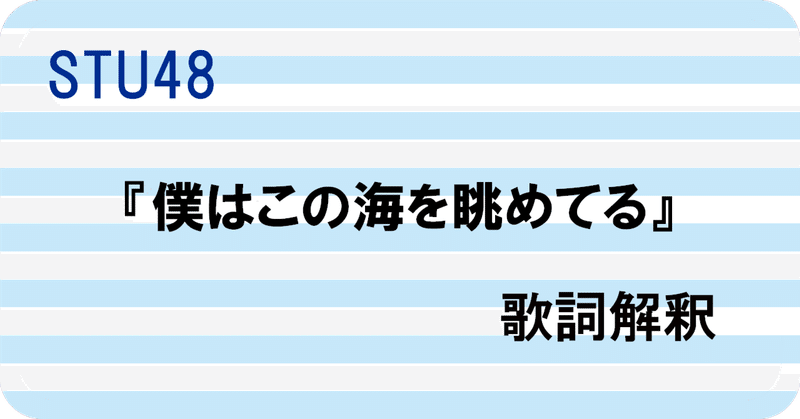
親愛なる海よ ~STU48『僕はこの海を眺めてる』~
STUは瀬戸内を拠点としたグループとして誕生しているだけに、その楽曲にも「海」を舞台としたものが多い。
直接「海」を舞台としていなくても、歌詞の中に何かしら「海」にまつわることが描かれていることが多いですよね。
6thシングル「独り言で語るくらいなら」のカップリング曲であるこの曲も、そういった「海」を歌った曲になります。
1番Aメロ
人間関係 得意な方じゃなくて
一人きりが一番楽だと思ってた
誰もいない冬の浜辺も
僕は寂しくなかった
街の中にどんなに人がいたって
喧騒が溢れてたとしても
語りかける誰かがいなきゃ
孤独を感じてしまう
人間を相手にすることほど厄介で面倒くさいことはありませんからねぇ……。
人見知りな人だったり、人付き合いが苦手な人にとっては、孤独ではあっても一人でいることのほうが、ずっと気持ちは楽でいられますよね。
この主人公にとって、生まれてからこの方、海(生まれ故郷の海)は身近な存在としてずっと親しんできた対象なのでしょう。
誰もいないその海に一人で佇んでいても、少しも寂しさを感じることはない。
海の広大さを目にし、心地よい波の音を耳にしていると、心が解放されて寂しさなど感じなくなるのでしょう。
喧騒の中で感じる孤独感は、誰もいないところに独りぼっちでいるときに感じる孤独感よりもはるかに強いかもしれません。
自分が喧騒の一部であるときには感じなくても、喧騒から切り離された自分に気づいたときに、その孤独を強く感じてしまう。
これだけ人がいるのに自分は誰ともつながっていないという不安と焦燥。
とりわけ、現代のようにネット環境が発達して、四六時中誰かとつながっているのが通常状態となっていると、こういった状況に身を置いたときに、余計に孤独を感じやすくなってしまうかもしれませんね。
そんな喧騒の中の孤独を感じることがあったとしても、この主人公には、一人でいても寂しさを感じることのないこの海があるわけです。
1番Bメロ
潮風に吹かれたくて
自転車を漕ぎ続けた
国道の坂を登れば
ホッとして来る
この主人公は、心の内に何かしら悩みなり葛藤なりを抱えているのでしょう。
それらを払拭するために、いつものあの海に向かって自転車を漕いで行く。
そして、坂を登りきった先に、その海が見えてくる。
その瞬間、ホッとして心が安らいでくるわけです。
1サビ
人生であと何回
この海を眺めるだろう?
防波堤に腰掛けて
いつも問いかけているよ
愛について 夢について
生きるとは何かと…
答えずに黙ってても
聞いてくれるんだ
友は波の音
太陽は少しずつ膨張していて、50億年後には地球を飲み込んでしまうと言われています。
それ以前に、5億年後には太陽の熱で地球は干からびてしまい、当然「海」もなくなってしまう。
とはいえ、5億年というのは途方もない年月なわけで、人の一生に比べれば永遠にも等しい長さですよね。
「人生であと何回 この海を眺めるだろう?」というフレーズは、そんな海の永遠性に対する人生の有限性と儚さを物語っているのではありませんかね。
愛について悩み、夢について語る。
生きるとはどういうことなのか、「生」とは何か、「死」とは何か……。
そんな、いかにも青年らしい問いかけを海に向かってするわけです。
もちろん、海はそれに対して答えるわけがなく、ただ静かにそこに存在しているだけ。
この問いかけは、本当は海に対して行っているのではなく、自分自身に対して行っているのでしょう。
この主人公は、自分のいろいろな思いを、心許せる親しい友のような存在であるこの海に向かって吐露しているわけです。
2番Aメロ
青春なんて 悩みばかり多くて
ふと気づけば 俯(うつむ)いて歩いてた
自分だけが最悪だと
自己嫌悪の日々だった
そう誰かに打ち明けられればいいけど
なぜだろう 恥ずかしかったんだ
こんな風に自信のない
心 曝(さら)け出すこと
青春時代の悩みは、一体何に悩んでいるのか当人にすらよくわからなかったりするものです。
後々になって、なんであんなことでいちいち悩んでいたのだろうかと思うこともありますよね。
とはいえ、強烈な自我が芽生えてくる思春期には、どうしても周囲と比較して自分を卑下したり自信を失ったりしてしまって、落ち込むことも多くなりがち。
「ふと気づけば 俯(うつむ)いて歩いてた」というのは、まさにそうした状態を言い表しているわけです。
そんな苦悩を誰かに打ち明ければ、気持ちも楽にはなるのだろうけれども、そんな素直な気持ちにはなれないところが、思春期の心理の繊細さというものなのでしょう。
自分の弱さ、情けなさ、カッコ悪さなんか、そう簡単には他人に見せられませんよね。
誰かに聞いてほしいという切実な思いとは裏腹に、「恥ずかしい」という思いや人前ではカッコつけていたいという虚栄心が邪魔して、なかなか曝け出せない。
2番Bメロ
生きるって息苦しいね
知らぬ間に無理してるんだ
どこかで両手伸ばして
深呼吸しようか
自分の弱さを覆い隠して、無理に虚勢を張って生きていくのは疲れますよね。
武士が重い鎧を纏っているような、ハリネズミが硬いハリを総毛立たせているような、そんな状態をずっと続けていたのでは息苦しくてたまらない。
ときには、どこかで鎧を脱ぎ捨て、ハリを収めて、思いっ切り手足を伸ばしてリラックスしたくなる。
そして、その「どこか」というのは、この主人公にとっては、心許せるあの海に他ならないわけです。
2サビ
大人になってしまっても
この海を眺めていたい
そう僕だけが知っている
一番 美しい場所で
恋をしたら その人だけ
連れて来てあげたい
思い出がキラキラと
ずっと反射する
僕の友たちよ
「大人になってしまっても」というフレーズには、まだ大人にはなりたくないという気持ちが滲み出ていますよね。
大人にはなりたくないけれども、いずれ間違いなく大人になってしまう。
そのときに今の気持ちも変わってしまうのではないかという予感があるのでしょう。
たとえそうだとしても、「この海を眺めていたい」とありますように、この海への特別な思いだけは変わることはないということを言いたいのでしょう。
自分にとって最も美しい場所、最も心安らぐ場所、そして恋人ができたら連れてきて思い出を作りたい場所。
この海は、この主人公にとってそういうかけがえのない場所なわけです。
面白いのは、「僕の友たちよ」というフレーズでしょうかね。
この曲の歌詞の中では、親しき友として海を擬人化してきましたけれども、てっきり一人の友かと思いきや、「友たち」ということで、海を大勢の友人たちと見なしているわけです。
この海に向かうということは、気を許せる大勢の友人たちの輪の中に入るということと同義となって、そりゃあまあ寂しさを感じることなどありませんよね。
Bメロ
太陽が昇る時も
太陽が沈む時も
僕らを見守るような
瀬戸内の海よ
この海は、四六時中僕らを見守ってくれているということでしょうかね。
ここでも「僕」ではなく「僕ら」となっているのですけれども、この海は、僕一人だけではなく多くの人々(もしかしたら人に限らないのかもしれませんが)のことを見守っているということで、いろいろな意味で、その広大さを表現しているのでしょう。
そして、その海ですけれども、ここまで一般名詞としての「海」と表されてきたのが、最後にきて「瀬戸内の海」という固有名詞で表されている。
STUの楽曲ですから、海とくれば、それは瀬戸内の海のことだろうと大抵の人はイメージするでしょうけれども、この歌詞では最後に、この「海」というのは「瀬戸内の海」のことであると明言しているわけです。
そう、この曲は「瀬戸内の海」への愛惜を歌っているのですよね。
そしてその愛惜を通じて、この主人公の心の風景を浮かび上がらせているわけです。
ラスサビは1サビの繰り返しとなっていて、最後にAメロ2行分が追加されていますね。
幸せとはどこに存在するのか
手を翳(かざ)せば 誰にも見えて来るよ
幸せというのは、いつでもどこにでもあるものではないでしょうか。
例えば……、
夕食にサバの塩焼きが出てきたとします。
脂が乗っていてとても美味しい。
ご飯が何杯でも進みそうだ。
最高だな、幸せだなと思う。
日常生活におけるいたってありきたりな食事の中で、ただサバが美味しいというだけのことではあるのですが、これを、腹が満たされたとだけ捉えるか、それとも幸せだなと感じ取れるかは、その人次第なのではありませんかね。
つまり、誰でも見ようと思えばどこにでも幸せは見いだせる。
この主人公は、瀬戸内の海を眺めながら、ふとそんなことを思ったのでしょう。
引用:秋元康 作詞, STU48 「僕はこの海を眺めてる」(2021年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
