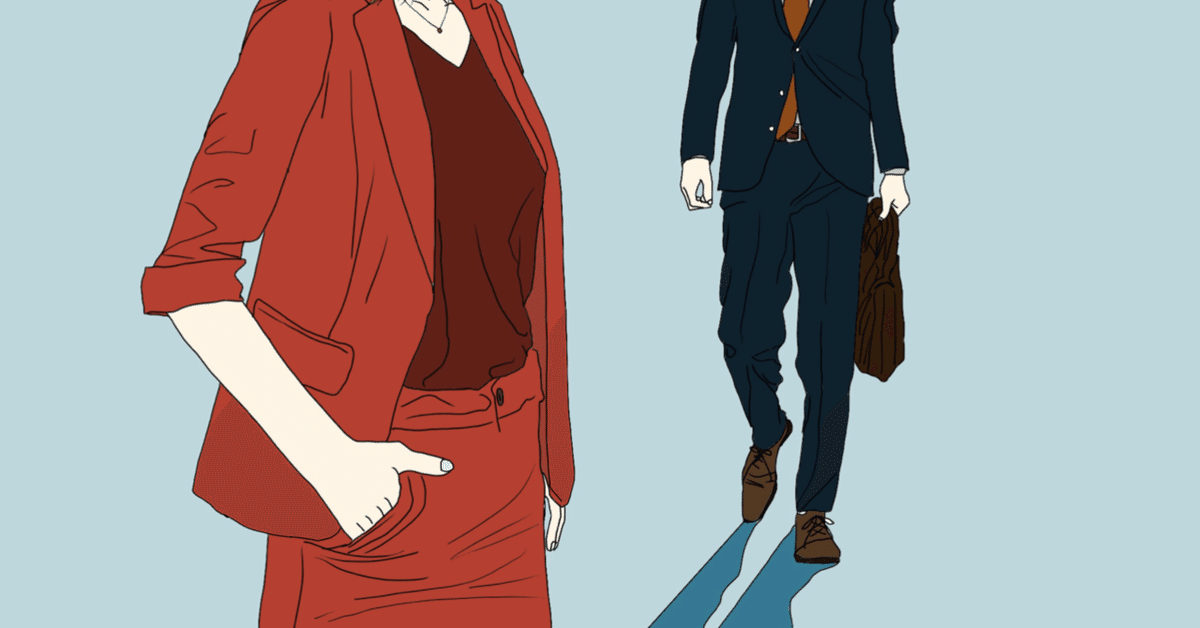
妄想日記「裸族のきみ」
八代奈々 30歳 会社員
「裸族って本当にこの世界のどこかにいるんだよね」
「裸族って、性癖の方?部族の方?」
「部族の方に決まってんでしょ。」
会社の休み時間、いつもの面々はそんな話題で盛り上がっている。
対するわたしは、不意に降ってきた痛点にどきりとする。
集中がうまくできず、フォークを落としてしまった。
「もう、奈々。なに動揺してんの。」
みんなが、優しく笑ってくれる。そのことに、安堵した。
わたしは裸族を知っている。しかも、部族でも性癖でもない方の。
真一とは、大学時代のサークルで出会った。
どこにでもいる大学1年生のように、どこか落ち着かない興奮した雰囲気に任せてわたしたちは急速に距離を縮めた。とはいえ、奴と恋愛をしたことはないし、間違いが起きたこともない。簡単に友達と言い切れないが、恋人ではないとは言い切れる。そういう、法で捌けない関係は誰しも経験があるはずだ。そう言ったわけで、わたし達は時に「友達」であり、時に「兄妹」という他人にとってはどうでもいいことを注意深く使い分けてきた。
奴が裸族だということを知るのにそう時間はかからなかった。
飲み会で終電を逃した夜、彼の家に初めて足を踏み入れた。室内は、さっぱりと整理されており、その19歳の男子に相応しくない無機質さに内心不気味だなと思った。
「綺麗にしてるんだね。」
「好きなんだよね、こういうの。全部、無印だけど。」
「一人暮らし、はじめてよね?」
「うーん。結構ずっとそんな感じ。」
さらりと奴が過去を匂わせて、わたしはどうしたらいいのかわからなくて無視をした。
「もう一杯飲みたい。」
「いいね。コークハイ作るよ。」
そう言ってから奴は「座ってて」とワンルームに置かれたビーズクッションの方を指差し、台所でお酒を作り始める。ビーズクッションがひとつと、ローテーブルがひとつ、その奥にネイビーのシーツがかけられたシングルベッド。ぐるりと見渡してもそれしかない。埃ひとつないフローリングにはラグも敷かれていなかった。誰もが息を潜めたくなるような静けさの中、奴が氷をグラスに落とす音だけが響く。
「そういえばさ」
沈黙に耐えられなくなったわたしが口を開く。
「真一って、誰かこの部屋連れてきたことある?」
奴が振り返って言う。
「なんで?」
「サークルの子達が言ってた。お願いしても入れてくんないって。」
「相手の家に行く方が楽だからなあ。」
「わたしはいいんだ?」
何を言っているんだ、と思った。しかし、出てしまった言葉はどうしようもない。照れ隠しに「てへ」なんて舌を出して笑ってみる。いや、もっと救いようがない。そんな風に、どんどんわたしがアタフタしていく様子を見て、奴が「ふ」と笑った。
「奈々はね。なんか、大丈夫な気がしたんだ。」
「大丈夫、ってなに。」
「僕が、裸族だって知っても大丈夫だってね。」
口の中で「ら・ぞ・く」と転がしてみた。全く意味がわからない。
「ほら、できたよ。濃いめ。」
奴は、やけにおしゃれなグラスに作ったコークハイを持って、わたしの方へ一歩一歩近づいてくる。わたしの本能が「危険!」と叫ぶ。だって奴の姿は、ゴジラの如く強大で(あのテーマ曲が聞こえていた気がする)どこかの狂気を孕んだ教祖のように(その両手に持っているグラスがキャンドルに見えた気がする)わたしの目には映ったからだ。
しかしながら、わたしの本能の叫びは杞憂に終わる。
細見真一 19歳。ヒッピー思考な両親は、定職につかず6つ離れた兄と共に奴は幼少期、日本中を移動しながら育つ。しかし、教師家系だった父方の両親は「子供の教育に悪影響だ」と、彼らの生き方を受け入れなかった。そうして、奴が10歳の時に兄と共に父方の両親の元に引き取られ暮らし始めるも、もはや普通の生活に適応できず兄と共に14歳でその家を脱出。以降、働く兄に変わって家事をこなしながら二人で暮らしてきた。
「別に、両親の生き方を否定するわけではないんだけどね。」
「楽しいことも多かったし。」
「でも、困ったのはやっぱ目立つよね。そう言う親を持つと。」
「俺、6歳まで服を着れなくて。いや、着せてもらえなかったんじゃなくて「着れなかった」んだ。あの肌に、布が当たる感じ。ゾワゾワする。」
「親も変だし、俺も変だったらこの世界で生き抜けない。そう思って、毎日必死に服を着る練習をしたよ。まあ、結局靴下と下着は今でも身につけられないんだけど。」
なんでもないことのようにそう話す奴に、わたしは相槌を打っていた。奴は、ずっと天上のどこかを見つめながら話し続ける。
「もしかしたら、俺にはヒッピーな両親の血と共に裸族の血も混じっているのかもしれない。そんなはずはないのだけれど。そんな妄想みたいな仮説は、一人で考えれば考えるほど膨らんで、より「隠さなくちゃ」と思わされる。「隠そう」と思えば思うほど、「言って楽になりたい」と思う。」
「で、奈々はなんか出会った時から俺と同じ「隠したい、でも言ってしまいたい」ってことがあるような気がして、自分のこの秘密を話しても大丈夫かもって思ったんだ。」
そこまで話してようやく、奴はわたしの目を見た。
わたしは、「誘われている」と思った。強烈な誘惑。喉が湿り始めていた。
「わたしは‥‥」
18時、仕事が終わった。オフィスビルから、大差ない服を身につけた人間達が一斉に溢れ出ていく。わたしは、帰り支度を終わらせてからその様子を32階のオフィスから見下ろしていた。この人間の中にどれだけの「秘密」が隠されているのだろう。そんなことを思うと嬉しくなる。しかし、「秘密」はたった一人に開示した方が欲情は強いまま保たれるのだ。わたしはスマホを取り出し、奴に電話をする。
「もしもし。」
「うん。」
「今日、これから家に行っていい?」
「いいよ。なんか作る?」
「ありがとう。掴みやすいものがいい。」
「当たり前でしょ。奈々が食べるんだから。」
19時半。広さだけが増えた殺風景な奴のリビングには、ダイニングテーブルと二つの椅子だけが置かれている。わたし達の好きなサイケデリック・ロックを流し、奴とわたしは食事を取る。全裸の奴が器用にフォークとナイフを使いローストチキンを頬張っている。その向かいには手づかみでローストチキンを頬張るわたしがいる。わたしは、人間らしく食べるために必要な道具が握れないのだ。しかし、奴の前では無理をして偽造しなくても良い。服が着れなくても、フォークが握れなくてもいい。今夜もわたしは奴の前で、その存在を許される。

あとがき
わたしは、できないことが比較的多い子供だったように思います。席に長時間座れないとか、奇声を発することがやめられないとか。しかし、誰しもに「頑張らないとできなかったこと」というものは存在します。そのままだと、社会の常識に溶け込めないから努力して、やがて「できなかったこと」を克服しようとするのです。そう考えれば、わたしのできなかったことは特に特別なことではありません。しかし、意識して矯正を重ねた分たまにその記憶は強く思い出されます。そして、そう言う時は逆に「開示してしまいたい」と言う蜜が出てきて、誰かを無意識的に誘っているような気がします。それは、結局のところ「ありのままを受け入れてもらいたい」という誰しもが願う祈りのようなものなのかもしれません。
