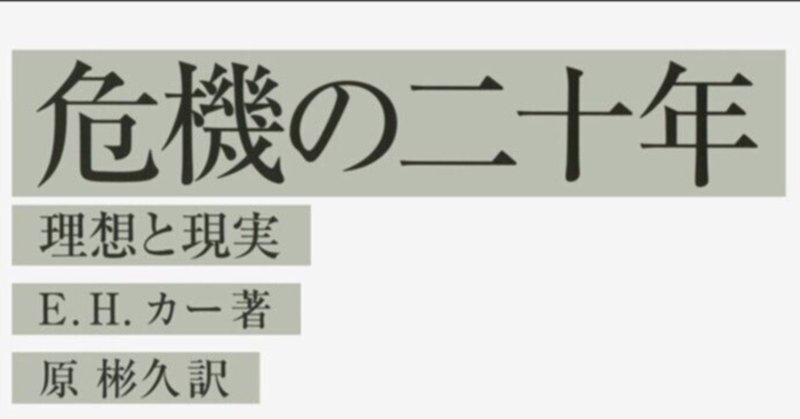
【巨人の肩の上から #1】 -終わることのない論争
強制と良心、憎悪と善意、自己主張と自己抑制はあらゆる政治社会に厳としてある。国家は人間性のこれら相反する二つの側面から形成されている。ユートピアとリアリティ、理想と制度、道義と権力は最初から国家のなかに分かち難く溶け合っている。(…)
もしこのことが正しいのならば、われわれは一つの重要な結論を引き出すことができる。すなわち、政治から自己主張を排除すること、そして道義だけを基礎にして政治体制をつくることは可能だと夢みるユートピアンは、愛他主義が幻想であり政治行動すべてが利己主義に基づいていると信じる信ずるリアリストと全く同様、見当違いをしているのである。
完全に抽象化してしまえば、政治とは常に、変革を求める理想主義(ユートピアニズム)と現状を重視する現実主義(リアリズム)の抗争という営みである。これはもはやあらゆる「政治」について言えることだが、こと国際関係においては、この両者の対立と確執は遥か昔、現在あるような「主権国家」という概念がヨーロッパに生まれた時から、フランス革命、ナポレオン戦争、第一次世界大戦、国際連盟の挫折と第二次世界大戦、国際連合の誕生、そして冷戦を経て今に至るまで、理論においても実践においても、常に最前線の問題として陰に陽に取り組まれてきた。
『危機の二十年』は今から100年近く前の1939年、歴史学者のE.H.カーによって生み出された著作であり、現在ひとつの学問分野として盛んに研究がなされている「国際政治学」の学問的出発点となったとも言われる古典だ。題名になっている「危機の二十年(THE TWENTY YEARS' CRISIS)」とは第一次世界大戦が終結した1919年から本著が発表された1939年までの20年間(いわゆる第一次世界大戦と第二次世界大戦のあいだの「戦間期」) をさし、この本はこの時期の「英語圏諸国の国際政治に関するほとんどあらゆる思考 -学問的思考および一般的思考の両方なのだが- につきまとう明白かつ危険な欠陥を打ち破る」という目的をもって書かれている。その「明白かつ危険な欠陥」とは、国際政治における権力の要素、すなわち現実主義的な要素がほとんど完全に無視されるということであり、人間の良心と世界共通の道義に基づいて一つの秩序を構築することができるはずだと信じきることであった。
ファシズムという怪物がヨーロッパに姿を現し、第二次世界大戦の足音が聞こえてくる中で、高尚な理念と変革を掲げていたはずの当時の国際連盟は「平和」のための貢献をほとんど何もなし得なかった。「危機の二十年」とは、カーに言わせれば、「道義の観点からはいい表すことのできない権力の問題」から目が逸らされ続けた20年間のことであった。

『危機の二十年』と『歴史とは何か』というふたつのあまりにも有名な著作がイメージとして先行しているためあまり知られていないが、歴史家としてのE.H.カーは主にロシア革命の歴史を研究していた人物だった。そんな彼がもし今生きていたら、どのようなことを考えるだろうか。ロシア帝国から革命によってソ連となり、ソ連の解体によって現在のロシア連邦となり…と、ロシアは不思議な歴史を辿った国である(不思議ではない歴史を持った国・地域など世界に存在しないかもしれないが)。2014年のクリミア危機は今となってはひとつの「はじまり」であったし、世界的なパンデミックもひとつの「はじまり」であったし、今起こっていることももしかするとひとつの「はじまり」なのかもしれない。ともかく、ほぼ丁度1世紀ぶりに、「危機」が訪れているのである。
ただし、もし現在の世界をカーが分析しようとした当時と並べて「危機の時代」と呼ぶのならば、その内実はかなり戦間期のそれとは異なるだろう。1939年、カーは国際政治の議論におけるユートピアニズムへの傾倒、リアリズム的側面への盲目を警告した。第二次世界大戦、冷戦を経て、人々の意識はどう変わっただろうか。私の目にはむしろ、当時とは逆、リアリズムへの傾倒とユートピアニズムの軽視、あるいは蔑視が人々の心の中に蔓延っているように映ることがある。
話が広がり過ぎてしまうのを防ぐためこの話題にはあまり踏み込まないが、私はカーは必ずしも「リアリズムの重要性」のみを『危機の二十年』のなかで説こうとしたわけではないと思っている。引用した部分にあるように、彼が伝えたかったことは、理想と現実、どうであるべきかについての議論とどうであるかについての議論は「分かち難く溶け合っている」ということだ。両者はまさに天秤のように揺れ、決してつり合うことはないながらも常に均衡を求めている。だからこそ、政治という空間において「不要な意見」「聞く価値のない意見」は存在しない。逆説的だが、絵空事のような理念を空虚に唱えることも、具体的な何かを成し遂げるための現実的な過程のひとつなのであり、それを鼻で笑って切り捨てる人物はリアリストとは言い難いのではないか、と私は現在目に入るさまざまな「論争」を見ながらぼんやりと考えることがある。
常に変革してゆく社会の中で、「平和」というものを仮初にも探すのであれば、それは、自らと異なる多様な主張を認め尊重した上でそれに厳として対面するという誠実さと、戦争のような惨事の政治的原因を特定の個人の野望や愚かさのような簡単な結論の内のみに安易に求めることなく、根源的な原因を追究するための思考を諦めないという忍耐強さ、そして、理想と現実、その両方が存在するような場で、一見不毛な議論を果てなく続けてゆくのだという覚悟の中にこそ、見出せるのではないだろうか。
実際、われわれは次のことを承知している。すなわち平和的変革は、正義についての共通感覚というユートピア的観念と、変転する力の均衡に対する機械的な適応というリアリスト的観念との妥協によって初めて達成される、ということである。成功する対外政策が実力行使と融和という明らかに対立する二極の間で揺れ動くのはなぜか、その理由はここにある。
2022/03/15
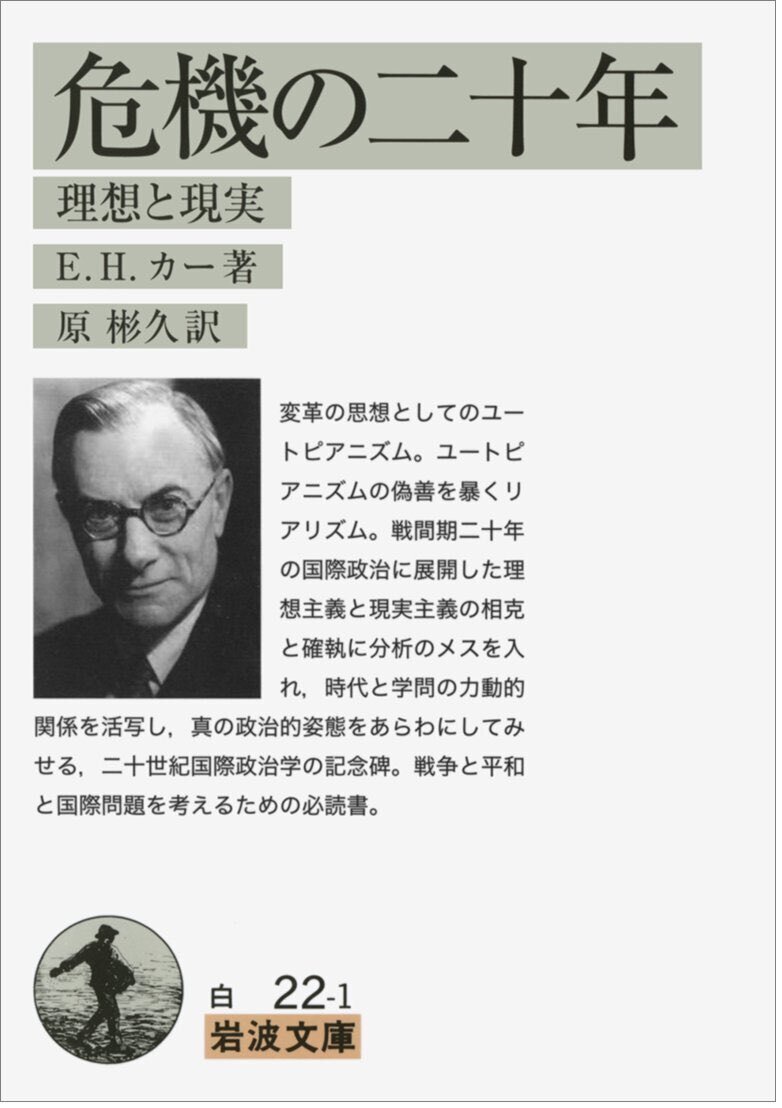
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
