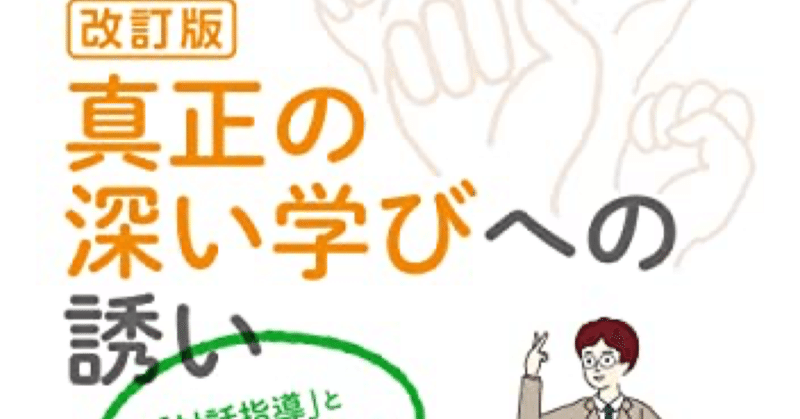
対話指導と振り返り指導で授業を変えよう
『改訂版 真正の深い学びへの誘い-対話指導と振り返り指導から始める授業づくり-』(小林和雄)
「真正」という言葉を最近よく耳にするようになった。教育書の中で好んで使われているように思われる。真正とは一言で言うと「本物」である。「真正の学び」は「本物の学び」。では、本物の学びとはどういった学びを指すのだろうか?
本書では、「真正の学び」を以下のように定義している。
教科の本質を踏まえた本格的で革新的な「主体的・対話的で深い学び」であり、なおかつ個々の学習者が自らの学びの深まりを自覚できる深い学び
さらに、「真正の深い学び」を学級のすべての学習者に実現するためには、教材研究、発問研究に加えて、学級のすべての学習者に深い学びにつながる質の高い対話ができるような「対話指導」と、自己の学びのプロセスを言語化して、意味づけたり価値づけたりできる「振り返り指導」が不可欠としている。本書は、「真正の深い学び」を「対話指導」と「振り返り指導」の重要性から捉えている。
その前に、本書ではまず従来型の授業レベルからの脱却を図ることが提案されている。従来型の授業とは、課題の設定レベルが教科書レベルであり、「わかる・できる授業」のことを指す。教科書レベルの問いや課題を与え、早くわかった学習者が、分からない学習者に教えるだけの教え合いのような従来型の授業を、「わからない・できない授業」に誘い込むことが「真正の深い学び」には必要だとしている。
わからない授業として、現在の学習者集団が、教師や仲間と協働することで達成できる限界ギリギリの理想的な振り返りを方向目標として設定するプロジェクト学習の必要性が挙げられている。限界ギリギリとは、発達の最近接領域(ZPD)のことを指す。ヴィゴツキーが提唱したものであるが、方向目標が高すぎず、低すぎず、頑張れば届くようなギリギリの目標設定のことを指す。
なるほど。ここまで読むと、ここでもやはりプロジェクト学習のようなパフォーマンス課題の設定が重要視されている。プロジェクト学習を設計する上で重要なのが、学習目標の設定である。ここで思い出すのが「逆向き設計」(G.ウィギンズ、J.マクタイ)だが、詳細は避ける。本書でも、その分野のエキスパート(熟達者)が、どのような見方・考え方をするのか、エキスパートレベルの方向目標を「理想的な振り返り」として明記し、そこから逆算して深い学びのプロセスを創出という授業の質的改善の試みが不可欠であると指摘されている。
さて、ここで「対話指導」と「振り返り指導」に戻る。まず前者について。
エキスパートレベルの認識を方向目標に設定した場合、唯一の正解を探るより、互いに考えを出し合うことが大切だと思ったり、「わからない」ことから深い学びは始まり、互いに相手の話のいとや意味が完全にわかるまで訊き合い聴き合うことが大切だと思ったりできなければ、深い学びに至ることはない。そこで提案されているのが、哲学対話レベルを目指す「対話指導」である。「わからない」から始まった学びは、わからないところが限りなく無くなるまで訊き合い聴き合うことで対話による理解が深まる。相手の話の意図や意味がよくわからない場合は「どういうこと?」「どういう意味?」とか、抽象的で具体性に欠けるときは、「例えば?」とか、主張の根拠や理由を知りたいときは、「どこから考えたの?」と言ったように、学習者同士の相互作用が起こるように対話の質を向上させなくてはならない。相手の話の意図や意味を本当にわかるまで、遠慮なく訊くことが重要であり、互いに「わからない」を見つけ出す。そして、新たに見つけたわからなさを深い学びへ向かうきっかけとして価値づけ、「問い、考え、語る」ことを繰り返す「哲学対話」レベルの豊かで質の高い対話を目指す。
次に「振り返り指導」について。
本書では、授業の終末に振り返り活動が不可欠だとしている。それもただの授業の感想程度のものではなく、個々の学習者が自らの学びの深まりを自覚し、言語化して可視化する「省察レベル」の振り返りである。振り返り活動は、今やどこの教室においても行われるようになってきている。が、授業が押してしまって「今日はこれで終わり」となってしまったり、書く内容が本時のまとめ+感想程度のものであったり、振り返り活動の時間の確保と内容の指導が十分であるとは言えない現状がある。また、あまりに振り返りに力を入れすぎて、毎時間書かせるなど、「振り返り疲れ」に子どもが陥ってしまうこともある。その点において、著者は5分程度の時間でいいし、すべての授業では必要ないとしている。教科や内容、状況によって多様な振り返りを組み合わせたり、時には省略して振り返りに軽重作ることが重要だ。なお、著者は振り返り活動に特化した本を書いている。こちらも振り返り活動を充実させる上でとても勉強になるのでおすすめだ。
『振り返り指導の基礎知識(梶浦真 著、小林和雄 監修)』
本書は、目指す究極の授業はどんなものかについて定義され、そのために「対話指導」と「振り返り指導」の必要性が示されている。さらにここでは割愛したが、それぞれの指導について具体的な手立てがたくさん紹介されているので、実践するときの参考になる。そして、脚注がとても充実している。「対話指導」や「振り返り指導」に悩んでいて、今できる範囲で変えていきたいという人には是非オススメしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
