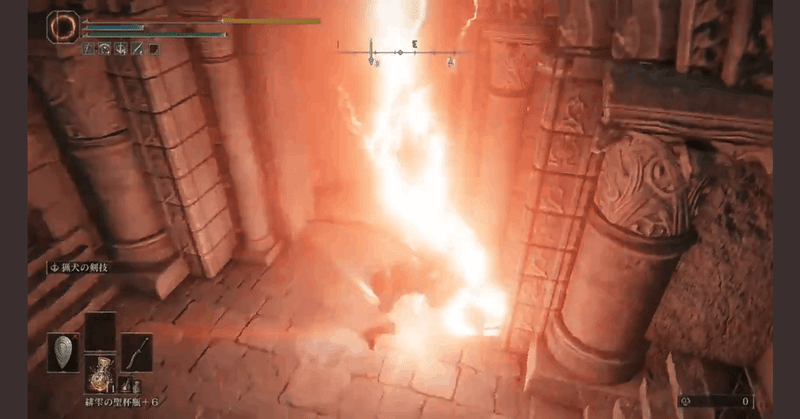
エルデンリングをクリアして/オープンワールド雑感
はじめに
はじめて(広義の)オープンワールドゲームでエンディングを見た。
ウィッチャー3、Ghost of Tsushima、fallout4…そうそうたるオープンワールドゲームを、僕は積んできた前歴がある。
どれも素晴らしいゲームなので、単純に僕に合わなかったというだけなのだが、以下それらが合わなかった理由を述べつつ、エルデンリング面白かった~な話が展開されるので、苦手な方はご注意いただきたい。
オープンワールドゲームの定義は難しいが、①マップがシームレスにつながっており②従来のRPGと比較すると移動の自由度が高い、というのが大きな特徴だろう。そして、僕はそこに不安を見るのだ。
以下、先に挙げた作品を「オープンワールドゲーム」として、僕に合わなかった理由を考えてみる。
オープンワールドゲームが僕に合わない理由
結論から言うと、僕の個人的なゲームのモチベーションは「世界に没入できるかどうか」に重きが置かれている。
オープンワールドゲームは「開始五時間までは楽しい」、これに尽きる。
一つの世界に降り立った感覚、これから旅が始まるワクワク感…それが五時間後にはおつかい作業になり果てている。
また、自由すぎるとなにをしていいかわからない「実存的不安」に陥るのだ(Minecraftとか特に)。
だから結局、僕の操作するゲラルトさんは「村一つ壊滅させるのが趣味のグウェントおじさん」になり果てていた。
自由すぎて不安になる→とりあえずピンにしたがって動く→受動的作業に感じられる…これが個人的オープンワールド負のスパイラルである。
風景に飽きてしまう
確かにプレイ当初は新しい発見があるが、五時間もしてくると「平原」「森」「川」「沿岸」「敵拠点」「集落」「都市」と類型化されてくるし、リアル寄りのゲームであるからこそ…正直代わり映えしない。
朝昼夜…という時間のうつろいも、それこそ「オープンワールドゲーム」という存在が物珍しかったころは驚いたものだが…。
リアルだからこそ「こんな風景さっきもあったな…」になってしまうのである。
動機づけが足りない
どのゲームも大体やることは同じで、「探索」→「バトル」→「アイテム採取」…といったループの動線をどう構築するかという話だと思うのだが、オープンワールドゲームだとこれが特に作業に感じられてしまう。
オープンワールドゲームにおいて、プレイヤーをミッションに導くモチベーションは「ピン」である。
ピン…。
サブクエにせよメインクエストにせよ、ピンがマップ上に表示され、そこに赴くとバトルが始まるか、アイテムの納品か、お使いかのいずれかが始まる。
僕にはこの淡白さと作業感が耐えられないのだ。
ゲーム体験として、マップを歩いたり世界観に導かれたり、つまりは没入感に重きを置いているというのは先述した通り。
この世界にはこんなバックグラウンドがあって、こうした謎があって、探索が楽しいマップで…。僕が求めているのはそういうゲームだ。
逆に、オープンワールドゲームには「探索そのものの楽しさ」が足りないように感じられてしまうのだ。
自由度が高く、リアル向きのマップであるがゆえに導線が散逸してしまっていて、その「お使い感」に嫌気がさしてしまう。
ピンの場所に赴くのも結局はファストトラベルで、移動してはバトルし移動してはバトルし…豊穣であるはずのマップにおけるひどく貧相な体験が、僕には耐えきれなかったのだ。
求めていたもの、エルデンリング
「ピンまでの道のり自体が楽しい」「探索自体が楽しい」、いわばそんなゲームがしたいのだ、僕は。
エルデンリングは、公式では「オープンフィールド」と呼称されている。ただ、①広大でシームレスなマップと②自由度という点で言えば、広義のオープンワールドだと捉えていいだろう。
ではなぜ、僕が途中で投げ出さずにクリアできたのだろうか?
誘ってくれる導線
まず、探索が楽しい。これに尽きる。
他のオープンワールドゲームがクエストに沿って進める形式だったのに対して、エルデンリングにおいてはそれがない。「進行度一覧」もないし、「サブクエスト」もない。
確かに不便ではあるかもしれないが(NPCイベントの進行のヒントくらいは「情報」で確認できても良かったかもしれない)、しかしかえってそれがプレイヤーのゲーム体験を豊かなものにしているとしたら、どうだろうか。
能動的な体験にしているとしたら、どうだろうか。
「祝福の導き」やNPCの会話で情報を集めつつ、地図の断片を見ながら探索を進めていく。
そこにあるのは「お使い」ではなく、「この建物に入ったらどうなるんだろう」「ここには何かいいアイテムがありそうだ」といった「能動的な探索の楽しさ」だ。
それに磨きをかけているのが、アイテムのフレーバーテキストである。
フレーバーテキストには、意味深な地名や人物名がさりげなく散りばめられている。かつてのソウルシリーズでは「名前だけ登場」も少なくなかったが、今作は違う。
「あーここってあのアイテムに書いてあったところか!」「言及されていたあのボスか!」などといった、点と点が繋がる快感がエルデンリングにはある。
自由だけど道導(祝福、NPC、アイテム、風景、マップなど)がある→自分で目的地を設定する能動的な体験が得られ、そこに至るまでが楽しい→ボス戦の試行錯誤が楽しい…正のスパイラルである。
「探索それ自体が楽しい」、このことは、ファストトラベルで各地を回っては戦闘やお使いに勤しむゲームでは十分に体験できないだろう。
景色の変化が良すぎる
シームレスにヤバいエリアに迷い込む。これもエルデンリングの楽しみの一つだ。
エルデンリングは各エリアごとに空の色が違う。それほどに、エリアに特徴があるのだ。
オープンワールドゲームが「現実的なマップに落とし込まれたファンタジー」だったのに対して、エルデンリングは「ファンタジー世界そのもの」なのだ。
だから沼はヤバい色をしているし、厳かなエリアに赴けば空は荘厳な色になる。これも探索における新鮮な体験だ。
ファンタジー世界において、空の色は青だけじゃないのだ。
「次はどんな場所に辿り着いて、どんな敵が待っているんだろう」
雑魚敵、得られるアイテム、出会うNPC…これらの情報がバックグラウンドストーリーを開示し、冒険をさらに楽しいものにする。
気がつけばもう、世界に没入している。
能動的な探索体験。これがエルデンリングの楽しみなのだ。
さいごに
や~エルデンリング楽しかったな~~~~~~。
いやいつもどおりクソボスもいたしクソマップもあったけどね。
一応クリアはしたけどまだ全ボス見ていないしな~DLCどうなるのかな~~~~。
必然的に自分に合わなかったゲームと対比する形になってしまったが、改めて言うまでもないが、それらもどれも素晴らしいゲームである、と念を押しておきます。
※画像はとんでもねぇ範囲外から飛んできたクソ雷が直撃したシーンです、既プレイの方はどこだかわかると思います
