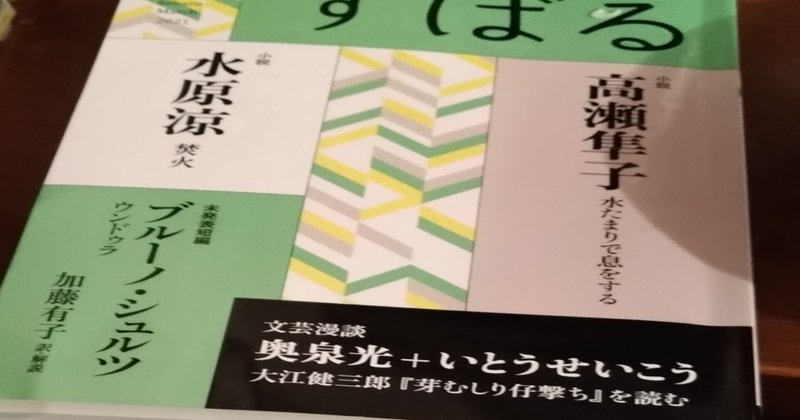
高瀬隼子『水たまりで息をする』
今回は高瀬隼子『水たまりで息をする』を紹介する。芥川賞の候補になっているからすでに読んだ人も多いだろうけれど、これはとても良かった。夫が風呂に入らないということを主たる原動力にして小説は突き進み、読者を飽きさせることなく、最後まで突っ走る、その勢いまず素晴らしい。カフカの小説やメルヴィルの書記バートルビー(何を頼まれても「しない方がいいと思うのです」としか口にしないバートルビーの姿は、風呂に入ることを拒否し続けるこの小説の夫の姿が重なるところがある)もそうだけど、小説の途中で問題が起こるのではなく、最初っから問題が起こっていて(この小説ではカフカなどと違って問題が起こった原因にも言及するけれど)、その問題を起点として転がり続ける小説の形があるけれど、この小説もそれだ。
この小説ではあることが切っ掛けで夫が風呂に入らなくなる。風呂に入らければ当然臭う。その臭いを当然妻は何とかしようとする。水道水がカルキ臭くて嫌だと夫が言うので、ミネラルウォーターを買ってきて、それを頭からかけたり、ドライシャンプーやデオドラントスプレー、ウェットタオルを買ってきて使用を勧めたり、あの手この手を使うのだが夫は嫌がり、臭いはどんどんきつくなる。読んでいると、その臭いがぷんとこちらまで漂ってくるかのようだ。例えば、すばる2021年3月号88ページ。
洗濯かごから濡れたスーツとシャツを取り出して見てみると、シャツの袖口と襟が土色に汚れていた。長い間蓄積した黒ずみの汚れではなく、夫の体からシャツへ移動したばかりの、明るい色をした汚れだった。シャツの襟を鼻に近付けてみる。目をこすった後の指のにおいに似ている。湿ったにおい。それを何倍にも濃くした感じ。
あるいは、すばる2021年3月号100ページ。
夫の体からはすえたにおいがしていて、服にいくら消臭スプレーや香りの強い柔軟剤を使っても、もう隠しきれなかった。彼女の中で夫のにおいが犬や雨水と結びつくこともあったけれど、この頃は、何かに似ているとか、何かをイメージするよりも前に、単純にくさい。近くに寄ると、まず嗅覚を遮断したくなる。口呼吸をはさみながら、鼻腔を狭めて少しずつ息をする。だんだん慣れてくる。慣れてくると、脳が自動でにおいの分析を始める。成分は、汗と尿と埃。毎日少しずつ違う。今日のにおいに似ているのは、自販機の隣の缶・ペットボトル専用のゴミ箱。
すばる2021年3月号102ページも。
彼女の後ろに夫が立った。鏡越しに目があい、ちょっと待って、と目で伝える。夫は歯を磨きたいらしく、手にはさっき余ったミネラルウォーターのペットボトルを持っていた。ひじでつつける距離にいると、今水ですすいだばかりなのに、においがきつい。髪と頭皮が濡れた分、においに湿度があって、重たい。夏の夕暮れ時の、短い夕立の後、アスファルトから立ち上る湯気の生ぐささを思い出す。
ぱっと目についた三カ所を引用したが、ここだけでなく、この小説には様々なにおいの描写がでてくる。『臭い』も『匂い』も。それが小説を生々しくしている。
さて、夫と妻はどんどん追い詰められていく。人によっては離婚をしてすぱっと切り替えるのだろうが、妻である主人公の衣津実は夫を見捨てたりはしない。夫の変化を受け止めようとする。すばる2021年3月号86ページ。
目を閉じると、夢に落ちて行く前のほの明るい瞼の裏に、子どもの頃に近所で飼われていた大型の雑種犬の姿が浮かんできた。犬は、小学生だった彼女と、体の大きさはほとんど同じだった。灰色と茶色のまだら色の毛で、いつもへっへっと垂らしていた舌がでろんと長く、頭を撫でてやろうと手を伸ばす彼女の腕をしきりに舐めたがった。舐められたところは熱く、唾液が乾くとくさくなったが、身をよじって逃げようとすると逆に喜んでしっぽを振り、舐め続けようと彼女の前側に回り込んでじゃれてくる犬はかわいかった。犬だって滅多に風呂に入らない。入らないけど、くさくたって、抱きしめていい。
ここの部分は要チェックだと思う。僕はここを読んで高瀬隼子さんのデビュー作『犬のかたちをしているもの』を思い出した。あの小説の中で犬は普遍的な愛を象徴していて、犬を愛するように夫を愛せるかと逡巡する妻の心理が描かれていた。なのだが、正直その部分は小説内であまり掘り下げられることなく終わっていた印象だった。一体あの小説の主人公の妻にとって、犬とはどういう存在だったのか? 僕には疑問だったが、上に引用した箇所を読んで、その答えの一端を垣間見た気がした。今作における風呂に入らない、動物に近い夫は、『犬のかたちをしているもの』における犬の特徴をもっており、あの小説の主人公にとっての犬のように、今作の主人公、衣津実にとって夫は特別な存在なのではないか?
小説の物語を追いながら考えてみたい。
夫が風呂に入らないことで、妻はさまざまな困難に巻き込まれていく。夫の会社、自分の会社、義母。問題山積。八方塞がり。どう考えても離婚か、心中かしかないような状況だ。だが、この小説ではそうはならない。どうしてか? 主人公の衣津実がド田舎の出身であるという、抜け道が用意されているからだ。
夫が風呂に入らないことが第一に仕掛けなら、この小説の第二の仕掛けは間違いなくそこにある。第一の仕掛けと第二の仕掛けが絡みあうことで、小説は前へ前へ進んでいく。詳しくは読んでもらうとしても、ちょっとだけ具体的に書くと、夫の症状は進み、人間社会への回路を断ち切ろうというところまで進む。それと逆行するようにどんどん自然へと開かれていく。その自然志向が妻の過去と結びつく。前の段落で出てきた『犬』も自然の側にあり、妻の過去(『犬のかたちをしているもの』と結び付けて考えると特に)に関わる存在で、だからこそ、妻は容易に夫を切り捨てたりはできない。かといってすでに都会の快適さを知ってしまった妻は、簡単に田舎に馴染むこともできない。都会と田舎に引き裂かれた妻とひたすら自然を求める夫、社会からはみ出た二人の行き着く先は?――是非雑誌を購入するか、7月13日発売の単行本で見届けてください。
最後に情景を長めに引用して終わる。この小説は素晴らしい描写だらけでどこを引用するか迷ったが、最初に二人で妻の田舎に行った時に、夫が川ではしゃぐ場面にした。すばる2021年3月号119ページ、120ページ。
夫は熱い温泉に入る時みたいに、膝を曲げて両手で水をすくい、太もも、腰周り、肩の順にかけ、徐々に体を慣らそうとしている。体に水をかける度に「めっちゃ冷たい!」と何度も繰り返して叫ぶ。彼女は立ち上がって水際まで行き、両手で持ち上げた石を夫の近くに投げ入れた。大きな水しぶきがあがり、夫の頭の上から水が降りそそいだ。何するんだよっ、と夫が叫び声をあげる。彼女は笑って、木陰に戻る。
夫は川の中で、膝を抱えてしゃがみ込んでいた。ちょうど首から上だけが水の外に出ている。やぶ蚊が飛んできて血を吸おうとすると、ざぶんと頭の先まで水に浸かり、また顔をあげた。
「冷たいの、ちょっと慣れてきたわ」
そう言って水の中で手足を広げ、「洗うか」と言って手足や尻や股間をこすり始める。流れ続ける川の水が、夫の体から出た垢をひとつも見せないまま遠ざけていく。足を下についたまま上半身だけ背泳ぎの体勢になって、髪を水に浸したまま頭をこする。夫の短い髪が左右に広がり、頭が膨張したように見えた。
「毛が抜けて流れてった」
起き上がった夫が川の流れていく方を見ながら言う。彼女も夫の視線の向いている方に顔を向けるが、太陽が反射して輝いているばかりで水の中は全然見えない。見えないよ、と夫に言う。夫は「なんかやだな」と悔しそうな顔をしている。
ひとしきり体の垢を流してしまうと、夫は浅瀬に寄って座り込んだ。腹のあたりまで水に浸かって、首を曲げて水の中を見つめている。
彼女の座っている木陰からは、水面に太陽の光が反射しているので水の中は見えない。夫が見ている水の中を想像した。魚は人間の立てる音に驚いて逃げてしまっているだろう。虫は泳いでいるかもしれない。植物の種や、虫以前のぐにぐにした埃のようなものも流れているかもしれない。それは彼女が子どもの頃に川でよく見たものだった。虫だか植物だか分からない、けれどゴミではないだろうと分かるものが、時々川を流れていくのだった。彼女が遊んでいたのは海に近い川下だったけれど、それが山から流れてきたものだということは、誰に教えられたというわけでもなく、なんとなく知っていた。両手でつくったお椀で捕まえようとしても、流れていってしまうのだ。おそらくは海まで。
「さぶい」
夫が立ち上がり、裸のままこちらへ歩いて来る。河原に濡れた靴下の足跡が付く。彼女が渡したバスタオルを体に巻きつけて、夫は日なたに座り込む。太陽が真上から夫を差す。
「やぶ蚊に噛まれるよ」
と彼女が声をかけると、夫は手足を小刻みに動かし始める。じっとしていたら噛まれると思って、ずっと動いている。その奇妙な動きに彼女は声をあげて笑い、その声を聞いて夫も笑った。
長い引用だった。素晴らしい場面。夫婦の特別な時間がしっかりと描かれている。『水たまりで息をする』おススメです。是非、芥川賞をとって欲しい。
今回はここまで。また来月、ヨロシクです。
よかったらサポートお願いしやす!
