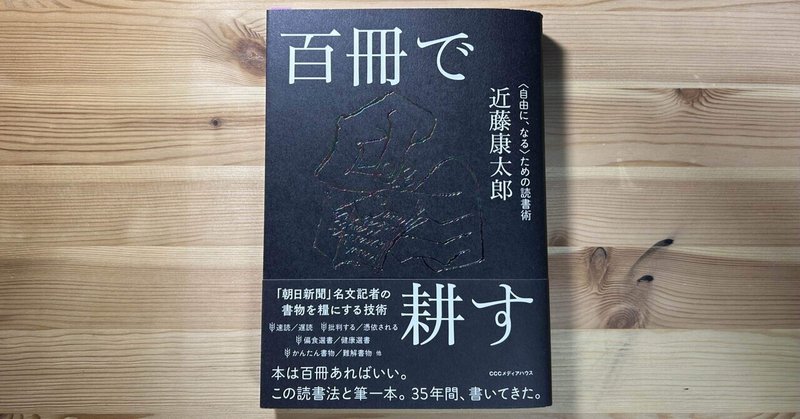
【書評】近藤康太郎『百冊で耕す 〈自由に、なる〉ための読書術』(CCCメディアハウス)
こんな大人がいたとは(!) 著者・近藤康太郎さんに対する私の感慨は、この一語に尽きる。何歳(いくつ)になっても知的好奇心を失わないその姿、私から見て、知的青春を謳歌し愉しみ生きるその姿は、わが人生のお手本にしたいとさえ思わせる。
まず、驚くべきはその読書量。さらには、日本語訳を読んで好きになった作家は、外国語原書を読んでいく、果てなきグルーヴの追求。そして、答えを得るためではなく、新たな問いを立てるためにという、読書への向き合い方。
◎ この世界とは、「生きる地獄」である
本書において、著者は、その読書術を語ることを通して、〈この世界で生きるということ〉の思想を語る。まず、著者の見るこの世界とは、端的に言って、「生きる地獄」である。
著者は言う。「長年つきあった恋人に別れを告げられた。愛する人に先立たれた。かわいがっていた犬や猫が死んだ。そんな、人から見れば”小さな”ことでも、本人にとっては生き死にの問題だ。(中略)そこに軽重はない。「生きる地獄」という意味では、等価だ」(p. 224)。
誰しも、日々辛いことがある。辛いのは、あなただけではない、わたしもだよ。そんなふうに、著者が私たちに語りかけてくれている。
では、そこで、この「生きる地獄」としての世界を、私たちはどう生きる(または、逃避する)ことができるのだろうか? 著者によれば、そのための読書であり、本書で開陳される読書術なのである。〈この世界で生きるということ〉の思想は、読書術を綴った本書のそこかしこに溢れ出ている。
◎ そもそも「分かる」とは何か?
本書を読み進むなかで、著者の読書量に私たちは圧倒されてしまう。がしかし、実は、著者だって、本を読んで全部「分かっている」わけではないと明かしてくれている。むしろ、「そもそも「分かる」とはなにを指してそう言うのか」(p. 197.)とさえ、著者は問うているくらいなのである。分からなくても、大丈夫だよ、と。
著者は言う。「読書は〈分からない〉。いや、〈分からなく〉なるために、本は読む」(p. 94.)。
本の中に、答えを探すのではない。そうではなく、〈分からなく〉なるためとは、問いを見つけるために読むのだ。読書、それは、みずから進んで〈分からない〉を体験していくことだろう。自分は何が分かっていないのかを炙り出す作業が読書とも言える。〈分からない〉体験により、世界に対する新たな「問い」が浮上する。
著者は言う。「そして、問いを発見した人が、世界を変える。答えは、世界を動かさない。/ なぜなら、世界にも、人生にも、そもそも「答え」はないから」(pp. 111-112)。
そう、この世界が、この人生が、語り尽くされることなんて、ありはしない。
◎ 入鄽垂手(にってんすいしゅ)、あるいは、〈自由に、なる〉ための読書術
入鄽垂手とは、禅の十牛図における最終段階のこと。仙人として悟ったままで終わらず、この苦しい世間に戻り来て、衆生(しゅじょう)へ救いの手を差し伸べることを謂う。
さて、インプットとアウトプットのバランスのくだりで、著者は次のように書いている。
「読書も同じだ。インプットだけでは完全ではない。アウトプットしなければならない。摂取した栄養を、消化し、養分を体内に取り込み、やがて体外に排出してこその健康だ。(中略)本から外界に出る。世間に戻る。/ わたしの場合、それが「書く」という行為にあたった。原稿を書き、新聞でも雑誌でも書籍でもネットでも、どこでもいい、発表する。そのことで、ようよう精神の平衡をたもってきた」(pp. 221-220.)。
ここで、アウトプットは著者自身の救いのためだと言われているが、私には、著者の姿が上述の入鄽垂手の仙人と重なるのだ。著者は、衆生の救いのため、戻り来た。「読書って、こんなに愉しいものなのだよ」という真理を伝えるために。
世界は、あらかじめ答えで埋め尽くされているのではない。むしろ、世界に答えなどなく、あるのは私たちの問う問いだけなのだ。私たちにできることは、その問いを問い、そうして言語化することを通して、「生きる地獄」と感じられるこの世界を冷静に客観視し、それにより救われ、わずかでも生きやすくすることしかない。この世界の生きにくさから、〈自由に、なる〉ために。
著者は言う。「なぜ、本など読むのか。勉強するのか。/ 幸せになるためだ。幸せな人とは、本を読む人のことだ」(p. 231.)。
本書を通して、このことを伝えるために、著者は戻り来たのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
