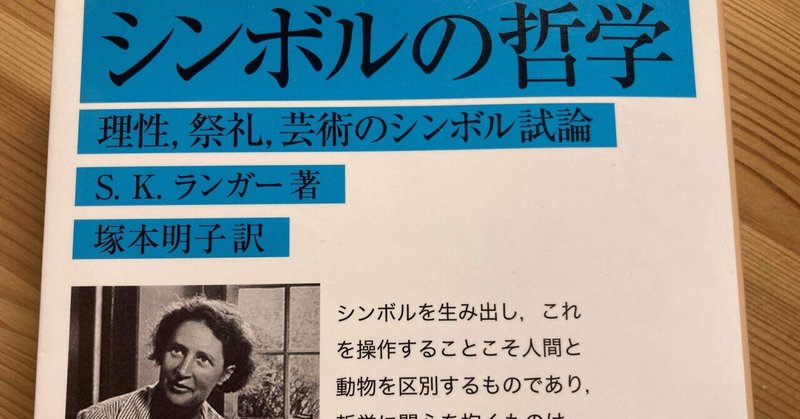
ランガー『シンボルの哲学』を読む(5)
第5章 言語
5-1 現実をシンボル的に見る傾向
動物でも情動や意思伝達のために「サイン」を使用する。しかし、「言語」は人間のみが使用できる人間特有の「シンボル作用」である。この言語とは何かという問いを「シンボル作用」という観点から解きほぐそうというのが、ランガーの狙いである。
そこで、「この言語という人類にとってもっとも重要な機能はどのように始まったと考えればよいであろうか」(p. 210.)、とランガーはまず「言語の起源」を問うてみる。彼女は科学的な研究成果に依拠して、人間の幼児が本能的に言語を話すようになるという「本能説」を否定する。周囲に言語を話す人間仲間が存在しなければ、幼児は言語を学習する機会を得ず、ゆえに幼児がたった一人で言語を話せるようになるという「本能」はない、と。
そして、彼女はこう結論づける。「「現実をシンボル的に見る傾向」こそ言語の基調音である」(p. 216)と。そして、もしそうならば、「言語機能の根(言語の起源)を追求してきたほとんどの研究者が見当違いをしてきたことになる」(p. 216.)。
それは一体、どんな見当違いなのだろうか。一般に、「言語の起源」を探ろうとして、人は言語による意思伝達の発生の瞬間を人間の幼児や動物に見ようと試みるが、その試みは「本能説」のように失敗に終わる。そこで、「言語の起源」なるものの難題に対して、ランガーは見方を変えようと提起する。ここで効果を発揮してくるものが、前章(4章)で我々が概観した論述的シンボル作用と現示的シンボル作用の区別である。
ランガーは、言語というものを絵画や踊りなどの芸術の表出と同じレベルに置き、まず言語を、レベルの高い論述的シンボル作用としてではなく、現示的シンボル作用として捉えなければならないと言っている。「現実をシンボル的に見る傾向」(p. 216.)こそが、我々のまず着目すべきことであると彼女は述べる。
この「現実をシンボル的に見る傾向」とは、言語の意味や意思伝達のための使用という実用性に還元できるものではないということである。ランガーは次のように述べる。
「シンボル作りとよびうる傾向がまず初めに姿をあらわすのは、或る種の事物とか何かの形態や音とかに付いてくる、単に何か意味があるらしいという感じであって、実際には危険でも有用でもないようなものに漠然と情動的に心が捉えられる、ということであったとおもわれる。(中略)恐らく審美的な魅力とか神秘的な恐れといったものは、人間特有の「現実をシンボル的に見る傾向」となる、あの心的な機能の最初の現れなのであって、それがやがて想念を抱く力になり、生涯言葉を話す習慣となってゆくのであろう」(pp. 216-217.)。
たとえば、何を指示し、何を意味しているのか周囲の大人には見当がつきにくい赤ん坊の「あーあー」「うーうー」という喃語、それこそが赤ん坊が現実をシンボル的に見ている証拠であるとする。
他方で、言語の論述的シンボル作用は、そのようなあらゆるシンボル的行為の中でも、「極めて高度な形式である」(p. 216.)。つまり、語を順々に発していく言語の論述的シンボル作用は、現示的シンボル作用よりもレベルの高いことなのである。
そのような高度な言語使用よりも、言語のシンボル作用というものをもっと低いレベルでの表出として捉えること、それを現示的シンボル作用と呼ぶ。ここで、言語は、絵画や踊りなどの芸術の表出と同じレベルに置かれる。先に見た赤ん坊の喃語が「現実をシンボル的に」見ている証拠というのは、「実用的」ではない、この現示的シンボル作用のレベルである。
5-2 有意義性と言葉遊びの区別
実用的ではない言語の現示的シンボル作用の表出を、赤ん坊や幼児の言葉遊びのレベルに見るとすれば、そこには有意義性は認められない。言語の現示的シンボル作用とは、初期の段階にあっては、赤ん坊や幼児の喃語などの言葉遊びであって、何らかの意識伝達のための有意義性はない。
慣習的な表現の外示作用ではなく、よって有意義でもない言語使用の行為こそが、シンボル的行為と呼ばれうる。その代表が赤ん坊の喃語である。赤ん坊は自らが発する喃語で、何かを指示しようとしているのではなく、それは「現実をシンボル的に見る傾向」であり、「審美的な魅力とか神秘的な恐れ」(p. 217.)を言語化しようとする傾向と言える。このような喃語は、言葉遊びの域にある。言葉遊びとは、言葉の世界に戯れることである。赤ん坊は目に入った現実をシンボル的に見ようとするのである。
この点、外示作用は感情や態度などの慣習的な表現を伴う。ここで言われる慣習とは、シンボルの伝達者も受信者も、そのシンボルが何を意味するかを予め了解していることである。そして、気をつけなくてはならない点は、シンボル的行為の外示作用は、「何かが欲しい」「好き」「嫌い」などの意思伝達に使用されるということである。ランガーは次のように述べる。
「言語の本質が自然の要望を伝達すること(中略)ではなく、想念に形を与え表現することであるという発想が、言語の起源についての謎めいた問題にも新しい視野を開いてくれる。言語の始まりは自然適応ではなく、生活手段を手に入れる方法ではないからである。言語の始まりはむしろそうした材料に絡みついてくる目的のない喃語本能であり、原始的な審美的反応であり、夢のようにおぼろげな観念の連合である。言語を準備するのは言語使用よりも低いレベルの理性であって、いかなる形であれ音声による伝達という進化のレベルよりも低い段階に見出されるのである」(p. 229.)。
言語の起源は、実用性とは別の領域において始まった。言い換えれば、「現実をシンボル的に見る傾向」が想念を言語化しようする欲求に答えることで始まった。意思伝達のための高いレベルの言語使用は、さらに低いレベルの「現実をシンボル的に見る傾向」が慣習化され、実用的に用いられるようになった結果であり、順序的には低いレベルが先で、後に高いレベルに至るのであって、その逆ではない。
初めに、「想念と遊ぶこと」(p. 240.)ありきである。「連想遊びが(中略)シンボル的変換の行使に他ならない」(p. 237.)とランガーは述べる。この「シンボル的変換」(p. 242.)こそが「人間に特徴的な活動」(p. 242.)である。
5-3 外示作用と共示作用の区別
「語の持つ最初のシンボル価値はおそらく祭祇の場合と同様、純粋に共示的(内包的)であった。何かしらの音節の繋がりが、祭礼のシンボルと同様一つの概念を具体化する」(p. 251.)。
たとえば、神を讃える「ハレルヤ(なんたる神の素晴らしさ)」という言葉は、共示的意味を持っているが、外示的意味をもっていないという例をランガーは挙げている。
第3章で概観したように、外示的意味と共示的意味とは、前者が外延的であるのに対して、後者は内包的である。
論理学で言うところの「外延」とは、ある語の指し示す対象の範囲のことである。たとえば、「鳥」という名は、眼前の「この鳥」自体を一対一対応で名指しているのではなく(これは、記号的表示作用になる)、「鳥」という名が鳥の様々な「想念」を惹き起こす。たとえば、スズメ、カラス、うぐいす、等。
対して、共示作用[=内包的意味、含意作用]とは、その語が指し示すものが共通して持っている意味である。たとえば、「鳥」という名が持つ共示作用[=内包的意味、含意作用]とは、「からだ全体が羽毛で覆われ、翼で空を飛ぶ動物」(『デジタル大辞泉』より)という鳥が共通して持つ意味にあたる。
さて、「外示作用こそが言語の本質である。なぜなら外示作用があって初めて、シンボルがもとの本能的な発声から開放され、それを生み出した状況全体から離れたところで意図的にそれを「使用する」ことの印となるからである。外示的な語は曖昧であるにせよ、直ちに想念に、また現実的で公開の場にあるもの(あるいは出来事、性質、ひと、など)に関連する。従って外示作用は想念を、全くその場限りの個人的な経験からひき離して、これを様々に違った状況の中へも入っていけるような恒常的な要素にしっかりと結び付けるのである」(p. 251.)。
対して、共示作用は個々の実例ではなく、個々を包括する意味であるので、祭祇で用いられる「ハレルヤ」という言葉は個々の実例を指し示しているのではない。それは、神を讃える情動の表出である。この情動の表出こそ、最初の「現実をシンボル的に見る傾向」なのである。
5-4 隠喩(メタファー)
「隠喩の本性の問題は、言語をサイン的にではなくシンボル的に捉えるのでなければ正しく理解できないテーマである」(p. 250.)とランガーは述べている。
言語をサイン的に使用する場合、「鳥」という語で眼前の「この鳥」を一対一対応で指示する。しかし、言語をシンボル的に使用するとは、「彼は背中に羽を持つ」という語で「彼が空を舞う」ことではなく、「(鳥のように)彼は自由に駆け回れる」ことを隠喩で表現している。
「全ての言説には二つの要素が含まれており、それぞれ(言語上あるいは実際上の)脈絡(コンテキスト)と新規要因(ノヴェルティ)と呼べよう。新規要因というのは話し手がそこで指摘しよう、あるいは表現しようとしている事柄である。(中略)話し手が指摘したい新規要因を厳密に表示できる語がない場合は、彼は論理的類推法の力に訴えて、何か別のものを外示する語を自分の意味するものの現示的シンボルとして使用する。文脈が、彼がその外示物を字義的に意味しているはずがない、何か別のものをシンボル的に意味しているのだということを明らかにする」(p. 260.)。
たとえば、上述の「彼が自由に駆け回れる」ことが新規要因なのであるが、そのことを言い表す語がない場合、「(鳥のように)彼は背中に羽を持つ」という表現を借りて、現示的シンボルとして使用する。字義的に、実際に彼は背中に羽を生やしているわけではないことは明らかである。これは隠喩なのであり、「何か別のことをシンボル的に意味している」ということになる。
「隠喩は抽象的に見ることの、人間の精神が現示的シンボルを用いる力を示す顕著な証拠である」(p. 263.)。
ここで外示的シンボルとの対比で用いられる現示的シンボルとは、言語による表現の「応用」と理解できるであろう。この「応用」こそが隠喩である。そして、この隠喩が「シンボル変換という人間の基本的な特徴である」(p. 267.)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
