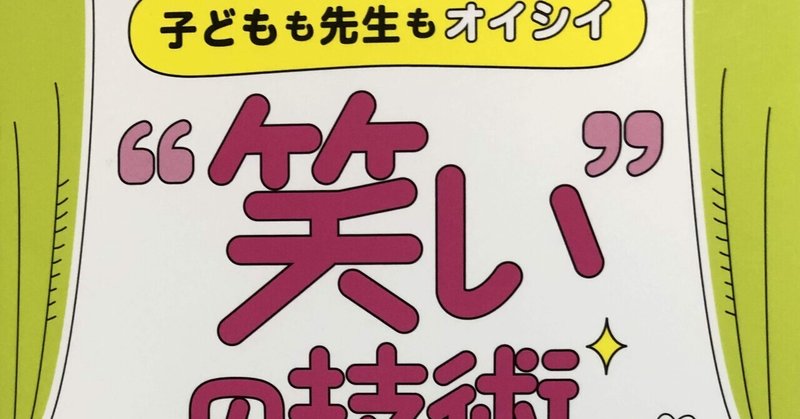
子どもも先生もオイシイ「笑いの技術」読んでみた
おはようございます。
本日は、夏休み中に読んだ本の紹介です。
廣瀬祐介さんが書いた「笑いの技術」です。
大阪で教師をされています。
モットーは、「子どもも大人もオイシク」
M-1やR-1グランプリにも出場している異色の先生です。
その本の中で、個人的な感想を3点紹介します。
①後出しジャンケンはマイナスしかない
学級スタートの4月、そこまできびしく指導をせず、むしろ緩いスタートの学級をよく見かけます。
当初は「今年の先生は叱ってこなくてやさしいぞ」と思っていた子どもたちも、5月ぐらいからチクチク指導されることがあると、「今更言われても・・・」と感じ、不信感につながります。
そこで、4月は比較的ルールを厳しくし、これは良いこと、これは良くないことと細かく伝えます。これは、後出しジャンケンを防ぐためです。
例えるなら、がま口です。入り口は狭いですが、あとは広い。これが逆の、入り口が広くて、あとから狭くでは、少し無理があります。最初は「今年の先生はきびしいぞ」くらいがベターです。
子どもと楽しい時間を過ごすのが大好きで、笑いが絶えないクラスを作っている廣瀬先生ですら、4月は比較的ルールを厳しくという意識をもっているというのがおどろきでした。
そういえば、同じ学校の「クラスが楽しそうな先生方」と話をしたときも同じでした。
「4月は厳しく」と言っていたことを思い出しました。
②教室に笑いという入浴剤を投げ込む
笑いをとりたいと思っている先生ほど、大爆笑が一気に起きると思っているのではないかと思います。
しかしそれは難しいことですし、必要ではありません。
まずは、教室に1人いる、よく笑ってくれる子を笑わせればいいのです。感情は人から人へ伝染していきます。
よく笑ってくれる子に笑いという入浴剤を投げ込めば、浴槽の中で入浴剤がじんわり広がっていくのと同じように笑いも教室の中に広がっていきます。相手の感情に共鳴して同じ感情を引き出すことが、教室全体を笑いで包み込むことにつながります。
この考え方も、なるほどなと思いました。
人を笑わせた経験値が多い廣瀬先生ならではの視点です。
「まずは、教室でよく笑うあの子を笑わせよう!」だったら、できそうだと感じませんでしたか?
その方法論も詳しく書かれています。
③1ボケ2ツッコミの法則
子どもたちのおもしろい言葉や反応に、1つではなく2つの言葉を返すことで笑いが倍増します。
子どもたちと休み時間などに話をしていると、面白いことを言う子どもたちがいることでしょう。
そのときに、「なんでやねん!」「なわけないやろ!」とだけツッコミをするのではなく、2つ目のツッコミに具体性や例えを入れてみるそうです。
これは、繰り返し意識すれば実践できそうだと、個人的に感じた実践でしたので書きました。
例
あるとき、子どもたちが店番をする子どもフェスティバルが学校行事で行われました。私も子どもたちに交じってゲームを楽しんでいました。
そこで子ども銀行のようなシステムでお金を払う場面があったのですが、私は大きな金額のお札しかなく、それを出しました。
そのとき、受付の子どもが「先生、全額ありがとうございます!」と元気に言ってきたので、
「なんでやねん!」「人のものを全部もらうとかジャイアンすぎるやろ!」と2つ連続でツッコミました。
まとめ
本日は、廣瀬先生の本を読んで、個人的にビビっときたところ3選を紹介しました。
教室の中に笑いがあることは、大人にも子どもにもメリットがあると考えます。
そんな教室に近づく考え方や方法のヒントがつまった1冊、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
