
SDGsの目標2に貢献する世界の事例3選!|私たちができることはある?
先日、目標2「飢餓をゼロに」に関する日本企業の取り組み事例をご紹介しましたね!
今回は日本企業ではなく、世界が実施している取り組みと私たちができる支援について解説していきます★
途上国を中心に多いとされる飢餓ですが、実は私たちが住んでいる日本にも経済的困窮を理由に栄養不足になっている方が・・・
私たちにはどんな支援ができるのでしょうか?
■SDGs目標2「飢餓をゼロに」|基本内容と8つのターゲット一覧

”飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する”
SDGs目標2は、飢餓(栄養失調)を無くすことを目指したもの。
世界で9人に1人が飢餓に陥っているとされている現代において、飢餓を解消するためには、持続可能な農業や世界中の人々が食糧を手に入れやすい仕組みの整備、そして食糧生産者の生活についても考えなければなりません。
以下に目標2に設定されている8つのターゲットをご覧ください。
【SDGs目標2:飢餓をゼロにのターゲット一覧】
2.1)2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層および幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。
2.2)5歳未満の子どもの発育障害や衰弱について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養失調を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦および高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
2.3)2030年までに、土地その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場および高付加価値や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民族、小規模な家族経営の農家、牧畜家および漁師をはじめとする、小規模食糧生産者の農業生産性および所得を倍増させる。
2.4)2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水およびその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。
2.5)2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源およびこれに関連する伝統的な知識へのアクセスおよびその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。
2.a)開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発および植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。
2.b)ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金および同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正および防止する。
2.c)食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場およびデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。
ターゲットを見ると、飢餓は経済的な理由だけでないことが分かります。
とくに女性や子供、高齢者といった方についても定められていることがポイントのひとつ。途上国において社会的弱者となってしまいやすい人たちは優先順位によって飢餓状態を悪化させてしまうという現状が伺えます。
世界の状況については下記のリンクにまとめているので、是非ご覧ください。日本政府の取り組みもご紹介しています!
■世界の取組み事例①「インド」|食用油にビタミンを加えて国民の健康を支える
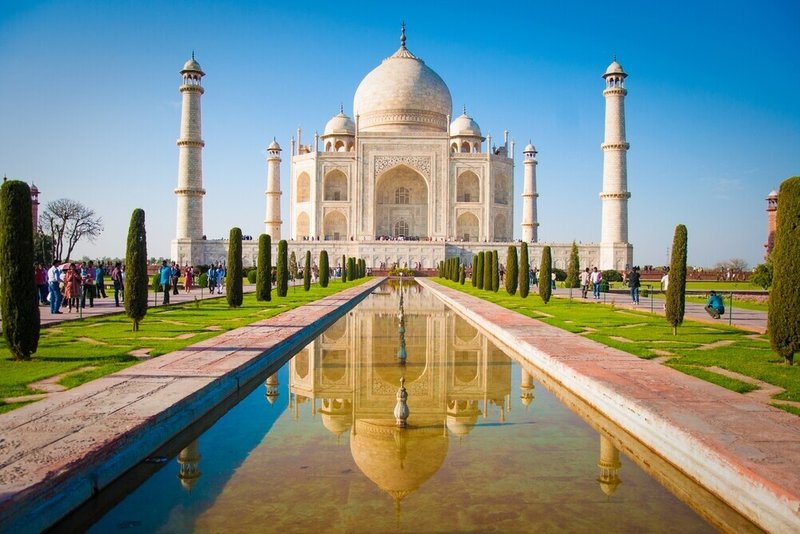
ITによって成長している一方、世界の飢餓人口の約1/4を占めているとされているインドは、子どもの40%が飢餓状態にあると報告されています。
インドにおける飢餓問題解消を支援する団体「カーギル・インド」では、一般家庭99%が使用している食用油に注目!
食用油にビタミンを取り入れ栄養を強化することで、ビタミン剤の販売よりも多くの人々に栄養を届けることができると考え、大手食用油メーカー3社に製品アイデアを提案しました★
結果として、必須ビタミンであるビタミンAとビタミンD を取り入れ、飢餓に苦しむ人々の健康状態を向上させることに成功!
カーギルの成功を受けて、競合ブランドが栄養価を強化した食用油の販売をしたことで市場にも大きな変化が生まれました。
■世界の取組み事例②「フランス」|食糧廃棄を法律で禁止し飢餓問題解消を支援

現在、世界では全人口を賄うのに十分な40億トンもの食糧が生産されていますが、そのうち13億トンが捨てられてしまっています。
主に食糧を廃棄しているのは先進国。
先進国は経済的に余裕があることから、世界で生産される食糧の約半分を占めているにも関わらず、見た目の基準なども厳しいため、食べられるのに捨ててしまう「食品ロス」によって貴重な食糧が捨てられてしまっています。
食糧廃棄や食品ロスを無くすことで、より多くの人々に食糧が行き渡る可能性が高まります。
フランスでは2016年に食品廃棄禁止法を施行。小売店などで賞味期限切れの食品を廃棄することを禁じ、慈善団体への寄付や肥料や飼料にリサイクルすることを法律で義務付けました。
食品廃棄禁止法により、フランスにおける飢餓問題解消や健康状態の向上のほか、循環型社会の実現にも貢献しています♬
■SDGs目標2達成のために私たちにできること

食品ロスは日本でも深刻化している問題です。
日本で排出される食品ロス量は年間約612万トン。なんと、東京ドーム約5杯分もの食糧が食べられずに捨てられています・・・!
日本における食品ロス量のうち、家庭から排出される量は約半分。食糧の62%を輸入に頼っている日本において、食品ロス問題は他の先進国と比べても早急に改善しなければならない問題のひとつです。
・すぐに使う食材を購入するときは棚の手前から取る
・安いからと言って買いすぎない
・捨てる前に食べきる
・献立や買い物リストを考えてから買い物に出る
上記を意識するだけでも大幅に食品ロスを防げます。
日本では3010運動(さんまるいちまる運動)も盛んになってきました♪
飲み会で飲食店を利用する場合において、食品ロスを防ぐための取り組みとして長野県松本市ではじまった運動が全国に広がっています。
【3010運動のポイント】
1. 注文するのは食べきれる分だけ
2. 食事の開始30分と終わりの10分前は料理を楽しもう!
3. 完食を目指す!!
ちなみに「食品ロスの削減の推進に関する法律」には、3010運動に由来して10月30日を「食品ロス削減の日」に定めています。
■食べ残しを減らして飢餓問題解消を支援しよう!
今回はSDGs目標2「飢餓をゼロに」について、世界で実施されている取り組み事例と食品ロスについてご紹介しました。
【今回ご紹介した内容】
・目標2「飢餓をゼロに」の内容とターゲット
・インドの取り組み事例
・フランスの取り組み事例
・私たちにできること
今回ご紹介した国のほかにも、多くの国でSDGs目標2達成に向けた取り組みが実施されています。みなさんが好きな国がどういった取り組みをしているのか、是非調べてみてください★
▼参考サイト
・みらいい|これですべてが分かる!【SDGs 2.飢餓をゼロに】とは?事例と家庭でできることを紹介
・SDGs one by one|02.飢餓をゼロに
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
