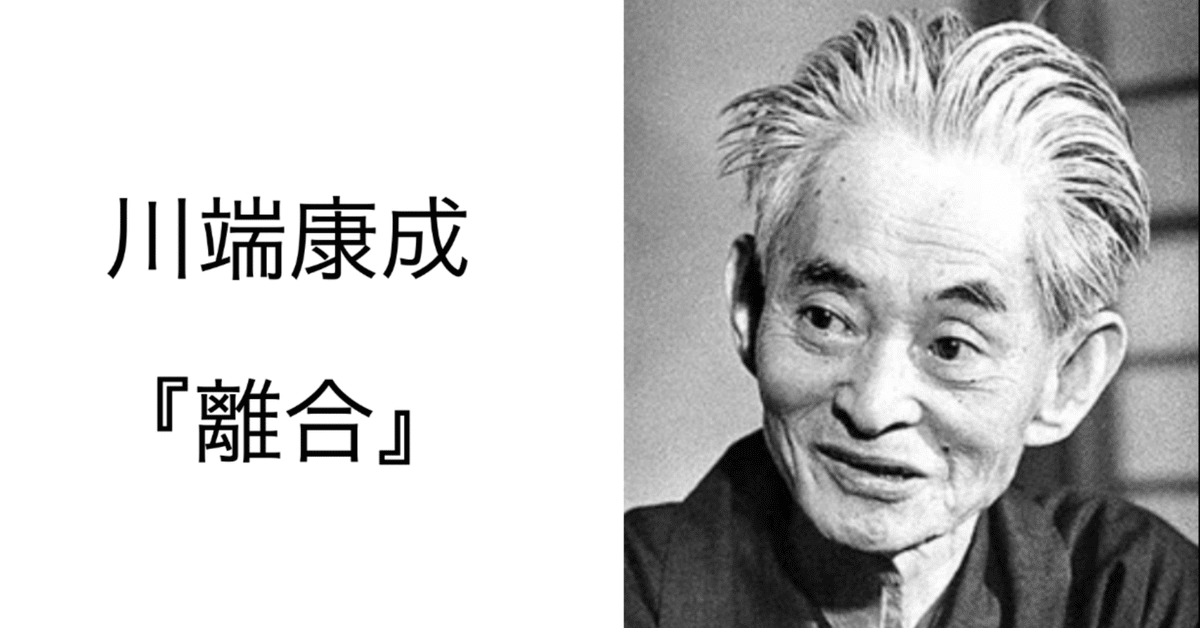
川端康成『離合』読書会 (2023.7.7)
2023.7.7に行った川端康成『離合』読書会 のもようです。
私も書きました。
「福島は男の未練を隠しているのだが、それが漏れていて、モヤる」
電気技師として東京に一家を構えるはずだった福島は、勤め先が戦災にあったのを機に、田舎に戻る。妻、明子の浮気と彼女をかばう妻の実家の不誠実が遠因となって離婚し、引き取った娘を育てた後は、彼はその田舎で教師をして埋もれている。
その娘が成人して結婚するにあたり、婿となる長雄が福島に結婚の承諾を得るために訪ねてくる。
福島は長雄に導かれ上京して、結婚を控えた娘のアパートを訪ねる。そこには別れた妻も現れる。
しかし、よく読めば、別れた妻はすでに死んでおり(それは白いカーネーションで暗示される)、福島も、生きているのか、浮遊霊なのかわからないような、頼りない存在感である。(飛行機に乗って、梅雨の雨雲をこえて上京してきたくだりは、なんだか、ヘミングウェイの『キリマンジャロの雪』の最後の夢のシーンのようでもある。)
散り散りになった一家が、娘のアパートで再び会う話である。これ、重要なのは、福島は久子の結婚に渋々賛成しているだけであるし、離婚のきっかけとなった明子の浮気を許してもいないことである。長雄への言動は、終始やや屈託があるし、手紙を燃やすことにこだわることにも、過去を精算できない「しこり」を感じさせる。
川端康成の意図は、生者と死者の現世への妄執と崩壊した「家」を描くことにあるように思う。
福島は、結局一家をなすことができなかった。戦前においては家同士の結婚であったものが、作品の描かれた戦後では個人の自由意志によるものになりはじめている。そのことは福島も理解している。娘の結婚に反対するいわれはない。久子の交際相手の長雄は、久子の両親に律儀に結婚の承諾を得にきている。このしっかりした家制度の意識のある保守的な婿とは対照的に、福島と明子と久子の一家の関係は、タイトル通り「離合」であり、この一家は、崩壊しているのだが、嫁入りをきっかけとして、一時的な再会によって、お互いが維持できなかった「家」を取り戻そうとする。
一人娘の嫁入りを前に、生きながらに片田舎に埋没している福島と、すでに五年前に他界しているのに、福島の前に亡霊として現れた明子が、家の責任を果たさずに嫁に出してしまう娘への未練と、家を崩壊させた自分の過去への後悔を匂わせながら、家を出たあとのその後の人生を、福島に娘のアパートの一室かりて報告する。
娘の嫁入りという事件を機に、福島の隠された本心(妻への屈託)が、徐々に明らかになっていくところが、読み手を釣っている。しかし、その本心は、明子の死を知らせる電報を福島が焼いて隠蔽することで、久子には、明かされなかったのである。読者の知っている福島の本心(別れた妻への屈託)は、久子にはふせられたままである。我が子に夫婦の秘密を知らせる必要なしと考えたのだろう。その親心を嫁入り前の娘への配慮とみるか、妻への屈託を久子に悟られたくないという福島の逃げとみるかは、意見が分かれそうだ。
福島は、もし飛行機が墜落したらとか、私と長雄くんのどっちを心配したかとか、娘に不穏なことを言って反応を試すとか、元カレの手紙や、元カレについて書いてある日記があったら焼いておけと、自分の後悔を交えて、久子にさり気なくアドバイスするあたりとか、それが、福島の娘、久子への妄執みたいで、読んでいるほうは、「モヤる」。(もやっとする)
娘の嫁入りという晴れ舞台の前に、死んだ明子と、生きながら死んでいる福島の二人に未練を語らせるというコントラストの強い構成に、川端の得意なドラマツルギーが浮かび上がる。
それにプラスして、梅雨の雨で、風情のあらわれた田舎の景色に、長雄が魅せられるシーンなどの、ささやかな描写が、非常に効いていると思った。
(おわり)
読書会のもようです。
いいなと思ったら応援しよう!

