
給料アップ交渉 ~「会社側の報復手段」と「サラリーマン側の最終兵器」について~
このコンクリートジャングルでは、自分の給料を上げ、市場価値を高め、自らのキャリアと生活を守ることは、各労働者の責任であるといえます。
給料を上げる方法として、人事評価において端的に「給料を上げてくれ」と主張することが考えられますが、「雇う側の会社」と「雇われる側のサラリーマン」のパワーバランスを理解しておかないと、交渉の場において堂々と給料アップを求めることができません。
例えば、「給料アップの交渉をしたら、クビになったりしてしまうのではないか…」と不安を感じていると、結局何も求めることができず、ただ会社側が提示した給料をそのまま受け入れることになってしまいます。
給料アップ交渉の場につく前に、(ア)雇われる側のサラリーマンにはどのような権限があり、自分にはどこまでの主張が可能であるのか、(イ)反対に、雇う側の会社にはどのような権限があり、給料アップ交渉が決裂した最悪の場合に、どこまでの”報復”を受ける可能性があるのかを整理しておくことが必要です。
今回の記事は、(1)会社側の報復手段である「解雇」と、(2)サラリーマン側の最終兵器である「退職の示唆」について考えます。
なお、以下は正社員に関する法規制を前提としています。
(1)会社側の報復手段である「解雇」
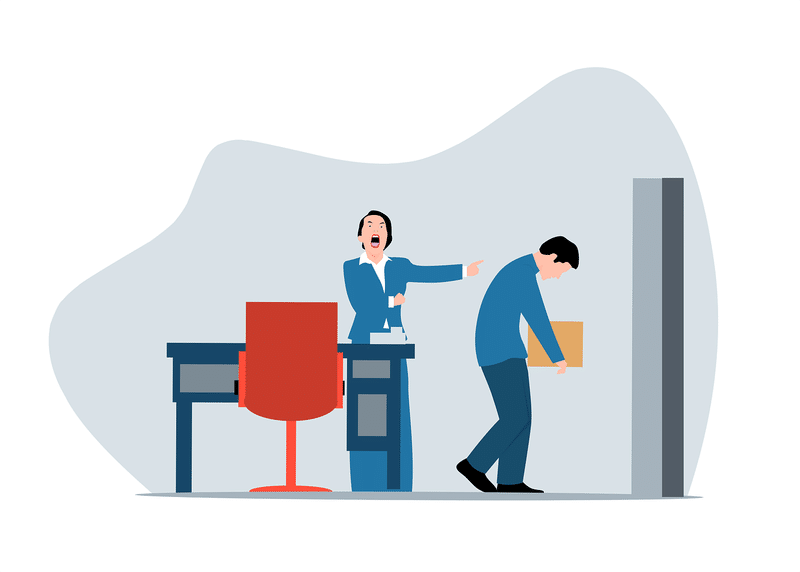
雇われの身であるサラリーマンが最も恐れているのは解雇です。独立をするには知識や経験が必要ですし、解雇後すぐに再就職をするにしても再就職活動期間中は無職となってしまい、貯金を切り崩す生活が続いてしまいます。
給料アップ交渉において会社側に解雇をちらつかされた場合、サラリーマン側はオドオドしてしまい、堂々と給料アップの要求をすることができません。
しかし、そもそも会社側はそんなに簡単に「解雇」という報復手段に出ることができるのでしょうか。
①民法上の原則
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法上の原則では、解雇は自由とされており、解雇の申入れから2週間を経過することによって雇用契約が終了する(すなわち、解雇の予告期間は2週間)とされています。
民法上の定めでは、会社側が「解雇」というカードを切ってくる可能性がああるということになりますが、大丈夫です。労働契約法によって民法の定めが修正されています。
②労働契約法による修正(解雇権濫用法理)
労働契約法第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法は、民法の原則を修正し、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であると認められ」ることが必要であるとしています。
「客観的に合理的な理由」があるか否かは、通常、労働者の行為が労働契約上の義務違反や就業規則違反に当たるか否かによって判断されます。
「社会通念上相当であると認められる」か否かは、通常、労働者の行為が(ア)解雇に値するほど重大か、(イ)労働者が将来も繰り返す可能性があるか、(ウ)解雇以外の選択肢がなかったのか、等によって判断されます。
この「社会通念上相当であると認められる」ことという判断基準は抽象的であり、明確とはいえません。もっとも、以下の通り、解雇事由によって、一定の基準が見られます。
(ア)労働者の勤務成績の悪化を理由とする解雇
労働者の勤務成績の悪化を理由とする解雇は、もはや使用者に解雇の継続を期待しえない程度に至ったことが必要であると考えられています。
具体的には、労働者の勤務成績の不良の程度が著しく、使用者による改善の努力にもかかわらず容易に矯正できず、さらにそれが将来にわたって継続することが合理的に予測されることと解されています。
(イ)労働者の性格を理由とする解雇
労働者が非調和的な性格をもっていること自体をもって直ちに解雇をすることはできず、具体的な勤務態度が職場規律違反となっているか否かという点から評価されます。
(ウ)労働者の勤務態度、業務命令違反を理由とする解雇
労働者の行為が労働契約上の義務違反や就業規則違反に当たり、かつ、解雇に値するほど重大であったり、労働者が将来も繰り返す可能性があったり、解雇以外の選択肢がなかったりした場合に認められます。
以上をまとめると、解雇規制は相当程度厳しく、「解雇のしやすさ・されやすさ」という点では、サラリーマン側は会社側よりも非常に優位に立っているといえます。
給料アップ交渉について見てみると、給料アップ交渉をしたからといって、労働契約上の義務違反や就業規則違反になることはありません。また、給料アップ交渉をするくらいですから、労働者の勤務成績の不良の程度が著しいということもないでしょう。
そうであれば、会社側の解雇が認められる前提を欠くわけですから、給料アップ交渉においては、会社側の「解雇」という報復手段を恐れる必要はないといえます。
(2)給料交渉の際のサラリーマン側の最終兵器である「退職の示唆」
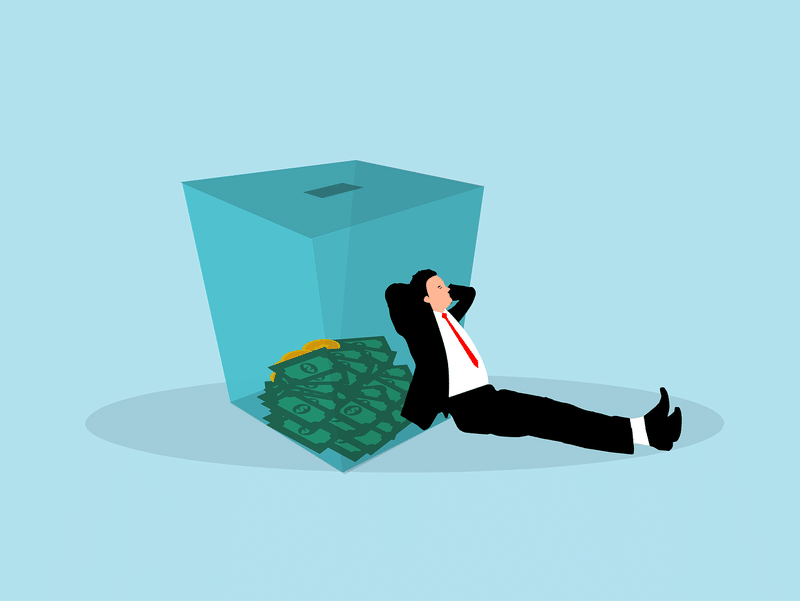
「給料を上げないんだったら、この会社を辞める!」。この「退職の示唆」は、給料交渉の際のサラリーマン側の最終兵器です。一度退職をほのめかしてしまうと、その後の出世争いに響く可能性があり、諸刃の剣であるとも思えますが、何が何でも給料をアップさせるという目的達成の手段としては非常に直接的・効果的であるといえます。
しかし、「実はそんな簡単に会社を辞められなかった…」というのでは、会社側に対する牽制にもなりません。
サラリーマン側の最終兵器として十分に牽制効果があることを確認しておきましょう。
解雇の予告期間の修正
労働基本法第20条(解雇の予告)第1項
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
上述の通り、民法上の原則では、解雇は自由とされておりましたが、労働基本法は、民法の原則を修正し、使用者による解雇は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の賃金を支払わなければならない旨を規定しています。すなわち、解雇の予告期間が30日に延長されています。
一方、労働者による辞職については、労働契約法による修正はなされておらず、民法の原則通り、解約申入れの日から2週間経過することによって終了します。たとえ就業規則において2週間前よりも早い時期の申入れを義務付けていたとしても無効となります。
このように、会社側が定める就業規則に対しても対抗できるほど、サラリーマン側は退職をしやすいといえます。「給料を上げないんだったら、この会社を辞める!」という「退職の示唆」は効果的であるといえます。
(3)まとめ
解雇規制は非常に厳しく、給料アップ交渉においては、会社側の「解雇」という報復手段を恐れる必要はありません。また、サラリーマン側は退職をしやすく、「退職の示唆」は効果的です。
「会社側の報復手段」を恐れず、「サラリーマン側の最終兵器」を隠し持ちつつ、給料アップ交渉に臨みましょう。
(4)参考文献
①西谷「労働法[第2版]」
②森戸「プレップ労働法[第6版]」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
