
森尚也氏インタビュー(2023年4月2日)【前編】
はじめに
2023年、日本サミュエル・ベケット研究会の発足30周年にあたり、記念論集『ベケットのことば』(未知谷、2023年12月)が刊行された。本書の編集が始まった2023年3月、編集委員の有志がベケットに関わる専門家へのインタビューを企画した。ベケット研究会の創設メンバーをはじめとして、他分野でもベケットに関心のある方に、ベケットという作家および研究・仕事に対する姿勢をインタビューし、ベケット研究会ホームページとリンクさせる形で公開しようと考えた。
そこには、研究会に所属する若手・中堅の研究者が、世代の異なる研究者の経験を共有し、日本のベケット研究の来し方を振り返ることによって、今後の研究会のさらなる発展につなげていくという目的がある。しかし何よりも、論文という学術的な形式とはべつのひらかれた形で、ベケットという作家に対峙してきた人間の「なまの声」を聴きたい、その声を広く届けたい、という思いがある。
ここに掲載される諸氏のインタビューには、黎明期の日本のベケット研究の様子や専門的知見だけでなく、それぞれの個人的な経験や思いが溢れている。ベケットという作家の持つ射程は、狭義の文学研究という学術領域を超えて広がっていることが確認できるだろう。
※無断転載は固くお断りします※
森尚也氏プロフィール
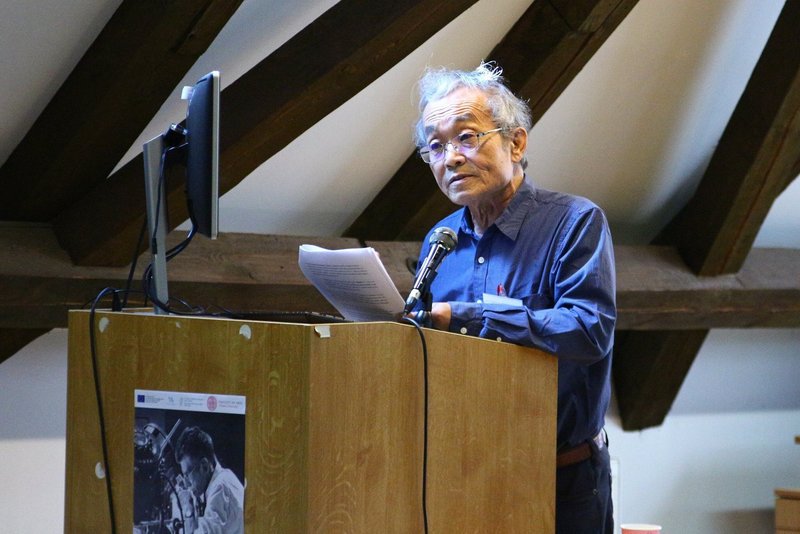
神戸女子大学文学部英語英米文学科 特任教授
日本サミュエル・ベケット研究会創設メンバー
小説『モロイ』や戯曲『ゴドーを待ちながら』で知られるアイルランド生まれの作家サミュエル・ベケット(1906-1989)。その作品に見られるドイツの哲学者ライプニッツの影響を中心に、ベケット文学の思想的射程を研究。1988年8月から1989年3月までに行ったベケット草稿を多数所蔵するレディング大学のベケット・アーカイヴ(国際ベケット財団)での草稿研究がきっかけで、ライプニッツにも嵌まっていく。以後、ベケットとライプニッツというふたつの巨大な迷宮のなかをさまよいつづける。
【前編】
聞き手:宮脇永吏
(桃山学院大学国際教養学部専任講師、ベケット研究会幹事事務局)
ベケット研究を始めたきっかけ
宮脇永吏(以下、宮脇): まず、ベケットという作家にご関心を持たれた経緯についてお伺いしたいと思います。森先生はなぜ、ベケットを研究しようと思われたのでしょうか。
森尚也(以下、森): それは卒論なんですよ。1978年、昭和53年、岡山大学の英文科4回生の春に、ぼくはまだ卒論のテーマを決めていなくて、研究対象を誰にしようか探していました。当時は、フランス文学のサルトルだとか、カミュだとか、あるいはロシア文学に凝っていたので、英文学で好きな作家はいませんでした。卒論の指導教授はヴィクトリア朝のジョージ・エリオットが専門で、今ならその面白さも分かるのですが、当時はだめでした。それで困っていて。探しているうちにベケットの『モロイ』(1951年) *1 と出会いました。でもこの時は、最初読みかけてすぐに投げだしました。なんだこれは、と思ったんですね(笑)。入っていけなかった。夏にかけて他の作家も読みました。ソール・ベローやピンターとかいろいろ。ですが、そのうちまた『モロイ』が気になりだして。卒論の準備としては遅すぎるのですが、秋口から読みだしました。今度は読んでいるうちに、頭をガーンとやられました。何をやられたのかもわからないのですが、強烈なインパクトがあって、これはピンターとかベローにはなかったものですね。
それで卒論はベケットにしました。ただ、卒論では『モロイ』はどうにもできなくて、それで『ゴドーを待ちながら』(1953年初演)について書きました。『ゴドー』ならわかるというわけではまったくないんだけれども、まだアプローチの余地がありました。フランク・カーモード〔John Franck Kermode, 1919-2010〕の『終りの意識』(1967年)と、バート・O・ステイツ〔Bert Olen States, 1929-2003〕のThe Shape of Paradox: An Essay for Waiting for Godot (A Quantum Book, 1978)(未邦訳)における『ゴドー』の構造分析を手がかりに、『ゴドー』の時間構造について書きました。
宮脇: 英米文学の卒論を書くことになって、まずは『モロイ』と『ゴドー』を読みこんだのですね。しかし、じつはその当時凝っていたのはフランス文学やロシア文学だったとのことで、カミュやサルトルが流行っていたという哲学的な雰囲気はあったのでしょうか。
森: ありました。初めて読んだフランス語作品は、カミュの『異邦人』(1942年)でした。第二外国語はドイツ語を選択したので、英訳を片手に、仏文の大先輩(8回生という噂)にフランス語を手ほどきしてもらいながら、友人と3人で読みました。当時、実存主義がブームで、バタイユも含めて人気がありました。
宮脇: 当時、サルトルも読んでいらしたのですか。
森: 学部生のときにも別の読書会でサルトルの『想像力の問題』(1940年)などを読みました。もちろん『嘔吐』(1938年)も。
宮脇: そのような中で、あえて『モロイ』にご関心が向いたのはなぜでしょうか。
森: 20世紀の作家で卒論を書きたかったのと、1970年代に白水社からベケット著作集が出版されて、代表作『モロイ』も図書館にあったので読み始めたんです。それで、ご存知のようにわけが分からない内容で困惑しました。
二回目に読み直して、ベケットの言葉にくらくらしました。何処にも行き着かないというか。第一部でなにかに突き動かされるかのようにモロイは松葉杖、自転車、さらには這いながら進んで行って、最後に森を抜けて溝に転げ落ちます。そこで、「モロイはそこにいていいんだ」、“Molloy could stay where he happened to be” という、あの文章に頭をガーンとやられたんですよね。ものすごく強いメッセージを持っている文章でした。何だかわからないながらも、生を肯定する強いイメージがありました。あの文章にやられたっていうのはありますね。

モロイのおしゃぶり石を彷彿とさせる
宮脇: 最初に『モロイ』の、ベケットの言葉があったわけですね。
森: そうですね。最近「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉をときどき見かけますが、わからないものを許容するということです。これは、ベケットが好きな詩人ジョン・キーツの書簡の言葉ですが、それを心理学者のウィルフレッド・ビオン〔Wilfred Ruprecht Bion,1897-1979〕が再発掘して使いました。ベケットの伝記に書かれていますが、ベケットは1933年6月の父の死を契機に、不眠症や不整脈、呼吸困難や全身麻痺に苦しみます。死の恐怖を感じていました。ダブリンの路上で動けなくなったりもして、親友の精神科医ジェフリー・トンプソン〔Arthur Geoffrey Thompson, 1905-1976〕の勧めで、ロンドンに行きます。1934年から1935年にかけてロンドンで、約18ヶ月間、150回以上のサイコセラピーをビオンから受けることになったんですね。
ビオンの「還元型分析」というのは、症状と結びついた過去の原因を突き止めようというものでした。ベケットは長椅子に寝て、できるだけ古い過去を思い出しました。過去を遡る中で、最終的にベケットは胎児のイメージ、母親の胎内のイメージにまで行き着いた。それは母親の胎内での幸福感、安心感とは正反対のもので、ベケットは「囚われ、閉じ込められ、逃げることもできず、出してくれと泣き叫んでも誰にも聞こえず、誰も耳を傾けてくれない」と回想しています *2 。これがベケットの閉ざされた空間の原点とみてよいでしょう。
宮脇: 学部生時代の先生の心に、人間のネガティブな感情もそのまま受け入れるというあり方が響いたのでしょうか。
森: そうですね。分からないからこそ、これは何だ? という疑問を持ち続けられる。理解できないものもそういう形で受け容れる「ネガティブ・ケイパビリティ」は、当時知らない言葉でしたが、今も疑問は続いていますね。
[注]
*1 サミュエル・ベケットの作品には基本的に英語とフランス語の版が存在するが、以下には英語・フランス語のいずれかで書かれた初版の刊行年のみを記す。
*2 ジェイムズジェイムズ・ノウルソン『ベケット伝 上巻』高橋康也ほか訳(白水社、2003年)217頁。
レディングへ行くまでの経緯
宮脇: ベケットの研究を始めたのち修論を書かれる頃には、もうライプニッツにご関心を持たれていたのでしょうか。それとも、少し後になってライプニッツは出てきたのでしょうか。
森: ライプニッツはもっと後ですね。修論もやっぱりベケットでした。苦労しました。それこそ1980年代、いろんな批評が日本に次から次へと入ってきて、フーコー、ドゥルーズ、デリダとか。でも、自分の批評方法が見つからない。それでいろいろ探っていました。
当時、デカルト研究の山口信夫先生が大学院で『方法序説』の演習を開いておられて、もぐりで入れてもらいました。また、厳しいという噂のサルトル研究者の藤中正義先生の講読もとりました。受講者はぼくと、ジョイスを研究している友人の2人だけで、テキストは『家の馬鹿息子』(1971年)。まだ翻訳が出てないときでした。藤中先生は噂のとおり厳しくて、午後1時から始まる演習は夕方6時、7時まで続くことも。でも、毎回、途中で本格的な紅茶を入れてくれました。お会いしたい!
ただ、ライプニッツはずっと後です。話は長くなりますが、大学院卒業後、岡山県北部の女子大・短大に就職し、教員生活の第一歩を、そこで始めました。そこには、児童教育関連の学科があって、とにかくイベントが多かった。学生主導ということで、学生を事前にキャンプ場に何度か車で連れて行き、学生に計画を立てさせたりしていました。そんな数年間が過ぎたころ、ある日、研究室に旅行業の方が入って来られて「遠足の先生のお部屋はこちらですか‥‥‥?」と(笑)。
そんな中、あのゴンタースキー〔Stanley E. Gontarsky, 1942-〕の草稿研究が出たんです。1985年の The Intent of Undoing (未邦訳)です。批評の方法が定まらなかったなかで、こんな研究があるんだと驚きました。その本でベケットの草稿やノート類がレディング大学図書館にあると分かり、大胆にもというか(笑)、ジェイムズ・ノウルソン教授〔James Knowlson, 1933-〕に手紙を書いて、受け入れてもらえないでしょうかと聞きました。お金もなかったのですが、ブリティッシュ・カウンシルの奨学金があるということを知り、応募しました。この2つの試みが奇跡的にうまく組み合わさり、1988年の8月から89年の3月までレディングに行けることになりました。ラッキーでした。東京のブリティッシュ・カウンシルで面接試験を受ける前日か前々日に、ノウルソン教授から「来てもいいよ」という返事が届いたんですよ。ぼくはその手紙を胸ポケットに入れて面接に行きました。最後はその手紙が効いて面接に通ったのだと思います。
ライプニッツとの出会い
森: ライプニッツとの出会いですが、レディングのベケット・アーカイヴに、『なおのうごめき』(1988年)の膨大な手書きノート群と数種類のタイプスクリプトがありました。この作品は公には1989年3月、ガーディアン紙で全文が公開されるのですが、ちょうどその前年にぼくはレディングに行っていたわけです *3 。今は原則コピーでしか読めませんが、当時は草稿の現物を見ることができました。聞いたこともない作品の草稿に、どきどきしました。それはフランス語の散文から始まり、英語の散文、あるいは途中で戯曲にも展開されたりして、最終的に英語の散文に落ち着くのですが、そのものすごいうねり、それが最後には2000語足らずの短いテキストにまとまるのです。ベケットの文字はご存知のように判読が難しくて、一語を読むのに何時間も、何日もかけることがありました。でもタイプ草稿で最終版のテキストは読めました。書き写して、自分なりに訳しました。それで、『なおのうごめき』を元の草稿から見ていこうと試みていた時に、ある一文に出会いました。英語草稿の初期のあたりで、最終的には “One night or day”、つまり「ある夜、あるいは昼」という文章になるのですけど、草稿段階では “So dark in his windowless cell that no knowing whether day or night”、「窓のない小部屋の中であまりにも暗くて昼なのか夜なのか知ることもできない」 *4というものでした。
この “windowless” という言葉、これはいったい何なのだろう、と疑問に思いました。ベケットの言葉ではない、他の誰かの言葉だろうと。でもそれが誰の言葉であるかは、分かりませんでした。インターネットはまだ使われていない時代でした。
その後、帰国して4年が経った1993年、岡山市郊外の短大で働いていた時です。学長に呼び出されて、「君は来年度、岡山大学の博士課程に行くことになったよ」と告げられました。前日に岡山大学文学部の古川隆夫教授が来られて、「博士課程を新設するため、博士論文が書けそうな学生を求めている」とのことで、入学許可の依頼があったそうです。それで、学長は「許可しておいたよ」、と。ぼくの知らないところで運命が動いて、博士課程に行くことになったんです。
博士課程では何単位か履修することになっていたので、ひとつは哲学を取りました。その授業担当の先生が、後にライプニッツ協会初代会長になられる若きライプニッツ研究者の酒井潔先生でした。「ベケットで博論を書きたいんです」と言うと、酒井先生はご著書『世界と自我——ライプニッツ形而上学論攷——』(創文社、1987年)を貸してくださったのです。それを持ち帰って目次を眺めていたときです。「モナドの無窓性」という言葉がありました。電気が走りました。あの “windowless” じゃないか?『モナドロジー』の解説を読むと、モナドにはドアも窓もなく、他者とコミュニケーションをとる手段はないが、モナドには全てが充足していて、現在も過去も未来もすべてがその中に収まっているという「マーフィーの精神の部屋」そっくりの記述がありました。何年も抱えていた謎がとけた瞬間でした。
1994年のこの出会いについては、「サミュエル・ベケットの〈無窓性〉再考」(神戸女子大学文学部紀要、2017年)に書きましたし、酒井先生の退官論集『モナドから現存在へ』(工作舎、2022年)にも、「ベケットとライプニッツの出会い」というコラムを書かせてもらいました。酒井先生との出会いがなければ、この“windowless”の謎は解けませんでした。しかし、知った後に『マーフィー』(1938年)を読み直してみたら、「モナド」という言葉も書かれているし、『マロウンは死ぬ』(1951年)にしてもテキストにはライプニッツの形而上学的概念がたくさん転がっていたんですね。
この時期に考えていたベケット作品におけるライプニッツの影響について、1995年12月のベケット研究会で発表しました。翌年1996年2月号の『ユリイカ』で、「ベケットのモナド的無窓世界、あるいは闘争する時計たち」を掲載してもらいました。一連の偶然と出会いが重なり、研究がまとまっていきました。
宮脇: 人生において非常に重要な局面に、ライプニッツが関わっていたのですね。先生にとって、ベケットの研究とは別のところでライプニッツに出会ったということになりますでしょうか。
森: そうですね。
宮脇: 酒井潔先生はベケット作品をご存知だったのでしょうか。
森: 酒井先生は、おそらく最初は、ベケットについて詳しくはご存知なかったと思います。でも、毎週ぼくのレポートを真剣に読んでくださり、貴重な助言をもらいました。また、ぼくのベケットとライプニッツ論に関心をもっていただき、岩波の『思想』(2001年10月)のライプニッツ特集や法政大学出版の『ライプニッツ読本』(2012年10月)にも、声をかけていただいたのです。それだけでなく、2013年の酒井先生ご自身の著書で、ベケットの無窓性の現代的意義を、捉え直されました。そしてすべての風景が "imago"(想像されたもの)であるベケットの窓と無窓性を、現象学的にとらえなおす可能性について触れられました。ライプニッツからハイデッガーまで、「窓」は外へ向けた「窓」であったが、ベケットの「窓」は〈内へ向けて開けられた窓〉を示唆する点において、それは現象学にも通じる独自の位置を占める、と *5 。ぼくではとても届かない広い哲学的視座からのベケットの「窓」論には感謝しかありません。
[注]
*3 Stirring Stillはまず、ルイ・ル・ブロッキー〔Louis le Brocquy, 1916-
2012〕のリトグラフとベケットの自筆サイン入りの特別限定版(226部)が1988年に出版された。その後、1989年3月2日、ロンドンで世界初演の朗読会があり、俳優のレナード・フェントンが朗読した。
*4 1988年時点において、森は "windowless cell" を "windowless self"と 解読した。2011年、ベケット研究者のマーク・ニクソン〔Mark Nixon〕とディルク・ファン・ヒュレ〔Dirk van Hulle〕による、ベケットの草稿の電子化プロジェクト(Samuel Beckett Digital Manuscript Project)が始まり、ベケットの草稿は紙媒体とオンラインで公開され始めた。その第1冊目がThe Making of Stirrings Still/Soubresauts and Comment dire/what is the word (University Press Antwarp, 2011)(未邦訳)である。問題の「窓のない」という "windowless" は、草稿番号 MS UoR-2935-1-5 に登場するが、ファン・ヒュレは "windowless cell" と解読した。検討の結果、以後は森も "windowless cell" に修正した。
*5 酒井潔『ライプニッツのモナド論とその射程』知泉書院、2013年。
草稿研究とライプニッツ
宮脇: 先ほどのお話ですと、先生はブリティッシュ・カウンシルの助成に応募されて、ノウルソン教授のお手紙を携えてレディングに行かれたということでした。その時、ベケットの哲学的な読書傾向が読み取れるノート群、いわゆる「フィロソフィー・ノート」 *6 の存在はご存じでしたか。
森: そうではなかったですね。トリニティー・カレッジ・ダブリンにある「フィロソフィー・ノート」との出会いは、ベケット生誕百年祭がベケットの故郷ダブリンで開催された2006年以降です。「フィロソフィー・ノート」にはヴィンデルバントの哲学史経由で、ライプニッツに関係する記述がずいぶんあります。2002年ぐらいから公開されていて、様々な研究者が論文に書いていましたので、気になっていました。しかし、1988年のレディングでの『なおのうごめき』の草稿との出会いが先でした。
宮脇: 現在ですと、手元に「フィロソフィー・ノート」を見ながらベケットが何に関心を持っていたのか知った上で作品を探っていく人も多いと思います。当時、先生は海の中を泳ぐようにして研究を進めていたのですね。
森: そうですね。海で溺れて漂流して、たまたまぶつかった岩がライプニッツだった、そんな感じですね。
宮脇: 先生のご論文を拝読すると、ライプニッツに由来するイメージがベケット作品でどれだけ使われているのかわかります。でも、「無窓性」の概念を先にご存知だったというわけではなかったのですね。
森: 「無窓性」という言葉は知りませんでした。この言葉とぶつかって、そのルーツを探していったら、ライプニッツの膨大な世界が広がっていたというか。ベケットだけでも迷宮的な広い世界ですけども、ひょっとしたらそれを上回るぐらいの迷宮であるライプニッツという、この二つの迷宮を相手にすることになりました。
[注]
*6 この読書ノートについては、以下の文献に詳しい。Samuel Beckett’s ‘Philosophy Notes’, Steven Matthews and Matthew Feldman (eds.), Oxford University Press, 2020.
ベケットとライプニッツの比較研究
宮脇: ライプニッツの哲学を知った後、ベケットの作品中にたくさんの「証拠」を見つけていく過程があったと思います。『マーフィー』においてもそうかと思いますが、こうした発見にはものすごい喜びがあったのではないでしょうか。
森: 酒井先生の哲学ゼミで、ライプニッツ研究関係の文献を教えていただき、それを読んでいると、モチーフは向こうからやってきました。「無窓性」だけでなくヴォルテール的なライプニッツの「最善律批判」や「存在のための闘争」などです。また、「予定調和」や、ライプニッツのいう無意識下の知覚としての「微少表象」もそうです。ベケットがプルースト論で「隠れた数学」"occult arithmetic" というこれまた聞き捨てならない言葉を使っています。それは、ショーペンハウアーがライプニッツの「隠れた数学」としての音楽概念を批判したという文脈で出てきます。でもショーペンハウアーはライプニッツを否定してはいなくて、むしろ評価していました。「隠れた数学」とは、音楽を聴くときの無意識的計算、つまりライプニッツの「微少表象」のことだったと気づいたときには、もうハイになってしまって(笑)。
『マーフィー』では、マーフィーが住み込みで働くことになる精神病棟の独房が、「モナドのように窓がなく」、“windowless like a monad” と表現されています。『伴侶』(1980年)でも、様々な語りを展開していく中で、最後の方ですが、「そこには窓がない」、“The place is windowless” という文が唐突に出てきます。強烈な言葉ですね。ライプニッツへの言及であることがわかってしまうと思うのですが、あえてベケットはこの言葉を残している。
演劇の方を見ても、窓が一種の装置のように使われていますので、やっぱりモナドの「窓がない」を踏まえているのかなと感じます。『勝負の終わり』(1957年初演)でも、暗い部屋に二つの明かりがほとんど入ってこない窓、頭蓋と眼のような閉ざされた空間が舞台です。この系譜を追いかけて書いたのが、2003年の1月にシドニーであった国際ベケットシンポジウムでの論文です。 “Beckett’s Windows and ‘Windowless Self’” ですが、これがぼくの論文のなかで一番インパクトがあったようです。
今年1月には堀真理子さん、田尻芳樹さん、対馬美千子さんが編集執筆された Samuel Beckett and Catastrophe(Palgrave MacMillan, 2023)が出版されました。そこにぼくの研究のまとめに近い論文を書かせてもらいました。「ベケットのモナドロジー」というタイトルです。そこでも書きましたが、コミュニケーションの不可能性という主題は、プルーストにもあります。ドゥルーズは、プルーストにおける無窓性についてはライプニッツを参照しつつ論じていますが、ベケット論ではライプニッツに触れていません。ベケットの無窓性には触れていないのです。その辺についても書きました。
面白いのは、ベケットにおいて、この無窓性も変化しているということです。人とコミュニケーションができない、会話がちぐはぐになるというのはベケットの劇の特徴ですが、それにもかかわらずベケットは、第二次大戦直後の1946年に執筆された『メルシエとカミエ』(1974年)以降、小説と演劇においておかしな2人組を登場させていきます。『ゴドーを待ちながら』がその代表例ですが、ベケットの世界で、2人組がうまくいくはずがない。でも、ベケットはそれにこだわっていく。ぼくはこれをベケットにおける「無窓性の中の連帯」と呼んでいます。ベケットは、ホロコーストでポール・レオン〔Paul Léopoldovitch Léon, 1893-1942〕やアルフレッド・ペロン〔Alfred Rémy Péron, 1904-1945〕を始め、多くのユダヤ人の友人や知人を失いました。その痛みを機に、ベケットは原理的に不可能であっても、人間の連帯、その可能性を探っていたんじゃないかと思います。そのさわりの部分は、2021年に「窓研究所」のWebコラムで「無窓性、あるいは消える小さな窓」*7 というコラムを書かせてもらいました。このテーマを深めて、例えば現代思想のブランショの「友愛」とどう違うか、といったテーマで展開できたらいいなと思っています。
[注]
*7 https://madoken.jp/article/8077/
文学研究と哲学研究
宮脇: ライプニッツの話とも関係することですが、哲学研究と文学研究とは、一応べつの研究領野であると認識されているわけです。先生はそれを両立する形でずっとご研究されてきたということになるかと思います。ライプニッツ研究の学会にも所属されていますが、その両立の難しさと面白さについて、教えていただけますか。
森: うーむ。決して両立なんかできていないですし、両立を目指そうとも思っていないのですが、難しさは感じます。ライプニッツ協会ができたのは2009年4月で、翌年の11月、第二回大会で初めて発表をしました。震えました。参加者も多く、100人近くいたでしょうか。それまで発表されてきた人のペーパーを見ると、みなさんほぼ完成論文を書いているんですね。注も参考文献もできていて‥‥‥まずそれにビビりました。『方法序説』を翻訳されているデカルトで有名な谷川多佳子先生に司会をやっていただいて。厳しい目で見ている研究者もいたと思います。スピノザの上野修先生からは、あらためてデカルトの重要性についての注意喚起もしていただきました。良い経験でした。それでも好意的に受け止めていただいた方もいて、哲学の壁は少しだけ破れました。中に入れたかなっていう感じはしました *8 。
ただ、ベケット研究とライプニッツ研究の違いも知りました。ライプニッツ研究だったら、テキストについては、ゲルハルト版、アカデミー版という底本があります。たとえばゲルハルト版第2巻の30ページだったら、「G. II. 30」とか、表記方法まで決まっているんですね。二カ国語作家ベケットの研究ではどのテキストを使うかほんとうに悩ましいですね。英語版とフランス語版の違いに加えて、英語版にしてもいろいろですしね。最近は英語版については、4巻本の Grove Centenary Edition を使っていますが、この点はライプニッツ研究がうらやましいです。
逆に文学研究の良いところは、その緩さというか、自由に境界を乗り越えていけるところだと思います。ライプニッツもベケットもジャンルを超えていきますが、越境するのは大事なことですね。
宮脇: 哲学の専門家の前でベケットとライプニッツについての発表をされてきた勇気と努力に感銘を受けました。ライプニッツ研究会では、文学研究に関心を持っている方はいらっしゃいましたか。
森: 一般論は言えませんが、文学がとても好きな人もいます。ライプニッツの数学論が専門の研究者と、研究会の二次会で飲みに行ったことがありました。ぼくはお酒が飲めないのに誘われて、アラブのウォッカを飲んで、文学談義をしたことがあります。現ライプニッツ協会会長の稲岡大志さんですが、彼は読書家で、フォークナーの『アブサロム アブサロム』(1936年)の重層的語りについて熱く語りました。また、ぼくが「ライプニッツは、ベケットだけではなくて、他の作家、ボルヘスやピンチョンとか他にも影響していますね」という話をしたら、彼はピンチョンも読んでいました。ボルヘスやプルーストが好きな方もおられて、哲学研究者おそるべし、です。
文学と哲学についてですが、そもそも例えばアリストテレスは『詩学』を書いています。あれは文芸批評ですよね。悲劇の本質とは何かとか、その形式とは何かみたいなことをものすごく丁寧にまとめている。もはや文学なのか哲学なのか、わからないですよね。プラトンの『パイドン』にしても、ソクラテスの死を扱ったものですが、ソクラテスが死ぬ前に、お前は何か物語を創作しないといけない、「ムシュケー」(創作物語)を書かなくちゃいけないと何度も夢に見たという記述があります。死ぬ前に物語を書くって、まるでベケットのマロウンですね!『パイドン』自体が、人間の魂が不死なのか、それとも唯物論的に死んだら魂も肉体も雲散霧消するのかという議論です。酒井先生のお話では、ライプニッツは『パイドン』を読んで影響を受けているとのことでしたが、この主題はベケットの作品にも繋がります。デカルト的二元論なのか、あるいは死んでも記憶が残るライプニッツ的モナドなのか、という話です。
18世紀のヴォルテールとかディドロも哲学者であり文学者ですね。ハイデッガーもヘルダーリンの詩の分析をしています。先に触れましたが、ドゥルーズもプルースト論やベケット論を書いている。もっともベケットは自分は哲学者ではないと何度も言っていますね。『モロイ』を書き始めた動機について胸に刺さる言葉を残しています。「私はインテリじゃない。感覚がすべてだ。『モロイ』をはじめとする作品は私が自分の愚かさに気付いた時に訪れた。その時はじめて感じたことを書き始めた」と。それに続く言葉は、The Critical Heritage の出版稿からは削除されたのですが、マシュー・フェルドマンが論文で引用しています。
「もし私の小説が哲学用語で表現できるなら、私は小説を書く理由などなかったでしょう」 *9 。
[注]
*8 この発表は、『ライプニッツ研究』 第2巻に「砂粒の叫び――ベケット作品における微小表象」としてまとめられ、J-stageで2023年11月より公開中。https://www.jstage.jst.go.jp/article/slj/2/0/2_109/_article/-char/ja/
*9 ガブリエル・ドーバレードによるベケットへのインタビューは、以下に所収。The Ctitical Heritage: Samuel Beckett, Lawrence Graver, Raymond Federman (eds.), Routledge Kegan&Paul, 1987. 削られたベケットの言葉は、フェルドマンの次の論文で読める。Matthew Feldman, ‘“I am not a philosopher.” Beckett and Philosophy: A Methodological and Thematic Overview,”’ in Beckett and Philosophy, Matthew Feldman, Karim Mamdani (eds.), Stuttgart: ibidem Press, 2015, p. 35.
【中編へつづく】
©2023 Samuel Beckett Interview Project
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
