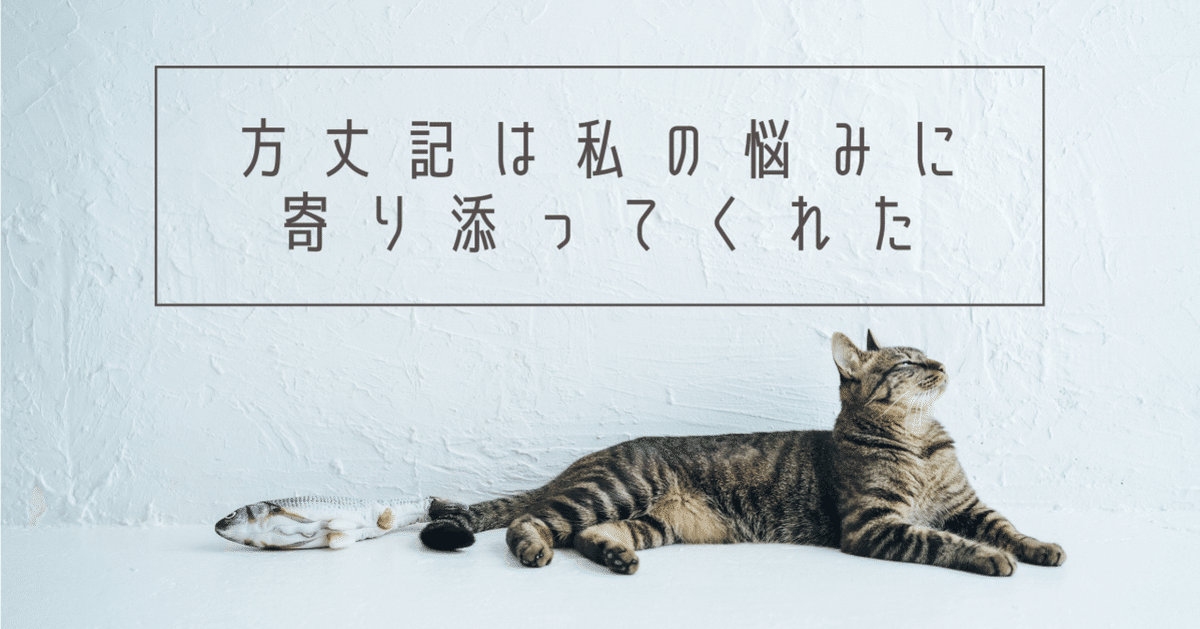
方丈記は私の悩みに寄り添ってくれた
鎌倉時代より日本で受け継がれている「方丈記」。
それを記した鴨長明には、根源的な人間らしさの魅力がある。
きっと、方丈記を読めば、多くの人が、人間の普遍的な悩みに鴨長明が寄り添ってくれている感覚となるであろう。
彼こそが、自分自身の悩みや孤独を追求し続けた者であり、そんな彼の思いは、人々の悩みと深く共鳴する。
そして、そんな私も、鴨長明と同じように、「孤独」という名の人間的な課題と向き合っているんだな〜と方丈記を読みながら考えていた。
第10章 理想の住処はどこにあるのか(自由訳 抜粋)

人間と住居・・・。
それらがいかに、はかなく、悩ましいものであるということは、これまでつぶさに見てきた通りである。
言うまでもなく、住環境や身分の違いなどによって、悩みの種はいよいよ増えて尽きることがない。
たとえば、低い身分にある私が、たまたま高い身分にある権力者の家の隣りに、住むことになったとしようか。
そんな場合、仮にもしわが家に喜びごとがあったとしても、隣家への気づかいから、大袈裟に喜び騒ぐようなことはしないだろう。
反対に、今度は悲しいことがわが家にあったとしようか。
その場合もやはり、隣家への配慮から、大声で泣き叫ぶようなことはしないに違いない。日常生活の立居ふるまいに、いちいちこまかな神経をつかい、息をころしてびくびく暮らす・・・。
これではまるで、鷹の巣の近くに引っ越してきた雀ではないか。
あるいはまた貧乏な私が、たまたま大金持の家の隣りに、住むことになったとしようか。朝から晩まで隣家のことが気になって、ついつい二つの家を比べてしまう。そのうち自分たちのみすぼらしい姿を、恥ずかしいと思うようになる。やがて自分の家だというのに、隣家に向かってぺこぺこ頭を下げ、へつらいながら出入りするようになる。
「おとなりが、うらやましい・・・」
妻や子供、召使いたちまでが、隣家をうらやむようになる。
すると裕福な隣家の者たちは時おり、貧乏な私たちを軽蔑するような言葉を口にするようになる。そんな言葉がもれ聞こえてくると、私の心は動揺し、休まることがなくなるのだ。
もしも家が密集した、街のどまん中にある土地に住んだとすると、近くに火事があった場合、防ぎようがない。
一方、京都から遠く離れた辺鄙な土地に住んだとすると、往き来するのに不便な上、盗賊におそわれる危険もある。
総じて今の世の中は、財力があって権力と勢力のある者は、何事に対してもいよいよ貪欲に事を成す。その一方で、群れることなく、誰にもへつらわず、孤独に生きようとする私のような一匹狼は、世の中の人々からますます馬鹿にされるのだ。
財産があればあったで、失くしはしないか、誰かに奪われはしないかと、心配でならない。貧乏であればあったで、わが身が情けなく、裕福な人間がうらやましくてならない。
他人を頼りにすれば、弱みが生じて自由を失ってしまう。やがては、家来同然に扱われてしまう。世間の流れにしたがうのは、窮屈である。
かと言って、世間の流れにさからうと、「あいつは、頭がおかしい」などと言われてしまう。
いずれにしても人生は、それほど長くはないのである。いったいどんな場所で、どんなふうに暮らせば、わが身をくつろがせ、わが心を休ませることができるのだろう。(p54-57)
第10章 原文

すべて、世の中にありにくく、わが身の栖との、はかなく、あだなるさま、また、かくのごとし。いはんや、所により、身のほどにしたがひつつ、心をなやます事は、あげてかぞふべからず。
もし、おのれが身、数なからずして、権門のかたはらにをるものは、深くよろこぶ事あれども、大きに楽しむにあたはず。なげき切なる時も、声をあげて泣くことなす。新台安からず、立ち居につけて、怖れをののくさま、たとへば、雀の鷹の巣に近づけるがごとし。
もし、貧しくて、富める家の隣りにをるものは、朝夕、すぼき姿を恥ぢて、へつらひつつ出で入る。妻子・童僕のうらやめる様を見るにも、福家の人のないがしろなる気色を聞くにも、心念々に動きて、時として安からず。
もし、狭き地にをれば、近く炎上ある時、その災をのがるる事なし。もし辺地にあれば、往反わづらひ多く、盗賊の難はなはだし。
また、いきほひあるものは貪欲ふかく、独身なるものは、人にかろめらる。財あれば、おそれ多く、貧しければ、うらみ切なり。人を頼めば、身、他の有なり。
人をはぐくめば、心、恩愛につかはる。世にしたがへば、身、くるし。したがはねば、狂せるに似たり。いづれの所を占めて、いかなる業をしてか、しばしもこの身を宿し、たまゆらも心を休むべき。
人間は皆、孤独であり、自由になりたい。

鴨長明が記した住居の話。
私はこの文章の真髄は「自分自身らしく自由に生きていくこと。」であるように感じた。
しかし、そんな自由の先には孤独が待ち受けているものでもある。
それを受け入れ、結局、私たちは不自由を選択してしまうのだろうか?
それとも、孤独と向き合う覚悟ができるのであろうか?
そんなことを頭の片隅で考えながら、方丈記を読めば、私たちの心の中ですっと鴨長明の言葉が響くかもしれない。
*SayaのTwitter:https://twitter.com/l0vu4evr
*異文化の魔法:https://saya-culture.com/
*Medium英語日記:https://saya-culture.medium.com/
皆さんのご支援が今後の活動の大きな支えになります!サポートしていただいたものは、ブログ「異文化の魔法 https://saya-culture.com」の運営やnoteの記事の内容向上に使わせていただきます!サポートよろしくお願いいたします。
