
『徒然草』―名言ハイライト4 第六十八段―(2013年9月1日)
第六十八段は、『徒然草』でも有名な段落で、本文を読んだことがなくても〝大根が助けに来た話〟と言うと、思い出す方も多いと思います。
筑紫に、なにがしの押領使(おうりょうし)などいふやうなるもののありけるが、土おほねを萬にいみじき薬とて、朝ごとに二つづつ焼きて食ひけること、年久しくなりぬ。
※押領使…令外官(りょうげのかん=律令制において、令に規定されていない官をいう。)で、平安時代、諸国の凶徒鎮圧のため設けられた。国司・郡司中から選任。初めは臨時職であったが、承平・天慶の乱(しょうへい・てんぎょうのらん=平安時代中期にときを同じくして起った平将門、藤原純友の反乱)の頃から常設となった(ブリタニカ国際大百科事典)。
筑紫(つくし=現在の福岡県。古くは九州全体を称した。)に住んでいたなんとかいう押領使は、「土おほね」、つまり大根をすばらしい薬だといって、毎朝二つずつ焼いて食べ続け、長いことたった――というのです。
確かに、今でもいます。健康に良いといって、同じものを食べ続けている人。でも、私もそうなのですが、皆さんはこの「なにがしの押領使」のように「朝ごと」「二つづつ」「年久し」ということができていますか。現代は特に、次から次にマスコミが今はこれ、次はあれ、みたいな感じで様々な食品をすすめるので、気づけば昨日とは違うものを食べてはいないでしょうか。また、現代人はとにかく忙しいので、毎朝欠かさずに二個焼いてというのもかなりハードルが高いですよね。
さて、ある時、その「なにがしの押領使」の家に、「敵(かたき)」が隙を突いて急襲してきました。人も少ない時で、彼は「囲み攻め」られます。ところが、突然、家の中に「兵(つはもの)二人出で来て、命を惜しまず戦ひて、皆おひかへし」てしまいました。「二人」の「兵」が、主人のピンチを救ったのです。しかし、彼にはその二人が何者なのかわかりませんでした。
「日頃ここにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戦ひし給ふは、いかなる人ぞ」
「年来(としごろ)たのみて、朝な朝なめしつる土おほねにさうらふ」といひて失せにけり。
(「長年頼りに思って、毎朝召し上がっている大根でございます」と言って消えてしまった。)
子供たちはだいたい〝うそだー!〟と言います。みなさんもお信じにはなれませんか。
しかし、とてもすがすがしい気持ちになりませんか。私は信じます。
何百年も前の知的レベルの人たちだからこそ、逆に、見たままだった、体験したままだったとは思いませんか。私は、ある時期を境に、古文に書かれている不思議な話は、事実であったととらえ、わからないながらもまるごと受け入れるようにしています。
深く信(しん)をいたしぬれば、かかる徳もありけるにこそ。
キーワードは「信(しん)」です。
現代人は何事も疑うことから入りますから(私も疑り深いのを承知の上での発言ですのでどうぞ気を悪くなさらないで下さい…)、理解できないのです。「理解」というのがそもそも間違いです。「信」と「理解」は次元が違うのです。一分の疑いも、理解しようという態度も入らない境地というのを、我々は経験してはいない(できないでいる?)のです。
「なにがしの押領使」が「土おほね」のことを、心から「年来たのみて」、「朝ごと」「二つづつ」焼いて食べるということが、ただもうそれとしてできるかの問題なのです。
しかし兼好は、どうも頭ではわかっていても、あるいは、肯定しつつも、自分はできるかというと、できない人だったのかもしれません。なんといっても、兼好はインテリですかからね。
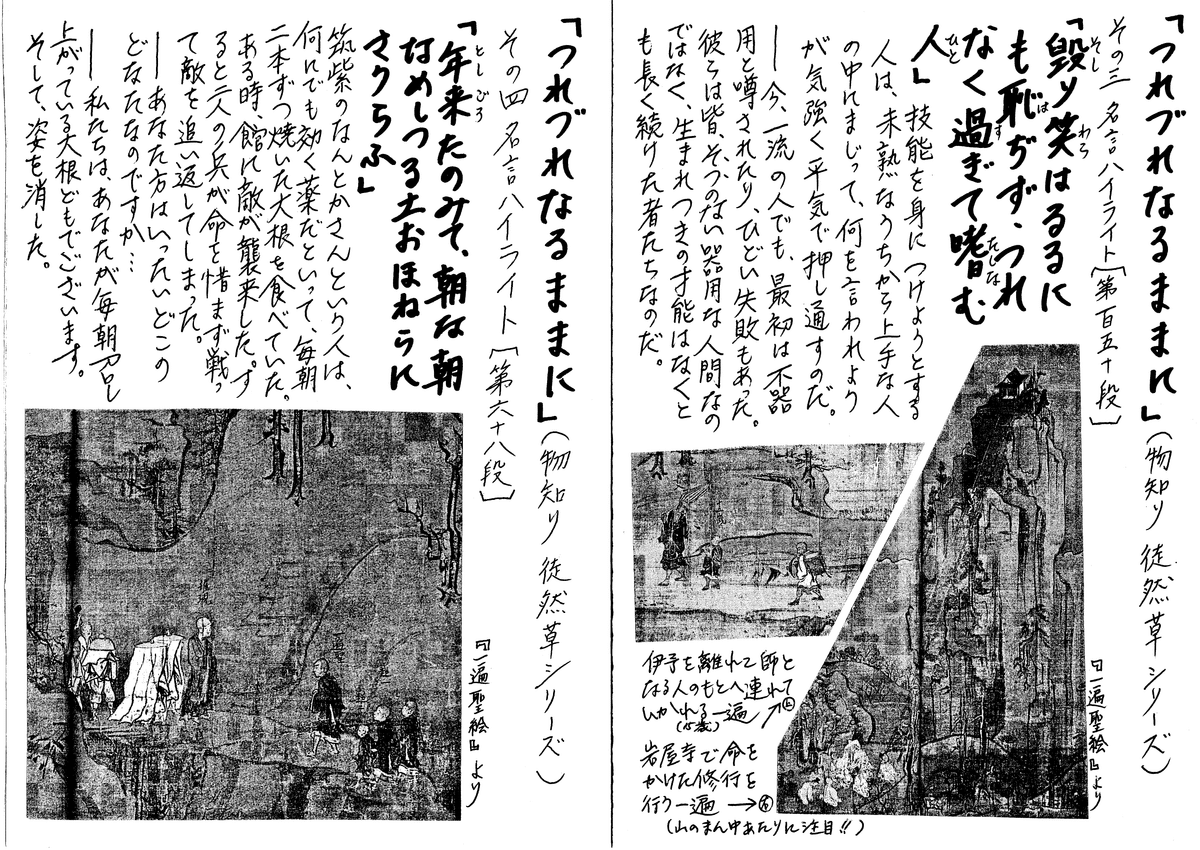
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
