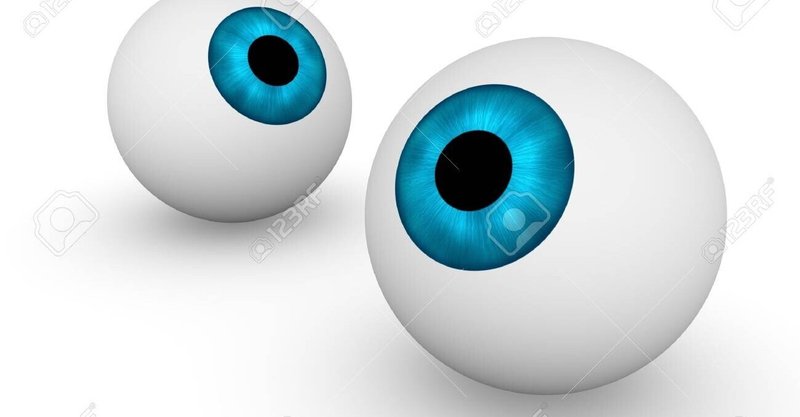
二つの眼球(2021)
二つの眼球
Saven Satow
May, 30, 2021
「君はまるで自分の頭を玩具にしてるんだね」。
小林秀雄『一つの脳髄』
グーテンベルク革命もあり、近代社会の識字率は全般的に向上している。けれども、印刷物であるがゆえに、それを障害になることもある。
本を開き、ページに目を落とす。一列に続いたインスタントラーメンの黒い切れはしが目に映る。
矯正視力は両目共に0.1未満で、中心視野が欠けている。矯正視力0.1未満では、支援ツールなしに、本を読むことができない。支援ツールはない機能をあるようにするものではない。あくまである機能を拡張してそれを補うためのものだ。
また、人間の視野は中心視と周辺視に分けられ、前者が後者より感度がよい。意識的に見ようとする時、中心視野で対象を捉えるべく試みる。ところが、そこが欠けていると、脳は頭や眼球を動かし、見えるポイントを探す。この場合の強制視力0.1未満は周辺視野での値である。
頭が見ようとしても、二つの眼球は逆らう。そこで情報入手には活字媒体の代りに電子媒体を利用し、読み上げソフトを活用する。
だから、耳は目でもある。
パソコンのモニターに向かい、Wordを起動する。黒いユーザーインターフェースを見つめ、キーボードを指で叩く。その配列は体が覚えている。キーの立てる音が透明な空気の中に響く。
緑色のインスタントラーメンの切れはしが画面の左から右に次々に出現する。文字サイズは10.5、ズーム200%、印刷レイアウト、40字×36行に設定してある。句読点を打ったら、変換キーを押す。ただし、適正変換の困難が予想される際にはその前に実行する。
すると、切れはしの羅列が短くなる。1文は40字を超えない。また、1段落は5行以内に抑える。読み上げソフトによる校正をしやすくするためだ。1段落が書き終わるまで、指を動かし続ける。
だから、体も目である。
段落を範囲設定して読み上げソフトにかける。読み上げソフトは斜め読みができない。指定した最初の文字から逐次読み上げる。速度は変えられるが、ざっと読むことはできない。
ソフトの読み上げを聞きながら、自分のイメージ通りに打っているか、あるいは文字変換されているかを確認する。句読点は間を開けて読み上げ、「。」は「、」よりわずかにそれが長い。また、同音異義語でもアクセントの違いから聞き分けることもできる。例えば、「箸」と「橋」の場合、ソフトは前者を「は」、後者を「し」にそれぞれアクセントを置いて読み上げる
誤りに気がついた場合、記憶を参照して問題の個所まで数えながらカーソルを移動し、修正する。苛々することもなく非常な努力で四角な画面から目を離さない。1行や1段落が長すぎると、記憶できない。修正したら、その個所を範囲設定してソフトに読み上げさせる。また、訂正したい場合も同様の作業を行う。直しが終わったら、再び段落全体をソフトに読み上げさせる。ただ、そうして間違いがないはずと思っても、誤字脱字は多い。
読み上げソフトは漢字を読み間違えることが少なくない。例えば、「菅義偉」は「かんぎい」と読み上げる。自身の知識と照らし合わせながら、それが読み間違えにすぎず、適切に漢字変換されているか確かめる。
だから、知も目である。
二つの眼球を動かすと、ぼんやりとした色の塊の染み出した世界の中心が歪み、突然、何かが現われる。元に戻すと、その物体は消える。
視野を始め機械による目の検査では、全般的に、画面の中心に焦点を合わせることが求められる。しかし、中心視野が欠損しているので、それが困難だ。焦点がこれで合っているだろうと当て推量で画面を見つめる。見えないのだから欠損している中心視に焦点が合っていると期待する。だが、検査結果はたいていデタラメな値で、医学的に信用できない。
別に病院の検査機器を玩具にしているわけではない。医者もうまくいけば儲けものと機械検査を捉えている。仕方なく、人力による計測可能な検査の結果で状態を推量するほかない。
視野欠損は周辺が主で、中心は珍しい。検査器具もそれを前提に設計されている。機械検査がうまくできないのだから、状態がシビアなことは医者もわかる。しかし、その客観的なデータが取れない。どう見えているのか確かめるのが難しい。認識が外界と符合しているのかも曖昧だ。けれども、それは世界を捉える一つの認識ではない。
だから、目は自分だけの世界である。耳も体も知もその世界を作っている。こうした一つの世界がこの世界に存在する。
〈了〉
参照文献
小林秀雄、『Xへの手紙・私小説論』、新潮文庫(Kindle版)、1962年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
