
なぜ少女革命ウテナのOP曲タイトルは「輪舞曲−revolution」でなくてはいけなかったのか
※Twitterでやっていた「少女革命ウテナ」シリーズ考察のまとめ
※「少女革命ウテナ」シリーズのネタバレを過分に含みます
はじめに
みなさま、少女革命ウテナ見てますか?
私はずっとチューハイを飲みながらOPとEDを聴いて泣いています。
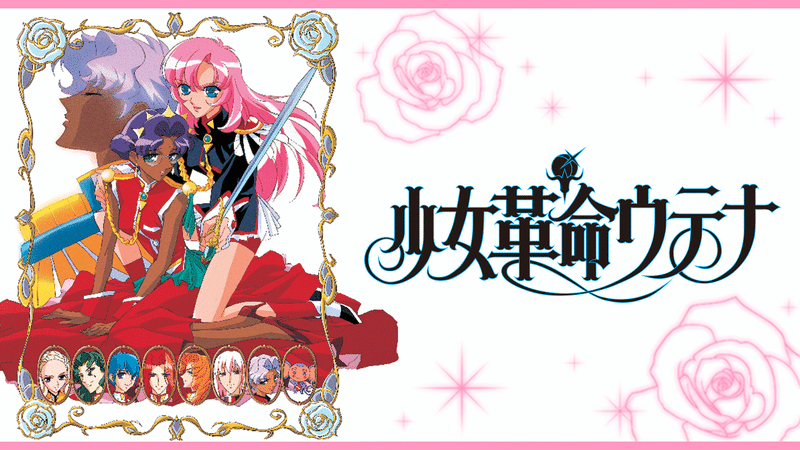
※画像引用 dアニメストアより
今回は作品の内容や演出の考察というより
「なぜこの作品のOP曲タイトルが『輪舞曲−revolution』なのか」
という一点だけを考えたものです。
考えのためにテレビシリーズと劇場版の知識を前提としています。
まあ「こういう考えもあるんだな」という感じで読んでいただけると幸いです。
そもそも「輪舞曲」と「revolution」とは
まずこのタイトルには2つの単語が使われています。
「輪舞曲」(ロンド)と「revolution」
オタクをした方には聞き馴染んだ方もいらっしゃるかと思いますが、
改めてその意味を辞書で調べるとこう書かれています。
ロンド 〘名〙 (rondo 「円い」の意)
① 舞曲形式の一つ。大勢が円く輪になって歌いながら踊る。フランスで発達した。輪舞。
※珊瑚集(1913)〈永井荷風訳〉九月の果樹園「甘き輪舞(ロンド)の列にわれを取巻け」
② 楽曲形式の一つ。異なった楽想の挿入部をはさんで、主題が少なくとも三度繰り返される。歌や舞曲から発達して器楽の重要な形式となり、ソナタや交響曲、協奏曲の終楽章などにしばしば用いられる。回旋曲。輪舞曲。ロンド形式。
※連句雑俎(1931)〈寺田寅彦〉二「第四章が大抵急テンポのロンドやソナタ形式のものになって居る」
(精選版 日本国語大辞典)
これの②です。
アニメ「ヘタリア The Beautiful Would」の主題歌「まわる地球ロンド」や
ボカロ曲「ドレミファロンド」などが分かりやすい例(個人的見解)でしょうか。
ちなみに結婚式などで流れる「テテテテー、テテテテー」で始まる曲
メンデルスゾーン『結婚行進曲』もロンド形式が使われています。
こっちの方が分かりやすいか。
対して「revolution」とは
レボリューション〘名〙 (revolution)
革命。変革。
※新帰朝者日記(1909)〈永井荷風〉二月一五日「革命(レボリュウション)という語はその発音が音楽的刺戟を人に与えると論じながら」
(精選版 日本国語大辞典)
「革命。変革。」
めちゃんこシンプル。
では「革命」とはなんなのでしょう?
(ネット辞書からコピペしたら結構な文量になったので、太字以外は用法として
直接関係ないと考えてください)
革命〘名〙
① (「革」は「あらたまる」意。中国で、天子は天の命令を受けて天下を治めるので、王朝がかわるのはその天命が改まったからとされていたところから) 王朝が改まること。今までの政治権力者にかわって、新しい政治権力者があらわれること。易姓革命。
※本朝文粋(1060頃)七・奉菅右相府書〈三善清行〉「天道革命之運、君臣尅賊之期」 〔易経‐革卦〕
② 被支配階級が支配階級を暴力的に打倒し、政治権力を握り、社会を変革すること。国や社会の組織、形態、権力などを、急激にまたは暴力的に変えること。フランス革命、ロシア革命など。
※西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉外「兵乱に由て俄に政府の革まるを革命と云ひ」
③ すべてのものの状態、作用に、突然根本的な変化が現われること。人の性質、古い伝統などが急激に変わること。
※破戒(1906)〈島崎藤村〉七「精神(こころ)の内部(なか)の革命が丑松には猛烈に起って来て」
④ 社会活動の特定の領域での急激な変化。産業革命、技術革命、文化革命など。
※日本の下層社会(1899)〈横山源之助〉日本の社会運動「此処に恐るべき勢力を以て工業革命は行はれ来りたるは」
⑤ 暦道で、三革(さんかく)の一つ。辛酉(かのととり)の年をいう語。甲子(きのえね)の年を革令、戊辰(つちのえたつ)の年を革運といい、これらの年には変乱が多くあるというので、年号を改めたりした。
※北山抄(1012‐21頃)一〇「革命事 広業申毎辛酉年可当之由、随即左相願文作載也、陣頭令議之場、役是申云、善相公勘文」
※史記抄(1477)三「前代を改を革命と云ぞ。嘉吉元年辛酉は革命之年ぞ」
(語誌省略)
(精選版 日本国語大辞典)
なっがい。一般的用法は②ですが、ウテナ世界の『革命』は③の用法。
つまり「意識革命」ですね。
(特にテレビシリーズ39話やアドゥレセンス黙示録で、
③の用法で使用されている・いたことが明確になりました。
しかし王子対姫、大人対子供、システム対個人の物語でもありますので
②の用法も混ざって使われています。
そもそも③は②から発展した用法だから当たり前と言えば当たり前)

暁生さんでも見て箸休めしていただいて
※©️1997 テレビ東京/読売広告社
長々と申し訳ない。先に進みましょう。
相反する二つの単語
結局まとめると
・「輪舞曲」という言葉は形式が示す通り
「異なる部分を挟みながら、同じ部分が何度も繰り返される」という要素を持つ。
・「revolution」という言葉は
「急激に、突然に、それまで当然だったものが大きく変わる」という要素を持つ。ということです。
「小さな変化はあれど、同じことが何度も繰り返されていく」
「それまで当然だったものが突然ひっくり返る」
この二つの要素は明確に「相反する意味」を持っています。では何故、この相反する二つの単語がタイトルでは並び立っているのでしょう。
それにはこの作品のもう一つの主題とも言える
「『革命』はどのような状況で、どうやって起きるのか」という問い。そして作品が提示したその問いの答え。それが深く関係していると考えています。
革命はどこで起きるのか
「事件は会議室で起きているんじゃない」という偉人の格言()がありますが、
この「革命」もその考えが適用されます。
ウテナ世界で頻出する革命という単語は「意識革命」のことだ、と前述しました。
意識革命は「心」の中で起こるというのが本章タイトルの答えとも言えます。
それならば「心の中で意識革命が起こる」という「革命」は一体「どこ」で起こるのか。
その答えは「日常」です。
日常の中でしか人は生きられず、それ故に心も日常の中にしか存在しない。
だからこそ「日常=現場」なんです。現場でしか事件は起こらない。
日々を生きている日常の中でしか、革命は起こり得ない。
少女革命ウテナシリーズが徹底的に「鳳学園」という舞台の上で描かれているのもそうです。社会に出ていない子供にとって「学校=日常」ですし、学校を舞台にしたアニメが「日常系」とよく呼ばれるのも近いですかね。
人間関係も夢も、社会的要素も個人的要素も全部詰まっているのが「日常」ですから。
そして日常は「少しの変化がありながら、基本的に同じような毎日を繰り返す」という最大の特徴を持っています。
そうです。それは「輪舞曲」という形式が持つ要素ととても似ています。
「輪舞曲」はウテナ達、そして私達が暮らす「日常」を表した言葉だったのです。

くるくる回ってるのも「日常」のメタファーですかね〜
©️1997 テレビ東京/読売広告社
革命はどうやって起きるのか
革命は日常の中で起きます。ならば、どういう道筋を辿って起きるのか。
これは劇場版の「アドゥレセンス黙示録」の内容がかなり分かりやすいです。
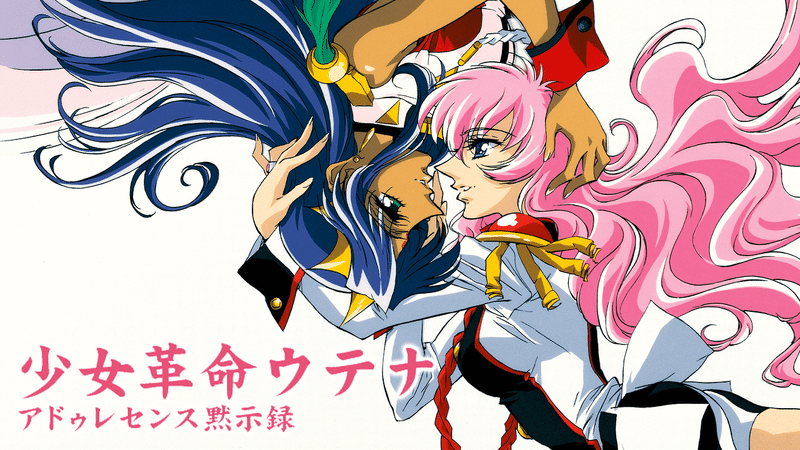
画像引用 dアニメストア
日常と輪舞曲に共通する要素の「少しの変化を挟みながら」という箇所がミソです。テレビシリーズ39話ではラスト、アドゥレセンス黙示録では最初から、
ループ系作品の如く何事もなかったように同じような物語が再開します。
これが「変化を超えた日常」であり、ロンド形式における「繰り返される主題」です。
しかし39話ではアンシーの心に革命が起こり、外の世界に旅立ちました。
「アドゥレセンス黙示録」ではテレビシリーズで起こったアンシーの意識革命を引き継いでいるのもありますし、ウテナや周囲にも変化がありました。その結果、劇場版での日常は微妙に異なった形をしていて、そして世界は違う結末を迎えます。
つまり革命とは、日常の中に挟み込まれる「小さな変化」が積もり積もった結果として起きるということです。
テレビ版のアンシーにとってはウテナの存在や、ウテナ自身の「意識革命」が
「日常の中の小さな変化」であり「革命」への鍵でした。
そして一人一人の心の中で起きた「革命」は、バタフライエフェクトのように他人にも影響を与え、そしてジワジワと広がり、世界全体=繰り返される日常をも変化させる大きな「革命」に発展します。(まさにTake my revolution=革命を受け止めた結果、革命が起こる)
その結果、当然ながら日常は、物語は変化する。
「アドゥレセンス黙示録」でウテナとアンシーが共に「外の世界」に旅立てた事。
生徒会メンバーのミッキーが「やがて僕たちもあなた達に続くかもしれません」と言った事。
すべては日常の中の小さな変化、一人一人の革命の結果。
日常の中で革命が起き、日常によって革命が起こる。
日常なくして革命なし。
それがこの作品が提示した問いに対する、作品の答えなのです。
まとめ
少女革命ウテナは革命を描いた作品。
日常なくして革命なし。
つまり輪舞曲の中でしかrevolutionは起こらない。
だからこそ
「少女革命ウテナ」OP曲タイトルは「輪舞曲-revolution」でなければいけない。

長々と言いましたが、つまりそう言う事だと思います。
「少女革命ウテナ」という日常の中の小さな変化によって革命を起こした人が、
少しでも読んで楽しんでいただければ幸いです。
そして「輪舞曲-revolution」という曲をこの世に生み出してくれた
作詞・歌唱の奥井雅美さん
作曲・編曲の矢吹俊郎さん
タイトルを考案した原案・監督の幾原邦彦さん
その他「少女革命ウテナ」という作品に関わった全ての方々に、20数年越しの感謝を伝えたいです。
ありがとうございました。
入りきらなかったおまけの考察
はい、脱線とも取れるおまけの考察です。
・revolutionの頭文字が大文字でない事。
あくまで革命は結果的に行われるもの=「文」の最初に来ていないとも読めます。
・単語の間にある−(ハイフン)にも
複数の単語から構成された熟語にあって、それらの語を1単語として扱うにはまだ構成する語の独立性が残っているというほどの結合のときに、構成する単語の間に置かれる。(wiki)
こういう用法があるので、二つの単語が一つの熟語とされているとも読める。
・もっと根本から言うと沢山の人間が輪になって踊る「輪舞」も、ウテナやアンシーらほぼ同じメンバーだけがずっとぐるぐるまわって踊っているという、作品世界の閉じられた空間のことを表現してるとも言えますね。メタフィクション!
ここまで付き合っていただきありがとうございました。お疲れ様です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
