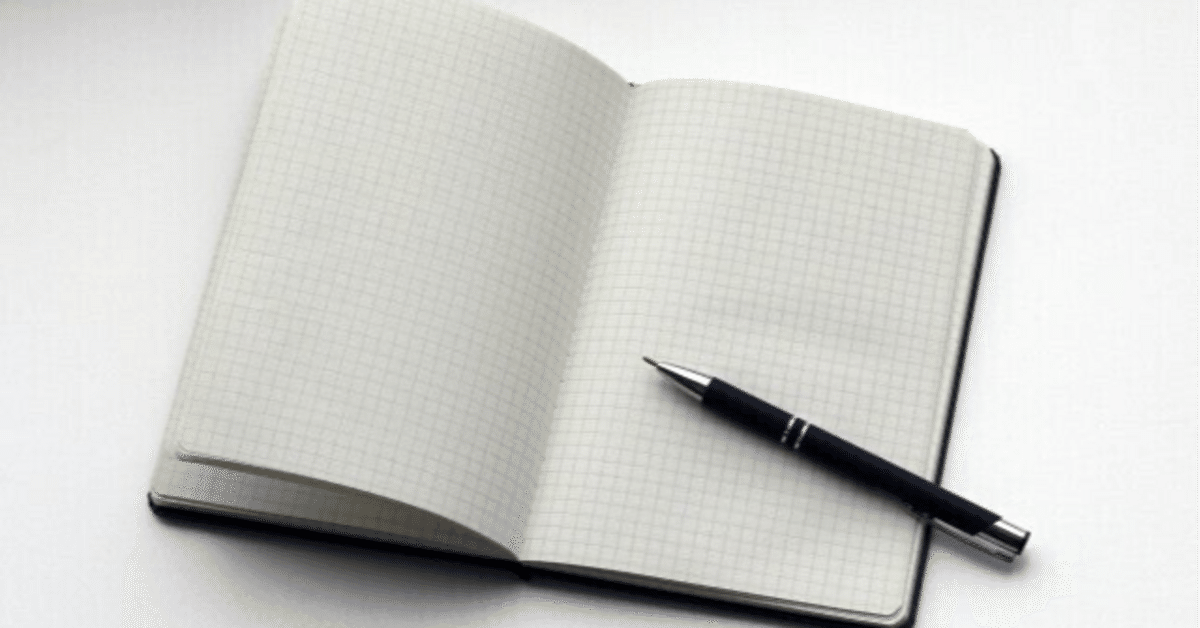
あらゆる文章をコミュニケーションツールとして捉え直す 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.776
特集 あらゆる文章をコミュニケーションツールとして捉え直す〜〜〜SNS時代の「日本語の作文技術」について考える(第9回)
現代の文章力とは、名文や美文を書く能力ではありません。現代の文章は、小説のように広く多くの人に読んでもらうためのものではなく、特定少数の人たちとのコミュニケーションのためのツールなのです。ときには上司や部下、取引先などビジネスの相手とのコミュニケーションだったり、ときには家族や恋人、友人とのメッセンジャーでのやりとりだったり、ときにはSNSでフォローしてくれている人たちとのコミュニケーションだったり。
言い換えれば、SNSが普及した現代は、あらゆるものがコミュニケーションに吸い込まれて言っている時代とも言えるでしょう。
写真が典型的です。インターネットが広まる以前、デジカメもまだなかったころは、写真は過去を記録するためのものでした。アナログなフィルムカメラでは、写真のコストは安くはありませんでした。フィルムや現像焼き付けの価格は高く、保存するのにも場所が必要だったのです。しかしデジタルカメラが普及し、さらにスマートフォンによって写真を撮影するという行為がきわめて日常的になり、消費者から見れば写真という記録のコストは限りなくゼロに近づきました。
この結果、記録ということの意味が希薄になっています。いつでもすぐにスマホで撮影できるし、自分が撮影しなくてもまわりにいるだれかが撮っている。SNSを漁れば、同じ場所で同じ時間に撮られた写真を見つけることだってできます。だから「これは記録しなきゃ!」というモチベーションそのものが下がっている。
では記録や保存のためではないのであれば、なぜ私たちは写真を撮るのでしょうか?
日本ではさほど盛り上がっていませんが、アメリカではインスタグラムと並んで人気があるとされるスナップチャットという写真SNSがあります。上記は古い記事になりますが、創業者のエヴァン・スピーゲルが写真の意味について語った内容が紹介されています。
「歴史的には、写真は非常に重要な記録を残すために撮られてきた。今日では、スマートフォンについているアプリによる『(インターネットに)つながっているカメラ』のおかげで、写真は人と"会話"をするために撮られている」
「なので、子どもたちが何百枚もの写真を撮っている場面に出くわしたら、しかもあなた自身は写真になんか撮らないだろうと思うようなものを撮ってるとしたら、それは彼らが写真を使って他のユーザーと"会話"をしているからだ」
コミュニケーションのための写真、ということなのです。しかも2010年代以降にスマホとSNSが合体したことで、写真はつねにリアルタイムなものとなりました。2010年以前はデジカメで撮影し、それをパソコンに取り込んでSNSにアップロードするという面倒な作業が必要だったので、SNSでシェアされる写真はつねに過去の記録だったのです。
しかしスマホの普及で、写真はつねにリアルタイムでSNSでシェアされるようになりました。
「スマートフォンが『その瞬間に表現する(instant expression)』というアイデアを強化した。それは今現在アナタがどこにいて、何を感じているか、をその瞬間にシェアするというものだ。これはアイデンティティと結びつくので非常に重要だ。というのも、アイデンティティはソーシャルメディアの核となっているものの一つだからだ」
「『ためていく』という考えの下ではアイデンティティとは『私がこれまでしたすべてのこと』によって形成されていたが、『その瞬間に表現する』というアイデアはその定義を『私が今この瞬間に誰であるか』へと変えてしまった」
昔のフィルムカメラは、家族や友人など「過去のだれか」を記録し保存するものでした。しかしスマホの自撮りは、「今この瞬間の自分」を誰かに伝えるコミュニケーションツールになったのです。
写真のこの変化と同じことが、文章にも当てはまります。かつて文章は、作家や新聞記者、編集者など一部の限られたプロのものでした。一般社会の人が文章を書く機会など、学校を卒業してしまえばほとんど皆無だったのです。
だから谷崎潤一郎や三島由紀夫など文豪が著した「文章読本」は、作家予備軍などプロを目指す人をターゲットに書かれていました。これはジャーナリストの本多勝一氏が書いた「日本語の作文技術」も同じで、明らかにジャーナリストやノンフィクション作家など、文学ではない硬質で簡潔なジャーナリスティックな文章を書こうとしているプロをターゲットにしています。
こういう古い文章入門は、文章がコミュニケーションツールへと変わった現代にはあまり当てはまりません。ただし、作家志望の人にはいまでも有効だとは思いますので念のため。
では、コミュニケーションツールとしての文章術とはどのようなものになるのでしょうか。ここで、文章についての本シリーズで少し前に書いた「わかりやすく簡潔な文章は、生成AIに取って代わられる」という話を思い出してください。生成AIはインターネットの大量のテキストを学習し、そこから平均的なものを生成しています。だから平均的な文章はすべて生成AIが書いてくれる時代になりつつあります。ビジネスで使うようなメールの文章、プレゼンの文章などの定型文は、今後はすべてAIの仕事になっていきます。
だから平均的な文章を書けるようにしましょうという文章術も、不要になっていくのは間違いありません。
そこで大事になってくるのは、生成AIには書けないような「外れ値」の文章です。外れ値だけれども、読み手とのコミュニケーションで読み手を納得させ、心を動かせるような文章です。それはどのようなものか。
本シリーズでは、それらを「思いも寄らないものを二つ結びつけることによる説得力」や、突拍子もないけれど情熱が伝わることによる人心掌握などで説明してきました。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
