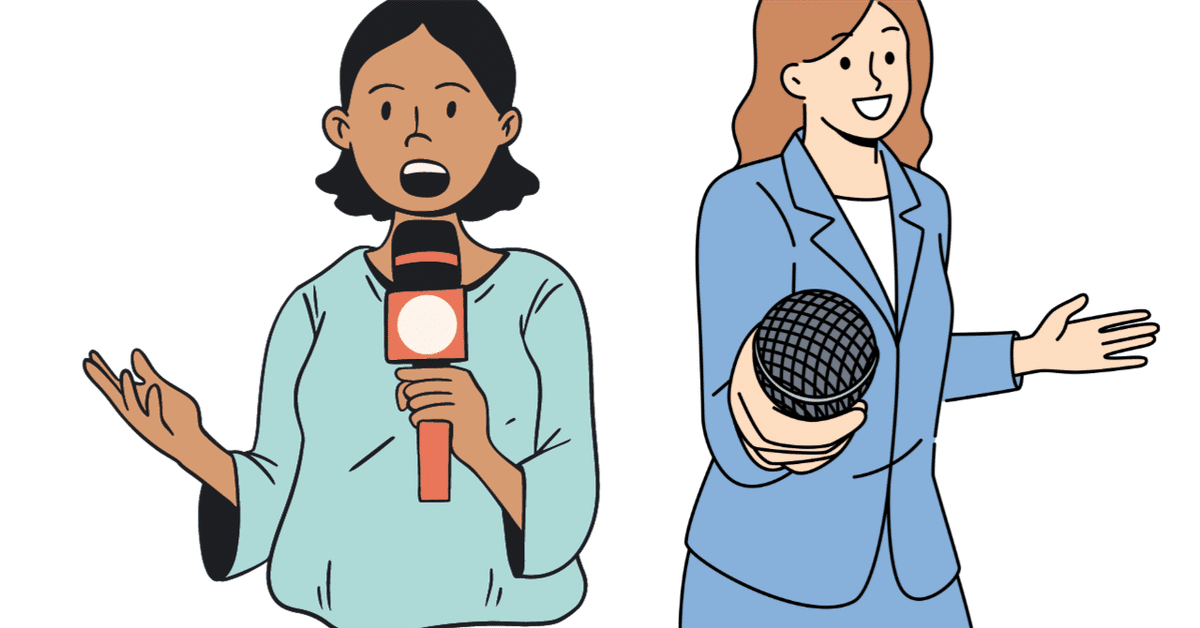
なぜワイドショーのコメンテーターはクソリプみたいな発言をするのか 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.810
特集 なぜワイドショーのコメンテーターはクソリプみたいな発言をするのか〜〜〜マスコミとネットと政治の関係の未来を考える(2)
テレビのワイドショーに出てくるコメンテーターとは、いったいどのような存在なのでしょうか。そもそもコメンテーターは必要なのでしょうか。
ワイドショーをときどき目にすることがあるのですが、コメンテーターの人の発言を見ていると奇妙な感慨が湧いてくることがあります。どのようなものかというと「ツイッターでこういうクソリプよく来るなあ」という感慨です。ワイドショーの内容がくだらないことに情けない気持ちを抱く人は、特にネット上には多いのではないかと思いますが、その心理の背景には「コメンテーターの発言がクソリプそっくり」ということがあるのではないでしょうか。申し訳ありませんが口汚い言い方をすれば、「公共の電波を使って、クソリプ垂れ流してるんじゃねえ!」
ではなぜ、コメンテーターはクソリプを発するのでしょうか。テレビに出ているコメンテーターだって、いちおうはいろんな分野で名をなした人たちばかりのはずです。なのになぜクソリプのようなどうでもいいコメントを意気揚々とドヤ顔で言いたがるのか。
その答は、テレビにおけるコメンテーターという存在のそもそもの意味にかかわってきます。ここからそれを解きほぐしていきましょう。
ところで、わたしは過去にフジテレビの午後のワイドショーに準レギュラーでコメンテーターとして出ていたことがあります。また近年はネット放送のアベマプライムにレギュラーコメンテーターとして出演しています(アベプラは決してワイドショーではなく「討論番組」だと思いますが)。またその他のニュース番組やワイドショーなどに、コメンテーターとは異なる「専門家」枠として出演した経験はたくさんあります。
それらの経験から感じたのは、コメンテーター枠と専門家枠はまったく異なるものであるということ。つまりコメンテーターの位置づけというのは、決して「専門家としての意見」を言う人ではないということです。たとえばアベマプライムでは、MCと司会者に加え、コメンテーターとゲストという4者の組み合わせになっています。これは他のワイドショーなどでもよく見る構図です。
ワイドショーでは、このゲストが専門家として発言する人という位置づけです。それに対してコメンテーターは、専門家の意見に対し、庶民的な目線で反応をする人、という位置づけになっているのではないかと思います。つまり「一般視聴者の代弁」というのが、コメンテーターの役割なのです。
そう捉えれば、ものごとへの無理解やレベルの低い感想、見事にズレたクソリプのような発言ばかりをコメンテーターが発するのも、理解できてきます。それらのおかしな発言は、「レベルの低い一般視聴者なら、そういう反応をするだろう」とテレビ制作者やコメンテーター自身が認識しているからなのです。
つまりコメンテーターの意見は、テレビがイメージする「大衆の意見」そのものなのです。それはテレビが考えている世論ととらえてもいいかもしれません。しかしこれが問題なのは、実際の世論とはイコールではないということです。極論を承知で言ってみれば、それはナマの世論の中から、クソリプだけを抽出したようなものであると言えるでしょう。テレビや新聞がなぜナマの世論をクソリプと見誤っているかというと、ひとことで言えば「一般社会を見下している」からでしょう。
では、ナマの世論というのは、どのようなものでしょうか。
ここで補助線を引きましょう。メディア史の研究者として知られる佐藤卓己・京都大教授の著書「輿論と世論 日本的民意の系譜学」(新潮新書、2008年)です。この本は、世論というものの歴史的な意味について徹底的に解き明かしたたいへんな名著です。とくに秀逸なのが、われわれが世論ということばを聞いて「よろん」「せろん」と読んでいることについて、それは単に読み仮名のブレなのではなく、もともと「よろん」と「せろん」はまったく異なるものだったという驚くべき指摘がされていることです。
同書によると、もともと「よろん」は「輿論」で、「せろん」は「世論」。前者の輿論は公的な意見(public opinion)の訳語。そして世論は、世間的な感情(popular sentiments)の訳語でした。しかし戦後に当用漢字のルールが定められて「輿」の字が使えなくなり、どちらも「世論」という漢字に統一されてしまった。これが誤解と混同の始まりだったということです。
この「輿論と世論」のAmazonレビューに、「まさにこれが重要なのだ」というポイントを突いた内容のものがあったので引用しましょう。
「本書を読んで、あらためて、お前の考えていることは、輿論 (public opinion) を構成しうるのか、単なる世論 (popular sentiments) なのかと問われれば答えに窮する自分がいることに思い至り、大変恥ずかしい思いをした」「一方で、開き直ってみると、では今の日本で、どこに輿論を見いだすことができるのだろうかという素朴な疑問が頭に残った。概念としての『輿論』は想像可能なのだが、これこそが輿論の形成過程だと言えるものを正直なところイメージできない」
現在のワイドショーでは、社会を代表すると思われているコメンテーターが世論を形成してしまっています。テレビタレントでもあるコメンテーターが何かを発言すれば、それはスポーツ紙などのメディアにも紹介されて拡散され、「人々はこのように考えているのだ」と政治家に伝わってしまう。しかしコメンテーターの発言は、しょせんは「世間的な感情」(popular sentimetns)にすぎません。決して「公的な意見」(public opinion)ではないのです。
しかしこういう「世間的な感情」を写し絵のようにそのままテレビに映していれば、視聴率のとれるコンテンツになってしまうのは間違いありません。たとえばテレビ朝日「モーニングショー」の玉川徹さんが目を三角にして政権批判をしている姿は、そういうのを求める視聴者にとってはまさに「我が意を得たり」でしょうし、怒りはそもそも気持ちの良い娯楽でもあるのです。ワイドショーは「世間的な感情」を電波で増幅させることによって、世間に浸っている人々に快楽を与えているということも言えます。
これはまさに古代ローマの「パンとサーカス」のサーカスであり、玉川さんが目を三角にして批判してる人を視聴者が「そうだそうだ!」と快楽とともに叫ぶというのは、ライオンの前で脅える原始キリスト教徒を見世物にするのに近い快楽なのかもしれません。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
