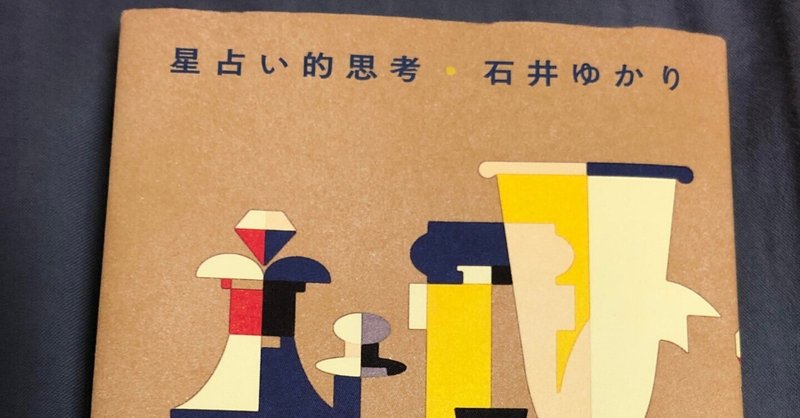
石井ゆかりさんの言葉と私の「名前」。
石井ゆかりさんの『星占い的思考』(講談社)を読んだ。12星座の各章を楽しみにして読んだのだけれど、私は特に射手座の章が心に響いた。12星座のどの章も、占いとは関係なく、どの章を読んでどう思ったかが自分を知るヒントになるような文章だった。
そしてそれ以上に、その後の4篇がとてもよかった。どれもいまの社会に向ける彼女の気持ちがこれでもかと伝わってくる文章だった。特に『占いという「アジール」』は、研究室でデータと格闘していた頃に読みたかったと強く思った。
私はもともと占いが好きなのだけれど、石井ゆかりさんは特別な存在でもある。高校生の頃から「筋トレ」(石井さんが運営していた個人サイト、2019年に閉鎖)を読んでいて、イベントで直接ご本人にお会いして「ひとこと占い」もしてもらったほどのファンである。学生の頃に彼女の文章を浴びるほど触れられたことは大きな財産だった。年月が経って彼女の文章も少しずつ変わったと思うけれど、この本もやはりとても素敵だった。
☆☆☆
さて、12星座占いをはじめとして、占いとはいわば「分類」の話である。もちろん究めていけば「その人自身」を読むことができるのだろうけれど、12星座もハウスもアスペクトも、ある程度までは「分類」の域を越えることはできない。
私も彼女の著作のすべてを読んだわけではないのだけれど、石井さんは、12星座それぞれの「固有性」を伝えるだけでなく、星座に関わりなく存在する人間の「普遍性」も同時に伝えようとし、さらには両者を「統合」しようとしているように私は感じている。
それは『12星座シリーズ』や『星読み+』にも表れているし、だからこそ『星なしで、ラブレターを。』や『愛する人に。』のような作品を創り出し、それらが広い支持を集めたのだと思う。
そして、彼女が「固有性」と同時に「普遍性」を大切にしているのは、彼女がさまざまな場で語っている、「占いは「ナシ」である」という言葉と表裏一体ではないかとも思う。現代社会で占いを、そして言葉を扱うことへの責任や矜持のようなものがそこにある、と。
「固有性」と「普遍性」、その両者に向き合うということ。
☆☆☆
なぜ、この文章を書こうと思ったのか。石井さんの言葉と私自身を重ねるのはおこがましいのは承知のうえで書いてみる。
私は病気の治療を開始してから10年が経つが、実は未だにはっきりとした病名はわかっていない。もちろん役所での手続きなどに必要なので一応の診断名はついているのだが、自分の病気が「精神病」の範疇なのか、「精神病に近い感情障害」なのか、「たまたま精神病のような症状が現れた心因反応」なのかわからないのだ。これは詐病だとか誤診だとかそういう話ではなくて、いまの精神医学では「(場合によっては10年以上の)長いスパンで診ないと病名はわからない」という考えが主流になっているから、だそうだ(もっとも、これは主治医の説明なので、私も完全にそれを鵜呑みにしているわけではないが)。
だから、私は自分の病気にはっきりと「名前」をつけることが(現段階では)できないし、そうすることにあまり意味がないとも思っている。そして、仮に「名前」がついて同じ「名前」のひとに出会えたとしても、その背景にあるものは全然違う。そうやって「固有性」ばかりを追い求めてしまうと、私は孤独なままだし行き詰ってしまう――それが10年経ってわかったことだ。
だったら、「名前」に関係なく誰かとのあいだに存在する「普遍性」を求めていくほうがまだ希望や救いがあるのではないかと考えるようになった。もっとも、れが簡単に達成できれば世界はもっと平和なはずだし、それはそれですごく大変なことはわかっているのだけれど。
だから、石井ゆかりさんの文章は、「名前」を持たない自分の背中を強く押してくれる。私は孤独ではないし行き詰ってもいないのだということを信じて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
