
- 運営しているクリエイター
#戦略

わたしを「趣味:戦略」に駆り立てた1冊:『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』(6/6)【間違いだらけの読書備忘録(8)】
こんにちは、さらばです。 現在、以下の本について備忘録を書いています。 楠木 建『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』 1~5はこちら。 非合理な合理性を組み込む第5章"「キラーパス」を組み込む"では、ストーリー上の「起承転結」の「転」にあたる「クリティカル・コア」について書かれています。 この耳慣れない言葉である「クリティカル・コア」を、筆者はこう定義しています。 そして「クリティカル・コア」が「クリティカル・コア」として機能するための条件を二つ挙げていま

わたしを「趣味:戦略」に駆り立てた1冊:『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』(5/6)【間違いだらけの読書備忘録(7)】
こんにちは、さらばです。 現在、以下の本について備忘録を書いています。 楠木 建『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』 1~4はこちら。 誰になにを提供するのか第4章"始まりはコンセプト"では、ストーリーをつくるときの起点である「コンセプト」についての説明が行われます。 前回触れた「高く売るか、安く作るか、ニッチを狙うか」という点についても最初に考えるべき点なのですが、これはどちらかというとビジネスとしての「方針」に近いと思います。 誤解を恐れず俗っぽい言い
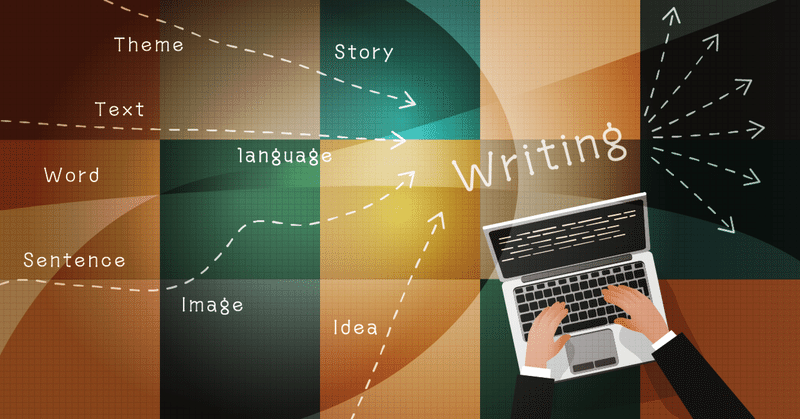
わたしを「趣味:戦略」に駆り立てた1冊:『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』(4/6)【間違いだらけの読書備忘録(6)】
こんにちは、さらばです。 現在、以下の本について備忘録を書いています。 楠木 建『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』 1~3はこちら。 三種類のシュートでゴールを狙う第3章"静止画から動画へ"から、筆者のいう競争優位性として絶大な価値を発揮する「戦略ストーリー」についての話が本格的に始まります。 第2章で語られたSPやOCという競争優位性そのものは単なる静止画であり、これに対して優れた戦略ストーリーは動画である、という話です。 個別のSPやOCといった静止

わたしを「趣味:戦略」に駆り立てた1冊:『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』(3/6)【間違いだらけの読書備忘録(5)】
こんにちは、さらばです。 現在、以下の本について備忘録を書いています。 楠木 建『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』 1、2はこちら。 競争優位性を語る上での前段第1章は「戦略とはなにか?」について書かれていたのですが、第2章"競争戦略の基本原理"は、「競争優位性とはなにか?」について書かれています。 本書のタイトルにもある本題は第3章からです。そこまでに166ページを費やすあたりが、この本の文脈の豊富さを物語っています。 第2章の内容について、まずはざっ

わたしを「趣味:戦略」に駆り立てた1冊:『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』(2/6)【間違いだらけの読書備忘録(4)】
こんにちは、さらばです。 現在、以下の本について備忘録を書いています。 楠木 建『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』 1はこちら。 戦略はバズワード本書の第1章、"戦略は「ストーリー」"を読んだ時点でわたしがしみじみ思ったのは、 「"戦略"というのはつくづくバズワードなんだなあ……」 ということです。 バズワードとは「もっともらしく使われるが、定義が曖昧な言葉」で、流行り言葉の大半がそうだったりします。例えば昔で言うとIT化とかCloudとか。IoTとか

