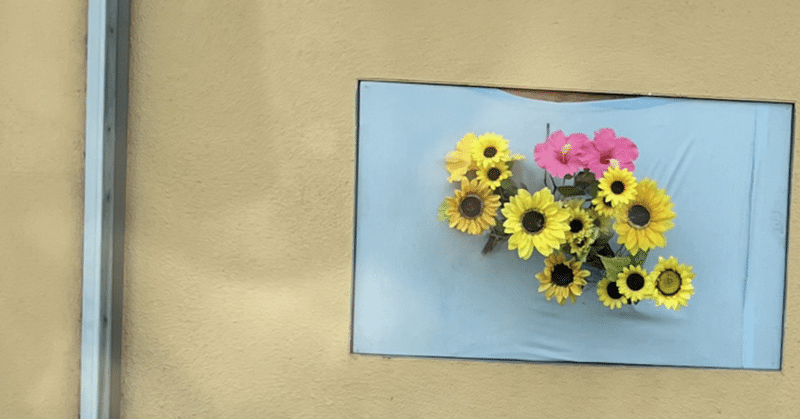
"戦争を知らない世代"のジレンマ
77回目の終戦記念日です。
サブスク中心に映画を結構観てるんですけど、
この時期になると毎年一本はWWⅡ関係の日本映画を観るようにしています。
"戦争を知らない世代"と言われる僕たちですが、
そういうラベリングをされることで、
何かから許されたり、
何かから逃れられたり、
何かから糾弾されたり、
何かから見放されたり、
何かから見て見ぬふりをされたり、
過度にそういうことがあるんじゃないかなってふと思いました。
僕も1980年代の生まれですし、
そもそも戦後すぐの産まれの方も80歳近くなってるわけで、
現行の日本社会はほぼほぼ"戦争を知らない世代"で成り立っています。
第二次大戦以降に生まれた僕たちは、
確かに戦争を"体験"はしていません。
ただ、"知らない"ことはないんじゃないか。
こう思います。
戦後の平和教育を受けてきた僕たちは、
WWⅡにおける日本の惨状を"知って"はいます。
ヒロシマ・ナガサキはもちろんのこと、
地元がいつ大空襲にあったかとか、
概論としての始まりと終わり、
インパール作戦などの国外での惨事、
様々な情報を"知って"います。
興味を持って見ていけば、おそらく戦争体験者より"戦争"のことを"知って"います。
WWⅡ以降も世界中で戦争は起きています。
現在のウクライナとロシアの争いも、紛れもなく"戦争"です。
特にウクライナの惨状はIT技術の進歩によって情報発信の精度と速度が格段に上がっていますし、プロパガンダの側面も同時に伝播しやすくなっている面は忘れてはいけないとはいうものの、
これまでの"戦争"よりもかなり身近なものとして感じられていることは間違いないと思っています。
僕たちがこの戦後77年経ったいま考えなくてはいけないことは、
自分たちが戦争を知らない世代ではなく、
戦争を体験していない世代、
もっといえば自国が侵略にあっていない、若しくは侵略を行なっていない世代、
ただそれだけであるということをどう自覚するかなんじゃないかなぁとぼんやり思います。
日本の戦後教育がWWⅡに特化してるということは別に否定するつもりはなくて、
ただそこだけに特化した教育をベースとして現在の平和を語ることはちょっと無理があるし、
その教育を受けてきた側の自分たちはむしろそのズレに気づいてる人多いんじゃないかなってことを認識しましょうよって話です。
経験に勝る学びはないわけで、
第二次大戦中の日本のことはちゃんと継承していくべきです。
テレビはもっと特番バンバン打ったらいいし、
サブスクも特集してほしいし、
映画館も1週間とかだけでいいから過去作の再上映とかやってくれていいんじゃないかなと思います。
(ちょうど今日なにか都内で映画ないかなと思ったけど特段見つからなかったこともちょっと残念でした。渋谷の野火くらいかな。)
体験者の方々がご存命のうちに伝えていただけることはメディアを通じてどんどん発信していくべきだと思いますし、
それと同時に体験者任せにせずに、様々な角度からの"戦争"の検証を僕たちは知らなければならないなって思います。
そのうえでいまのウクライナの問題、台湾有事の問題、北朝鮮、、あらゆる日本列島を取り囲む戦争の脅威に関して考え、各々の意見を持って議論をすることができたらいいんじゃないかなと。
"戦争を知らない世代"なんて一括りにしてしまうけれど、80年も経ってればその中でも3世4世と子孫がいるわけで、
知らない世代の中でも直接体験者から話を伺えている世代だってかなり少なくなってきます。
いまの20代あたりがギリギリかもしれません。
そうなると体験の語りべのような存在も今後重宝されていくのかなと思ったりしますし、自分もその1人になれるのかな、ならなきゃいけないなとも思います。
"知らない"ことが決して免罪符にも罪状にもなってはいけないなと思う、2022年の8月15日です。
(はじめてのnoteオリジナルでした)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
