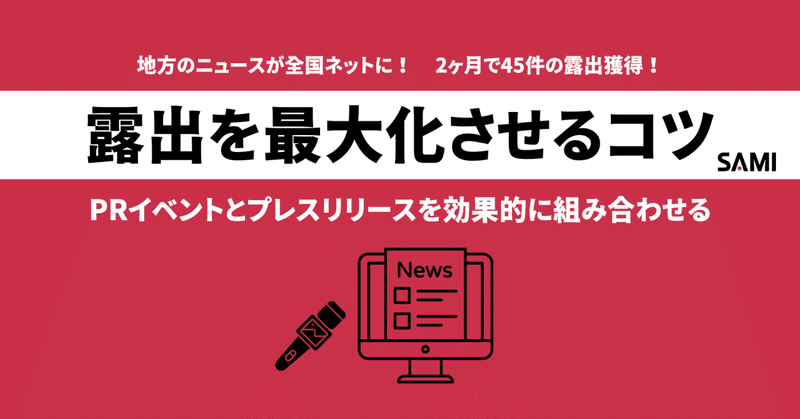
地方のニュースが全国ネットに。2ヶ月で45件の露出獲得。PRイベントとプレスリリースを効果的に組み合わせて露出を最大化させるコツ。
SAMIが実施した実際のPR施策の結果を交えてコツを解説
新商品をローンチするタイミングでメディア発表会やプレスリリースを出してたくさん取材を獲得したい!!と考える企業の広報さん向けに、「PRイベントの開催とプレスリリース配信を効果的に実施する方法」を、SAMIが実際にイベントに招致した媒体数や実際にOA・記事化された数と合わせてお伝えします。
私たちSAMIは、2023年5月に出雲市さんを含め計5者で合弁会社「株式会社People Cloud」を設立しました。プレスリリース配信とメディア発表会を効果的に組み合わせて施策を打っていった結果、発表会での取材からの露出が26件、WEB記事の転載も含めると45件の露出となりました。ローカル媒体での取材から全国ネットでの再放送にも繋がりました。発表会から2ヶ月以上たった今でも、このニュースに関してお問合せがあるほど、メディアさんからも注目される大発表となっています。この事例からリリース配信を含めて、効果的なメディアさんへの情報提供のタイミング・内容など、露出を最大化させるためのコツをお伝えします。
露出を最大化させる5つのコツ
SAMIの場合、5月31日のメディア発表会で発表した「新会社People Cloudを設立しました」というニュースに最も注目してもらえるように計画を立てました。具体的にしたことは、この5つです。
本番リリースとジャブリリースに分ける意識を持つこと
案内状を配信してイベント開催について徹底的にメディアさんに周知すること
案内状と同時にその周辺情報(合わせて取材したくなる情報)を提供すること
一番注目してほしいプレスリリースは、イベント当日に紙とWEB両方で配信
地方開催で参加するのが難しい場合や途中退席になった記者さんへのフォローアップ
①本番リリースとジャブリリースに分けて考える
本番リリース/ジャブリリースとは
本番リリースとは、一連の情報発信の中で最も注目してほしい"企業の一大
ニュース"です。ジャブリリースとは、本番リリースに注目してもらうための"ブースター情報"のような位置付けです。ブースターを打つことによって、メディアの方々からの注目をジワジワを集めることに役立ちます。SAMIは「5月31日にジョイントベンチャーを設立します」というここ最近での一大ニュースを出すことが決まっており、そのニュースを最大化させたかったので、そこに向けてその周辺情報/裏情報をジャブリリースで発信しました。
本番リリースの前に配信した3本のジャブリリース
SAMIが2023年3〜4月の約1ヶ月に渡って3本のジャブリリースを配信しています。
【ジャブ①】SAMIが島根進出します+資金調達します(2023年3月22日)
【ジャブ②】SAMIの夢は、テクノロジーを活用して世界を平和にすること(2023年4月1日/April Dream)
【ジャブ③】SAMIが島根県出雲市でハッカソンを開催します(2023年4月24日)
【本番】SAMIが新会社「People Cloud」を設立しました(2023年5月31日)

ジャブリリースには、個々のニュースのほかに"軸情報"を入れる
3本のジャブリリースで共通して伝えていることは「SAMIの既存事業(プロダクト開発)に加えて、東欧から流れてくるIT人材を日本の地方都市に呼び込み、これを事業化して運営していく」ということです。これを今回の一連のリリースの"軸"にして、SAMIが出雲でこの移住事業をやっています!ということそのものを訴求します。もちろん、これだけではニュース性が無く、リリース配信できないので、この軸を中心に、その時々でのニュースに仕立てます。資金調達をして島根にオフィスを作り本格的に島根進出をしたり(ジャブ①2023年3月22日)、国籍や年齢、性別にとらわれずSAMI Peopleと働き、人々の豊かな人生を作るのがSAMIの夢だと語り(ジャブ②2023年4月1日)、ハッカソンを開催したり(ジャブ③2023年4月24日)などでニュースを作り、ジャブリリースを打ちます。
下記は、実際のジャブリリースの中で伝えている"軸情報"の部分を抜粋しています。
SAMIは、東欧の高度ITエンジニアやデザイナーを活用して、自社のWEBサービス開発、ソフトウェアの受託開発、デジタルプロダクトを生み出す新規事業開発に携わってまいりました。今後は、これらの既存事業に加えて、ウクライナ侵攻による世界情勢の変化を受けて流出してくる東欧の高度ITエンジニアを日本の地方都市に呼び込み、彼らの高度な技術力が日本企業で継続的に活用されるような体制を構築し、事業化を進めます。この新しい事業は、今後、SAMIの主力事業の一つとして、地方から日本企業の国際化を後押ししてまいります。
■2023年より、本格的に日本企業の国際化を推進します
「国際化」とは、日本で開発したプロダクトを海外に持っていくことに限りません。SAMIが考える、企業の「国際化」とは、日本企業が社内で海外人材を活用するにあたり、民族や言語が異なる人々でも受け入れることができる社内ルールや業務ツールを整備していくことであり、ひいては多様な人々を受け入れる価値観=企業文化が醸成されることです。むしろ、このような環境の中でこそ、海外でも普及するサービス・プロダクトが開発できると信じています。このような「広義の国際化」を、地方から日本全国に浸透させていくことを目指します。
それに向けて、SAMIが2023年に具体的に着手したいと考える事業は、現在SAMIが抱えている東欧の高度エンジニアの人材プールから、日本企業がれぞれ抱えているプロジェクトのニーズに合わせて適切な人材をアサインし、日本企業のプロダクト開発チームを国際化するというものです。これを実行するために、まずは、東欧のITエンジニアたちに、日本の企業文化に対する理解を深めてもらうために、オンラインで日本語のレッスンを提供し、訪日プログラムの企画をしています。
このような事業を、まずはSAMIの開発拠点のある出雲市で先駆的に展開し、成功事例を作ることに全力を注ぎたいと考えています。まずは、出雲を中心に”SAMI People”の輪を作っていき、将来的には、この輪を日本全国に拡大していきたいと考えています。私たちは、企業の成長を売上のみで評価するのではなく、いかに”仲間 - SAMI People”を増やしたか、という視点でも自らの企業価値を評価しています。
SAMI Japanが推進する、東欧の高度ITエンジニア向けの日本移住プロジェクト「Hello, Yaponiya」の一環としてハッカソン「Hack Izumo」を開催し、出雲市を外国人目線で見てより住みやすくするためのシステムやプロダクトを開発します。成果発表会となるDEMO Dayでは、東欧のエンジニアより、日本企業向けに日本語でのプレゼンテーション発表があるほか、実際に東欧のITエンジニアの活用を考えている方を対象に、来日エンジニアとの個別面談会や人材活用相談会の実施も予定しています。
「Hello, Yaponiya」は、東欧の高度ITエンジニア向けの日本移住プロジェクトです。国内向けには、高い技術力を持つ外国人IT人材の活用や採用を検討している日本企業を対象に、東欧の高度ITエンジニアの活用を提案しています。これによって、ウクライナ侵攻による世界情勢の変化を受けて流出してくる東欧の優秀な人材を日本の地方都市に呼び込み、彼らの高度な技術力が日本企業で継続的に活用されるような体制を構築することを目指しています。
この過程で、だんだんと事業の詳しい中身や事業名が決まってきたり、実際に発表会に合わせて東欧の人材が出雲にやってくるという話も持ち上がり、メディアさんに提供できる情報も増えてきたのがわかります。(逆に伝えたい思いが強くなりすぎて、毎回のリリースに盛り込む情報量が多くなりがちなのは今後改善していかなければなりません・・・)
②案内状を配信してイベント開催について徹底的にメディアさんに周知する
案内状を配信したら、必ず各媒体の担当者にイベントの話を通す
イベント当日の1ヶ月〜2週間前を目処に、メディア向けに「取材案内状」を出します。これはプレスリリースとは別物で、「発表会を開催するので、取材に来てください」とメディアに直接案内するための文書です。SAMIからはイベントの3週間前にメール+電話でまずお知らせをして、そこからはこのニュースを担当してくれる記者(ベンチャー企業担当、東欧エリア担当、地方創生担当など、その媒体でホットなネタには担当者がいます)につながるまで毎日電話をかけ続けます。
民間+自治体の2つのチャネルから取材招致
今回は出雲市さんとの共同でのイベント開催だったため、SAMIと出雲市の2つのチャネルを活用して集客していきました。出雲市さんからは、1週間前にリマインドとして同内容の案内状を出雲市記者クラブに投げ込んでいただきました。この2つのチャネルを使ってイベントへの集客を徹底しました。
実際に配信した案内状を大公開
案内状には、タイトル、開催日時・場所、オンライン配信の有無をはじめ、新会社設立に至った経緯や、発表会の式次第、登壇者(その時点で登壇が決まっている人のみ)など取材したくなるような情報を盛り込みます。


ただし、あくまでも取材のための案内なので、イベント当日に配信するリリース(本番リリース)に入れている情報や発表会当日に登壇者がスライドで発表する内容(新会社名、事業戦略、出資企業、それぞれの出資比率など)は案内状からは読み取れないようにします。ニュースの全てを伝えるのではなく、あくまでも取材招致することが案内状を配信する目的です。
結果、事前に12媒体17名の記者さんに参加表明いただきました(当日不参加となったが、のちにあらためて取材/記事化いただいた媒体を含める)。
下記PRTIMESさんのサイトで、案内状の書き方や書く上でのコツなどをわかりやすくまとめてあるので、ぜひチェックしてみてください。
③同時に、合わせて取材したくなる周辺情報を提供する
周辺情報の提供で取材全体に深みが出る
案内状を配信して、取材招致に動き出すタイミングで、またブースターとなる情報提供をしていきます。それが"合わせて取材したくなる周辺情報"です。せっかく発表会をするのに、出来上がったニュースが「出雲市にPeople Cloudという新しい会社ができました。事業内容は、~~ということです。」だけでは面白みに欠けます。そこで、これまでのジャブリリースで軸情報として発信してきた「東欧のIT人材を出雲に招き入れる」という文脈を詳しく取材してもらえるチャンスがないか探します。「東欧のIT人材を出雲に招き入れる」という情報単体だけでは、リリースとして成立することがありませんが、今回は新会社でこの「東欧のIT人材を出雲に招き入れる」事業を展開していく、という強力な一大ニュースが生まれそうな一歩手前のタイミングで、東欧のIT人材が実際に出雲市にやってきた様子を映像や写真に撮るチャンスがあれば、ぜひ取材したい!と動いてくれる可能性が高いです。メディア的には取り扱える情報が多ければ多いほど、視聴者や読者にわかりやすく情報を編成することができ、また、記者自身のニュースの全体像に対する解像度も上がり、ニュースを正しくダイナミックに届けることができます。
周辺情報への取材は、信頼関係のある記者さん限定で案内
ただし、ここでの注意点は、この情報を提供できる相手は、これまでにお付き合いがあった記者さんで、すでにSAMIについてある程度興味を持ってくれている人限定です。始めましての方誰彼構わず、ニッチな企業情報を広く伝えすぎてしまうと、ニュースの質を確保するのが難しくなります。記者の方々も一度に案内状やら他の取材情報やらが届いてしまうと、何を取材してほしいのか処理するのに時間がかかってしまいます。ニュースの全体像を理解せずに報道されてしまっては、私たちの望まない文脈での露出になりかねません。始めましてのメディアの方には、まずは発表会に来ていただき、直接お会いして、メディアさんの興味に沿った情報をその都度提供していくことをお勧めします。
解像度高く報道してもらうために、提供した具体的な情報
このように、発表会とは別の取材チャンスを与えることによって、単に新会社の設立を発表するだけのニュースにとどまらず、その新会社が設立に至るまでの社会の流れや、将来的に出雲でどんな面白いことをしていくのかなど、解像度高く報道してもらいやすくなります。
特別に提供したのは主に下記のような「いつ」「どこで」「誰が」「何をする」という5W1Hのうちの「5W」に関する情報です。残りの1H「どのように」の部分を実際に取材してもらい、映像や写真に収めてもらう狙いがあります。
東欧のIT人材が何人で、いつ出雲に到着するのか
東欧のIT人材は出雲で何をするのか、取材できそうなシーンがどのタイミングであるか
当日のハッカソンでは、東欧のIT人材のうち誰がどのお題のハッカソンを担当しているのか
東欧のIT人材の中で取材に答えてくれそうな人がいるかどうか

この情報提供により、大手TV局から2件、地方紙から1件の取材申し込み(発表会への出席とは別)があり、東欧のIT人材が出雲大社を視察している風景や、現地のIT企業を訪問している様子などを取材いただきました。私も実際に取材に同行させていただき、現段階で撮り溜めた取材映像と、出席予定の発表会での取材事項とをどのように組み合わせてVTRや記事を作っていくか、など記者の方々と都度相談しつつ進めました。
最終的に、一つのニュースが全国ネットやワールドワイドに展開が決まる時に重要なことは、企業が伝えたいニュースの全体像と記者さんが見ているニュースの全体像が完全に一致しているということです。記者さんが作ろうとしているニュースが、過不足なく、私たちが伝えたいないようなのか、ということを常にお互いに確認する気持ちで進めることが大切だと感じました。
④一番注目してほしいプレスリリースは、イベント当日に紙とWEB両方で配信
イベント当日の受付で、紙に印刷したリリースを手渡し
一番注目してほしいプレスリリース=本番リリースですが、発表会の当日までに本番リリースを紙に印刷して用意しておき、会場の受付でプレスキットとして配布します。プレスキットにはリリースのほか、取材に役立つ情報を一緒にファイリングします。SAMIが新会社の設立発表会を開催したときに同封したものは、登壇者指名と肩書き、登壇の順番(プログラム)、登壇者が発表する内容、撮影上の注意事項などです。紙で印刷して手渡しする事によって、発表会の最中に手元で肩書きや名前などを参照しながら、発表を聞くことができます。(この時にすでに記事を執筆しながら発表を聞いている記者さんもいます。)
※紙に印刷すると考えると、本番リリース1本がA4用紙4枚にも・・・泣
※本番リリースを含むプレスキットの印刷とアッセンブリ(複数の情報を1部ずつファイリング)には時間がかかるので、早めに原稿を仕上げて印刷作業に移りましょう!当日来場(取材)予定の記者の人数に合わせてプレスキットを用意します。SAMIが企画していた発表会には、12媒体17名の記者さんがいらっしゃる予定だったので、12部+予備5部で17部ほどのプレスキットを準備しました。

発表会終了後すぐに本番リリースがWEBで公開されるように配信予約しておく
メディア発表会の終了時刻を本番リリースの配信時刻として、前日に配信の予約をしておきます。イベントで発表された情報は、発表された瞬間に情報解禁となり、参加してくださった媒体がWEBメディアだった場合、早いところではイベント終了後の数十分で記事化されてしまいます。TV番組や新聞でも概ね当日〜翌日にかけてニュースになります。(ありがたいことです!)ですので、その情報源となる本番リリースは、WEB上できちんとリアルタイムで公開されていることが望ましいです。これによって、注目されたいプレスリリースが1~2日の短期間で一斉に記事化・OAされ、露出を最大化する効果があるのと、企業の情報発信の信憑性を確保する効果があります。

ここまでで、イベント終了直後に9件のOA/記事化をいただき、WEB記事の転載を合わせる19件となりました。
⑤地方開催で参加するのが難しい場合や途中退席になった記者さんへのフォローアップ
YouTubeやZoomでオンライン配信をする
SAMIが実施したような地方でのPRイベントは、在京メディアさんにとって会場まで足を運ぶことが難しいですし、メディアの方は速報の対応などで、イベントの最中でも都合によって途中退席になってしまう方もいらっしゃいます。そういった記者さん向けに、オンラインで参加できる方法や、アーカイブを後日確認できるようにすると喜ばれます。 SAMIは今回出雲市さんとの共同でのPRイベントだったということもあり、出雲市YouTube公式チャンネルからの生配信をしました。出席いただいたメディアさんには、イベント終了後に公開アーカイブとしてYouTubeのURLを案内し、VTRや記事制作にお役立ていただきました。

PRイベント終了後に、事後リリースを配信する
事後リリースとは、どのような発表会だったかというレポーティングをプレスリリースを通して報告するものです。イベント当日に参加できなかったメディアさんの中には、事後リリースの配信を待って記事化を検討してくださるところもあります。
事後リリースは、イベント本番を迎える前にあらかじめ原稿をほぼ仕上げておく必要があります。「ほぼ仕上げる」とは、タイトル、サブタイトル、本文の内容に至るまで、イベント本番を見てみないとわからない部分(例えば、登壇者のコメントや当日にしかわからない誰かのリアクション)以外は、すべて仕上がっている状態にすることです。当日は、イベントの進行を見つつ、その原稿を埋めていきます。また、差し込み写真も当日でないと手に入らないので、イベント終了後にカメラマンからデータを大急ぎで転送してもらう必要があります。
SAMIの場合は、私が手一杯で事前に原稿を「ほぼ仕上げ」ておくことができず、イベント終了後にゼロから原稿作成に取り掛かり、イベントからかなり時間が経ってからの事後リリースの配信となってしまいました・・・(ぶっちゃけ1ヶ月くらい開いてしまいました・・・)それでも、SAMIからの事後リリースを待ってくださるメディアさんがいて、、泣 事後リリース配信後に1件記事化いただき、そこから1件転載もしていただきました。
発表会とハッカソンの2部構成だったため、事後リリースも前半(5枚)と後半(8枚)に分けて作成。それでも長かった・・・。
発表会から時間が空きすぎたのでニュースレターとして、温度感の高そうなメディアさんにメールで配信し、PRTIMESでの掲載はせず。新会社のHPのニュース欄に掲載しました。

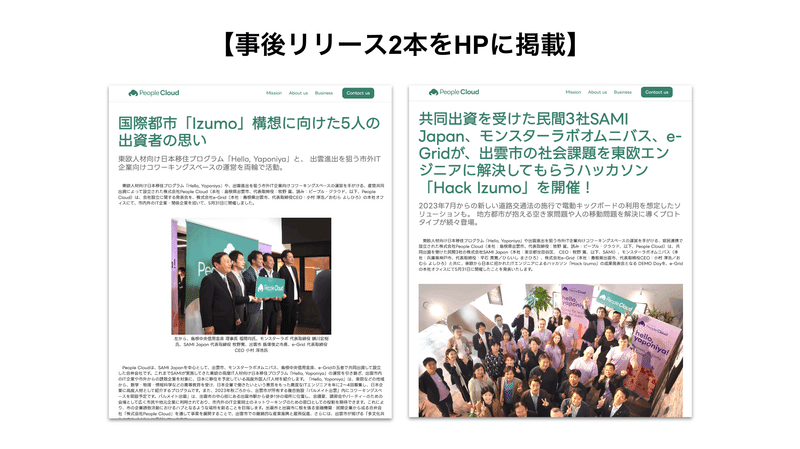
【まとめ】プレスリリースとイベントを組み合わせ、一大ニュースに注目を集めて露出を最大化。周辺情報にも言及してもらい、報道内容の質をぐんとアップ
このように、PRイベントとプレスリリースの配信をうまく組み合わせて、PR施策を実施していった結果、新会社People Cloud設立のニュースは「東欧からIT人材がきた!」という会社設立にまつわる社会的な文脈も絡められ、島根県や山陰地方を飛び越え、全国ネットの番組やラジオで放送いただき、海外ニュースにまで展開されることになりました。
国内だけの露出結果を見ていくと、イベント終了後も追加での取材やVTRのほか番組への転用(再放送?)があり、最終的にOA / 記事化が26件、WEB記事の転載も合わせると45件ほどになりました。この間に全国ネットの番組での再放送やラジオ放送も決まり、視聴者の方々からも多くの反響がありました。
また、露出数が伸びたということ以外に、放送内容や記事の一つ一つの内容をとってみても、SAMIが伝えたい内容を丁寧に伝えてくださっており、質の良い露出が多かったと実感しています。単に「SAMIが新会社People Cloudを設立しました」というだけでなく、「東欧から出雲にIT人材がやってきた!」という部分が意味する社会的な背景と地方都市に与えるインパクトなどとも絡めて興味深い内容で伝えてくれています。このように露出の量だけでなく、質も担保するための2つの大きなポイントは、"軸情報"をジャブリリースに落とし込み絶えず訴求することと、発表会以外の取材チャンスについても情報提供することです。これによって、記者がニュースの全体像を把握する助けになります。
以上、とてもざっくりとした指南書になってしまいましたが、広報・PR担当のみなさんのご参考にしていただけますと幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
