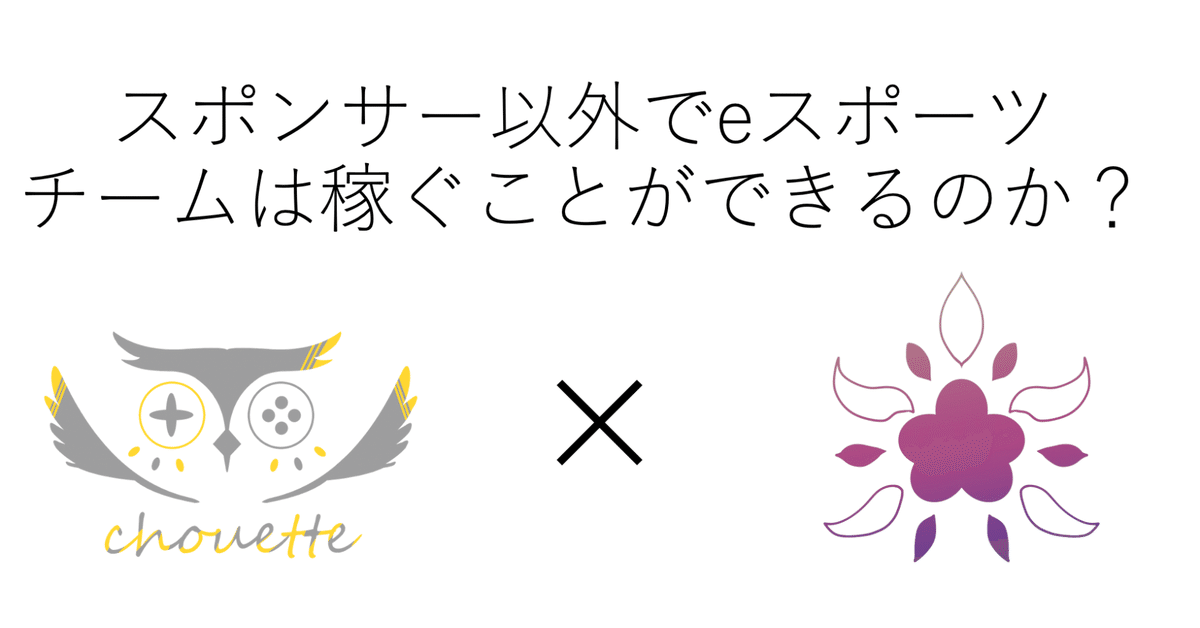
スポンサー以外でeスポーツチームは稼ぐことができるのか?
結論から申し上げますと「スポンサー以外で稼ぐことは可能」です。
皆様こんにちは。
桜野はるでございます。
最近note放置しすぎていてそろそろ誰かに怒られそうだったので、時間を見つけて執筆に勤しみます。
まぁ、誰に怒られるんだって話ですけどね笑
さて、今回表題にあるような内容なのですが、eスポーツチームの稼ぎ口、所謂キャッシュポイントについて「スポンサード以外に稼げないのでしょうか?」という質問をちょこちょこTwitterのDMにいただくので、今回はこれについてお話をしていこうと思います。
まず、eスポーツチームの収益源はどれくらいあるのでしょうか?
私が考えるに大きく分けで4つあります。
では、一つずつ見ていきましょう。
広告収入
皆様おなじみスポンサー料金はここに入ります。
eスポーツチームであれば下記に広告を掲載するのではないでしょうか?
・ユニフォーム
・自社Webサイト
・生放送画面上
・自社運営SNS
・その他活動露出時に掲載できる場所
これらに企業のロゴマークなどを載せて広告料を徴収しています。
また、チームの力がないときは料金ではなくスポンサーが取り扱っている製品を協賛してもらっているチームもあります。
おそらく、私のTwitterへこのスポンサー以外でも稼ぐことはできないのかと聞いてきている人の殆どは、会話のやりとりや普段のツイートを拝見していて察するに「営業ができないからほかの方法を探したい」ということなんだと思います。
正直な話、eスポーツに限らずスポーツチームの運営におけるほとんどの収入源はこのスポンサー料金から成り立っています。
このスポンサーを獲得できる力がないと、次からお話をする内容をすべて達成したとしても、大きなチームの運営を行うことは難しいでしょう。
ですので、まずはスポンサーを獲得する努力をすることが重要なのではないかなと思っております。
もし、私のTwitterDMに相談してきた人のなかで、スポンサーを獲得から逃げたくて相談してきたのであれば、その考えは改めたほうがいいでしょう。
そのほか、YouTubeなどの動画サイト上での広告収入などもあります。
入場料・観戦料での収入
次に、入場料や観戦料での収益です。
野球やサッカーを見に行った人であれば想像しやすいと思いますが、その会場に入場して試合をみるためにチケットを購入する必要があります。
このチケットを購入することによって、収益が発生するわけですね。
しかし、eスポーツはゲームで行うため、日本国内でeスポーツの試合で観戦料金を取ることは「風営法」に抵触する恐れがあるため、これを開催するためには警察や弁護士と相談して念入りに準備を行う必要があります。
正直、大きな企業が行う大会であればわかりますが、小さな団体がここまでeスポーツの大会を開いて入場料をとろうと思うとコスト的に見合わない部分もあるでしょう。
特に弁護士費用の部分が負担になるかと思われます。
入場料を取るのであれば、ゲームの試合や大会ではなく、ファンイベントなどの開催で入場料を徴収するしかありません。
この辺りはチームの企画力が試されますね!
そして、観戦料について。
これは一番得やすいところで言うと「ドネーション」を受けること。
所謂投げ銭です。
eスポーツイベントをオンラインで放映したり、普段の放送などで観戦してもらう時に視聴者の好意で行われるドネーションが収入源になります。
YouTubeのアプリ内課金で行われた場合、AppleやGoogleに30%、YouTubeに40%(諸説あり)取られるので、30%が金額の収益となるわけですね。
例えば、100万円の投銭をもらえたら、30万円が収益となるわけです。
上記でもお話しておりますが、YouTubeなどの動画サイト上での広告収入などもあります。
このように、閲覧してもらうことによって得られるお金は存在します。
物販収入
そのままの意味なので特に言うこともないと思います。
ユニフォームや独自のマウスパッド、マウスなど
様々なオリジナルグッズを制作して販売することによって、eスポーツチームへ収益が入るという仕組みでございます。
単純に【売上高ー原価=収益】ですね。
そこから税金や経費などを引いて税引き後純利益となるわけです。
実際に物販商品を作っても売れるのか。
こういう問い合わせについても腐るほどいただきました。
・物販の作り方を教えてください。
・商品を作っても売れるでしょうか?
・商品の売り方を教えてください。
・商品ってどうやった買ってもらえるんですか?
という「知らんがな。自分たちで考えるか調べるべき内容やんそれ。」案件から
・商品の販売を行っていますが、マーケティングをもう少し強化したい。
・商品のコンセプトを変えたいが、ターゲットを見失い始めているからターゲティングからしっかりやっていきたい。
など、頑張っている人たちの質問や相談など様々です。
これらについては、マーケティングコンサルをしている立場上これで食っていってる部分もあるので、無料で情報を提供するわけにはいきませんが、いつも返答していることが「調べられるところは自分で調べてみる事」を言っています。
例えば販路。
販路においてもユニフォームを売るのに適した販路があります。
それもeスポーツチームそれぞれに。
大きなところで言うと「野良連合」さんがユニフォームを売るときの販路と「父の背中」さんがユニフォームを売るときの販路ではどちらも適した販路があります。
そもそも客層(=ファン層)が異なっている部分がありますから、そりゃそうでしょって話なんですよね。
なので「どうやって売ればいいですか?」というような質問に対してしっかり答えるのであれば調査した上で答えなければならないので、時間と労力がかかる関係上お金をいただいております。
汎用的な答えで言えば「自分で考えるか調べるか勉強してくれ。」ということですね。
放映権収入
自分たちで試合を開催したり、イベントを行い、テレビ局やインターネットで配信する場合に放映権での権利収入を得ることができます。
ただし、試合などになるとeスポーツタイトルの権利を持っているパブリッシャーに対して許可をもらったり、パブリッシャーとのお金のやりとりなどが発生する可能性がありますので、そのあたりは慎重にしておかなければなりません。
自分たちが商材となって、ファンイベントの風景などを放映したいというオファーがあったりした場合は、その権利を売って収益にすることもできますので、権利販売による収益化というのも視野に入れて運営してみるのもいいのではないでしょうか。
まとめ
ものすごく簡単にまとめましたが、一般のスポーツ産業とeスポーツチームのビジネスモデルについては大差ないと考えております。
ただ、eスポーツという少し特殊な特徴を持っているジャンルなので、eスポーツタイトルの権利や各種法律などが絡んでくると、少し知恵を絞らないといけなくなったりします。
手放しで収益を得られるのは「スポンサー」と「物販」でしょう。
スポンサーについては同業種のスポンサーを得なかったり公序良俗に反していなければいい話ですし、物販に関しては自分たちのブランドであり、著作権や特許に違反していなければあとは売るだけですので。
また、ちょくちょくTwitterのDMで多い相談があれば、このような形式でnoteを執筆していきますので、次回の記事もご覧いただけましたら幸いでございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
