
江戸時代の食糧事情を勝手に想像した
江戸時代の農家ってなにを食べていたんだろうとふと気になり、調べ物をします。「江戸患い」という言葉があります。地方では白米食が普及していませんでした。大名でも玄米を食べ、農民は雑穀を食していたという記録が散見されます。それに対し江戸では白米食が普及していたことから玄米等に含まれるビタミンB1が不足し、脚気が発生するというものです。
慶安2年(1649年)に江戸幕府が公布した触れ書きのなかには「粟稗菜大根其外何に而も雜穀を作り米を多く喰つふし候ぬ樣に可仕候」と米を食いつぶさぬよう雑穀を作ることを奨励しています。

少し変わり、古い本「幕末・維新の農業構造」という本を見つけてきました。日本の4地域を取り上げ綿作、稲作、養蚕等の状況を記した本です。明治初期における農作物の生産高が示された表が示され水稲以外にも大豆、麦、雑穀、甘藷などが生産されていたことを示しています。
小学館「少年少女日本の歴史」第13巻には雑穀を食べる少年の様子が描かれていました。その時代を偲んで白米を一切使わずに雑穀だけで炊事をしてみましょう。

今回は穀物としてきびだけをしようしておかゆを作ることにします。動物性たんぱく質は入手困難だったと想定して使用しないことにします。
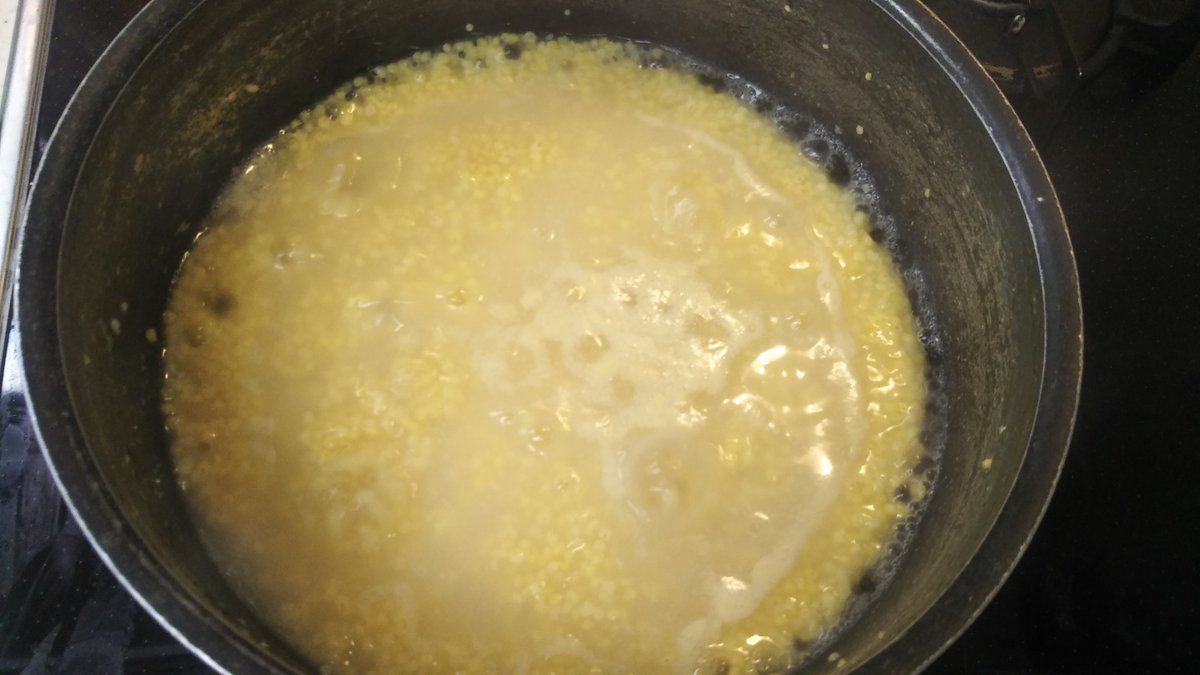
まずは”きび”だけを炊くことにします。鍋にたくさんの水をはって、きびを炊き上げます。かなりふやけてきたような気がします。

根菜、葉物野菜を入れて嵩を増すことにします。江戸時代でもこれくらいはやってお腹を満たしていたことでしょう。

いい感じに馴染んできました。

水分がなくなってきたので、蒸らすことにします。蓋をしてしばらく置いておくのは炊飯と変わりません。

調味料は梅干しにしました。当時でも保存食として文献に散見されていたことから使用制限を解除したいと思います。
いまは雑穀でも綺麗に精製されたものが販売されていますが、昔は精製する技術はなかったと思います。茎などが混じった雑穀はあまり美味しくなかったことでしょう。現在の恵まれた食事情に感謝して雑穀のおかゆをいただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
