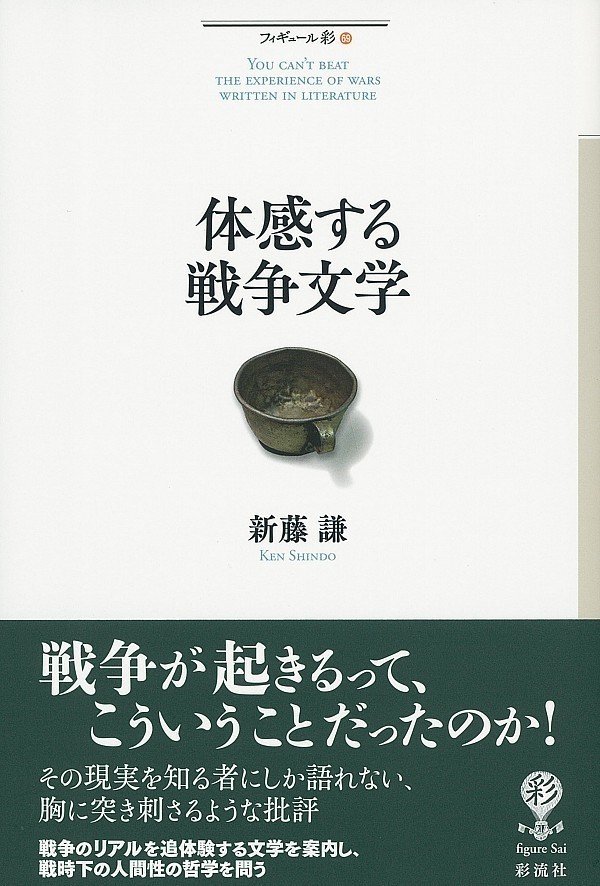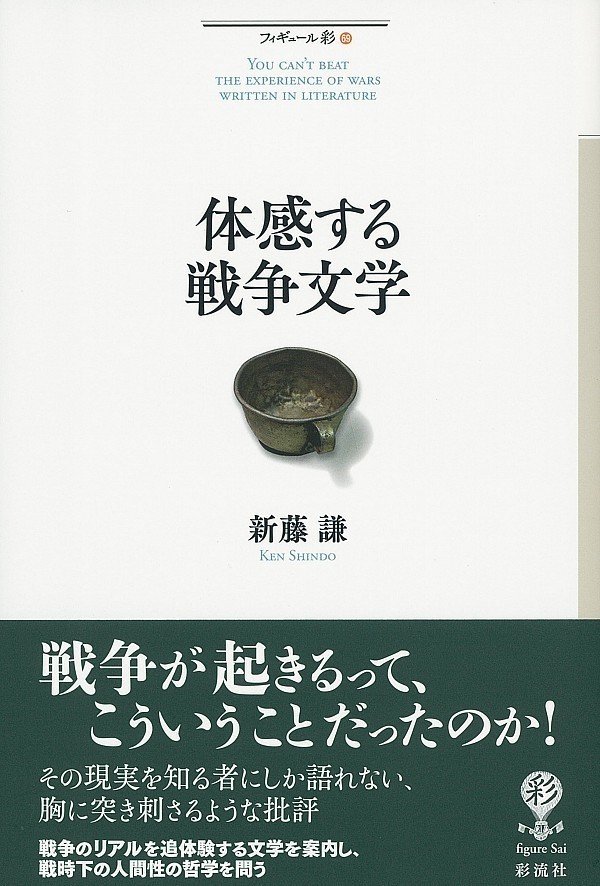【既刊紹介】『体感する戦争文学』
◆新藤謙著『体感する戦争文学』
2016年9月12日初版発行
どんな年にも、なにかしらの節目はめぐってくる。2020(令和2)年は、阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件から25年であり、東京オリンピック・パラリンピックが延期開催されるらしい2021(令和3)年は、東日本大震災から10年の節目となる。
今年の夏がくれば、終戦から75年になる。15歳だった人が、90代を迎える。「人生百年」というけれど、戦争を知る世代は確実に減りつつある。
『体感する戦争文学』を著した新藤謙は、1927(昭和2)年に生まれた。2016(平成28)年9月に本が出て、その翌月、89歳で亡くなった(※)。文字どおり、遺著である。
□□□
戦争がいかに人を狂わせるか。戦時下で人は、人でいられるのか。そこにどういう思想が芽生えるのか。さまざまな作家たちが、あの時代を言葉にした。この本は、戦争文学がいかに多彩で、豊かな視点に満ちたものか、まず気づかせてくれる。
見識ある家に育った少年の戦争観(妹尾河童)、極限に追い込まれた人間(大岡昇平)、戦場における兵士の心理(石川達三)、軍部への怒りと告発(五味川純平、高木俊朗)、市井に近しい芸能人の日記(徳川夢声、古川ロッパ)、個の思想を強いる強制収容所という場(石原吉郎)、反戦思想が引き起こす心の動揺(イシガオサム)、転向と国家と天皇制(鶴見俊輔)……。
第二章「少年たちの心の闇――学童疎開の文学」では、佐江衆一、小林信彦、高井有一の視点を通して、子どもたちの分断、支配、服従、傍観を明らかにする。大人であろうとなかろうと、戦争は容赦なく、人を集団の狂気に巻き込んでいく。
第六章「輸送兵の眼――水上勉『日本の戦争』を読む」には、短い作品評がいくつか並ぶ。新藤の人柄が、おだやかに迫ってくる。前半の重苦しさが、ちょっとやわらぐ。水上の『リヤカーを曳いて』のくだりを、新藤が引用する。
《『日本の一番長い日』とか、『歴史的な日』とかいうのは、観念というものであって、人は『歴史的な日』などを生きるものではない。人は、いつも怨憎、愛楽の人事の日々の、具体を生きている。『波乱万丈の人生を生きるなどという表現があるが、そんな人でも、ひょっとしたら、その人生は何枚かの風景写真にすぎないのではないか』と、私はのちの『風景論』に書いた。》
新藤は、こう続ける。《庶民の偽りない姿である。(略)それを「歴史的な日」とか、主情でいいくるめるのは、特殊な「観念」にすぎない》。あの日、新藤は18歳だった。
戦争を知らない世代でも、終戦日の風景は、なんとなく見ている。
皇居の前でひざまずき、嗚咽する人たち。その映像や写真に、「耐え難きを堪え、忍び難きを忍び」の語りが、決められたように流される。テレビの昭和特集で好まれる演出に接すると、終戦の匂いを感じた気になれる。それは、現代人の勝手な解釈であって、体感とはちょっと違う気がする。
戦争文学を体感する。それは“風景への共感”なのかな、と思う。
日米開戦の日、少年Hは学校で、急な下痢に見舞われる(妹尾河童『少年H』)。田村一等兵は、フィリピンの自然にみずからの死を想う(大岡昇平『野火』)。徳川夢声は、東京大空襲下の町と夜空に、美しさを見、感じる(『夢声戦争日記』)。
それぞれの人に、それぞれの風景がある。8月15日もまたしかり。“歴史的な日”などと解釈するのではなく、共感にとどめておく。それが、あの時代への向き合い方なんだと、腑に落ちた。
□□□
新藤の言葉づかいは、あたたかい。冷めた、乾いた批評であったなら、風景への共感もきっとなかった。多感な10代を戦争真っ只中で過ごし、兄は西部ニューギニアで餓死した。苛烈に、鋭く、読者に迫るであろう生い立ちなのに、その言葉には情味がある。プロフィールが「評論家」でなく「文筆家」であることに、納得した。
いっぽうで、現代への警鐘と、ゆるぎない怒りを行間に秘める。あの時代の言葉と人、風景を感じるであろう読み手に、さまざまな問いかけをする。政治腐敗、社会の閉塞感、同調圧力、人権無視、そして、差別。最終章の第十章「今も続く日本の鎖国性――鶴見俊輔『戦時期日本の精神史』」に、こんな一文がある。
《著者が危惧するのは、現在の日本のアジアへの経済進出が、かつての大アジア主義のような「日本中心の一方的な性格」に陥ることである。中国、韓国、アセアン諸国のめざましい経済発展が、「日本中心の一方的な性格」を抑える力となっているが、日本企業や日本人に、安い労働力としてアジア人を蔑視する意識が強いかぎり、また前述の間違った歴史認識を抱くかぎり、日本がアジア諸国民から尊敬と信頼を得ることはむずかしいだろう。》
偏狭かつ鎖国的な国体観念、傲慢な大国意識を、間違った歴史認識だと断じる。日本の戦争責任を「自虐史観」とする論調への姿勢はするどく、厳しい。
あとがきに《満身創痍のなかでまとめざるを得なかった》とある。それが重く響く。死を前にした書き手の言葉を、どこまで受けとめることができたのか。あの時代をどう書き、編み、語りついでいくのか。それをどう“いま”に投影させるのか。自分に、突きつけられている気がする。
折にふれて読みなおせば、あらたな体感が得られるのかも。そう言い聞かせて、本棚に戻した。
(※)「新藤謙さんの死」(ブログ「いわき日和」)
http://blog.livedoor.jp/aryu1225/archives/52174998.html
濱田研吾(はまだ・けんご)
1974年生まれ。ライター、編集者。著書に『徳川夢声と出会った』(晶文社)、『脇役本 増補文庫版』(ちくま文庫)など。
『体感する戦争文学』
新藤 謙 著
定価:1,800円 + 税
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?