
#0003
映画批評の中で、何だかよく分からない表現に出会ったとき「あの映画は実験的だった」とか「あの映画は前衛的な表現をしていた」とかいう言い方がされることがあるかと思います。映画に限らず音楽や舞台でも似たように言うことがあるでしょう。
それではこの実験的/前衛的という言葉に関して、両者の間にどのような違いがあるのか、ないのか、考えてみたことはあるでしょうか?
結論から言えば映画の中で両者の間にほとんど違いはなく、「小さなスケールで製作された非商業的で、多くは非物語的な映画」というくらいの作品のことを指すのですが、一応、映画史という文脈では両者の使い分けが重要になってくる場面があります。
具体的には映画表現の実験をする為に実験映画/前衛映画を製作しているのか(積極的)、それとも商業映画、メインストリーム映画に対する反発として実験映画/前衛映画を製作しているのか(消極的)、という動機の違いですね。往々にして映画史は映画運動の繋がりで語られる訳ですが、運動の大元である動機の部分を混同してしまうと解釈の仕方が全く異なってきてしまうことがあるのです。
今回は両者を区別しながらアカデミックな文脈で実験的(experimental)、前衛的(avant-garde)という表現がどのように使われているのか確認していくことにしましょう。
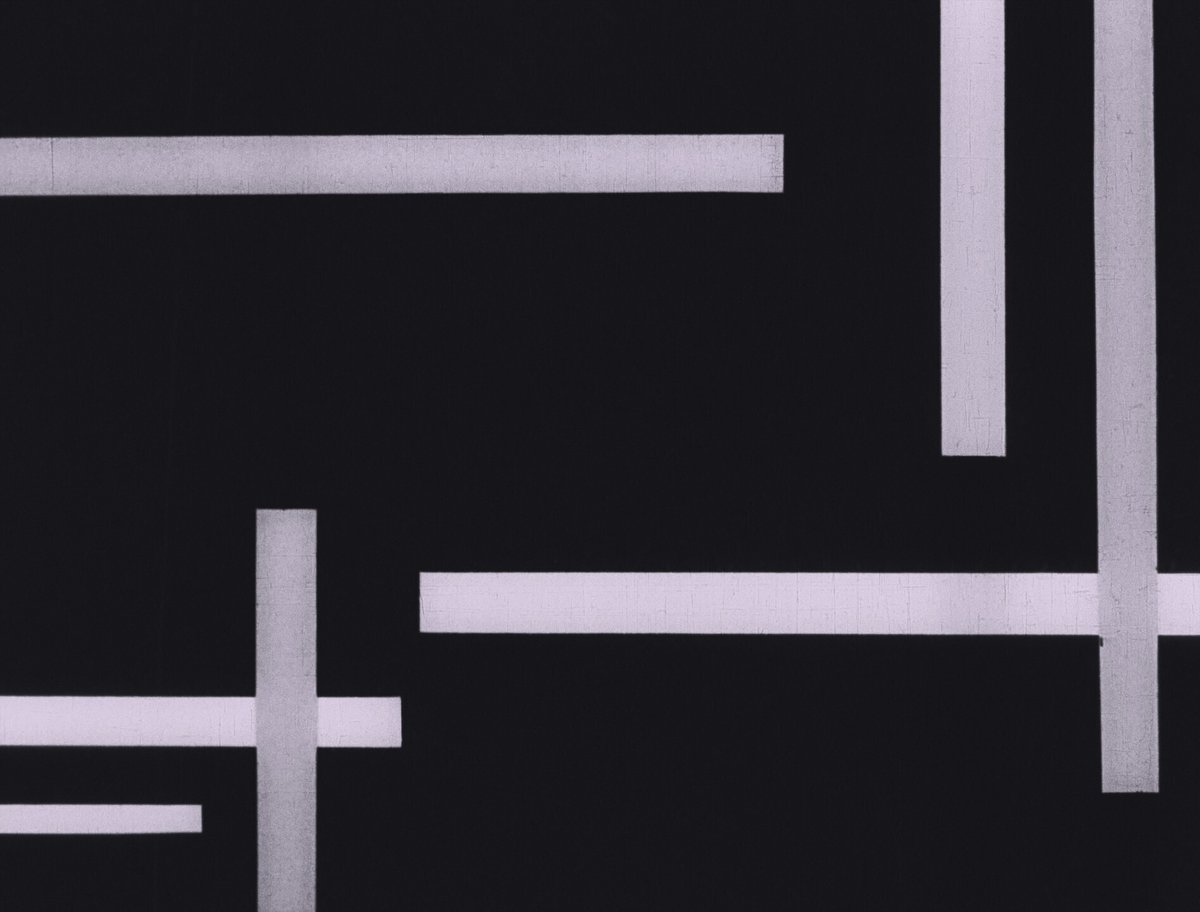
議論に当たって、用語を整理し今回取り扱う映画は全て”Radical Cinema"(ラディカル・シネマ=改革的映画)であると一旦呼ぶことにしましょう。それが実験映画であろうが前衛映画であろうが押し並べて映画表現の改革に何らかの形で貢献している、或いは少なくとも表現自体に関心があり故に自己の表現方式に自覚的である、ということです。
この”Radical"という単語は例えば「ラディカル・フェミニズム」や「ラディカルな政治」といった風に用いられることから分かる通り、急進的という意味を、そこから転じて「反〇〇」といった意味を持ちます。政治的にラディカルな人はほとんどが現行の政治に批判的であり、何らかの社会的変化、構造的革新を求めている、というようにですね。
この解釈は映画に於いても流用可能なもので、ですからラディカル・シネマといった時にそれを「反映画的映画」であると解釈することが出来るでしょう。
それでは反映画的映画というものを考えてみると、ここで反発されている映画というのは具体的にどういったものとなるでしょうか?
これに関しては直ぐにハリウッド映画、ハリウッド的商業映画であると断言してしまって良いと思われます。特に1950年ごろまでの映画を議論するのであればこの時代以前に(そもそも数の少ない)途上国の映画を真剣に検討していた先進国の文化人/インテレクチュアルはほぼゼロに近かったと言って良く、またその時代から染み付いた「映画産業の中心=ハリウッド」という幻想は皆さんの中にも根付いていることでしょう。
さて、それならばハリウッド的映画の特徴とは何なのか?
これは実験映画を定義するのと同じくらいに難しい質問ではありますが、今回は「観客に与えられる映画」である、と簡単に記して置きたいと思います。「下賜された」と言って良いかも知れませんね。逆を取れば「観客が獲得する映画」ではない、ということになります。
これは実験映画/前衛映画の誕生に関わる部分でもあり、後に詳しく述べますが我々の思う「アート」が現在の形に変化するのは大体18世紀の終わりから19世紀にかけてだと考えられます。出来事で言えばフランス革命の起こり(1789)から第二帝政の終焉(1870)頃までの1世紀ほどでしょうか。
フランス革命に象徴される通り、啓蒙主義の発展は人民(≒個人)の目覚めを促し、結果的に封建主義、王政の打倒へと繋がっていきました。それに呼応するように産業革命(英:1760年代、フランス:1830年代)のうねりが社会を包んでいきます。
ここで見られたのはシンプルな権力構造の変化であり、神託とされていた権力は所有する財産の多寡によって決まるものへと、勿論それは過剰な単純化ですが、とは言え社会の中心が貴族や聖職者からブルジョワへと移っていったことは事実です。そして富を手にしたブルジョワは芸術を自分の管理下、影響下へと置くようになりました。
それまでは芸術家は教会や宮廷の依頼に伴って製作することが多く、その価値も彼らによって決定されていた。しかしながらブルジョワによるアートの「所有」という行為が広まると、アートを所有するということ、そして所有するからにはその出所が、即ち製作者の名前に則った価値が作品に付与されるようになっていきます。この所有していることに価値があり、且つその所有物が高名であればあるほど価値も大きい、というアートに対する考え方は現代に近く、展覧会に出品されギャラリーに収蔵されているアート、或いはブルジョワの税金対策に購入されているアートの歴史的な原型がこの時代に生まれたと言えるのではないでしょうか。そう、美学(aesthetics)とは異なってアートとは資本主義/消費主義の産物であるのです。
さて、こうして経済システムの中に(より正確に言えば価値交換システムの中に)組み込まれていったアートは、だからと言って全てが所有されるという訳ではなく一部は民衆へも与えられるようになります。
例えばギリシアの時代からヨーロッパ中で受け継がれてきた芸術の1つである演劇は中世では主に教会の為に、ルネサンス期には社会的な芸術としてみなされていましたが、18世紀になると市民劇などが誕生、チケットの価格も低下していきます。映画『天井桟敷の人々』では1820年代のパリが舞台ですが、そこで見られる劇場から分かる通り庶民や中流階級が足を伸ばせる程度の芸術に変化していた訳です。
そうした劇場で上映されていた演劇というのはきっと説教臭い15世紀のような宗教劇ではなかった筈で、特別の教養のない市民でも楽しめるようなものであったと考えられます。こうした演劇が単なる娯楽かと言えばそれは間違いで、その中にも一定以上の芸術性があった筈ですが、少なくとも「見せるもの」として過剰に高度で難解な表現は一般的でなかったと思われます。
これと同じことが恐らくハリウッド映画にも当てはまるだろうと考えられ、即ちハリウッド映画とは大衆に向けて提供された芸術という視点からは、それは分かりの易い(けれども一定以上の芸術性がある)表現だと言うことが適当だと思います。その意味で「観客に与えられる映画」と書いた訳ですね。
それは本来アートが持っていた価値が大衆に通ずる形で伝えられているということであり、或いは社会構造的にブルジョワが独占しているアートという価値を庶民へと分け与えている(「下賜された」)ことでもあります。随分偉そうな言い方ですが、価値を決めているのも、保存しているのも、取引しているのも、特に何億というお金が動く映画では製作しているのも殆どがブルジョワの導きで、ラスティニャック的芸術家は彼らのゲームに参加するしかないというのだから仕方がないことです。
前提知識がなくても鑑賞が可能で、ストーリーには大抵明確な起伏があり、そして感動や興奮など何らかの感情を結末に容易して満足感を高める。こうしたハリウッド映画の特徴はどれもアートを専門にしていない庶民にも広く映画を開く為に必要な要素であり、それ故に映画は特別の考察を必要とせずそれ自体で完結することが出来るでしょう。

ここまでの芸術史の展開から自然に想定されることかとは思いますが、20世紀になりブルジョワによるアートの所有がますます一般化されるにつれ、そうしたアートの形態に異議を唱える人物も生まれてきます。社会主義的芸術や芸術至上主義運動(Art for Art's Sake)など19世紀中にも幾つかの芸術運動が展開されますが、それらは結局ブルジョワが定義した「アート」という産物のルールに則ったものでしかなく、従って「アート」自体を解放し、再定義するようなものではありませんでした。
ですから究極の反動として非アート的な作品を「アート」に対して投げかけ「アート」を外側から解体していく試みが必要ではないか、という声が持ち上がってきます。反芸術的芸術ですね。この試みは運動としてダダイズムと呼ばれ、特にトリスタン・ツァラの挑戦的で攻撃的なフレーズを旗印にその勢いはスイスからパリ、パリからニューヨーク、ベルリンと世界中に飛び火していきます。有名なダダイストでありその理論的発展に大きく貢献したハンス・リヒターの文章をちょっと覗いてみましょう。
The devising and raising public hell was an essential function of any Dada movement, whether its goal was pro-art, non-art, or anti-art. And when the public, like insects or bacteria, had developed immunity to one kind of poison, we had to think of another.
(訳)
社会の上に地獄的混沌をつくり出し、それを煽り立てることがどのようなダダ的運動に於いてもその本質的な役割であり、その運動の目的が果たして芸術肯定であるか、非芸術であるか、反芸術であるかは問題とはならなかった。そして社会が例えば虫や細菌のするように、ある種の毒に対して免疫を獲得したのだとすれば、我々は別の類を考えださねばならなかった。
その芸術の目的が何であれダダとは社会に対して混乱を突きつけるものであり(これはダダ的芸術が本来的には芸術とはみられないものだということを暗示しています)、そして一旦その芸術が社会に受け入れられたならば更なるアンチを突きつけていかねばならない、ということですね。作品としてはニューヨーク・ダダに分類されるデュシャンの『泉』こそが最も有名かとは思いますが、ここでは逐一取り上げないこととします。加えてリヒターは芸術の目的は問題ではない、と語っていますがそれはこの文章が1966年に出された懐古的なものであるからであり、シュルレアリスムなどを取り入れて変質していったダダの総体について語っているからだということを補足して置きましょう。
肝心なのはダダイズムが「アート」に与することを拒否した概念であったこと、故に本質としてダダは「アート」とは見做されない作品をアートだと称していたこと、それから運動が映画にも飛び火したこと、この3点です。
冒頭に掲げたハンス・リヒター然り、ヴィキング・エッゲリング然り、フェルナン・レジェ然り、ニューヨークからはマン・レイにマルセル・デュシャンと、多くのダダイストたちが新たな表現方式への挑戦として写真や音響術などと並んで映画を選択、ラディカル・シネマの製作に乗り出していったのです。
これは正しく実験映画/前衛映画に於いて画期的なことだったと言って良く、サイレント時代の幾つかの作品はあれど、一般には実験映画/前衛映画の発祥、初めての作品であると言う風に語られています。特にハンス・リヒターの"Rhtythmus 21" (1921) はその中でも最初期の例でしょう。記録的/物語的な映画を離れて幾何学的な模様がリズミカルにスクリーン上に現れるだけの様子はダダが大きな影響を受けたワシリー・カンディンスキーの抽象画理論を思わせますが、彼の絵画が一面的な表現に留まったのに対しリヒターは時間と連続性という概念を採用して空間を拡張しており、これは紛れもなく映画的、後のハリー・スミス作品やスタン・ヴァンダービーク作品などに継承されていくことになります。

さて、草創期に於いてラディカル・シネマは前衛的であり、同時に実験的でもありました(実験的であることが」映画の枠組みを外れることと殆どイコールだったから)。しかしながら2つの戦争、特に第二次世界大戦がヨーロッパ中を包むと、多くのアーティストたちはアメリカへの亡命を決断し次第にラディカル・シネマの中心はアメリカへと移っていきます。
その過程で当初のヨーロッパ人が持っていた様式に関する思想的な統一(ダダイズム、シュルレアリスムなど)は失われる/希薄化していくようになり、より自由で、けれども非メインストリーム的な映画が多く製作されていくようになるでしょう。ここに至って前衛と実験の間に開きが見られるようになってきます。
そもそも前衛(Avant-Garde)とは19世紀のフランスで生まれた考え方であり、その背景には社会を治めるようになったブルジョワ階級に対するオルタナティヴとして生まれた社会主義(socialism, ≠ communism)からの影響がありました。
市民革命は既に述べた通り啓蒙主義に基づく理性的な人間による統治の実現を目指した革命だった訳ですが、その中で人間の代表のような立場でブルジョワ階級が社会のトップに立つようになります。マルクス主義ではこれは有産階級による労働者階級の圧迫として批判される訳ですが、当時は(恐らく王制・封建主義との比較から)彼らによる統治は寧ろ社会の健全な在り方であるとして推奨されておりました。
そんな理想主義的ブルジョワ社会に於いて芸術家の役割とは何なのか?それは彼らの広く、素早く民衆に訴えかける力を生かし、彼らの先駆者となって社会を正しく導く守護者的立ち位置にいることである、そういう考え方の下に提唱されたのがアヴァンギャルド(advanced=先進的、gurdian/vanguard=守護者)だったのです。
しかしながら、20世紀に入り、ブルジョワ階級は必ずしも民衆の代表という訳でもなく、彼らの価値観は全く「アート」を導くものではないということがはっきりしてくると、このアヴァンギャルドという概念はより「純芸術的な」方向性で用いられるようになっていきます。avant-gardeは「社会の守護者」から「芸術の守護者」という意味へと変わっていく訳ですね。彼らによって作られた「アート」ではなくより純粋で社会に必要なアートを求める動きが、芸術家からもインテレクチュアルからも起こってくるでしょう。
その芸術家側からの動きの1つがダダイズムだった。しかしアヴァンギャルドとしてダダを括ってしまうと本来の{「アート」ではないアート}が「アート」の軍門に下ってしまう、というジレンマもあり、正にその問題ゆえにダダイズムの消費期限は短かったのですが、ともかく歴史的に言ってこのような{「アート」ではないアート}を求める作品を前衛的と呼んでいるのです。
ダダの時代、1920年代に於いては映画は誕生から凡そ30年かその程度であり、慣習に逆らうことと新たな表現様式を開発することは殆ど同義と言って良かった。従って前衛=実験という図式は十分に存立可能でした。しかし戦後のアメリカのように散発的で思想的にも自由な製作がなされるようになると、その等式はあっさりと崩れ去ってしまいます。
例えばケネス・アンガーの代表作『スコーピオ・ライジング』を見てみるとホモセクシュアル、バイク、ロック、ナチスなどスキャンダラスなイメージが連打されていることにまずは気が付くでしょう。しかしスタイリッシュな音楽やテンポ感の良い編集などのお陰もあって、映画として格好の良い作品に纏まっており、作品は非常に映画的である、少なくとも映画の慣習を破壊するよりは破壊的なイメージの中から映画を製作する、という意図があるように感じられます。
商業映画からは排除されていたモチーフを映画の中に取り込みアメリカ社会を描く、という試みには確かに実験的(experimental)な価値があると言えますが、それでは前衛(avant-garde)という観念からはどうなのか?つまり『スコーピオ・ライジング』は「アート」の枠組みを拡張したのかも知れないが、その出発点に於いて「アート」だったのではないか、ということですね。
ですから少なくとも「反映画的映画」を志したダダイズム作品とは異なるタイプの前衛だということは言えるでしょう。アンガーその人は特段の主義主張を立てて、何らかの運動を促進したということはありません。その仕事は散発的で、理論に裏打ちされたものではありませんでした。
確かにMGMやWarner Bros.のようなスタジオが作るブルジョワ的な映画とは無縁だった美学の領域を切り開き、後のジョン・ウォーターズ作品に影響を与えたことなどを考えれば前衛的と表現することも可能なのかも知れません。しかしながら何度も述べている通り、(今回の場合スタジオが製作した)ゲームのルールに則った作品がどこまで前衛的であるのか、その点は常に検証されるべき問題であり続けます。

総括しましょう。
実験映画と前衛映画は多くの場合混同して、同じものとして語られています(その総体を此処ではラディカル・シネマと呼びました)。
しかしながら「アート」の成立過程を振り返ってみると、芸術の中には反「アート」であることを目的とするものと、非「アート」であるとを目指すものの2つがあり、ラディカル・シネマに分類されるような映画の中にも反「映画」的な作品と非「映画」的な作品の2つが存在することが分かります。
どちらにしてもそれらは「映画」の典型的な文脈から逸脱し新しい表現を模索していることから実験的(experimental)である訳なのですが、それでは前衛的(avant-garde)かどうかという段となると、それは多分に「映画」の境界線をどこに引くのかという問題にならざるを得ません。ある区分では『スコーピオ・ライジング』は前衛的ですし、別の区分、例えばダダ的な区分からは単に実験的ということになるのではないかと思います。その映画が表現方法の探究をしているが故に実験的であるのか、それとも前衛であろうとして実験的であるのか、その点も重要な違いとなるでしょう。
ですから語法として考えるならば、単に映画の表現が斬新だということを言いたいのであれば実験的という言葉を用いるか、「前衛的と言われるような表現」とヘッジを掛けるのが正しいだろうと思われます。
前衛という言葉を使うのであれば、何に対しての前衛なのか、という区分を明確にする必要があり、そうした映画の分類は極めて映画史的だと言えるでしょう。デイヴィッド・リンチやロバート・エガースなど風変わりな作品に対して何でも「実験的/前衛的」と呼称する映画評を多々見かけますが、その使い分けには注意したいところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
