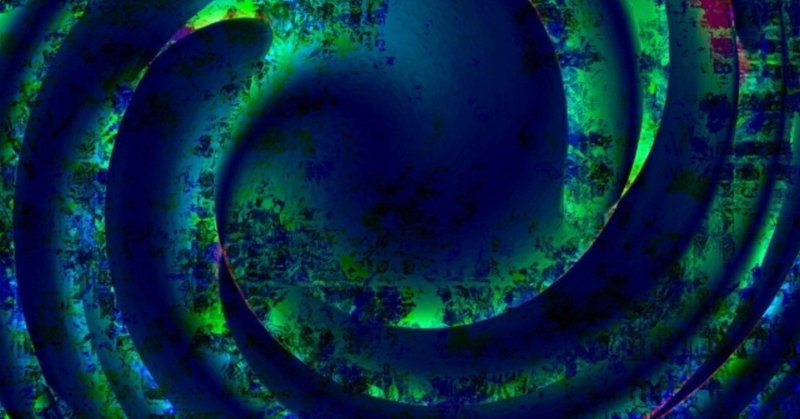
国際的常識に接続する形で「日本」の成り立ちを説明する
日本書紀の書き出しは、こうなっています。
「古に天地未だ剖れず。陰陽分かれず。渾沌にして鶏子の如く、冥涬にして牙を含めり。其の清陽なる者は薄靡きて天に為り、重濁なる者は淹滞りて地に為るに至りて、精妙の合搏すること易く、重濁の凝竭すること難し。故、天先づ成りて地後に定まる。然して後に神聖其の中に生れり」
昔むかし、天と地がまだ分かれていませんでした。陰と陽も分かれていませんした。混沌とした状態で、生玉子のようにドロドロとした状態でした。ほの暗くて見分けにくい状態でしたが、何かが生じる兆しがありました。澄んで明るい気は薄くたなびいて天になりました。重くて濁った気は停滞して地になりました。清らかな気が集まる事は簡単ですが、重たい気が固まるのは難しいことでした。そこで、天が先に出来て、その後、地が出来ました。この後、何か神聖なものが生まれてきました。
この書き出しのうち、「天地未だ剖れず。陰陽分かれず。(天と地も、陰も陽も分かれていませんでした)」は、中国の古典・淮南子に書かれている言葉と同じです。
「渾沌にして鶏子の如く([固体や液体・気体が分離していない]混沌とした状態で、生玉子のようにドロドロとしていました)」は三五暦紀と言う本にあるそうです。
「冥涬にして牙を含めり(ほの暗くて見分けにくい状態でしたが、何かが生じる兆しがありました)」は三五暦紀、「其の清陽なる者は薄靡きて天に為り、重濁なる者は淹滞りて地に為る(澄んで明るい気は薄くたなびいて天になりました。重くて濁った気は停滞して地になりました)」は淮南子に出てくる言葉です。
「精妙の合搏すること易く、重濁の凝竭すること難し。故、天先づ成りて地後に定まる。(清らかな気が集まる事は簡単ですが、重たい気が固まるのは難しいことでした。そこで、天が先に出来て、その後、地が出来ました。)」も淮南子に出てくる言葉が元にあるそうです。
三五暦紀には「天より神、地より聖」と言う表現があり、天地が分離した後、神聖なものが天地から出てきたとしています。「然して後に神聖其の中に生れり(この後、何か神聖なものが生まれてきました。)」は、この記述を踏まえていると考えられています。
日本書紀は、この後、「時に天地の中に一物生れり。状葦牙の如く、便ち神になる。国常立尊と号す(天地の間に、一つの物が生まれてきました。形は葦の芽のようでした。これが神様になりました。国常立尊と言うお名前です)」と書いています。
つまり、日本書紀は、淮南子や三五暦紀など、中国の古典に記載されている「天地が分かれて世界が始まった」と言う物語に接続して、日本最初の神様「国常立尊(クニトコタチノミコト)」の出現を語っているわけです。
中国の古典は、当時のグローバル・スタンダード。国際社会で知識階級の常識だったと思います。その国際的常識にすり合わせる形で、日本の成り立ちを説明しようとしているのが、日本書紀の本文なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
