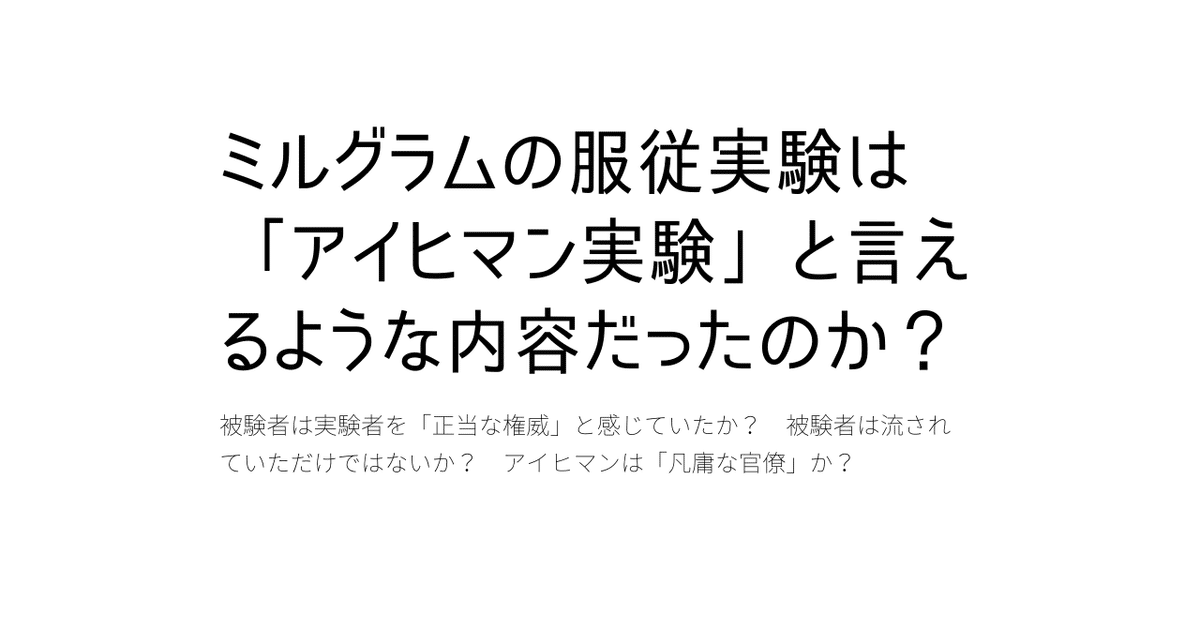
ミルグラムの服従実験は「アイヒマン実験」と言えるような内容だったのか?【心理学】
スタンレー・ミルグラムの服従実験について、二つの記事に分けて検討しています。私にとっても特に印象深い実験だっただけに、一度より深く、より批判的に捉え直してみようと思い立ったわけです。
前回の記事では、実験の概要と結果についてやや詳しく紹介しつつ、ミルグラム実験がそもそも真に受けてよい実験なのかという「信頼性の問題」について検討しました。「残念ながらオリジナルの実験はあまり信頼できなさそう。追試実験も鵜呑みにはできないだろう」という結論を出しています。
この記事では、仮に実験の手続と結果が信頼できるとして、ではそこからどのような現象がどこまで説明できるのかという「解釈の問題」について検討していこうと思います。
◆
ミルグラムによる服従実験の解釈
1960年代に行われたスタンレー・ミルグラムによる服従実験は、社会心理学の中でも特に有名な実験です。「アイヒマン実験」とも呼ばれています。人間は、権威の命令とさえあれば、非倫理的な内容であっても容易く従ってしまうことを示したものとされています。
ミルグラム自身、この実験から「ほとんどの人間は、正当な権威の命令だと思えば、どんな種類の行為であろうと良心の呵責なく実行してしまう」であるとか、「イェール大学所在地でも、死の収容所のメンバーは揃えられると思い始めている」などと、刺激的な結論を引き出しているようです。
「ユダヤ人であるミルグラムが社会心理学を専攻したそもそもの理由は、ホロコーストで殺人に加担した人間の心理が知りたかったからだ。まさか正常な精神の持ち主が残虐行為に手を貸すはずがないと彼はこの実験を構想したとき信じていた。ミルグラムは言う。
おぞましく、意気消沈させる結果だった。(……)少し前まで素朴な考えに囚われていた私は、邪悪な政府がアメリカ合衆国に生まれても、ドイツで維持されたような死の収容所を管理するために必要な道徳欠陥者は国中を探しても見つからないだろうと思っていた。しかしニューヘイヴン[実験の実施されたイェール大学の所在地]だけでも必要な人員を集められるだろうと今は思い始めている。正当な権威が発する命令だと思いさえすれば、ほとんどの人々はどんな種類の行為であろうと、やれと言われれば良心の呵責を感じることなく実行してしまうのだ。」
設計の妥当性への批判
ミルグラムの実験は、何を示したとされているのでしょうか。権威が人を服従させる力です。「ほとんどの人間は、正当な権威の命令だと思えば、どんな種類の行為であろうと良心の呵責なく実行してしまう」などと言われるのもそのためです。
しかし、ミルグラム実験は、「正当な権威の命令に対する服従」を測定する検査として妥当な設計になっているのでしょうか?
この点については、さまざまな議論があるようです。『服従の心理』(河出書房新社)の翻訳者である山形浩生さんは、「訳者あとがき」において参考になる批判を複数行っています。それらを大いに参照しつつ、私なりに批判を行いたいと思います。
批判1 「正当な権威」からの「正当な命令」を演出できていたか?
ミルグラムは、服従実験によって「正当な権威の命令」の力が示されたとしています。しかし、被験者たちは、本当に実験者たちのことを「正当な権威」だと思っていたのでしょうか。もしそうでないならば、ミルグラム実験は、「正当な権威への服従」などとは関係のない他の何かを示していることになります。
そして、考えてみると、実験の被験者たちは「権威の命令」の正当性に対して疑問をもっていたのではないかと推察されるのです。権威への疑問には、「①実験者が正当な権威者であることに対する疑問(権威の正当性への疑問)」と、「②命令が正当な内容であることに対する疑問(命令の正当性への疑問)」が考えられますので、分けて検討します。
① 実験者は「正当な権威」を演出できていたか?
まずは、実験者が「権威の正当性」を演出できていたかを考えます。
山形さんは、社会もまた権威の一つであることに注意を促していますが(347頁)、このことを踏まえるといっそう問題がはっきりします。
社会も権威の一つであるとして、「正当性が信じられていた権威」の一例は、それこそナチスでしょう。ナチスは揺るぎのない社会的権力でしたから、正当な権威であると信じられていたと言ってよいと思います。
それに対して、ミルグラム実験の実験者たちの権威は、研究のよしあしを判断する「社会」という上位の権威によって容易く覆る「疑問の余地のある権威」です。そんな実験者が「覚えの悪い生徒役に電撃を食らわせよ。危険だけれど死にはしない」などと異様なことを命じてくるのですから、「この実験者は本当にまともな権威なのか」「実験がバレたら権威は失われるのではないか」という疑いが被験者の心に生じていてもおかしくありません。
「さてこの実験の場合、軽いショックが学習の役に立つという仮説はもっともらしい。
だが学習者がのたうちまわるほどの電撃、学習行為そのものを放棄すると宣言させるほどの電撃が学習にいささかも役立つとは、冷静に考えればとても思えない。
つまり実験が進むにつれ、実験の目的と内容とは大幅に乖離する。
多くの人が感じた葛藤や不安には、そうした乖離にともなう権威の正当性に対する疑問もあったのではないだろうか。」
スタンレー・ミルグラム 山形浩生訳『服従の心理』河出書房新社 350頁
傍点部分を太字に変更してあります。
② 「正当な命令」を演出できていたか?
続いて、「命令の正当性」を演出できていたかを考えます。
ミルグラムは、「ホロコーストで殺人に加担した人間の心理が知りたかった」と言っていますが、そうだとすれば、ミルグラム実験における命令の内容は、正当性をもつように見えるものでなければなりません。なぜなら、ユダヤ人の排除命令は、ナチス信奉者たちにとって、自衛という目的に資する正当な内容だと感じられていただろうからです。
「ナチスであれば、なぜユダヤ人を抹殺すべきかについて(ひどいものとはいえ)理屈を一応は持っていた。ユダヤ人は社会の破壊を画策しているから自衛のために排除が必須だというものだ。ガス室のボタンを押す人々は、単に権威の命令だからというだけでなく、自分の行為の社会的意義を確信して崇高な使命感さえ持っていただろう。」
スタンレー・ミルグラム 山形浩生訳『服従の心理』
河出書房新社 350頁
当時は反ユダヤ主義が蔓延していたわけです。実態こそ言葉にできないほど悪逆非道な大虐殺であったわけですが、そこに正義を見いだすほどの異常な心理状態があったということです。
他方で、ミルグラム実験の被験者たちは、生徒役に対して差別意識を持っていたわけではありません。ミルグラム実験における命令は、被験者たちにとって、内容の正しさに疑問の余地があるようなものになっています。実際、ミルグラム実験の被験者たちの多くは強い葛藤や不安を示してしまっています。ミルグラムの言に反し、良心の呵責に苛まれているのです。
①と②を踏まえ、ナチスのホロコーストとミルグラム実験を対比させてみましょう。
ナチスの場合は、揺るぎのない権威性と、社会に蔓延していた容赦のない差別主義とが結合していたといえるでしょう。ナチスによる命令は、「正当な権威」からの「正当な内容の命令」であると思われていたわけです。
それに対し、ミルグラム実験における命令は、「正当な権威であるか疑問の余地のある実験者」からの「内容の正しさに疑問の余地のある命令」となっています。両者の命令には、性質に大きな違いがあります。
ミルグラム実験は、「ある意味で人間の善良さを示した実験だ」と言われているようです。というのも、ミルグラム実験の場合、それなりの人数が命令を拒否しましたし、また注目すべき事実として、服従した人間たちにしても、強い良心の苦しみを感じていたからです。この見方も一面では正しいのだとは思います。
しかしながら、ミルグラム実験における命令には、権威者の正当性にも命令内容の正当性にも疑問の余地があったのですから、「人間の善良さ」についても普遍化はできないと思います。被験者たちがナチス・ドイツを普通のドイツ人として生きていたとして、反ユダヤ主義に基づく命令を拒否したり、服従に良心の苦しみを感じたりしていたのかはわかりません。ミルグラム実験は、社会的権威と差別主義が結合したときの恐ろしさ——良心の苦しみさえ感じさせない・感じない——を見逃している可能性があります。
加えて、ミルグラム実験が「差別主義」を取り扱えていない点は見逃せません。「権威」の存否などとは関係ない場面でもヘイトクライムは起きているわけです。また、同じ考えをもった人々が徒党を組んでいると排外性がいっそう高まることがあるわけですが、こうした「集団心理」についてもミルグラム実験の守備範囲外です。私としては、ナチズムを理解するためには、「権威と服従」よりも、もっとストレートに「差別主義」や「集団心理」に着目する方が素直であり、かつ本質的な話になるのではないかと思います。人間はときとして敵だと認定したものに対して寄ってたかって攻撃を加え、そのことに何の疑問も持たないばかりか、快感さえ覚えるような存在であることは忘れてはならないでしょう。
批判2 被験者は流されていただけではないか
批判のもう一つは、被験者は突然わけのわからない状況に置かれたゆえに流されただけの可能性がある、というものです。
ミルグラム実験において、被験者たちは、単に「記憶に関する実験」と聞いてやってきます。それなのに、生徒役の両手を縛るだの電極を繋げるだの電気ショックだの異常な話がでてきて、自分はといえば他人様に電撃を与える作業をやらされるのです。
1960年代を生きていた人間であるとはいっても、この展開には強烈な違和感を感じたのではないでしょうか。しかも、先生役(被験者)はするべき作業が多かったようです。このような状況では、冷静に考える余裕がなく、通常時にするような判断ができない可能性があります。
「さらにこの実験にはもう一つ困ったところがあるのだ。先ほど「冷静に考えれば」と述べた。だがこの実験で被験者に冷静に考える余裕があるだろうか? 人々が服従したのは、単にそれがものの三十分ほどで一気呵成に実施されたために勢いに流されたのではないか。
人々が視野狭窄を起こしたとミルグラムは述べるが、この実験で先生役がやるべき作業はずいぶん多い。それが証拠に一部の人は実験の手順すらなかなか修得できず、説明を受けてもこれが本当に学習実験だったと思いこんでいたという。そういう人は、きちんと判断を下すだけの余裕がなかっただけの話では?」
スタンレー・ミルグラム 山形浩生訳『服従の心理』河出書房新社 350頁
つまり、ミルグラム実験において命令に従った人でも、冷静に考える時間のある場面ならば権威に抵抗するかもしれないのです。パニック状態における人々の心理状態の分析をもって、一般生活における人々の心理状態を説明するのには無理があるでしょう。
ちなみに、山形さんは、実験を二日に分割すれば良かったのではないかと指摘しています(351頁)。実験を途中で切り上げて「後日続きを行う」と言われた場合でも、被験者が冷静に判断した上で服従していたならば、再びやってくるでしょう。もちろん、実際には二度とやってこない人が多そうです。しかし、それならば命令は被験者たちにとって「冷静に考えれば服従できないもの」だったことになってきます。服従した被験者たちは冷静な心理状況ではなかったと推察されるわけです。
結論 「アイヒマン実験」と呼ぶべきではなさそう
以上の批判を踏まえた上で、ミルグラム実験を捉え直します。いったいこの実験はどんな現象をどう説明できているのでしょうか。
ミルグラム実験は、ときに「アイヒマン実験」とも呼ばれます。
ミルグラム実験の被験者は、実験者の命令に対して服従し、生徒役に電気ショックを与えた。アイヒマンも同じく、権威からの命令に対して服従し、ユダヤ人をガス室送りにした。〈普通の人々〉も、〈アイヒマン〉も、権威の命令とあれば残忍な命令にも容易く従ってしまう点でそっくりだ。ほとんどの人間は、正当な権威の命令だと思えば、どんな種類の行為であろうと良心の呵責なく実行してしまう。「凡庸な悪」の問題だ、というわけです。
しかしながら、「〈普通の人々〉は正当な権威の命令だと思えば、どんな種類の行為であろうと良心の呵責なく実行してしまう」という現象は、ミルグラム実験において確認できたのでしょうか。
先述の通り、〈普通の人々〉である被験者たちが、実験者のことを「正当な権威」だと確信していたのか疑問です。しかも良心の苦しみは感じています。何より焦らされていました。実験結果の数々は、「正当だと思った権威へ服従することの恐ろしさ」とは別の何かを示しているのではないでしょうか。例えば、困惑時の流されやすさ、パニック時の倫理感低下、緊張時の判断能力低下などです。これらはこれらで恐ろしいものでしょうが、「権威/服従」とは別の話でしょう。
少なくとも、ミルグラム実験がホロコーストで殺人に加担した人間の心理に迫れているとは(今となっては)思えないのです。以下の指摘には頷いてしまいます。
「ナチス・ドイツの大量殺戮政策(ユダヤ人に対するものだけではない!)が成功するためには、一回限りの服従ではなく、持続的な服従が必要であった。常識的に考えれば、(ミルグラムの実験のように)拷問者が被害者は同情に値すると考えるよりも、(ナチズムのように)被害者は軽蔑に値すると考える方が、被害者への拷問を継続するのははるかに容易である。
問題はもっと基本的なことです。一日かそこらの単純な実験(297ページ)が、第二次世界大戦中のドイツ人の、何度も熟考し、繰り返し実行され、継続された殺人行為に、どうして匹敵するのだろうか? さらに、もし「普通の」人々が、何かの権威に言われて他人を拷問したり殺したりすることがそんなに簡単にできるのであれば、なぜナチスのような大量虐殺は、歴史上もっとずっと一般的ではなかったのでしょうか。」(DeepL翻訳)
「German Guilt Dilution and Diffusion: Milgram’s German-Exonerating Experiments Doubted. American Universities NUMERUS CLAUSUS. Perry」https://www.jewsandpolesdatabase.org/2019/11/04/german-guilt-diffusion-milgrams-experiments-doubted-perry/
〈アイヒマン〉についてさらに詳しくみていきましょう。
最近のホロコーストの歴史学においては、アイヒマンは、「権威に逆らえずに服従してしまった凡庸な官僚」などではなく、義務感と責任感を持って行動した「確信的な反ユダヤ主義者」であったという見方が有力になっているようです。
「第三に、ブラウニングやゴールドハーゲンの著作に見られるように、最近のホロコーストの歴史学では、普通の加害者のエージェンシーを強調している。彼らは、上司からの報復を恐れて行動したのではなく、強要や不服従への恐れから行動したのでもなく、盲目的に従順であったわけでもない。義務感と責任感を持って行動したのである。セザラニとリップシュタットのアイヒマンに関する証言は、最終解決策の最大の提唱者であるアイヒマンを描いている。これらの記述は、ミルグラムの研究が永続させた悪の凡庸さ、つまり制服を着れば道徳的主体性を持たないオートマトンのイメージとは劇的な対照をなしている。ミルグラムが構築しようとした実験的な説明は、実際には元の現象を誤って伝えていたのです。」(DeepL翻訳)
「Stanley Milgram’s Obedience Experiments: A Report Card 50 Years Later」
2013年10月9日
https://link.springer.com/article/10.1007/s12115-013-9724-3
身柄拘束後のアイヒマンは、責任逃れのため、あえて「凡庸な官僚」を装っていたと言われるようになっています。
「国家機構によって組織された行政的殺戮、「上からの命令」という事実が人間の良心の正常な働きを著しく阻害するという問題、さらに上層の社会前提が何らかの形でヒトラーに屈服し、社会的行動を規定する道徳的格率や宗教的戒律——汝殺すなかれ——が実質的に消えてしまった状況を踏まえ、アーレントが『イェルサレムのアイヒマン』で提起した、人間の最も人間的な、考える力、善悪識別能力を喪失したという意味でのアイヒマンにおける「悪の陳腐さ」概念は、その後世界的な大論争を惹起したが、アーレント自身当時は参照できず、最近ようやく多くの研究者によって用いられるようになったザッセン関係文書(身柄を拘束される以前、アルゼンチンの潜伏先でアイヒマンが本音を明らさまに語ったもの等)において、アウシュヴィッツ絶滅収容所で最多最悪のガス殺犠牲者を出すことになったハンガリー・ユダヤ人の一九四四年の強制移送を「歴史上未曽有の、自らの最大の業績」と誇り、自分は「きわめて用心深い官僚であると同時に自らの血(ドイツ人の血)の解放を求めたファナティックな(狂信的)戦士」と自己規定し、「私にとってドイツ民族に役立つことこそ神聖な命令であり神聖な法であることにかわりはない」と彼がその紛うかたなき信条を吐露開陳(Bettina Stangneth,Eichmann vor Jerusalem. Das unbehelligte Leben eines Massenmörders,Reinbek 2014,S.341,345f.,391)しているのを読むにつけても、尋問聴取収録の本書ではアイヒマンは慎重に事実を曲げ複雑な嘘を各所でついているといわざるをえない。」
ヨッヘン・フォン・ラング編 小俣和一郎訳『アイヒマン調書 ホロコーストを可能にした男』
岩波書店 2017年 431-432頁
ちなみに、上記引用文の中にあるBettina Stangnethによる『Eichmann vor Jerusalem. Das unbehelligte Leben eines Massenmörders』は『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』(みすず書房、香月恵理訳)として邦訳されています。拘束される以前のアイヒマンについて非常に詳しく書かれています(私は読了していません)。
「こうしたことについて今日我々が多くを知ることができるのは、幸運な偶然のおかげである。過去二年間に、それまで研究に使うことができなかった記録文書が多くの文書館で見つかった。それによって「アルゼンチン文書」、つまり逃亡中のアイヒマンが自ら記したものと、今まで「サッセン・インタヴュー」というあまり適切でない名前で知られていた対話の記録やテープ録音が初めてきちんと再構成された。
一三〇〇ページを超えるこの書類が、逮捕以前のアイヒマンの人生や思想について漏らし伝えているのは偶然ではない。(中略)
とりわけ、一つの事実は極めて明白である。
逃亡中ですら、アイヒマンは闇にまぎれようとはしなかったし、秘密裡に行動してなどいなかった。彼はアルゼンチンでも人に見られたがったし、かつて持っていた影響力を行使しようとした。新しい時代の象徴になろうとしたのだ。
光を求める者は、人に見られる。
一九四五年以降のアイヒマンと付き合いのあった人間の数は、従来考えられていたよりも明らかに多い。アイヒマンが地下に潜り逃亡した道を辿る者が出会うのは、追跡者や殺人部隊だけではない。何よりも援助者、シンパ、彼を崇拝する者、友人である。こうした人々は、アイヒマンを知らないとか、あるいはほんの短い期間知り合いだっただけという嘘の背後に身を隠していた。(中略)
遠い地で、亡命者の自由を利用して、アイヒマンの周囲の男たちはドイツや世界で活動をどう展開するかについて意見を戦わせた。野心に燃えて政治的転覆の計画を練り、志を同じくする者同士のネットワークを熱心に紡ぎ、輝かしい国民社会主義という自分たちの見解を現実から守るために記録文書の偽造にまで手を染めた。
そしてアドルフ・アイヒマンはそうした男たちのただ中にいた。」
香月恵里訳『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』みすず書房 2021年 8-9頁
アイヒマンは、「正当な権威から命令されたから」というよりも、端的に言って「正しいことだと信じていたから」虐殺行為に加担していたようなのです。アイヒマンが確信的な反ユダヤ主義者であり、主体的に行動していたというならば、ミルグラム実験は、アイヒマンが抱いていた心理状態とは別種の心理状態を扱っていることになります。
このように、「正当な権威の命令だと思えば、どんな種類の行為であろうと良心の呵責なく実行してしまう」という現象がミルグラム実験において確認されたとは言いがたく、そもそもこうした現象があるにしてもアイヒマンの心理とは関係がない可能性があるのです。ミルグラム実験を「アイヒマン実験」と呼称するのは実態にそぐわないのかもしれません。
では、「アイヒマン実験」でなければ、何なのか。
難問かもしれません。
ミルグラム実験を解釈する際には、「権威」や「服従」という解釈の余地が大きい言葉が持ち出されます。その上、「別名:アイヒマン実験」などと言われると「人種差別」や「集団暴力」などの本来はこの実験と関係ないはずの要素まで連想してしまいます。ついつい実験の射程範囲を広く受け取りがちです。しかし考えてみれば、ミルグラム実験がいったい何を説明できているのかは定かではないようにみえます。
ミルグラム実験の追試実験についても同じ問題が発生していると言えるでしょう。「ミルグラム実験と同じような状況を用意した場合に、多くの被験者は実験者の命令に従って生徒役に電気ショックを与える」。ここまでは追試実験によって再現されたとしましょう。ただ、こうした事象が再現されたからといって、「ほとんどの人間は、正当な権威の命令だと思えば、どんな種類の行為であろうと良心の呵責なく実行してしまう」というような結論が出てくるとは限らないわけです。そもそもの実験の設定が、「正当な権威の命令に対する服従」を測定する検査として妥当とは言いがたいからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
