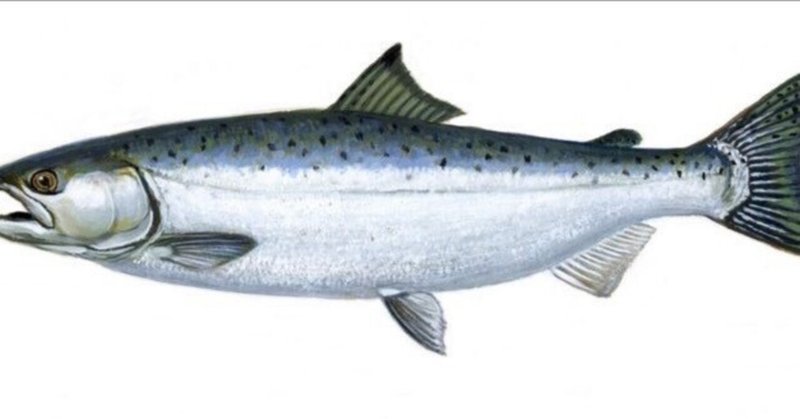
「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」第2話
山梨県で一番古く明治・大正・昭和と続く甲府の真ん中にあるこの高校は、平成の時代には受け入れ難い、古の伝統行事を今でもたくさん残している。
一番の狂気は【強行遠足】という制限時間を24時間として山梨県甲府市から長野県小諸市まで夜通し歩くというものだが、4月に入学したまだあどけなさの残る1年生に向かってまず最初にせまる狂気は【応援練習】と呼ばれる伝統行事だ。
入学する前に散々聞いた噂がある。「応援練習はヤバイ」。
高校に入学して3日目。すべての授業が終わると、1年生は全員教室に残され、男子も女子も裸足で自席に待機させられる。
今から何が起こるのか、わからないまま時は流れ、だんだんと教室を異様な緊張感が包んでいく。
不安から誰も話す人はいない。
1日の役目を終え人気の無くなった教室は、いつもなら夕日が暗闇に溶け出し、大人と子供のはざまで起きる体内の変化から沁み出た青葉臭が床に沈殿し、木材の匂いと塗られたワックスの匂いとが混ざり合い正方形の部屋を満たすが、今日は異様な緊張感が教室を支配している。
遠くから勢いよく教室の扉が開く音と誰かの怒鳴り声が聞こえる。何が起きているのか。
目の前の席に座る小泉はドカンと言われる異常に太い学ランのズボンを履きながらポケットに手を突っ込み、一点を見つめている。常呂も川上もアコも違うクラスになってしまい少し不安を感じていた登校初日、いきなり後ろを振り返ってきた小泉から話しかけられた。
「ギルガメ見てる??」
【ギルガメッシュ★ナイト】、略して【ギルガメ】。まさかいきなりそんな話を堂々としてくる奴がいるとは!話せる奴がいることにうれしさを感じ少しにやにやしながら、しかしなめられてもいけないという15歳ならではの複雑な心境とちょっとした警戒心を同居させつつ、「見てるけど」とそっけなく答えた。
「あれって最高だよな」。
こんな始まりだった。ここから3年間、小泉を含めた川上、常呂、おれの4人はつるむようなった。
振り返りまじまじと小泉の顔を見ると、目鼻立ちははっきりとして凛々しく、身長は180センチはあるだろう、厚い胸板と太い腕、そして学ランを着崩し、下はドカン。いわゆる男前という言葉が似合う風貌だが、世間が言う【良い生徒】ではない部類の人間だろう。
その小泉はいまこの時間をどう思っているのだろうか。長い廊下の一番端にあるおれのクラスに、だんだん音が近づいてくる。緊張感は頂点に達し、物音ひとつしなくなる。静寂に包まれる教室。隣の女子のつばを飲み込む音が聞こえてきそうだ。
突然、ものすごい勢いでドアが開き、「出ろ!」という怒鳴り声。
学ランを着たいかつい連中が教室の中に入ってくる。多くは語らず、「早く出ろ!」とだけ叫ぶ。周りは軽い混乱状態に陥っている。女子の中にはすでに半分涙目の子もいる。おれは何が起きたのかわからず、廊下に出た。すると廊下には教室から出されたすべての1年生が全員不安そうな顔をして整列している。
一体何なんだ。
「歩け!」また短い言葉で指示が出て、おれたちは裸足で廊下を歩き体育館へ。体育館に入ると、等間隔で整列させられる。そして、ドンッという和太鼓の音がなり響く。
マイクを通じて、「応援団の入場です」。
なんなんだ?
マイクのアナウンスが終わり少しの沈黙の後、唐突に吹奏楽部が勇ましい軍歌のような入場曲を流す。しばらくすると、おれたちが入ってきた体育館の入り口から、団旗と言われる大きな旗を先頭に学ランを着た一団が隊列を組んで一列に入場してきた。
一番最後を腕を組んだ羽織袴の男がゆっくりと歩いてくる。
あれが団長と言われる人だという事はその見た目ですぐに分かったが、2年後、まさか常呂がその団長になるなんてこの時は夢にも思っていなかった。
そこから3時間、俺たちはひたすら校歌と応援歌の練習をさせられ、歌詞カードも無く、もちろん入学したてで歌詞を知るわけもなく、吹奏楽部の演奏とともに、ただひたすらに声を出し、声が出ていなければ見回りに来る応援団の連中に「小さい!」と怒鳴られ、歌詞がわからないと前に連れていかれて応援団の前で歌わされ、拍手の練習をしすぎて最後には腕が上がらなくなった。ドカンを履いていた小泉はもちろんすぐに目を付けられ、ずっと応援団に囲まれながら歌を歌っていた。
この応援練習が3日間続き、小泉は3日間ドカンを履き続けた。
高校は、中学校の時よりも色々な文化が入り混じるため、刺激が強い。
小泉のいた学校ではみんな中学で童貞を捨てることが当たり前で、小泉も童貞ではなかった。おれと常呂はモテないことをネタにしながら、心底うらやましいと思っていたが、このふつふつとした気持ちをどこにぶつけるべきなのかとか、そんな難しいことを考えようとも思っていなかった。そこまでの思慮深さをおれたちは持ち合わせておらず、この気持ちが何なのかさえ、考えたことはなかった。ただ、そのありあまる生命力から、常呂は映画に傾倒していった。そして川上はアコともっとべったりして、小泉はよくケンカをしていた。
おれには好きな人ができた。
ミヤ。
小泉と同じ中学校の子で、血管が透けて見えるように白く、細い、近くを通ると甘いミルクのようなにおいのする髪の長い背の高い子だった。黒い部分の多い目と彼女の匂い、そしてどこか暗い雰囲気に魅かれていた。
そのことを小泉に言ったとき、小泉が、ミヤは中学校の時に子供を堕していると言った。おれはそこについてなんの現実味も感じずに、そっか。と言った。
ミヤのポケベルの番号を入手して、いつも夜の公衆電話からメッセージを送った。何日もやり取りを重ね、そろそろ夏が始まろうとしていた。
山梨の夏は暑い。
特に甲府の気温は全国でも有数の暑さだ。盆地はすり鉢の底だから太陽が逃げずに暑いと言うが本当だと思う。その暑い日に、野球部の応援で高校から南へ下った球場へ行った。太陽に照らされる観客席で黒い肌と土に汚れたユニフォーム姿の野球部員を見ている。
応援団はこの暑い中、学ランを着て吹奏楽部の演奏に会わせ懸命に演舞と言われる空手の型に近い動作を繰り返し声を出している。
あの応援練習の後から、応援団の女子人気は過熱しており、学年一人気の小坂さんが応援団長と付き合ったということがもっぱら俺たち新入生の熱い話題になっていた。
川上と常呂と小泉は応援団に入った。あの応援練習のあと声をかけられた。川上から一緒に入ろうと誘われ応援団のたむろしている団室と呼ばれる部屋の前まで一緒にいったが、おれはやっぱりやめておくと、その場から逃げた。怖かったのだ。そのあとしばらくおれは、お前らそんなにもてたいかと笑っていたが、それはただのひがみだった。
野球応援の帰り道、自転車置き場に行くとミヤがいる。
「すこし話さない?」「いいよ」
おれとミヤはベンチに座り、ペットボトルのジュースを飲んだ。ずっと暑い中外にいたせいで、汗が絶え間なく流れ、いつものミヤの甘いミルクの匂いを今日はすごく強く感じる。
応援に来ていたほかのやつらはみんな帰り、周りはおれたちだけになっていた。
女の子と話をすることは得意ではない。いつも恥ずかしくなり、あたふたと早口でまくし立ててその場を去ってしまうか、逆になにもしゃべらないかそのどちらかだ。
ミヤとはなぜか会話が途切れない。
気持ちはものすごくたかぶっているが、それを上回って話すこと自体が楽しい。
南アルプスの稜線が青い空の中に溶けようとしている。
こんなに会話が楽しいと女の子に感じたことは今までない。
目の前を自転車に乗った川上とアコが何かを叫び手を振り笑いながら通り過ぎていく。
夕暮れが、二人の肩を叩き始めたころ、俺はミヤに言った。
「付き合ってください」
彼女ができた。
親父が購入した家は、築数十年は経っている古い平屋だった。家の柱には前の住人が残した身長を測るための柱の傷が残っているようなそんな家だ。
高校に入り、常呂、川上、小泉以外にも多くの友人ができて、その友人たちはよく家に遊びに来た。平屋の家はなんとなくみんな居心地がよかったのかもしれない。
よく家に遊びに来た木下がアンという子を連れてきた。
同じ高校で顔を見たことはあるが、話したことはない。
アンは昔この家に住んでいたと言った。
まさかと思ったが、柱の傷の横には「アン」と彫られていた。
その日を境に夜中、おれの部屋の窓をアンが叩くようになった。
こっそりと。みんなが寝静まった夜に。
続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
