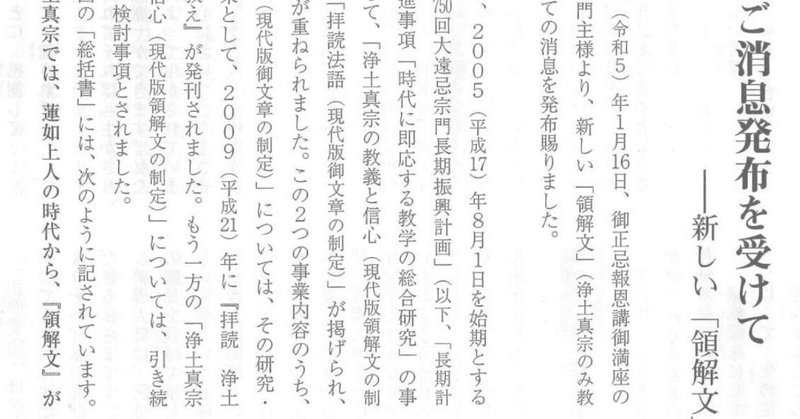
ご消息発布を受けて-新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)制定の経緯-(補足付)
宗報2023年2月号
新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)制定の経緯
2023(令和5)年1月16日、御正忌報恩講満座の法要後、ご門主様より、新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)についての消息を発布賜りました。
宗門では、2005(平成17)年8月1日を始期とする「親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画」(以下、「長期計画」)の推進事項「次代に即応する教学の総合研究」の事業内容として、「浄土真宗の教義と信心(現代版領解文の制定)」及び「拝読法語(現代版御文章の制定)」が掲げられ、研究・検討が重ねられました。この2つの事業内容のうち、「拝読法語(現代版御文章の制定)」については、その研究・検討の成果として、2009(平成21)年に『拝読 浄土真宗のみ教え』が発刊されました。もう一方の「浄土真宗の教義と信心(現代版領解文の制定)」については、引き続き、研究・検討事項とされました。
長期計画の「総括書」には、次のように記されています。
浄土真宗では、蓮如上人の時代から、『領解文』が「真宗教義」を会得したままを口に出して陳述する」(註釈版解説)ものとして依用されてきた。内容は簡潔で、当時の「一般の人にも理解されるように平易に記されたもの」(同上)であり、今なお「領解出言」の果たしている役割は少なくないであろう。
しかしながら、時代の変化により、領解文の理解において、当初の目的であった「一般の人にも理解される」平易さという面が薄れてきたことは否めない。その為、「浄土真宗の教章」や「浄土真宗の生活信条」が創出されてきた。「浄土真宗の教章」は、五項目にわたって浄土真宗の骨格を示すものであり、「浄土真宗の生活信条」は念仏者の生活の心構えが示されている。いずれも、その果たしてきた役割は大きいが、宗門の骨格や生活の心構えであるが故に、『領解文』で述べられる如く、「信心正因・称名報恩」の内容が直接説示されているわけではない。
布教伝道のポイントの一つは、「簡潔さ」と「繰り返し」であるといえる。教えの内容が簡潔に示され、しかも口に出して繰り返し味わう場面が設定されることが重要となる。
したがって、僧侶や門信徒が教義の内容や同信の喜びを簡潔に繰り返し陳述するもので、しかも現代の人々に理解しやすい言葉で表現したものが必要である。つまり、『領解文』の精神を受け継ぎつつ、浄土真宗の教えと信心を現代の言葉で表現した、言わば「現代版の領解文」(領解文を現代語訳したものではない)を製作し普及することが、布教伝道に大いに資することになるのである。
その後、長期計画の「浄土真宗の教義と信心(現代版領解文の制定)は、2015(平成27)年6月1日を始期とする「宗門総合振興計画」に移行され、新たな事業内容「現代版『領解文』を制定し、拝読する」において、引き続き、研究・検討が重ねられてました。その結果、「現代版領解文の制定については、権威あるもの、かつ正しく、わかりやすく伝わるものとなるよう、制定方法も含め、されに慎重に検討を進める」ことが確認されました。
これを受けて、常務委員会の議決を経、2022(令和4)年4月1日付、宗則・「現代版「領解文」制定方法検討委員会設置規程」が施行されました。この委員会の委員長には勧学寮頭の徳永一道氏が互選され、委員には勧学の浅田恵真氏、太田利生氏、北塔晃陞氏、満井秀城氏、龍谷大学学長の入澤崇氏が就任され、鋭意検討が重ねられました。
その結果、2022(令和4)年11月8日付にて、徳永一道委員長より「答申」が石上智康総長に提出されました。
この「答申」には、
本委員会は、(親鸞聖人750回大遠忌宗門長期計画の)「総括書」の内容を基本とするとともに、さらに、現代版「領解文」の考え方、位置づけについては、信心の自己表明を行い、成否の裁断をうけ、自身の歩む道の確認を行うということ。もう一方では、間違いのない現代版「領解文」を拝読、唱和することで、自身を含む、聞いた者にも浄土真宗の肝要を端的に伝えることができるものではならないと結論づけた。
すなわち、「念仏者として領解すべきことを、正しく、わかりやすい文言を用い、口に出して唱和することで、他者に浄土真宗の肝要(安心)が伝わるもの」でなければならいあということである。
と示され、現代版「領解文」の制定方法については、次のように示されています。
『領解文』の変遷は、(中略)蓮如上人時代に信心の自己表明(改悔の告白)として奨励されたことに始まり、以降、法灯を伝承された歴代宗主が深く関与されてきたことが伺える。
さらに、この『領解文』の精神を受け継ぎつつ、現代において「念仏者として領解すべきことを、正しく、わかりやすい文言を用い、口に出して唱和することで、他者に浄土真宗の肝要(安心)が伝わるもの」を制定するのであれば、法灯を伝承されたご門主様にご制定いただくよりほかはない。
宗報第8条には、「門主は、宗意安心の成否を裁断する」と規定されるように、宗意安心に関する立場が明確にされている。
このご門主様にご制定いただくにあたっては、宗法第11条に、
①門主は、総局の申達によって、教義の弘通のため、又は特定の事項について意思を先述するため、消息を発布する
②前項の消息の発布は、あらかじめ勧学寮の同意を経なければならない。
と規定される消息をもって制定いただくのが最もふさわしい制定方法である。
このたびの新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)についての消息は、この「現代版「領解文」制定方法検討委員会」からの「答申」に基づき、ご門主様より発布賜ったものであります。
ご門主様は、このご消息のなかで「新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)を僧俗を問わず多くの方々に、さまざまな機会で拝読、唱和いただき、み教えの肝要が広く、また次の世代に確実に伝わることを切に願っております」とお示しくださっています。ご門主様の願いにかなうよう私たち一人ひとりが行動し、自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に努めてまいりましょう。
(文責 統合企画室)
以下、新しい領解文を考える会運営チームによる補足
上記では、「浄土真宗の教義と信心(現代版領解文の制定)」について引き続き研究・検討事項とありますが、『拝読 浄土真宗のみ教え』には、「浄土真宗の救いのよろこび」が領解文の精神と伝統を受け継いだものとして記されています。なぜか、この「浄土真宗の救いのよろこび」が存在しなかったものとされています。
「宗報」2009年6月号には以下のように記されています。

また、「拝読 浄土真宗のみ教え」にもこのように記されています。
その研究成果が、『領解文』のよき伝統とその精神を受け継いだ「浄土真宗の救いのよろこび」、ならびに『御文章』のよき伝統とその精神を受け継いだ「親鸞聖人のことば」であります。

その後、2018年に真宗教団連合(当時の理事長は石上氏)が行った実態把握調査でオリジナル設問として「浄土真宗の救いのよろこび」が調査され、8ページにわたって取り上げられています。
その翌年、2019年に「浄土真宗の救いのよろこび」が「拝読 浄土真宗のみ教え」から削除されました。一部では高く評価され、依用していた寺院が少なからずあったため、説明もなく突然の削除に戸惑いの声が多数あがりました。
今回の経緯説明の中にも、そのことについて一切触れていません。それどころか、「拝読 浄土真宗のみ教え」は、一方の「拝読法語(現代版御文章の制定)」を受けて制定されたこととして記されており、現代版領解文の制定については検討事項とされ、事実と異なります。
いただいた浄財は、「新しい領解文を考える会」の運営費に活用させていただきます。
