
Chain, Saw, and Man──『チェンソーマン』『ルックバック』、虚構と現実と物語の先
藤本タツキ『チェンソーマン』(集英社)の題名は、なんで「チェーンソー」マンではなく「チェンソー」マンなのだろうと以前から思っていた。刃のついた鋸をモーターで回転させ樹を切り倒したり氷の彫刻コンテストをやったりするあの機械はチェンソーという表記をすることもあるし、チェーンソーマンよりチェンソーマンのほうが語呂も良い気もする。しかし、はたして語呂だけの問題なのだろうか。
単行本を読み返すと、そこに書かれた英字での表記はChainsaw manでもChainsaw-manでもなくChain saw manで統一されていた。英単語においてはChainsawだけでなくChain sawという表記もあることはある。しかし、ここに置かれた'saw'とは鋸ではなく'see'の過去形「見た」ではないのか。
ジャレド・ダイアモンドによる文明史のノンフィクション本『銃・病原菌・鉄』は、原題が'Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies'だが、『チェンソーマン』はChain, Saw, (and)Man、「連鎖・見た・ひと」ではないのか──実際のところは商標とかなんとかそういう些細なことなのかもしれないけれど。

画像『チェンソーマン』9巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2020)より
物語の解釈にはおおまかに、
(1)作家の意図した語り口や演出が成立しておりそこに解釈の自由度は少なく示された正解に立脚し論じたもの
(2)リドルストーリーや暗喩など正解はないが予め広く設定された自由度の中で説得力のある仮説を提示したもの
(3)作家の意図とは無関係に読者や観客が主観・私見に関する読み方を示したもの
があるとして、本文章はそのうち(3)なのでご注意を。正解でも不正解でもない。こういうのは「考察」でもなんでもない。これは、ただの「読み方」だ。
以下の文章は『チェンソーマン』「第一部 公安編」の結末である単行本11巻までの内容に触れている。その点にもご注意を。さて、これから私の空想にしばしつきあっていただくこととなる。
【注意:以下の文章は『チェンソーマン』単行本11巻までの内容に触れています。物語の舞台設定や登場人物の背景や用語などの説明は省いているので、本編を未読の方がお読みになることは想定していません】
藤本タツキが『少年ジャンプ+』で2016年から18年にかけて連載し全8巻で美しく完結した『ファイアパンチ』を私がなぜ好きだったのか。それは物語(フィクション)とひとの話、虚構と現実との話だったからだ。先日(2021年7月19日)Webサイト『少年ジャンプ+』で無料公開され大反響を巻き起こした同作者の143ページ描き下ろし読み切り作品『ルックバック』もまさしくそういう作品だったと私には感じられた。内容に関してはここでは多くは触れない。現時点(2021年7月22日)ではまだ無料で読めるし、2021年9月3日には単行本が出るということなのでそちらをご自身でお読みになって確認していただきたい。
藤本タツキ『ルックバック』
https://shonenjumpplus.com/episode/3269754496401369355
『チェンソーマン』は「フィクションとひと」「虚構と現実」の風味が当初は薄く感じられて、自分は単行本が出たらその都度入手はしながらも「ファイアパンチのほうが好みだったかな」とは感じていた──これまでは。
『チェンソーマン』の各所にとても気になる演出が出てくる。時折「物語の外」からの介入にしか見えないコマがあるのだ。手塚治虫マンガであれば作者が出てきて「メタですよ」とわかりやすく語るところだが、『チェンソーマン』ではまったく説明されず、エクスキューズなしに唐突に挿入される。コマの枠やページの縁──物語世界を壊すノイズかのような、黒板を爪で引っ掻かれたかのような、嫌な感じ。最初に目にしたときは「なんだ、これは」と唖然とした。


画像:『鉄腕アトム』1巻(手塚治虫/光文社文庫版より)

画像:『チェンソーマン』3巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2019)より



画像:『チェンソーマン』8巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2020)より
作中世界に登場して多くのひとを死に至らしめる《銃の悪魔》に顕著なように『チェンソーマン』では様々なかたちでの理不尽で不条理な暴力や死が描かれる。それらを現実社会の出来事の寓話として捉えることは可能だろう。しかし同時に、作中登場人物がナチスのことを知らないという衝撃的な描写がある。最初にこのくだりを読んだ際には虚構と現実のあいだにあったはずの輪郭──いや、コマの枠線か──が揺らいで目眩がした。不条理な虐殺、理不尽な大量死をもたらす《銃の悪魔》という存在が真ん中に据えられてきた物語世界の歴史にナチスが「存在しない」。登場する車両が妙に古めかしかったりソ連がいまだ存在したりと我々の現実とは違う歴史を持つ作中世界であることは仄めかされていたが、それでも衝撃は大きかった。
主人公デンジに宿るチェンソーマンの力のひとつには《食べた悪魔はその名前の存在がこの世から消えてしまう》能力がある。




画像:『チェンソーマン』10巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2021)より
劇中でチェンソーマンが食べて存在を消したと語られるモノの中には「ナチス」「エイズ」「第二次世界大戦」「核兵器」以外にも、現実には存在していない《アーノロン症候群》《租唖》《比尾山大噴火》《第六感》《子供の精神を壊すとある星の光》《生命が寿命を迎えると死の他にあった4つの結末》が挙げられている。
想像してみる。もしかしたら我々の住む現実社会もチェンソーマン的な存在によって変えられたあとの世界なのではないか、フィクションの力で既に変化させられた社会なのではないか──ここの段はあまりにも飛躍するが、「人間が物語を欲するその願望は、人間社会が戦争を生み出す心理と似通ったところから生じているではないか」という疑問すら私の中には浮かぶ。
私が『ルックバック』を公開直後に読んで激賞したのは、今ここに書いている文章のようなことを最近考えていたからだ。私にとって『ファイアパンチ』は「ひとにとってフィクションとはなんなのか」という話だったが(だから物語の後半になればなるほど好きだし最終回は完璧だと感じた)、『チェンソーマン』とフィクションとの関係は「フィクション(マンガ)で世界(現実)は変えられるのか」だ。『ファイアパンチ』、『チェンソーマン』第一部、『ルックバック』、それらすべてが物語についての物語だ。映画には「映画に関する映画」というジャンルがある。先の三作品のベクトルもそちらへ向かって語られているように思う。
(余談だが『ルックバック』を読んだ際に、私が最も「作者の意図」を知りたいと感じたのは作品執筆の動機や元になった人物や出来事があったのか──などではなく劇中で主人公二人が観た映画が何なのか?だった。作中で明示されている日付、登場人物のひとり京本が「2012年度AO入試」に現役合格していたなら、そこから逆算してあの映画館の場面が08年の春の出来事であれば5月公開『ミスト』だろうか。でも『ミスト』はR-15か。それならば6月公開『シークレット サンシャイン』だろうか。ちなみに作中で部屋に貼られて登場するカレンダーはそれが意図したものかは別にして日付と曜日から年代を特定しようとすると矛盾があることを付記しておく。なお、映画館で同じ物語を観ている観客席の左下にいる人物、これはあとで登場するキャラクターと同一存在なのではないか?とすら思うが──多くは語るまい、語り尽くせまい、何故なら『ルックバック』という作品は仕掛けられたアイディアを支える画力と構成力と演出力がそれを傑作たらしめているのと同時に、読んだ者が自身の実人生において過去にあった決して取り戻せない失ったものの記憶を差し出して完成するタイプの作品で──ひとに依って受け取り方も様々だろうから。私自身はイ・チャンドンの映画を観終えた直後と同様の魂消る感覚があった。静かな描写に圧倒的なエモーションが込められていたことに気がつくあの特別な感覚が)

画像:『ルックバック』(藤本タツキ/少年ジャンプ+/2021/p61)より
現時点での私の読み方を簡潔に記す。『チェンソーマン』は「物語と作者」の話だ。登場人物たちが対峙しなければならない真の敵は、自分たちのいる物語世界の創造主──作者だ。この物語の作者はどこかの時点で、ある日、ふと思ったのではないか。「自分が彼ら(作中人物)を苦しめて殺している」と。『チェンソーマン』第一部の終了後に『ルックバック』が公開されたことの意味を考える。「物語とひと」「虚構と現実」、そのさらに先へ。
先に書いたように自分は『ファイアパンチ』における虚構への言及、特に終盤のメタフィクション的な側面を好きだったこともあり、『チェンソーマン』第一部の中盤までは主人公デンジの貧しい境遇や、いくらでも暗喩的に受け止めることが可能であろう《銃の悪魔》の存在などから寓話的な物語だと捉えて「うーん、なんだかごく一般的な、少し捻ったヒーローものに脱色されてしまったような気がする……ファイアパンチのほうが好みだったかも」と感じていた。でもその印象は間違っていた。『ファイアパンチ』よりも『チェンソーマン』のほうが遥かに、並外れてメタフィクショナルな構造をもつ物語だったのだ。
『チェンソーマン』第一部終盤で起きるデンジとマキマとの衝突や二人の会話のあれこれ──物語の筋、表層的には当初から登場していた謎の人物がついに正体を表して主人公と敵対するだけだ──は最初に読んだとき「さ、さっぱり意味がわからん……なんだこれは……」と混乱していたが、これは寓話ではなく巧妙に表面処理されたメタフィクションだ、物語と作者の話だ、と本作の舞台や筋への捉え方が変化すると突如として読めるようになった。その捉え方の変化は『ルックバック』を読んで確信に変わった。
デビルハンターという職業につく主人公たちが敵対する《悪魔》が生まれ出ずる処、作中の人間社会で《悪魔》が死んだときに還る先として《地獄》という場所が設定されている。8巻にて《地獄》へ強制的に移動させられた主要登場人物たちはそこに現れた《闇の悪魔》に為す術もなくボロボロにされてしまう。直前まで圧倒的な強さを描写されていたキャラクターすらひとコマで切り刻まれてしまう。当然だ。どれほど強くとも彼らは、ただの絵だ。そう、あの《地獄》とはフィクション中のキャラクターである彼らにとって「我々のいる現実世界」のことではないのか。《悪魔》たちは現実から生じて物語世界でキャラクターへと化し現実へ還ってゆく。

画像:『チェンソーマン』8巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2020)より
さあ、ここまで長くなったが、本題に入る。太字にしたところだけ読んでくれてかまわない。これは空想なので同意してくれなくともいい。むしろ異論反論や反発を期待したい。
『チェンソーマン』の主人公デンジに与えられた力、「チェンソーマン」とは何か。それは作中ではっきりと明言されている。マンガの物語世界内で《いいですか?これは漫画の主人公の話じゃないですよ?》とテレビのアナウンサーが言う。逆説だ。チェンソーマン=マンガの主人公だ。「マンガ」そのものといってもいい。
Chain, Saw, and Man。現実と物語とのあいだで回り続ける刃のように繰り返されてきた寓話や暗喩や創作の連鎖を見てきた者だ。

画像:『チェンソーマン』11巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2021)より
作中でアンタッチャブルともいえるほどの強力な恐ろしい能力を持ち、一部のキャラクターからは無償の愛と敬意と畏怖の念を抱かれ、一部のキャラクターからは蛇蝎のごとく嫌悪され抹殺を望まれる謎めいた存在《マキマ》こと《支配の悪魔》とはいったい何なのか。この文章をここまでお読みになったあなたには、とてもお伝えしにくく言い難いことではあるが──マキマ=読者だ。作中登場人物たちが戦い・苦しみ・死に・《チェンソーマンの力》に何かを仮託する姿を愉しみ、マンガの主人公の活躍や苦悶をコマの外側からページを開いてエンジョイする、作者をも含めた私・我々のことだ。
マキマが他者を「匂い」で認識するのはここに書いた『シン・エヴァンゲリオン劇場版』感想における《なぜ真希波・マリ・イラストリアスが「匂い」のことを口にするかというと、画と音しかない映画というメディアの外側の者だから》と同じだ。マキマは読者で真希波は観客だ。何度死んでも甦ったマキマがラストで《復活》しなかったのは「第一部が終わったから」だ。物語が描かれてない以上、物語内世界を読者が観測する術はない。





画像:『チェンソーマン』9巻、10巻、11巻(藤本タツキ/集英社/kindle版/2020,2020,2021)より
マンガの登場人物がマンガの世界にいながらにして、作者や読者・我々のいる現実世界と対峙する物語、それが『チェンソーマン』だ。いまのところの・私の・理解としては。
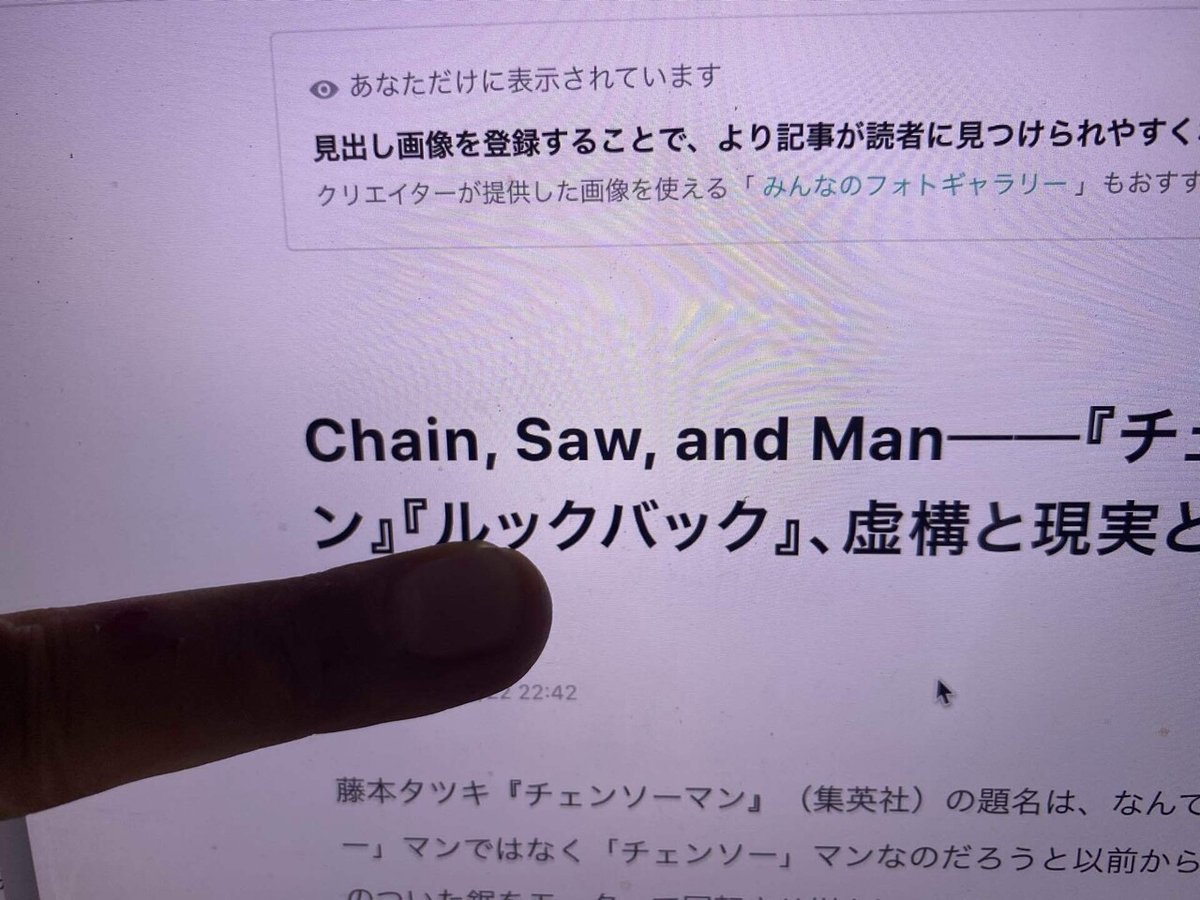
〈2021/09/12/追記〉
「どうしても気になっていて欲しい本がある」と言う子を連れて古書店や書店を回った日だった。自分の本を買う予定はなかったのだが──店頭に『ルックバック』単行本が積まれていて、あの作品がこうして本として目の前に存在することに、短めの中編が単独で単行本になってることもあってページ数が少なく一般的なマンガ単行本よりも薄いその本に、説明し難い現実感の無さがあり奇妙な気分になる。本棚の空きスペースが少なくなっているので電子書籍で手に入れるつもりだったが、実物を目にすると手にとってしまう。
平積みから持ちあげた瞬間に、その本は作品の重みと反した軽さで、虚構と現実の境目に置いてあるかのような存在感に心を掴まれて、子が欲しがっていた本と一緒にレジに持ってゆく。まるでフワッと自分が浮き上がったような錯覚を覚える。実際、私の身体は0.2mmくらいは浮いてたんじゃないか。気になっていた本を見つけることができ、本屋の棚で発見して欲しくなった本も買っていいと言われ、その両方を抱え店内をスキップしながら11cmほど浮いていた子を目にした。




『ルックバック』(藤本タツキ/集英社/2021/p.43,45)より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
