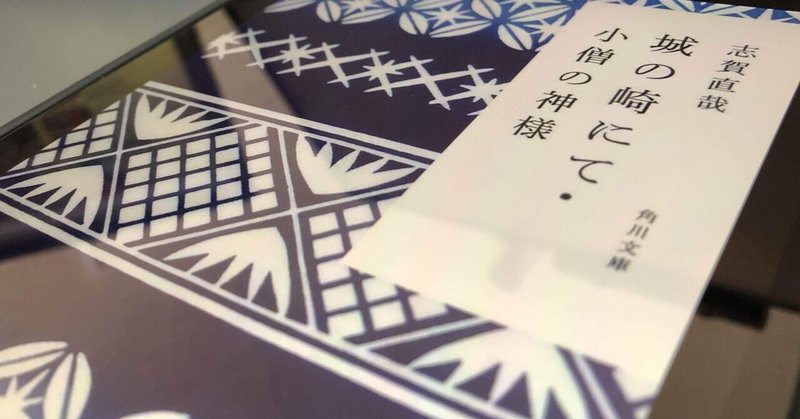
小説の神様が筆を折ってまで守った小僧への気遣い<志賀直哉『小僧の神様』>
志賀直哉『小僧の神様』の核心に触れるので、ネタバレしたくない人は回れ右。
創造主が創作物を犯していい領域とはいかほどのものだろうか。無論、これは神とか天地創造とかそういった類の噺ではなく、フィクションにおける問題だ。クリエイターが、自身の作ったキャラクターをどこまで好き勝手していいものなのか。特に、現在ではIPが企業によって運営されることも多い。その中で、資本主義に踊らされ「崩壊」してしまう人(キャラ)もいる。それが悪いということではなく、事実、いる。僕はこの一編(『小僧の神様』)を読んで、そんなことに思いを馳せてしまった。
小僧は神様に会えず、神様に配慮された
簡単に言えば、話の流れは以下の通りだ。
貴族院議員のAは、立ち食い寿司屋でお金がなく食べたい寿司を食べれない小僧に出会う。その時、声をかけておごってやることはできなかったが気にかかっていた。
後日、Aがたまたま入った秤屋にその小僧が働いていた。これは好機と思い、小僧を誘って立ち食い寿司へ行った。議員ということもあり、秤屋の帳簿に書く名前と住所は出鱈目にした。
寿司屋に着くとAは店主に何回か来ても足りるほどの金を渡し、小僧が食べたい時に何度来ても好きなだけ食べられるよう頼んだ。そして、何も言わずに去った。小僧は喜んで3人前の寿司を平らげた。
小僧は、こんなよくしてくれる「あの客」は何者なんだろうと思いを馳せる……
*引用ではなく僕が簡単にまとめた内容です。
と、ここで突如物語上に作者が登場。そして以下のように締めくくる。
「作者はここで筆を擱くことにする。実は小僧が『あの客』の本体を確めたい要求から、番頭に番地と名前を教えてもらってそこを尋ねて行くことを書こうと思った。小僧はそこへ行って見た。ところが、その番地には人の住いがなくて、小さい稲荷の祠があった。小僧は吃驚した。──とこういう風に書こうかと思った。しかしそう書くことは小僧に対し少し惨酷な気がして来た。それゆえ作者は前の所で擱筆することにした。」
ーー志賀直哉『小僧の神様』より引用
これはどうしたものか。突如神(作者)が現れて物語を終わらせてしまったのだ。作者である。やろうと思えば奇跡を起こしてAと小僧を引き合わせてハッピーエンドにすることも可能なのだ。
でも、それはしない。「少し惨酷な気がして来た」というふわっとした感じにその対応が現れているのか。はたまた作家としての矜持なのか。ひいてはこの展開すら計算の上なのか。
僕にはわからない。が、目が覚める気分となった。
僕もエンタメ業界の端っこに棲む存在として、キャラクターはどこまで制御していいのか。世界をどこまで壊していいのか。それとも、その常識や良識は「面白い」の障壁でしかないのか。
頭を抱えてしまった。
一言コメント
短編小説を夜に読むと寝付きが良くなる。*個人の見解です
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
