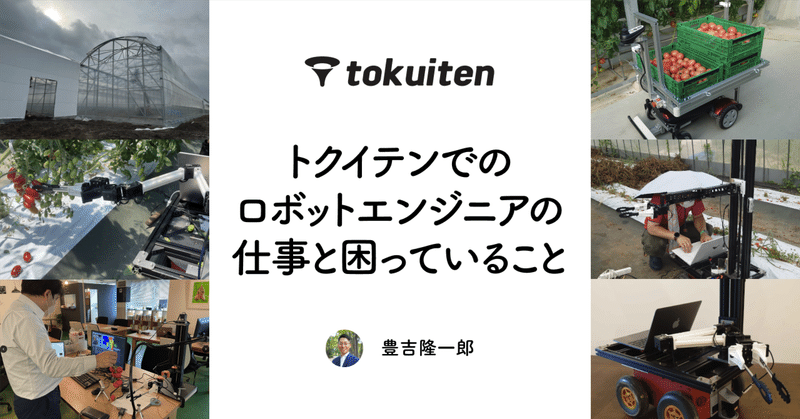
トクイテンでのロボットエンジニアの仕事と困っていること
トクイテンではロボットエンジニアを募集しており、採用ページもあるのですが、この記事では2022年10月6日時点でどういうことをどのようにやっているのか紹介させていただきます。もし興味を持ってもらったら応募をお願いします。副業、転職、バイト問わず募集しています。
ちなみに前回は森さんからの視点でリモート開発の様子を紹介しました。そちらも是非ご覧ください。
私の方からは「何を」「どのように」というところを中心にお伝えしたいと思います。
場所

我々の農場は愛知県知多市、オフィスは名古屋市と東京の大手町にあります。ロボット開発は各自の自宅やオフィスで行ってます。
働き方
副業を含めると現在Slackには17人のメンバーがいます。そのうちロボット開発に関わっているのは私含めて5人です。創業者の豊吉と森、副業で1名のメカエンジニア、パートタイムで2名のロボットエンジニアという構成です。
それぞれリモートで作業をして必要があればオフィスや農場に集まるというスタイルです。Slack、Github、Notionを使って情報のやり取りをしています。
副業の方には採用や財務や広報などをやっていただいています。農業系だと栽培の遠隔サポート、ハウス建築の管理などやってもらってます。トクイテンではオープンであることを大事にしているので副業であっても社員と同じ情報(財務データ含む)にアクセスできますし、数百万円〜数千万円のお金を扱うようなこともお任せしてます。副業だから何かをさせないというような差はありません。
今やっていること
長期的には食糧生産の自動化を目指していますが、今取り組んでいるのはミニトマトの収穫ロボットの開発です。
ミニトマトの栽培では収穫にかかる人件費(時間)が一番多く、人件費だけでなく、その時にだけ必要な人員を確保する労力が大きな負担になっています。それをロボットでできるだけ減らし、普段の人員だけで作業が続けられるようなことができると大きなインパクトになります。

またロボットが収穫できれば夜間の作業も可能なので、夜中に収穫し、朝出荷することができれば品質の高いミニトマトが消費者に届けられたり、余分な保管費用の削減にもなります。
普通の収穫ロボット開発との違い
普通のというほど他にやっている会社があるわけではないのですが、普通との違いは我々が自分たちで作物を作っているというところにあります。ロボットを売り出すつもりがないと言い換えてもいいかもしれません。
ロボットを売り出すつもりがないと次のような違いが出てきます
販売できるレベルのアフターサービス、販売できるレベルのメンテナンス性、販売できるレベルの信頼性などを考慮しなくてよい
施設や品種や栽培方法などの環境の違いを考慮しなくてよい
必ずしもロボットやAIで全てを解決する必要はなく、栽培方法や施設を改造できる
実際に我々がやってることとして、収穫対象のミニトマトかどうかの判断はAI任せではなく人も遠隔でクリックするようにしたり、LiDARの設定が難しければ畑の畝を高くしたり、通路を広くしたり、壁を作ったりということをしています。
SLAMのコードを書き換える代わりに800円の板で現実世界に壁を作って解決した。自社農場での運用が前提だと「これでいいのだ」となる。 pic.twitter.com/NLmjec8eLN
— とよし (@toyoshi) August 1, 2022
ロボットのために鍬を持って畝を作り替えるのはなんとも言えない気持ちになりますがそれでいいと思いますし、むしろロボットのための環境を作っていかないと何倍という効率の農業は実現できないだろうと我々は考えています。
直近の開発
現在は収穫ロボットの性能向上と複数台の生産に向けての準備をしています。1月ごろに10台近くの収穫ロボットやモニタリング、運搬ロボットが農場で動くような状態を目指しています。
次の動画は7月時点でのロボットです。
次の動画は状態を変えながら30回収穫動作をさせた実験です。30回中14回収穫できました。かなり良い条件で実験しているのでまだまだ改善が必要ですが100%の収穫は目指していません。もし半分でも収穫してくれれば収穫の人件費は半分になるので十分役に立ちます。
どうでしょうか?数ヶ月後にこういったロボットが何台も農場を自律的に働いている姿を想像すると私はとてもワクワクします。
もっと早く、もっと高い成功率でできるようになりたいというのが我々が今取り組んでいることです。開発はPythonとROSを使ってやっています。もし「私がやれば早くできるかも?」「こういうアイデアがあるんだけど?」というのがあればぜひお話し聞かせてください。
どんなスキルのある人を探しているか
さらに細かくいうと今やっていることはこういうことです
収穫率の向上と、スピードアップ
LiDARとARマーカーを組み合わせて圃場内を自律走行できるようにする
現在使っている市販の移動台車を自社設計のものに置き換える
大まかな設計が終わったところです
さらには複数のロボットが協調して動いたり、遠隔で監視・操作するためのソフトウェアが必要です。この辺りの技術で興味がある、やったことあるという人はぜひ!(興味ありそうな人がいればシェアをお願いします)
こんな会社の文化・行動指針にしっくりくる方が向いています
オープンであること、なんでも試すこと、文書やテキストベースで進めていくことというのに特に力を入れています。

オープンさについては資金調達状況から保有現金額まで副業含めて全員がわかるようにしています。文書化についてはNotionとSlackをベースになんでも書き残し、非同期で意思決定が進んでいくことを意識しています。
これらはメンバーが全国にいる中で、十分にコミュニケーションをとりながらも迅速に進めていくための工夫です。そういった文化に共感してくださる方は大歓迎です。
最後に
いま農業従事者の平均年齢は67歳程度と言われており、今後人が減っていくことや、有機農業などの農法への変換は不可避と我々は考えています。そこで必要になるのがIT、AI、ロボットの活用です。
私豊吉は岐阜高専出身です。高専に行ったのはロボコンに出場したかったからです。今そのロボットを仕事にできており、しかも人類には絶対に必要な農業の発展に貢献できるかもというのは本当にやりがいのあることだと感じながらやっています(起業の経緯の詳細はこちら)
会社説明会などでは何度も繰り返し言っていることですが、持続可能な農業というのは誰かが実現するか人類が絶滅するかのどちらかです。今はそれに貢献するチャンスです。誰かに任せるのもいいですが、僕らの力でそれを少しでも早めるチャレンジをできたら最高の人生になるのではと思っています。
ぜひ一度ロボットやロボットのアイデアについてお話しさせてください。いますぐ軽い気持ちでカジュアル面談や今月開催の会社説明会にお申し込みください。お待ちしております。
カジュアル面談・Meetyは下記リンク。会社説明会はこちらをクリック!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
