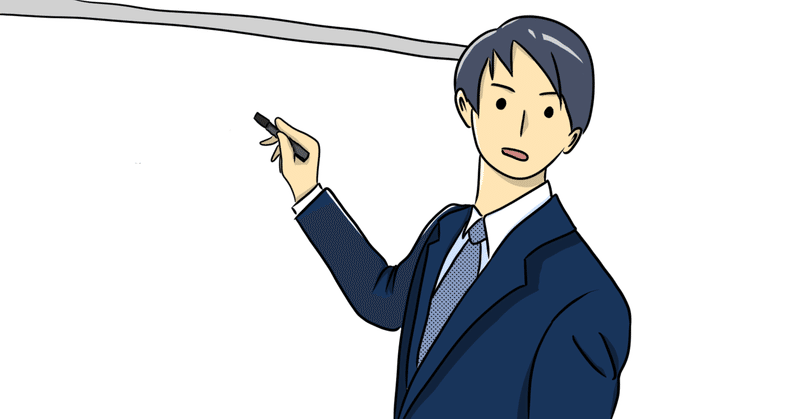
管理系部門がIPO準備でやること Part.03 - 法務編① -
「管理系部門がIPO準備でやること」について、数回に分けて説明・ご紹介しています。前回までは管理系部門全体編、経理編でした。管理系部門は守備範囲が広いですね。
今回は法務編です。
(*着手する順序は時系列ではないので、その点はお許しください。)
(*約7分程度でお読みいただけます。)
法務の守備範囲は狭い/広い?
IPO準備をする会社で、多くの社員がその準備に携わりますが、その業務の範囲(守備範囲)によって、ずいぶんと偏った業務の割り振りがなされるかと思います。なかでも、この法務については、IPO準備会社によって様々なかたちが取られているようです。例えば次のようなものです。
上場会社として維持されるべきガバナンス、コンプライアンスを経営面、会計面など多方面から強化することをメインとするもの(経営方針等を重視/法務は中核メンバー)
永続可能なシステムとしての内部管理体制を構築することをメインとするもの(組織・体制等を重視/法務は中核メンバー)
規程、基本方針、ガイドライン等のドキュメント類作成をメインとするもの(法務は中核メンバーではない)
各IPO準備作業について、その法的観点からアドバイスするという側面支援としてのメンバー、またはこのアドバイスを顧問弁護士に依頼しているので、この顧問弁護士との連絡窓口
上記のように、かたちはいろいろあると思います。
そのどれが正解か?間違いか?というものはありません。また、その準備会社の法務の方の素質、性格、キャリア、知識などによっても用いられ方があると思いますので、「これが最良の方法」ということはできません。
ただしこれだけは言えます。
その会社の方針(ポリシー)に基づいた会社の進路としてIPO準備を進めるために、どのような体制(陣構え)で遂行していくか?
これについて全体を俯瞰して、今後5年、10年後の会社のあるべき姿に、どのような道程を辿っていくのか?
IPOは、会社の大きな成長、今後あるべき姿への道程の “ マイルストーン ” になっているか? です。
IPO準備の作業工程で、法務のやるべき守備範囲はかなり広いです。ご存知かと思いますが、例えば次のような事項です。
会社のコンプライアンス体制構築のための規程類(ガイドライン、業務マニュアルを含む)の整備
会社のガバナンス体制強化のための規程類の再検討と改訂
上場申請期までに形成すべき機関設計と取締役会/株主総会スケジューリングや、決議事項作成等準備
株式法務(資本政策の側面支援や持株会設立など)
契約法務(契約書雛形の整備や関係法令との適合チェック。締結済みの契約の関係法令との適合チェックなど)
社内各業務の法令遵守状況チェック(契約関係以外にも労務管理状況や各事業の商流の適法性チェックなど)
内部監査/内部統制体制構築の側面支援(特にコンプライアンス面に関する支援)
など
上記が全部ではありません。
その会社の事業内容や規模(社員数、売上額など)、経営方針、社風、所属する団体が定めた規則・ガイドライン・・・などの要素を考慮すると、法務の守備範囲が広いだけでなく、必要とする時間と業務量は膨大です。しかも、上に上げました事項をそれぞれ見てみますと、じつはIPO準備を進めるうえで、法務が守備範囲とする事項の準備進捗状況(進め方、時間の掛け方など)によっては、IPO準備全体が停滞/途中休止という事態になりかねない事項ばかりです。
「IPO準備が、なかなか進まず、遅延しているようだ」とお気づきの経営者の皆さん。その遅延の原因は、上の事項の停滞が原因かもしれません。一度ご確認ください。しかしその停滞は、法務担当者が原因ではありませんし、法務担当者による業務への怠慢ではありません。じつはその原因は、「そのすべての作業タスクを同時並行で進めなくてはならないものがある」ためなのです。
法務に分担される作業タスクは、それぞれを見ると個別にみて大変重要ものなのですが、しかしそれらはそべて連動/並行しており、いざ着手すると、他のタスクとの関連や社外的な要因との関係によって、意外と捗らないものがあるのです。
このようにみてみますと、法務が担う作業タスクや守備範囲は狭いものではなく、想像以上に広くて、しかも奥深いものがありますので、IPO準備のための準備の際には、しっかりとタスク整理とスケジューリングすること。これに外部委託を含む人員配置(法務とこれを補助する他部署からの応援など)を十分に検討する必要があります。
法務担当者と法務部門の必要性は「会社の方針次第」
前述のように説明しますと、IPO準備のためには法務担当者の人材採用が必要/必須だとか、法務部門設置が重要なKeyだと思われるかもしれません。もちろん、IPO後も上場維持の必要性からコンプライアンス、ガバナンスの面の各体制を維持/強化するために、法務の力は大いに必要ですので、検討する必要はあるかと思います。
ただし、その検討内容で、必ずしも正社員として人材採用が必要だとか、法務部門が無いとダメである、という根拠はどこにもありません。上場審査の際の代表取締役ヒアリング等で、法務の正社員がいないこと、また法務部門が無いことで、指摘があったり審査に不合格になったというお話しは聞いたことがありませんし、仮に指摘があったとしても、審査に不合格となることはないと考えます。その理由は、法的にもCGコード上にも根拠がないためです。しかしながら、法務担当者がいない/法務部門が無いからと言って、法務が必要ないというわけではありません。必ず必要です。
言い換えれば、法務担当者・法務部門を外部委託(アウトソース)することで、会社のコンプライアンス、ガバナンスの各体制を効率的・効果的に維持/強化していれば、コンプライアンス、ガバナンス面が脆弱であるという指摘は無いと考えます。
ではここで、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード(以下CGコード)」(2021年06月11日改訂版)を参照して、法務がどのように取り扱われているかをみてみましょう。
<1つ目>
【原則4-11 . 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、 ジェンダー や国際性 、職歴、年齢 の 面 を含む 多様性と適正規模を両立させる形で構成 されるべきである。また、監査役には、 適切な経験・ 能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識 を有する者が選任されるべきであり・・・(以下省略)
「コーポレートガバナンス・コード(以下CGコード)」(2021年06月11日改訂版)
<2つ目>
【原則5-1 . 株主との建設的な対話に関する方針】
(前段省略)
補充原則 5-1
② 株主との建設的な対話を促進するための方針には、少なくとも以下の点を記載すべきである。
(中略)
(ⅱ) 対話を補助する社内のIR担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策
このようにCGコードでは、上のとおり2箇所です。ただし1つ目は、「監査役の任に適する知識として法務の知識を有する者が選任されるべき」とありますので、弁護士ほか士業等の法的な知識を有する方のことを指しております。これを除いたら、1箇所です。
また、2つ目ですが、会社が株主との建設的な対話を促進するための補助として法務部門等の有機的な連携とあります。この「有機的な連携」とは、お互いに不可欠な相互作用をする補完関係のことですので、補うことを目的としていますから、これが法務部門、法務担当者でなくてはならないわけではなく、これを補完する外部委託でも可能である、という理解です。しかも、ここでは「株主との対話」が大きな目的ですので、これの知識や経験を持った方(外部委託を含む)が適任であることに間違いはありません。
では、会社に「法務担当者・法務部門がまったく必要ないか?」と言われると、そのようなわけではありません。CGコードにこのように記載があり、また会社経営上、法務の要素は必要不可欠なので、存在は必要です。ただし、その存在が「正社員である」必要は無い、ということです。
例えば、企業法務の知識と経験を有する士業(弁護士、会計士、税理士、司法書士、行政書士)は適任です。その先生方の中では、会社の法務から転身した先生方もいらっしゃいます。企業法務全般、特にリスク予防法務、臨床法務(*1)、戦略法務、株式法務などの分野を守備範囲としていますが、これらの範囲は個別にそれぞれが成立しうるものではなく、知識と経験がバランスよくブレンドされ、守備範囲の隅々まで目が行き届き、それらに対応しうる方策と行動力で成立するものです。このため、逆に知識だけで経験の無い正社員については、「株主との対話」を大きな目的とした他部門との有機的な連携をする際に、法務担当者が法務全般を守備範囲としていないままで対応するのは、危ういところがあります。
(*1 : 臨床法務は非弁行為に当たる部分がありますので、外部委託で臨床法務の受託可能なのは弁護士のみです。)。
法務業務を担当する人材は、相応の知識と経験を持っている方が適任です。しかし現在の人材市場ではこのような人材は不足していますし、長期的には社内で育成する必要があります。さらに、目先の、特にIPO準備直前またはいままさにIPO準備中の会社であれば、個別の業務をいったん外部に委託するのが現実的だと考えます。
このように考えますと、法務担当者を採用してどのように活躍してもらうか、そのためには会社はどのような知識と経験も持ち合わせた人材が必要なのか。さらに会社は必要としている人材の知識と経験について、経営方針を参照して適合しているのか、適合している以上に企業価値(ベネフィット)を向上させる要素を持っているか。これらを検討することで、本当に法務担当者を正社員として採用すべきなのか?人員数はどの程度必要か?また、法務部門も同様に、守備範囲をどの程度にするのか?そもそも法務部門は必要か? ・・・ 会社、経営者層は、会社の経営方針に基づいて十分に検討しなければなりません。そうすると、おのずと法務を担当する人員、部門の必要性と並行して外部委託する選択肢が出てくると思います。繰り返しますが、法務担当者と法務部門の必要性は、会社の方針次第なのです。
法務がIPO準備で活躍するカギは「タスク整理とスケジュール管理」
この記事の冒頭で「IPO準備の作業工程で、法務のやるべき守備範囲はかなり広い」と説明しました。おそらく細かいものまで拾うと、範囲が広いだけでなく膨大です。それに、この “ 細かいもの ” ですが、あらかじめ「やるべき業務」とわかっていれば良いのですが、準備中に発生するイレギュラーな対応やそのフォロー、各タスクの各所に潜んでいる各担当の業務の間のスキマ作業の抜け漏れ対応などがあり、これらは私の経験としては、大抵法務が担当することになります。理由は、他のIPOメンバー(経理、人事など)の業務量との兼ね合いや、調べてみると実は法務面の専門性が必要な抜け漏れ対応であった等あります。この抜け漏れも、ちょっとした対応で完了するものもあれば、例えば行政機関への許認可申請など、書式準備や形式に則っていれば比較的対応しやすいが、当該機関での審査期間(数日〜2週間、現地視察がある場合などは数か月以上)があるので、結局は時間がかかってしまうものがあります。このように見ると、特に法務には知識と経験に加え、必要な業務と単発のイレギュラー対応・抜け漏れ対応の業務が、その時期や内容の軽重などを含めて頻発する可能性がありますので、タスク整理とスケジュール管理の能力も必要ということになります。
上の「法務には、タスク整理とスケジュール管理の能力も必要」という点についての深掘り説明や、その他の法務に関連する内容については、文章のボリューム上、次の機会とさせていただきます。
ここで申しあげたいことは、IPO準備期間中にやるべき業務量は、IPOメンバーそれぞれ守備範囲と業務の専門性から分量の多少はありますが、それぞれがどのように業務を分担し、タスクごとに協力・連携し、個々のタスクを消化することに専念するだけではなく、全体スケジュールをよく理解して、IPO準備を推進していくことです。個々のタスクに優劣は無いですが、作業手順の意味での優先順位はあります。この「作業手順の意味での優先順位」さえ把握してポイントを押さえることができれば、IPO準備自体は難しいものではありません。
このことはIPO準備前だけでなく、ぜひ準備期間中においても全体進捗を検証していただきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
