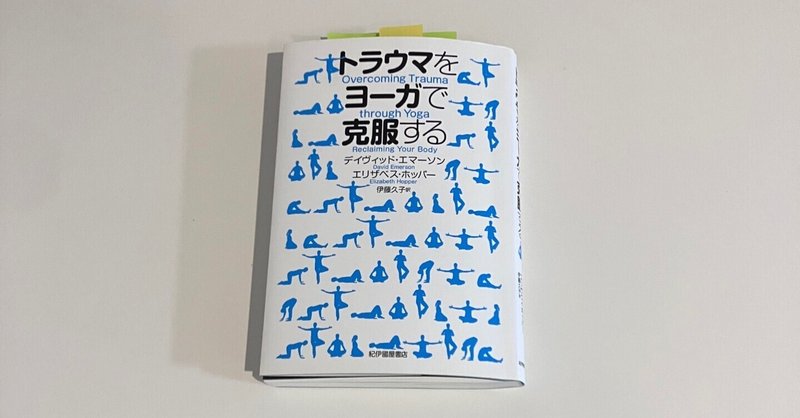
トラウマ関連の読書記録⑫「ヨガ」
ヨガをやればトラウマ治療になるのか
ヨガは好きで、コロナ禍まではスタジオに通って2年ほど続けていた。いわゆるパワー・ヨガで、身体を絞ったり汗をたくさんかくことを目的にやっていた。呼吸法や瞑想は自分を落ち着かせてくれたし、難しいポーズができると嬉しかった。
ヨガがトラウマにいいというのは、トラウマ治療の本を読む中で知った。呼吸法もマインドフルな瞑想も、確かに効果的だろうと思う。
でも待てよ。私はヨガをずっと続けていたけれど、トラウマに効果的だったと思えたことは無かった。やり方にもコツとかがあるのだろうか。
そう思って書籍を探したところ、こちらの本を見つけた。
「トラウマ治療には体との協働が不可欠」
著者は、ベッセル・ヴァン・デア・コーク博士が創設したアメリカのトラウマ・センターのヨガ部門長らしい。ヴァン・デア・コーク博士がトラウマ治療にヨガを取り入れるくだりは、こちらの博士の著書にも載っていた。
前書きには、そのヴァン・デア・コーク博士と、SE創設者のピーター・A・ラヴィーン博士が文を寄せている。SEを受けつつヨガにも取り組むとか、かなり良さそうだ。
本の前半は、トラウマについての基本的な知識や歴史が書かれている。そして、身体志向のセラピーや治療を受けることの意味と、ヨガでどうやって身体志向の回復を目指していくのかということや、ヨガの歴史や種類、特徴についても解説されている。わかりやすい。
いろいろな本を読んできたが、改めて「ですよね…」と納得するようなことがいくつも書いてあった。
「膠着感や無力感と結びついたその身体感覚には『自らの人生の成り行きを全くコントロールできない』という記憶が保存されている。」
わかる。身体感覚に記憶されているという意味が、今の私には本当に身につまされる。
「われわれが憎んだり怒ったりすれば必ず、生体も憎んだり怒ったりしている。」
「大多数の人たちが自分の内部感覚に抗って踏ん張ったり、体の中の世界を無視したりすることに長けているようである。」
私はこれまで、自分の体を無視してきたように思う。健康には気をつけてきたつもりだけど、体の声はあえて聞こえないフリをしてきた。思考に頼り、体のことは無視して頑張るのがいいことなのだと思っていた。それ以外の方法は自分で思いつくことができなかった。
トーク・セラピー(いわゆる普通に言われるカウンセリングのような、過去のことや自分の感情を話して内面に向き合おうとするもの)も大事ではあるけど、やはり身体志向のセラピーがとても重要だと感じる。頭ではわかっている、という状態になるのは身体の記憶が残っているからなのだと思う。
そしてこの文章にグッサリ刺された。
「“知性でとらえようとすること”は一般的に防衛として使われる方法であるが、とらえようとしているものが何であれ、解決のために相当な時間を費やしても『その精髄には決して到達し得ない』と言うことができる。」
わかってはいたけれど、私はものすごく防衛している。ここから抜け出していきたい。そうしたら本当の「リラックス」ができるはずだ。
トラウマ・センシティブ・ヨガ
本の中にはエクササイズやプラクティスがいくつか載っている。1人で自宅で取り組むこともできる。
トラウマ・サバイバーが回復のために行うヨガは「トラウマ・センシティブ・ヨガ」と呼ばれる。通常のヨガとは異なる。
通常のヨガのクラスでは、トラウマ・サバイバーが圧倒されたり「引き金」を誘発してしまうことが多いらしい。そういったことを配慮しながら、万全のサポート体制を整えてレッスンを行なっているそうだ。
その際に、4つの主要なテーマがある。
・「今この瞬間」を経験すること
・選択すること
・有効な行動をとること
・リズムを作ること
安心な環境の中で、これらのテーマに即した内容のレッスンを進めていく。とにかく慎重だ。セラピストがヨガの要素を取り入れて、一緒にポーズを取ったり呼吸を行ったりすることもあるらしい。日本でこんな取り組みがされる日は来るだろうか。
どんなポーズを取るのか
じゃあヨガのポーズはどんなものなのか?特殊なポーズだったりするのだろうか?
と思ったら、基本のきのようなポーズばかりが載っていて拍子抜けした。全てのポーズがトラウマ・センシティブ・ヨガの視点から解説されている。
自分の体の感覚に気づくこと。体を動かすとどんな感覚になるのかを感じてみること。
そして、全てにおいて「自分はやめたいと思ったらいつでもやめることができる」という選択権が自分にあり「自分を苦しめることをやめる」という選択ができること。ただ、この選択ができるようになるまでは時間がかかるらしい。何となくわかる。
インストラクターは「〜しなさい」という指示はほぼしない。ポーズが綺麗だとかうまくできるとか、そういったことは目的ではない。
「言われた通りにうまくやらないと」「上手にできるようにならないと」という気持ちでレッスンを受けたら全く意味がない。ただでさえトラウマ・サバイバーはそうなりがちなのだ。
私も以前ヨガをやっていた時は「綺麗にポーズを決めたい」「前よりうまくなりたい」という気持ちでやっていた。身体の感覚を味わうというよりも、ふらついたりしないように、とか、そういうことに気を取られていた。
もちろん最後の休息でリラックスしていたし、集中することは楽しかった。私はヨガのレッスン中に圧倒されたことはないので、この本に出てくる事例よりは軽症なのか、こういったことには強いのかもしれない。
この本に載っていたポーズは、体が覚えていて自然にできる。でもできるできないではないのだ。ポーズを通して、体の感覚を感じること、「今ここ」にいるということを体感することが大事なのだというのはわかる。
自分でやってみるつもりはあまりないけれど
興味があってこの本を読んでみたし、いずれはやってみたいとも思うが、今は体を動かす系だとフェルデンクライスの方に興味がある。
自分1人でのんびり取り組むなら、この本を読みながら身体感覚に気づいていけるようになれたらいいけれど、今の日本でこういったヨガのレッスンを受けるのなら、どうしたらいいのだろうか。レッスンを受ける機会があるのなら、ぜひやってみたい。
調べてみると「こころのケアとレジリエンス研究センター」というところがあり、そこでトラウマ・センシティブ・ヨガのレッスンのイベントが開催されたりすることがわかった。
ちょうど2月と3月にイベントがある。オンラインでも受けられる。
あとは、個人的には「ヨガニドラ」が気になる。トラウマに特化しているわけでも、身体感覚に気づくようなものでもなさそうだが、ゆったりしていて深くリラックスできそうな感じがする。こういったレッスンの中で、自分の身体を感じるようにしていくのもよさそうだ。
いろいろ見つけたら楽しくなってきた。
オンラインのヨガレッスンやヨガニドラをもし受けたら、また感想を書いておきたいと思う。
追記
小林さんのこちらのレビューがとてもよかった。私はせわしなく思考が働くので、ボディスキャンのようなじっくりしたワークが苦手なのだけど、続けていきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
