
民放AMラジオ、FM転換へ その3
タイトルの通り、先日の続きです。今回はAMがFM転換するための条件や、さらに広げて「(日本の)ラジオ局が儲かっていないのはなぜ?」「(日本の)これからのラジオの課題は?」的なところまで書いてみます。
僕自身は、(一部を除く)民放AMラジオ局のFM転換に大いに賛成をしています。その理由については、その1を読んでいただくとして…
その2でもチラッと触れておりますが、「AMは聞こえるけど、FMが聞こえづらい」地域はもちろんあります。仮に今の状態のままでFM転換してしまうと?そのまま該当エリアからラジオリスナーを奪うことになりかねないですね。それを防ぐために、今のFM送信所の数とか、出力の強さのままでFMに転換するという話なら僕も猛反対します。FM完全転換には条件が必要ですね。
山口放送(KRYラジオ)のように、AMの倍以上の数のFM中継局を設置する。或いは、1つのFM送信所の出力を大きくして、カバーエリアを広くする。どちらかを行ってFM電波(ワイドFM)が今よりも広範囲で良好に受信できるようにした上での完全転換でないと、リスナーの救済はされません。またそのような措置を行った場合、以前からFMラジオ局として放送してきたラジオ局にも同程度の出力増を許してあげないと、均衡が保てません。掘り下げて考えると、各地域ごとに色んな議論を重ねなければならなそうです。

(典型的なAMラジオの送信所。広大な土地と高さのある鉄塔が必要となる。)
さて。AMは費用対効果が…ということでFM転換を決めたわけですが。民放ラジオ局が儲かっていれば、そもそもこの話にはなっていないのです。
日本人は世界的に「ラジオを聴かない国民」としてデータが出ています。国民の大多数が興味ないメディアならば、儲からないのも仕方がない。それはなぜでしょうか。僕自身、西鉄バスで通勤していますが。朝も、夕方も、横を走っている車を上からチラッと覗き込むと、ナビの画面の映像が動いてる車両がほとんど。おそらく地上波テレビ放送を見ているのだと思います。そんなにみんなテレビが好きなのでしょうか。おそらく僕が考えるに、「テレビが大好き!ってわけではないけど、何となく運転中であっても家の中での過ごし方と同じにしたい」ぐらいに思って何となくテレビをつけているんじゃないですかね?車を運転する際に「何となくラジオ」…というイメージが大多数のドライバーに浮かんでこない時点で、この国でいかに「ラジオ」というものが支持されていないのかが解ります。

海外でなぜラジオが当たり前に広く聴かれているか?の理由は、音楽を多く掛けているからです。しかも音楽のジャンルでラジオ局が区別されている。もちろん音楽中心ではないニュースやトーク中心のラジオ局もあるのですが、人気のあるラジオ局の系統はやはり音楽をメインで掛けていますね。
特に若い世代も、これだけ世界的な音楽サブスクリプションのサービスが発達しながら、未だにラジオで最新の音楽情報を得ているようです。そのラジオで得た情報を基にサブスクに飛んだり、ダウンロードサイトに飛んだり…等々。またラジオで流れているという手前、「今の若者にはどんな音楽が流行っているんだろう?」と思っている上の年齢層でも、その類のラジオ局を熱心に聴けば、流行りの音楽に付いて行けてしまうという。
どうですかね。ざっくり書いただけですが、日本のラジオとはだいぶ立ち位置が違うことがお解りいただけたかと。。日本のラジオでは、AM局は特にですが、トークの分量がかなり多くを占めています。ここ最近ラジオを特集した雑誌が人気ですが、それも大体内容としては「誰がどんな面白いことを喋っている番組か」にとどまっています。もちろん「オールナイトニッポン」シリーズなど、有名人がトークする番組は「裏の顔」が「聞けて」面白いですよね。
ただ、僕が思うにそこがまさに今の日本のラジオの課題のような気がしまして。ラジオのマイクの前で喋る人が、みんな神田伯山さんのような噺家じゃないです。フリートークのスキルは、局アナであってもそこまで上手くないかもしれない。事実、放送局のアナウンサーになってからラジオ放送に初めて触れる新入社員もたくさん居て。そのような若手に「はい、喋って」と局としては若返りたいのでラジオを任せる。でもラジオをよく知らない若手が喋っているのを、何十年かそのラジオ局を聴いているリスナーたちが聴いてとある人は酷評する。その繰り返しがずっと行われている気がするんですよね。局アナだけでなく、新人タレントさん、新人アイドルさん…などなど。急に「はい、今から噺家になってください」というのは無理です。
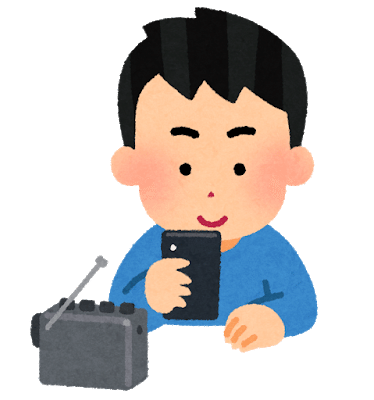
それから、絶対にNHKも民放も必ず番組冒頭に聞こえてくるアレ。
「メールアドレスは…」「メールの宛先は…」
僕が海外の色んなラジオ局を聴いてみたところ、メールアドレス的なのを読み上げている場面がないんです。生番組であっても。おそらく「ホームページからどうぞ」「(ラジオ局の)専用アプリからどうぞ」みたいなのは英語で言ってるっぽいけど。ほとんどアドレスやメールそのものの紹介をあまりせずに曲がたくさん流れていきます。
日本のラジオ番組の例として、生放送のトーク番組を平日5日間で数時間、トークで持たせようとするととても間が持たないので。リスナーからのメールで間を持たせることになります。毎日テーマを決めて、それに沿って番組が進んでいく。日本では当たり前だけど、海外ではさほど当たり前ではないようです。中には「早くメール欲しいので…」「メールで皆さんからメールのテーマを募ります」「メールが無いと番組が成り立ちません」などなど。中にはそういう種類のラジオ局もあるよ?ではなく、全部その方向ですよね。最近それがヘンだなぁと思えてきました。
そこでメール(昔はハガキ)職人が生まれるわけですけど。最近僕も含めてリスナーさん達はSNSを駆使しているので。「またメール読まれなかった」「あの人のが採用されてなぜ自分のが採用されないんだろう?」等々、それが少しトラブルになったりもしているようです。殺伐とした空気感。好きなラジオ番組がその出所となっていたら、嫌ですよね。
西暦2000年の前後数年間に生まれた世代を「Z世代」と呼んだりしますが。その若者代表「Z世代」が思う、ラジオについての記事があったんですね。生まれてこの方、ラジオを聞いて来なかった人が大多数ですが、「ラジオの何が苦手?」という質問には、「メッセージテーマについてメールで参加しようと思ったが、新顔が入り込める雰囲気でなかった」や「(車を運転しないので)交通情報が要らないなぁと思った」、さらには「映像がないとどうしたらよいかが分からない」なんて意見もありました。

あとは「音楽が流れないので、サブスク聴いてるほうが良い」という痛いご意見も。ラジオが真の意味での若返りを図るなら、一番重要なのはそこだと思っています。今の若者たちは、とにかく自分に必要な情報だけが欲しいのです。邪魔なものが紛れ込んでいると、すぐやめる。そこを指導するわけにはいかないので(笑)、交通情報や高齢者向けの健康食品・サプリメントの宣伝、啓発系の暗めなCM枠。このあたりを排除した、新しい音楽をじゃんじゃん掛けるラジオ放送があれば若者も好んで聴きそうな気がしませんか?(実際に大阪の人気局FM802は、交通情報はたくさんだけどそれに近い編成をやってます)
「音楽サブスクに対抗するラジオ局」とか、「音楽サブスク上位の曲ばかり流すラジオ局」そういうラジオ局が各都道府県に1つずつぐらいあれば、「ラジオを聴かない国民」のデータが、年を追うごとに徐々に薄らいでいくような気がしますけどね。
また長くなってしまった・・・(;´∀`) 最後まで読んでいただきありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
