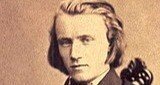#Brahms

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100(Brahms:Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100)
00:00 I. Allegro amabile 08:28 II. Andante tranquillo - Vivace 14:41 III. Allegro grazioso quasi andante 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 演奏者 Nicola Benedetti, violin Katya Apekisheva, piano 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100は、彼の3つのヴァイオリン・ソナタの中で2番目に書かれました。この作品は1886年に作曲され、ブラームス自身が非常に気に入っていた曲の一つであることが知られています。 このソナタは以下の3つの楽章から成り立っています: 1. **Allegro amabile**: 優美な旋律が特徴的な楽章で、その名前の通り「愛らしく」(amabile)な雰囲気を持つ。この楽章では、ヴァイオリンとピアノが互いに対話するかのようにテーマを交換しながら進行します。 2. **Andante tranquillo – Vivace – Andante – Vivace di più – Andante vivace**: リズミカルな中間部(Vivace)を挟んで静かなAndanteの部分が繰り返される構造になっています。この楽章は変則的なロンド形式を取っており、情熱的で舞踏的な要素が含まれています。 3. **Allegretto grazioso (quasi Andante)**: この楽章は舞曲のような軽やかなムードを持ち、終始明るく楽しい雰囲気が続きます。 全体的に、このヴァイオリン・ソナタは深い情熱やドラマチックさよりも、優美さや明るさが強調されている作品となっています。ブラームスのヴァイオリン・ソナタの中では最も人気があり、演奏会のプログラムに取り上げられることが多いです。 この作品は、ブラームスが自身の生涯の中で恋愛の対象としてみた数少ない女性の一人、クララ・シューマンに捧げられていると言われることもあります。ブラームスとクララ・シューマンの間の関係は、音楽の歴史上でも特筆すべきものとして知られています。 - **創作の背景**: ブラームスはこのソナタを夏の間にスイスの湖畔で過ごしながら書きました。彼はしばしば夏のリゾートで静かに過ごしながら新しい作品を書くことが多かったのですが、この環境がソナタの明るく穏やかな性格に影響を与えたのかもしれません。 - **愛称**: この作品は「太陽のソナタ」とも呼ばれることがあります。これは作品の全体的な雰囲気が明るく、太陽のように暖かいからです。 - **構造の独特さ**: ブラームスは伝統的なソナタ形式や楽章の区切りに縛られることなく、自由な形式やテクスチャーを用いて作品を作ることが多かった。このソナタもその傾向が見られます。特に2楽章の変わった形式や、3楽章が独自のリズムとメロディで始まることなどが挙げられます。 - **音楽的な特徴**: ピアノとヴァイオリンの間の対話は非常に密接で、2つの楽器が絶えずテーマや動機を交換しています。ブラームスはピアノとヴァイオリンの両方に非常に繊細なパートを書いており、この作品を演奏するには両方の楽器の奏者に高い技術と感受性が求められます。 - **受容**: ブラームスのヴァイオリン・ソナタは当初から非常に好評を博しました。第2番のソナタも、その優れたメロディと均整の取れた構造によって、ヴァイオリン・ソナタのレパートリーの中でも特に人気のある作品となっています。 総じて、このソナタはブラームスの成熟期のスタイルと技巧を反映しており、彼の音楽的な思考や情熱を深く理解するための鍵となる作品の一つと考えられています。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第2番 イ長調 作品100は、ヨハネス・ブラームスが1886年に作曲した室内楽作品。他作品に比べて明朗な響きで典雅な構成になっている。 概要 ヴァイオリンソナタ第1番の完成から7年を経た1886年の夏に、避暑地のトゥーン湖畔(スイス)で作曲・完成された。この時期のブラームスは多くの友人たちと親交を結び、同時にピアノ三重奏曲第3番やチェロソナタ第2番など多くの作品を生み出すなど、充実した生活を送っていた。そうした日々から生まれたのがヴァイオリンソナタ第2番である。 この後に第3番が書かれているが、第2番とは対照的に暗い雰囲気が醸し出されている作品である。 初演は1886年の12月2日にウィーンでヨーゼフ・ヘルメスベルガーのヴァイオリン、ブラームス自身のピアノによって行われた 。 構成 全3楽章で、演奏時間は約23分。 第1楽章 Allegro amabile 4分の3拍子。イ長調。ソナタ形式。冒頭からピアノの主和音が流れ、ヴァイオリンがオブリガートを務める。主にピアノが主題を弾き、ヴァイオリンには補佐役を担わせていながら音色の美しさを印象づけている。第1主題が重厚なイ長調(C#-G#-A)の和声であり、ピアニスティックな表現であるが、第2主題は属調であるホ長調の主和音G#-H-Eが素材となっている。いずれも優雅でロマン派作家としての特徴が現れている。第1楽章の冒頭の主題について、ブラームスの生前よりリヒャルト・ワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の懸賞の歌との類似性が指摘されていたが、ブラームスは「馬鹿にはそう見えるんだろう」とコメントしている。 第2楽章 アンダンテ・トランクィロ - ヴィヴァーチェ Andante tranquillo - Vivace 4分の2拍子。ヘ長調。ロンド形式。冒頭ではピアノ右手とヴァイオリンとが対位法的に主題を表す。この穏やかな曲想はその後2回再現されるときにはニ長調で現れる。vivaceでは4分の3拍子。ニ短調。同様に対位法的処理がされている。前楽章・後楽章とも落ち着いた歌唱風なのでこの楽章はやや律動的に処理している。 第3楽章 アレグレット・グラツィオーソ Allegretto grazioso (quasi Andante) 2分の2拍子。イ長調。ロンド形式。三連符と8分音符、6連符の減七の和音を組み合わせてリズムが単調にならない配慮をしている。コーダはヴァイオリンの重音で締めくくっている。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ヨハネス・ブラームス 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ブラームス #ヴァイオリンソナタ第2番 #Op100 #Brahms #ViolinSonataNo2

ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115(Brahms:Clarinet Quintet in B Minor, Op.115)
ブラームスのクラリネット五重奏曲は、彼の最後にして最も有名な室内楽の一つです。作品番号115番で知られており、ロ短調で書かれています。 この作品は、ブラームスが晩年に作曲したものであり、クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトの依頼で書かれました。クラリネットを特に重要な役割で使用し、他の楽器との対話や対位法的なテクスチャを通じて、深い感情を表現しています。 作品は、四楽章の構成であり、次のように進行します: 第1楽章:アレグロ - ロ短調 情熱的な冒頭に続き、クラリネットの重要な旋律が導入されます。四重奏団との対話が進み、情感溢れるクライマックスに達します。 第2楽章:アデアージョ - イ長調 穏やかな歌唱性をもった楽章であり、クラリネットの旋律が美しい旋律を奏でます。優れた対位法的なテクスチャと繊細な共鳴が特徴です。 第3楽章:アンダンテ・トランクイッロ - イ短調 悲劇的な雰囲気を持つ楽章で、クラリネットとチェロの旋律が交差します。中間部では、力強いクライマックスが現れますが、最後は静かに結ばれます。 第4楽章:コン・モート ロ短調からロ長調への転調する華麗な楽章であり、情熱的なダンスのようなリズムと素晴らしい対位法的なテクスチャが特徴です。クラリネットの旋律が盛り上がり、壮大な結末に至ります。 ブラームスのクラリネット五重奏曲は、その情感豊かな旋律と対位法の技巧により、クラシック音楽の傑作として高く評価されています。 From Wikipedia, the free encyclopedia Johannes Brahms's Clarinet Quintet in B minor, Op. 115, was written in 1891 for the clarinettist Richard Mühlfeld. It is scored for a clarinet in A with a string quartet. It has a duration of approximately thirty-five minutes. 00:00 I. Allegro 13:24 II. Adagio 25:09 III. Andantino - Presto non assai, ma con sentimento 29:58 IV. Finale - Con moto 演奏者 William McColl (clarinet) 公開者情報 Pandora Records/Al Goldstein Archive 演奏者 The Orford String Quartet Andrew Dawes and Kenneth Perkins, violin; Sophie Renshaw, viola; Denis Brott, 'cello 著作権 EFF Open Audio License 備考 Performed June 1988. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヨハネス・ブラームスのクラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115は、彼の晩年に完成された、ブラームスを代表する室内楽曲の1つである。 作曲の経緯と受容 1891年の夏にバート・イシュルで作曲された。姉妹作の《クラリネット三重奏曲 イ短調》作品114と同時期の作品である。ブラームスは夏の時期に様々な避暑地を訪れていたが、何度か訪れていたこの避暑地以上に快適な土地はないとして、前年からその地で夏を過ごすようになっていた。バート・イシュル滞在中にブラームスは興が乗り、珍しく速筆で作品を仕上げている。 この2曲の初演は非公開を前提に、マイニンゲン公の宮廷において11月24日に行われた。演奏者は、クラリネット奏者のリヒャルト・ミュールフェルトとヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒム並びにマイニンゲン宮廷管弦楽団の団員たちであった。このときと同じ顔ぶれによる公開初演は、ベルリンにおいて12月10日に行われ、熱狂的な反響を得て全曲が繰り返し演奏された(ただしその2日後の上演は、評価が芳しくなかったという)。とうとう1892年1月5日にウィーン初演が行われた。このときの演奏者は、クラリネット奏者のフランツ・シュタイナー(1839 - 1902)と、ロゼー四重奏団であった。それから15日遅れで、ミュールフェルトとヨアヒム四重奏団もウィーンで上演を行って大成功を収め、無条件で称賛の念を表す批評で占められた。 ブラームスは、《クラリネット五重奏曲》のあまりの評価の高さに対して、「自分は《三重奏曲》の方が好きだ」と言っている。しかしながら《五重奏曲》はブラームスの暖かい秀作であり、楽章ごとに凝縮された内容と明晰な構成が見受けられる。 楽章構成 以下の4つの楽章から成る。全曲の演奏に36分程度を要するが、開始楽章をゆっくり演奏する風潮のために、39分前後掛かる例も少なくない。 アレグロ(ロ短調、6/8拍子、ソナタ形式) アダージョ(ロ長調~ロ短調~ロ長調、3/4拍子、三部形式) アンダンティーノ(ニ長調の間奏曲、4/4拍子) コン・モート(ロ短調、2/4拍子、変奏曲形式) 楽器編成は、通常の弦楽四重奏にクラリネットを加えたものとなっている。 第1楽章 Allegro 心に染み入る歌曲的な雰囲気に満ちたソナタ形式。冒頭でライトモチーフ風の短い動機が第1・2ヴァイオリンによって提示される(譜例1)。この動機は3拍子から6拍子へと滑らかに移ろい曲全体を統一的に貫いていく。ついで5小節目にクラリネットがピアノで入るが、本格的なクラリネットの登場は14小節目からのフォルテ・エスプレッシーヴォによる第1主題で、ここにチェロが含羞を交えた深い叙情を添える。最初の副次主題のあと38小節目からはクラリネットによる「非常に特徴的なハーモニーとメロディの柔和さ」(クロード・ロスタン Claude Rostand)を持つ第2主題へひきつがれる。その10小節後に第3主題が登場し、8分休符による効果的なシンコペーションのゆったりとした軽い間奏が続く。2番目の副次主題(59小節目から)は柔軟な旋律線のすべてをクラリネットが担当し、これを経過部として展開部へ進む。展開部ではじめて出てくる3番目の副次主題はここでしか登場せず、その間に提示部の各要素が、作品114の三重奏曲にはない自由さで用いられることは注目される。冒頭の動機が何度か繰り返されて展開部が終わり、提示部を踏襲した再現部へ続く。最後はコーダが付加され、またも冒頭の動機、さらにクラリネットにより第1主題が演奏されて楽章を終える。 第2楽章 Adagio 3部構成のリート形式による緩徐楽章。クラリネットが奏でる、虚飾を取り去った、夢見るようなときに苦みばしった旋律(譜例2)は、多くの識者により真の「愛の歌」と評されており、それを弦部がコン・ソルディーノで支え、包み込む。第一部は、クラリネットによってシンプルに奏される主要主題が、哀切と親愛のこもった調子によるドルチェで歌われ豊かに展開されていく。第一部の中間では主要主題を逆行的に処理した副次主題が挿入される。中間部のロ短調ピウ・レントの挿句(52小節目から87小節目)は主要主題を使用してはいるが色彩をやや異にし、クラリネットがアリア的にまたレチタティーヴォ的に、ときに優雅にときに澄みきった叙情をたたえさらには悲愴な抑揚も交えて装飾音型をつないでいき、弦部がトレモロを響かせる。この挿句のジプシー風の性格は、長いパッセージと、8分音符による急なアラベスクによりいくどとなく強調される。ここでは細かな装飾音の多用と、名実ともにこの楽章の独奏楽器たるクラリネットのヴィルトゥオーゾ的表現力やラプソディックな奏法によってもたらされる極度の緊張感とが特に目を引く。第一部の再現(88小節目から)は第一部に沿ったものだが、クラリネットが第1ヴァイオリンと親密な対話を行う点は大きく異なる。自由な雰囲気のコーダがこのきわめて個性的な、まさにブラームス的創作技法の極致とも言うべきアダージョ楽章を締めくくる。 第3楽章 Andantino 三部形式、23小節のアンダンティーノが、中間部の2/4拍子のプレスト(Presto non assai, ma con sentimento)を取り囲んでいる。軸になるのは急速な中間部で、より穏やかな両端部分はさしずめ前奏と後奏として機能している。この流動的な楽章において、アンダンティーノの主要主題がところを変えて現れる。ただし、明確な道筋が定まっているという感じではない。このアンダンテ主題は、初めはクラリネットによって弱音で示される。だがこの主題は、特定の形式によらないプレスト部にも引き続き現れるだけでなく、せかせかした足取りのスケルツォ主題として変奏されもするのである。このような構図は、いわゆるブラームス後期ピアノ小品集にも共通するものである。 第4楽章 Con moto ロンド形式にコーダを加え、主題と5つの変奏で構成される。主題は美しい旋律が弦によって軽やかに歌われ、そこにクラリネットが短く入り、後半部が二度繰り返される(譜例4)。第1変奏(33小節目から64小節目)は軽快なチェロに委ねられる。クラリネットは他の弦部とのユニゾンや、巧みに書かれた対位法を奏でる。第2変奏(65小節目から96小節目)は中音域の弦によるシンコペーションの伴奏が、16分音符で湧きあがるクラリネットよりもなお熱をこめて貫いていく。第3変奏(97小節目から129小節目)ではクラリネットの存在感が増し、16分音符のスタッカートによるアルペッジョがヴィルトゥオーゾ的というよりもむしろ快活さをにじませたドルチェで奏される。ロ長調で進行する第4変奏(130小節目から162小節目)では、中音域の弦による16分音符の刺繍音の上で、クラリネットと第1ヴァイオリンによる恋のようなピアノ・ドルチェの対話が続く。最後の第5変奏(163小節目から196小節目)は短調に戻るが主題のリズムは3/8拍子に変わり、そこへ曲冒頭のライトモチーフのひずんだこだまのような16分音符の音型が対位法により結びつけられていく。コーダ(197小節目から226小節目)では、表現豊かな短いカデンツァが高音のEのフォルテによって頂点に達した後、今度はライトモチーフが冒頭とまったく同じ形で繰り返される。最後の残響が曲に充溢感と循環的統一をもたらし、過ぎし時を振り返るかのようにこの夜想曲的大作に別れを告げる。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ヨハネス・ブラームス 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ブラームス #クラリネット五重奏曲ロ短調 #作品115 #Brahms #ClarinetQuintet #Op115

ブラームス:弦楽四重奏曲第1番ハ短調 作品51-1
In this video, we're taking a look at String Quartet No. 1 in C Minor, Op. 51, No. 1 by Johannes Brahms. This piece is a beautiful example of Classical Music and is sure to elicit a wide range of emotions. If you're a fan of Classical Music, be sure to check out this video and hear Brahms' beautiful String Quartet No. 1 in C Minor, Op. 51, No. 1. This piece is a classic and is sure to please! 00:00 I. Allegro 11:01 II. Romanze: Poco adagio 18:13 III. Allegretto molto moderato e comodo 26:55 IV. Allegro 演奏者 Borromeo String Quartet String Quartet https://www.borromeoquartet.org/ 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲第1番ハ短調 作品51-1は、ヨハネス・ブラームスの発表した最初の弦楽四重奏曲である。 第2番イ短調 作品51-2と同時に1873年に発表された。これらの2曲は著名な外科医でありアマチュアの音楽家であった親友テオドール・ビルロートに捧げられている。 しかし音楽上の助言はブラームスの友人ヨーゼフ・ヨアヒムから多くを受けている。 ブラームスの弦楽四重奏曲 ブラームスは自己批判が強く完璧主義で、自分の曲を発表するにあたり大変慎重だったため、交響曲第1番の作曲に20年以上の歳月をかけていた。弦楽四重奏においても同様に慎重を重ね、同時に発表された最初の2曲には最低8年間の歳月を要しているうえ、その前にも20曲を越える習作が書いては破棄されている。それも最初の2曲を発表した2年後に第3番を発表したあと、弦楽四重奏曲を書いていないため、室内楽曲を多く残したブラームスにしては、弦楽四重奏曲はわずか3曲しか残されていない。ブラームスは、先人ベートーヴェンの残した16曲の弦楽四重奏曲を敬いつつも、その偉大さから受ける重圧には悩まされなければならなかった。 ベートーヴェンの重圧を感じずに済んだピアノ付きの室内楽曲や、若い頃から筆が進んだ弦楽六重奏曲・弦楽五重奏曲各2曲に比べ、弦楽四重奏曲の3曲は地味な感は否めない。それでも残された3曲は、室内楽の大家らしくいずれも佳作ぞろいであり、ロマン派の弦楽四重奏曲として重要な位置を占めている。 楽曲構成 同じハ短調の交響曲第1番(この弦楽四重奏曲の3年後に完成)同様、劇的で力強い構成を持っている。演奏時間は30分ほどである。 第1楽章 Allegro (ハ短調、ハ長調で終わる) 第2楽章 Romanze: Poco Adagio (変イ長調) 第3楽章 Allegretto molto moderato e comodo (ヘ短調、ヘ長調で終わる) 第4楽章 Allegro (ハ短調) 編成 第1ヴァイオリン 第2ヴァイオリン ヴィオラ チェロ ヨハネス・ブラームス 『弦楽四重奏曲』再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zMdO7fTwSqHJWzWkfwzO4_ ヨハネス・ブラームス 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ブラームス #弦楽四重奏曲第1番ハ短調 #作品51の1 #StringQuartet #Brahms

ブラームス:パガニーニの主題による変奏曲 イ短調 作品35
In this video, we'll be listening to Johannes Brahms' 35 Variations on a Theme by Paganini, conducted by Philippe Herreweghe. This piece is in the classical violin repertoire, and is known for its difficult passages and virtuoso playing. It's a great piece to listen to when studying classical music, or when you're looking to practice your violin skills. If you're curious about what this piece is all about, be sure to check out this video and see how Philippe Herreweghe brings the theme to life! Book 1 00:00 Thema. Non troppo Presto 00:24 Variation 1 00:50 Variation 2 01:21 Variation 3 01:49 Variation 4 02:44 Variation 5 03:34 Variation 6 04:01 Variation 7 04:29 Variation 8 05:02 Variation 9 06:41 Variation 10 08:31 Variation 11. Andante 09:51 Variation 12. 11:12 Variation 13. 11:47 Variation 14. Allegro Book II 14:08 Thema. Non troppo Presto 14:32 Variation 1 15:20 Variation 2. Poco Animato 16:02 Variation 3 16:36 Variation 4. Poco Allegretto 17:35 Variation 5 17:57 Variation 6. Poco più vivace 18:21 Variation 7 18:43 Variation 8. Allegro 19:15 Variation 9 20:10 Variation 10. Veloce, energico 20:55 Variation 11. Vivace 21:24 Variation 12. Un poco Andante 22:57 Variation 13. Un poco più Andante 23:54 Variation 14. Presto, ma non troppo 演奏者ページ Peter Bradley-Fulgoni (piano) 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 Recorded in 1996 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 《パガニーニの主題による変奏曲》作品35は、ヨハネス・ブラームスのピアノ曲。1862年から1863年にかけて作曲され、1865年11月に作曲者自身によりチューリヒにおいて初演された。 パガニーニの有名な《カプリッチョ第24番 イ短調》を主題にした変奏曲で、親交を結んだフランツ・リスト門下のカール・タウジヒの提案で作曲された上に、もともと芸術的練習曲として構想されたこともあり、情緒の深みと至難な超絶技巧の要求で名高い。なお、初版の表紙には「変奏曲」の横に小さく「練習曲」と書かれていた。 弟子のピアニスト、エリーザベト・フォン・シュトックハウゼン(ハインリヒ・フォン・ヘルツォーゲンベルクの妻)に献呈された。 楽曲構成 次のように2巻に分けられており、それぞれパガニーニの主題の後に、12の変奏が続いている。特記しているもの以外は、すべて調性は原調(イ短調)と主題の拍子が保たれている。第1部・第2部のいずれとも、超絶技巧を要する華麗で長めの終曲が置かれている。 第1部(作品35-1) 主題 2/4拍子、ノン・トロッポ・プレスト Non troppo presto 第1変奏 右手は平行6度、左手は平行3度の練習曲 第2変奏 右手はオクターヴ、左手は平行6度の練習曲 第3変奏 6/8拍子 第4変奏 12/16拍子。アルペッジョとトリルの練習曲 第5変奏 右手が2/4拍子、左手が3/4拍子。クロスリズムとクロスフレーズの練習曲で、楽譜どおりに弾くのは困難。 第6変奏 オクターヴの練習曲 第7変奏 6/8拍子。オクターヴ連打と跳躍の練習曲 第8変奏 6/8拍子。オクターヴと平行3度の練習曲 第9変奏 トレモロと、オクターヴによる半音階進行の練習曲 第10変奏 シンコペーションと両手交叉の練習曲。右手は平行3度、左手はアルペッジョ。後半でカノン的に処理される。 第11変奏 Andante (イ長調) ユニゾンの練習曲と4声を処理する練習曲。 第12変奏 (イ長調)右手が6/8拍子、左手が2/4拍子。クロスリズムとクロスフレーズの練習曲。 第13変奏 オクターヴによる線的進行とグリッサンドおよび分散和音の練習曲 第14変奏 Allegro - Con fuoco - Presto ma non troppo これまでに使われた演奏技巧の回想ならびに総括。 第2部(作品35-2) 主題 第1変奏 左手の平行3度、右手のオクターヴによる跳躍。 第2変奏 Poco animato オクターヴによるアルペッジョとクロスリズムの練習曲。 第3変奏 平行3度とオクターヴの交替。 第4変奏 Poco allegretto (イ長調)3/8拍子。 第5変奏 3/8拍子。 第6変奏 Poco più vivace 3/8拍子。 第7変奏 第8変奏 Allegro 6/8拍子。 第9変奏 第10変奏 Feroce, energico 6/8拍子。 第11変奏 Vivace 第12変奏 Poco andante (ヘ長調)6/8拍子。 第13変奏 Un poco più andante 第14変奏 2/8拍子~6/8拍子~2/4拍子。 録音 有名なものとしてアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、スヴャトスラフ・リヒテル、ヴィルヘルム・バックハウス、エフゲニー・キーシン、ジュリアス・カッチェン、ペーター・レーゼルの演奏がある。若手ピアニストが国際コンクールの最終予選でよく弾く。録音点数はそのため、増加中である。 #ブラームス,#Brahms,#パガニーニの主題による変奏曲,#作品35

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.108
In this video, we'll be playing Johannes Brahms's Violin Sonata No. 3 in D minor, Op. 108. This sonata is one of Brahms's most popular pieces and is known for its emotive and romantic melodies. If you're a fan of classical music, then you should definitely check out this video. We'll be playing the sonata by ear and discussing the different aspects of the piece. From the solo to the chord progression, this video is a great way to learn about Johannes Brahms's Violin Sonata No. 3 in D minor, Op. 108. 00:00 I. Allegro 08:03 II. Adagio 12:25 III. Un poco presto e con sentimento 15:08 IV. Presto agitato 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 演奏者 Mayuko Kamio (violin) Pei-Yao Wang (piano) 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第3番ニ短調作品108は、ヨハネス・ブラームスが作曲したヴァイオリンソナタ。 概要 ヴァイオリンソナタ第2番を完成させた直後の1886年から1888年にかけて作曲されたものである。当時ブラームスは避暑地のトゥーン湖畔(スイス)に滞在中で、悩みのない十分な生活を快適に過ごしていた。しかし1887年に友人で音楽学者のカール・フェルディナント・ポール(1819年 - 1887年)の訃報を受けると、孤独感などに苛まれるようになった。これらが反映されているためか、第3番は第2番とは異なり、晩年に見られるような重厚で内省的な作品となっている。これ以降ブラームスは諦観の感情を出すようになり、短調の作品を多く書くようになる。 1888年に脱稿後、ベルンに住んでいた親友で詩人のヨーゼフ・ヴィクトール・ヴィトマンの邸宅でプライヴェートでの初演が行われた。ただしこの時の演奏者や日時は不明である。公的な初演は1888年の12月21日(22日とも)にブラームス自身のピアノ、ハンガリー出身のヴァイオリニストのイェネー・フバイによって、ブダペストで行われた。1889年にベルリンのジムロック社から出版され、良き理解者であった指揮者のハンス・フォン・ビューローに献呈された。 ヨーゼフ・シゲティは、この曲の試演がシゲティの師イェネー・フバイとブラームス自身によって行われ、その20年後にフーバイとレオポルド・ゴドフスキーの演奏をブラームスが聴いたこと、フバイからブラームス特有のテンポ指示について学んだことなどが語り、自らのブラームス解釈の正当性を主張した。しかし、自らジャケット裏面にそうした解説を書いたLP(米コロンビア ML5266)は、皮肉なことにアメリカの音楽雑誌『ハイ・フィディリティ』誌上で、当時人気のあった評論家ハロルド・ショーンバーグにたったの3行でけなされ瞬く間に廃盤となり、その後も長く復刻されなかった。 構成 全4楽章で、演奏時間は約30分。 第1楽章 アレグロ ニ短調、4分の4拍子。ソナタ形式による楽章。ヴァイオリンがロマン的でメランコリックな第1主題を奏で始めると、ピアノが右手と左手で穏やかなシンコペーションを奏する。終結部はニ長調で静かに終える。 第2楽章 アダージョ ニ長調、8分の3拍子。3部形式によるカヴァティーナ風の穏やかな楽章。ゆったりとしたテンポでG線のヴァイオリンで奏でる柔和な歌に始まり、抒情性豊かに歌われる。 第3楽章 ウン・ポコ・プレスト・エ・コン・センティメント 嬰ヘ短調、4分の3拍子。3部形式によるスケルツォ風(2拍子)の楽章。嬰ヘ短調で始まり、ホ短調になると憂愁の度合いが増して暗い情感が全体を覆う。また冒頭の重音の音型が後半で反復される際はピツィカートに変えられる。 第4楽章 プレスト・アジタート ニ短調、8分の6拍子。ロンド・ソナタ形式による。これまでの憂鬱な雰囲気や感情を払いのけるかのように、激しい響きの重音で開始する。終結部は最強音で曲を終える。第1楽章と同じくシンコペーションが効果的に使用されている。 #ブラームス,#ヴァイオリンソナタ第3番,#Op108,#brahms,#violin

ブラームス:8つの小品 作品76
00:00 1. Capriccio in F♯ minor 03:34 2. Capriccio in B minor 06:56 3. Intermezzo in A♭ major 09:53 4. Intermezzo in B♭ major 12:53 5. Capriccio in C♯ minor 16:03 6. Intermezzo in A major 20:15 7. Intermezzo in A minor 24:28 8. Capriccio in C major 演奏者ページ Felipe Sarro (piano) 公開者情報 Felipe Sarro 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 8つの小品(8 Klavierstücke)作品76は、ヨハネス・ブラームスが作曲したピアノのための性格的小品集。 概要 交響曲第2番の作曲から1年後、1878年の夏頃に、ヴェルター湖畔の避暑地ペルチャッハ(英語版)で作曲された。なお、第1曲の初稿のみ1871年に書かれている。第2曲がイグナーツ・ブリュルによって1879年10月22日に先行して初演されており、全曲の初演は10月29日にベルリンでハンス・フォン・ビューローによって行われた。ビューローはその後もこの曲集を愛奏したと伝えられている。出版は1879年春に行われた。 『ワルツ集』の独奏版以来、13年ぶりに出版されたピアノ独奏曲となった。マックス・カルベックは、ブラームスがこの頃ロベルト・シューマンやフレデリック・ショパンの作品の校訂を行ったことをピアノ曲への回帰と関連付けている。和声が晦渋になり作品が内向的になっていく、ブラームスの「後期」への入口にあたる作品[1]とも言われる。 楽曲構成 4曲の間奏曲と4曲の奇想曲を含む。全曲を通した演奏時間は27-28分程度。初版では1-4曲、5-8曲の2巻に分けて出版されていた。 第1曲 奇想曲 嬰ヘ短調 ウン・ポコ・アジタート、Unruhig bewegt(落ち着かずに、動きをもって)。6/8拍子。三部形式。1871年9月13日のクララ・シューマンの誕生日に贈られたとされる。中間部において下降アルペジオに乗って寂しげな旋律が奏でられ、上行アルペジオを中心にした両端部がそれを挟む。中間部を回想する短めのコーダが続き、嬰ヘ長調で終止する。 第2曲 奇想曲 ロ短調 アレグレット・ノン・トロッポ、2/4拍子。複合三部形式。スタッカートを中心にした軽快な作品で、演奏機会は多い。中間部はピウ・トランクイロとなって、なだらかな旋律も現れる。 第3曲 間奏曲 変イ長調 グラツィオーゾ、Anmutig, ausdrucksvoll(優美に、表情豊かに)。4/4拍子。二部形式。セレナード風の書法で、シンコペーションを伴った旋律を歌う。 第4曲 間奏曲 変ロ長調 アレグレット・グラツィオーゾ、2/4拍子。三部形式(中間部は主部の展開)。単一の伴奏音形と内声のEs音が執拗に保持される。曲調は優雅ではあるが、和声はかなり複雑に書かれ不穏さをにじませている。 第5曲 奇想曲 嬰ハ短調 アジタート・マ・ノン・トロッポ・プレスト、Sehr aufgeregt, doch nicht zu schnell(きわめて興奮して、しかし速すぎずに)。6/8拍子。A-B-A'-B'-A"の拡大された三部形式。分厚く書かれた活動的な作品で、曲集の中でも規模が大きい。3/4拍子と6/8拍子が共存するリズム法が特徴的。 第6曲 間奏曲 イ長調 アンダンテ・コン・モート、Sanft bewegt(穏やかに動きをもって)。2/4拍子。複合三部形式。無言歌風の穏やかな作品で、2:3のクロスリズムが用いられる。 第7曲 間奏曲 イ短調 モデラート・センプリーチェ、2/2拍子。A-B-C-B-Aのアーチ形式。比較的大きな場面転換が見られるが、各部は二度下降+二度上行の動機(交響曲第2番の基本動機と同一)で統一されている。 第8曲 奇想曲 ハ長調 グラツィオーゾ・エド・ウン・ポコ・ヴィヴァーチェ、Anmutig lebhagt(優美に、活動的に)。6/4拍子。広い音域を使うピアニスティックな作品。 #brahms,#ブラームス,#johannesbrahms,#8つの小品

ブラームス:交響曲 第4番 ホ短調, Op.98
00:00 I. Allegro non troppo 12:40 II. Andante moderato 23:55 III. Allegro giocoso 30:13 IV. Allegro energico e passionato 演奏者ページ Czech National Symphony Orchestra 公開者情報 Palo Alto: Musopen, 2012. 著作権 Creative Commons Attribution 3.0 備考 Source: Musopen 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第4番ホ短調作品98(ドイツ語: Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98)は、第3交響曲完成の翌年1884年から1885年にかけてヨハネス・ブラームスが作曲した最後の交響曲。第2楽章でフリギア旋法を用い、終楽章にはバロック時代の変奏曲形式であるシャコンヌ[1]を用いるなど、擬古的な手法を多用している。このことから、発表当初から晦渋さや技法が複雑すぎることなどが批判的に指摘されたが、現在では、古い様式に独創性とロマン性を盛り込んだ、円熟した作品としての評価がなされており、4曲の交響曲の中でも、ブラームスらしさという点では筆頭に挙げられる曲である。同主長調で明るく終わる第1番とは対照的に、短調で始まり短調で終わる構成となっているが、これは弦楽四重奏曲第1番、第2番やシェーンベルクが管弦楽に編曲しているピアノ四重奏曲第1番など、ブラームスの室内楽曲では以前から見られる構成である。ブラームス自身は「自作で一番好きな曲」「最高傑作」と述べている。演奏時間約40分。 作曲の経緯 1882年1月、ブラームスは友人であり指揮者のハンス・フォン・ビューローに、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのカンタータ第150番『主よ、われ汝を仰ぎ望む』("Nach dir, Herr, verlanget mich"、BWV.150)の終曲「わが苦しみの日々を」("Meine Tage in dem Leide"、4小節のバス主題に基づくシャコンヌ)を示し、「この主題に基づく交響曲の楽章はどうだろう。もっとも、このままではごつすぎるので、手を加えなければならないだろうが」と述べたという。このことは、第3交響曲の作曲前から、すでに第4交響曲の終楽章の構想が芽生えていたことを示している。ブラームスがシャコンヌの手法を管弦楽作品に使った経験は、『ハイドンの主題による変奏曲』(1873年)の終曲にその例があった。 1884年、51歳のブラームスはウィーン南西にあるミュルツツーシュラークで夏を過ごし、そこで第4交響曲の作曲に取りかかった。この年には前半の2楽章を完成させ、翌1885年に残りの2楽章を完成させている。 1885年9月、ブラームスのピアノの弟子であり、良い相談相手でもあったエリーザベト・フォン・ヘルツォーゲンベルクに第1楽章の楽譜を送って意見を乞うた。ヘルツォーゲンベルク夫人は、その返事で、作品の深みや統一性を称えつつ、「一般の善良な聴衆の耳よりも、分析的な専門家の『目』に訴えるのではないか」と、技法が複雑すぎることへの懸念も示した。 同年10月8日、ブラームスは初演に先立ち、ウィーンで友人たちを招き、イグナーツ・ブリュルとともにこの曲の2台のピアノ編曲版を弾いて試演した。ブリュルとの試演会は、第2交響曲以来の恒例となっていた。伝記作家のマックス・カルベックによると、第1楽章終了時には気まずい沈黙があたりを覆ったという。エドゥアルト・ハンスリックやハンス・リヒターらの反応は賛否両論で、カルベックに至っては、後半の2楽章を違うものに書き直してはどうかと提案したという。 初演後の1886年2月には、ヨーゼフ・ヨアヒムが曲の冒頭部分を改訂するようにすすめ、そのときはブラームスも同意して4小節の短い導入部を書いた。しかし、後日これはブラームスが抹消し、当初の構想は変えられなかった。 初演とその評価 1885年10月25日、ブラームス自身の指揮、マイニンゲン宮廷管弦楽団によって初演された。初演では、各楽章ごとに長い拍手が起こり、第3楽章はその場で直ちにアンコールされ、全曲終了後はマイニンゲン公ゲオルク2世の求めに応じて第1楽章と第3楽章をもう一度演奏したという。翌週にはハンス・フォン・ビューローの指揮でも演奏された。ブラームスは、11月からの同楽団の演奏旅行でドイツとオランダの各都市を回って演奏した。 ブラームスの友人たちもとまどったように、一見してわかる手法の古めかしさについては、「後向き」の態度ととる批判者もあった。当時ワーグナー派で、ブラームス批判の先頭に立っていたフーゴー・ヴォルフは、この交響曲について、ブラームスの創作活動が退歩している現れとし、「無内容、空虚、偽善」などと酷評している[要出典]。グスタフ・マーラーもこの曲を「空っぽな音の桟敷」と呼んだ[要出典]。一方で、ブラームスを擁護していたハンスリックは、ウィーン初演後の批評で、「その魅力は万人向きではない」と一定留保しつつ、その独創性を称え、第4楽章については「フィナーレは、暗い泉のようなものだ。長く見入れば見入るほど、星の光は明るく輝き映える」と評価している。また、当時ビューローの助手をしていた若きリヒャルト・シュトラウスは、初演前日の1885年10月24日に父親への手紙に「間違いなく巨人のような作品です。とてつもない楽想、そして創造力。形式の扱いや長編としての構造は、まさに天才的」と書いている。シュトラウスは、初演の際にトライアングルを担当したという。 楽器編成 ピッコロ(2番フルート持ち替え)、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ(3個)、トライアングル、弦五部。 楽曲構成 第1楽章 Allegro non troppo ホ短調。2/2拍子。ソナタ形式。ヴァイオリンが休符を挟んで切れ切れに歌う第1主題によって開始される。この主題は3度下降の連続、その後6度上昇の連続という動機から成り立ち、哀切な表情を湛えている(最初の8音は三度の下降分散和音に還元できる)。それがロ短調へ推移してロマンチックな緊張感を帯びていくと、突如、管楽器の三連音を含む古色味のある楽句によって断ち切られる。この楽句がこののち、第1主題と並んで重要な動機となり、続いて歌われるチェロとホルンによるロ短調の印象的な旋律も(これを第2主題と見る解釈もあるが、ここでは経過句とする)すぐこの三連音の動機へと移行する。木管と弦が緊張を解くように掛け合うと、木管がやはり三連音を使ったなめらかな第2主題をロ長調で出し、小結尾は三連音の動機で凱歌をあげる。提示部は、4つの交響曲中ただひとつ繰り返されない。そのためか展開部は第1主題が原型のままで始まる。展開部で最初に扱われるのは第1主題だが、やがて三連音動機も加わる。遠いティンパニ・ロールの轟をともなって、木管によって寂しげに第1主題冒頭が再現されるが、第1主題9音目から提示部と同じ姿に戻り、そのあとはロ短調への転調もなく、ホ短調からホ長調へと型どおり進む。しかし小結尾では三連音の動機を繰り返しながら再び悲劇的な高まりを強め、第1主題のカノン風強奏を迎えて、コーダにはいる。コーダはほぼ第1主題提示部の強奏変奏の形で、そのまま悲劇的に終結する。終止は、サブドミナント(IV)からトニカ(I)に移行するプラガル終止(アーメン終止・変格終止)を採用している。 第2楽章 Andante moderato ホ長調。6/8拍子。展開部を欠いたソナタ形式。ホルン、そして木管が鐘の音を模したような動機を吹く。これは、ホ音を中心とするフリギア旋法である。弦がピチカートを刻む上に、この動機に基づく第1主題が木管で奏される。これも聴き手に古びた印象を与える。ヴァイオリンが第1主題を変奏すると、三連音の動機でいったん盛り上がり、静まったところでチェロがロ長調の第2主題を歌う。単純明快な旋律だが、弦の各パートが対位法的に絡み、非常に美しい。再現部はより劇的に変化し、第2主題の再現は、8声部(第1・第2ヴァイオリンとヴィオラがディヴィジする)に分かれた弦楽合奏による重厚なものとなる。最後にフリギア旋法によるホルン主題が還ってきて締めくくられる。 第3楽章 Allegro giocoso ハ長調。2/4拍子。ソナタ形式。過去3曲の交響曲の第3楽章で、ブラームスは間奏曲風の比較的穏やかな音楽を用いてきたが、第4番では初めてスケルツォ的な楽章とした(ただし、3拍子系が多い通常のスケルツォと異なり、2/4拍子である)。 冒頭、第1主題が豪快に奏される。一連の動機が次々に示され、快活だがせわしない印象もある。ヴァイオリンによる第2主題はト長調、やや落ち着いた表情のもの。展開部では第1主題を扱い、トライアングルが活躍する。ホルンが嬰ハ長調でこの主題を変奏し、穏やかになるが、突如、第1主題の途中から回帰して再現部となる。コーダでは、ティンパニ(全交響曲中この曲のこの楽章と第4楽章では3台使用、通常は2台)の連打の中を各楽器が第1主題の動機を掛け合い、大きな振幅で最高潮に達する。 第4楽章 Allegro energico e passionato ホ短調。3/4拍子。バスの不変主題の上に、自由に和音と旋律を重ねるシャコンヌ(一種の変奏曲)。管楽器で提示されるこのシャコンヌ主題は8小節で、先に述べたとおり、バッハのカンタータから着想されたといわれる。楽章全体はこの主題と30の変奏及びコーダからなる。解釈上いくつかの区分けが考えられるが、ここでは、30の変奏をソナタ形式に当てはめた解釈によって記述する。 シャコンヌ主題 主音から出発して属音まで6つ上昇、オクターブ下降して主音に戻るという、E-F♯-G-A-A♯-B↑-B↓-Eの8つの音符からなる(上記のバッハの主題とは、A♯以外一致する)。注目すべきことに、シャコンヌ(またはパッサカリア)の通例とは異なり、旋律主題がバスではなく高音域に置かれている。IV度の和音に始まり、和声進行は定型通りではなく、属和音も5度音が下方変位させてあり、最後の和音は長調となるピカルディー終止。 提示部-第1-15変奏 第1主題相当部-第1-9変奏 経過部-第10-11変奏 第2主題相当部-第12-15変奏 ここでは3/2拍子に変わり、テンポが半分に遅くなる。第12変奏で印象的なフルート・ソロが聴かれる。第13変奏でホ長調に転調し、第14変奏と第15変奏では、管楽器によるサラバンド風の慰めるような歩みとなる。 展開部-第16-23変奏 第16変奏で冒頭のシャコンヌ主題が再現し(和声付けは異なる)、ここから後半部にはいる。第23変奏で再びシャコンヌ主題の形がはっきり現れてくる。 再現部-第24-30変奏 第24変奏から第26変奏までは、第1変奏から第3変奏までの再現で、より劇的。最後の2つの変奏(第29及び第30変奏)では下降3度音程の連続によって、第1楽章第1主題が暗示される。ブラームス自身によるピアノ4手(2台ではなく1台)連弾編曲版のみTempoIが置かれ、冒頭のテンポに戻される。 コーダ ピウ・アレグロに速度を速め、さらに緊張を高めて劇的に終結する。 #brahms,#ブラームス,#symphony,#交響曲,#第4番

ブラームス:交響曲 第2番 ニ長調, Op.73
00:00 1. Allegro non troppo 16:40 2. Adagio non troppo 25:56 3. Allegretto grazioso (quasi andantino) 30:59 4. Allegro con spirito 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヨハネス・ブラームスの交響曲第2番ニ長調作品73(ドイツ語: Symphonie Nr. 2, D-Dur op.73)は、1877年に作曲された。第1交響曲とは対照的に伸びやかで快活な雰囲気を示すが、構成的にも統一が見られ、音楽の表情は単純でない。ベートーヴェンの交響曲第6番「田園」にたとえられ、「ブラームスの『田園』交響曲」と呼ばれることもある。 作曲の経緯など ブラームスが交響曲第2番を作曲したペルチャッハ 1877年6月、ブラームスは南オーストリアのケルンテン地方、ヴェルター湖畔にあるペルチャッハ(ドイツ語版)に避暑のため滞在、第2交響曲に着手し、9月にはほぼ完成した。10月にバーデン=バーデン近郊のリヒテンタールに移り、そこで全曲を書き上げている。4ヶ月間の作曲期間は、第1交響曲の推敲を重ねて20年あまりを要したのと対照的だが、第1交響曲の作曲中にも準備が進められていたという説もある。 ブラームスは、ペルチャッハから批評家エドゥアルト・ハンスリックに宛てた手紙に「ヴェルター湖畔の地にはメロディがたくさん飛び交っているので、それを踏みつぶしてしまわないよう、とあなたはいわれることでしょう。」と書き送っている。その後、ブラームスは2年間続けてペルチャッハで夏を過ごし、この地でヴァイオリン協奏曲やヴァイオリンソナタ第1番「雨の歌」などが生み出された。ブラームスの親友のひとりである外科医のテオドール・ビルロートは、第2交響曲に接して「ペルチャッハはどんなに美しいところなのだろう。」と語ったとされる。 初演 1877年12月30日、ハンス・リヒター指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によって初演された。この初演は大成功で、第3楽章がアンコールされた。翌年9月にブラームスは故郷のハンブルクに招かれ、自身の指揮によって再演を果たしている。 楽器編成 フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ一対、弦五部。 ブラームスの他の交響曲で使われているコントラファゴットが使用されず、第2番だけにチューバが使われているのが特徴的である。 演奏時間 約45分(第1楽章の繰り返しを含む)。 楽曲構成 第1楽章 Allegro non troppo ニ長調、3/4拍子。ソナタ形式(提示部反復指定あり)。冒頭に低弦が奏するD-C#-D(ニ-嬰ハ-ニ)の音型が全曲を統一する基本動機となっている。ホルンが牧歌的な第1主題を出し、木管がそれに応える。ヴァイオリンが基本動機に基づく明るい旋律を歌う経過句ののち、チェロが第2主題を奏する。この主題の冒頭は「ブラームスの子守歌」として親しまれている子守歌 op.49-4を嬰ヘ短調にしたものを基にしており、イ長調へ向かう。提示部には反復指定があるが、あまり実行されない。展開部では、主として第1主題を扱い、経過句や基本動機も加わる。第1主題に基づくトロンボーンの響きが次第に高まってクライマックスを築く。緊張が緩んだところで再現部となる。コーダでは、独奏ホルンや弦楽の幻想的な響きが聴かれ、木管が基本動機に基づく旋律を示し、次第に弱くなって結ばれる。「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」(クレッチマー)と表現されることもある。 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso ロ長調、4/4拍子。自由なソナタ形式。 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I ト長調、3/4拍子。ABABAの形式。Aはチェロのピチカートに乗ってオーボエが吹く主題。基本動機の反行形である。Bは2/4拍子でテンポが速くなるが、主題自体はAの変奏で弦が奏する。二つめのBは3/8拍子に変えられている。 第4楽章 Allegro con spirito ニ長調、2/2拍子。ソナタ形式。

ブラームス:ドイツ・レクイエム 作品45
00:00 1. Selig sind, die da Leid tragen 09:15 2. Denn alles Fleisch 23:13 3. Herr, lehre doch mich 32:49 4. Wie lieblich sind deine Wohnungen 37:43 5. Ihr habt nun Traurigkeit 44:11 6. Denn wir haben hie 55:55 7. Selig sind die Toten 1. 第1曲 幸いなるかな、悲しみを抱くものは 2. 第2曲 肉はみな、草のごとく 3. 第3曲 主よ、我が終わりと、我が日の数の 4. 第4曲 万軍の主よ、あなたの住まいは 5. 第5曲 このように、あなた方にも今は 6. 第6曲 この地上に永遠の都はない 7. 第7曲 今から後、主にあって死ぬ死人は幸いである 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ドイツ・レクイエム(ドイツ語: Ein deutsches Requiem)作品45は、ドイツの作曲家ヨハネス・ブラームスが作曲したオーケストラと合唱、およびソプラノ・バリトンの独唱による宗教曲。1868年に完成し、翌年1869年初演された。全7曲で構成され、歌詞はドイツ語。 通常レクイエムはカトリック教会において死者の安息を神に願う典礼音楽のことであり、ラテン語の祈祷文に従って作曲される。しかし、ハンブルクで生まれ、ウィーンで没したブラームスはルター派信徒であるため、ルター聖書のドイツ語版の文言から、ブラームス自身が選んだ旧約聖書と新約聖書のドイツ語章句を歌詞として使用している。 これは、メンデルスゾーンが1840年に作曲した交響曲第2番『讃歌』ですでに行われた手法である。 また、演奏会用作品として作曲され、典礼音楽として使うことは考えられていないのが大きな特徴として挙げられる。ブラームス自身も、「キリストの復活に関わる部分は注意深く除いた」と語っている。 ポリフォニーが巧みに活かされた作品であり、初期作品ピアノ協奏曲第1番の第3楽章にも見られるようなバロック音楽、特に大バッハやハインリヒ・シュッツ(シュッツも、「ドイツ・レクイエム」を作曲している)の影響が顕著に見て取れる。また第1曲の旋律が全曲にわたり用いられており、楽曲構成にも統一が意図されている。 なお、この曲の理解者で1868年に一部演奏を担当した指揮者カール・マルティン・ラインターラーは、ブラームスの詞の選択に納得がいかず、ヘンデルの『メサイア』のソプラノによるアリア「私は知る、私を贖う者は生きておられる」を挿入した。 作曲の経緯と初演 この曲は1857年頃から書かれ始めた。この曲が構想されたきっかけは、1856年に自らを世に出してくれた恩人ロベルト・シューマンが死去したことにあったと言われている。1857-59年には早くも現在の第2楽章を完成させるが、そこからは進まなかった。しかし、1865年、ブラームスの母が死去し、これが彼に曲の製作を急がせることとなった。 まず、初演2年前の1867年12月1日、作曲されていた第1曲から第4曲までのうち、最初の3つの楽章の試演が、ヨハン・ヘルベックの指揮によりウィーン楽友協会で行われたが、演奏がうまくいかず聴衆の罵声を浴びて失敗した。エドゥアルト・ハンスリックもこの時、皮肉を込めた批評を書いている。しかしブラームスは諦めることなく作曲を続けて、第6曲と第7曲を書き上げ、初演1年前の1868年4月10日、ブレーメンで第5曲を除く全曲を自らの指揮で演奏し、成功を収めた。これにより、ブラームスは35歳にしてドイツ屈指の作曲家としての地位を確立した。その直後の4月28日、ラインターラーの指揮で再演され(上述)、5ヶ月後の9月17日、チューリッヒで8月までに完成した第5曲がフリードリヒ・ヘーガーの指揮で演奏された。 この5ヶ月後の1869年2月18日、カール・ライネッケ指揮のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により7曲全曲が初演された。この作品のユニークな特色の一つに、この初演以前に、上述のような部分的に作曲した楽章の分だけ演奏されてきた遍歴を持つことが挙げられる。 編成 演奏者ページ University of Chicago Orchestra (orchestra) 演奏者 Kimberly Jones (soprano), Jeffrey Ray (baritone) University Chorus, Motet Choir, Members of the Rockefeller Chapel Choir James Kallembach (conductor) 公開者情報 Chicago: University of Chicago Orchestra 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 From archive.org. Performed 30 May 2010, Mandel Hall. #brahms #requiem #brahmsthe boy #johannesbrahms brahms #thebestofbrahms

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 「雨の歌」, Op.78
00:00 1. Vivace ma non troppo 10:40 2. Adagio 18:53 3. Allegro molto moderato 演奏者ページ Stefan Jackiw (violin) Anna Polonsky (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 [tag/del] Purchase #violin,#johannes Brahms,#sonata,#violinist,#violin music,#twoset violin

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.83
00:00 1. Allegro non troppo 18:10 2. Allegro appassionato 27:04 3. Andante 38:40 4. Allegretto grazioso 演奏者ページ University of Chicago Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 演奏者 Edward Auer, piano solo 公開者情報 Chicago: University of Chicago Orchestra 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 Performed 2 February 2008, Mandel Hall. From archive.org. #brahms,#ブラームス,#concerto,#the best of brahms,#johannes brahms,#brahms lullaby