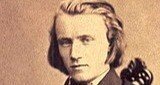#johannesbrahms

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調『雨の歌』作品78
This video is about Violin Sonata No. 1 in G major, Op. 78, "Regensonate", for violin and piano, by Johannes Brahms. In this video, I'm playing the first movement of this Violin Sonata, called "Regensonate". I'm using a violin by Antonio Stradivari, which I've borrowed from the Berlin State Museum. I really enjoy playing this Violin Sonata, and I hope you'll enjoy listening to it too! 00:00 I. Vivace ma non troppo 10:41 II. Adagio 18:53 III. Allegro molto moderato 演奏者 Stefan Jackiw (violin) https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Jackiw Anna Polonsky (piano) https://www.annapolonsky.com/ 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 ヴァイオリンソナタ第1番ト長調『雨の歌』作品78(ドイツ語:Sonate für Klavier und Violine Nr. 1 G-Dur op. 78)は、ヨハネス・ブラームスが作曲したヴァイオリンソナタ。 概要 第1番を作曲する以前にブラームスは、1853年秋頃(それ以前とする説もある)にイ短調のヴァイオリンソナタを作曲した。シューマンはソナタの出版を提案したが、ブラームスの判断(自己批判)で破棄されたという。 本作は1878年と1879年の夏に、オーストリア南部のヴェルター湖畔の避暑地ペルチャハで作曲・完成された[1]。1877年から1879年までの3年間はこの地で過ごしていたが、この3年間のあいだにブラームスは、交響曲第2番(1877年)やヴァイオリン協奏曲(1878年)なども作曲している。 「雨の歌」の通称は、第3楽章冒頭の主題が、ブラームス自身による歌曲「雨の歌 Regenlied」作品59-3の主題を用いているためである(ただし、ブラームス自身はそう呼んでいない)。これ以外にもヴァイオリンソナタ第2番作品100なども、自作の歌曲と主題の関連性が指摘されている。ブラームスは1879年2月16日にクララ・シューマンに送った手紙の中で病床にあったクララの末っ子フェリックス・シューマンを見舞うとともにこの曲の第2楽章の主題を送っている(ただし、皮肉にもブラームスが手紙を送ったその日にフェリックスは24歳の若さで死去した)。クララはその後このソナタについて「あの世に持っていきたい曲です」と述べるほどの愛着を見せている。 第1番は、ヨーゼフ・ヨアヒムのヴァイオリン、ブラームスのピアノによって、最初にプライベートな非公開の場で最初の演奏が行なわれた。その後、1879年11月8日にマリー・ヘックマン=ヘルティのピアノ、ロベルト・ヘックマンのヴァイオリンによってボンにて公開初演が行なわれ、その12日後の11月20日に、ブラームスとヨーゼフ・ヘルメスベルガー1世によって再演された。 構成 全3楽章の構成で、演奏時間は約27分。 第1楽章 Vivace ma non troppo ト長調、やや凝った複雑なソナタ形式による楽章。軽やかで抒情的な雰囲気をもつ第1主題と、より活気のある第2主題で展開される。音楽批評家の大木正純は、ズーカーマン盤の解説書(UCCG-9579)にて、この第2主題を「ブラームスの書いた最も印象的な旋律のひとつ」と評している。 第2楽章 Adagio 変ホ長調、三部形式で叙情と哀愁が入り交じる緩徐楽章。民謡風の旋律がピアノで奏され、ヴァイオリンが加わって哀愁を歌う。第2部は葬送行進曲風の調べで、この旋律は第3部で再び回帰する。 第3楽章 Allegro molto moderato ト短調、歌曲「雨の歌」と「余韻」に基づく旋律を主題としたロンド。主題は第1楽章の第1主題と関連があり、また第2エピソードとして第2楽章の主題を用いるなど、全曲を主題の上で統一している。最後はト長調に転じて第2楽章の主題により締めくくられる。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ヨハネス・ブラームス 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ブラームス #ヴァイオリンソナタ第1番 #雨の歌 #作品78 #ViolinSonataNo1 #Op78 #Regensonate #JohannesBrahms

ブラームス:弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 作品18(For 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons and 2 Horns)
In this video, we'll be looking at Johannes Brahms' String Sextet No. 1 in B♭ major, Op. 18. This work was composed in 1860 and is one of Brahms' most popular pieces of orchestral music. If you're interested in classical music, then be sure to check out this video. We'll be discussing the history and composition of this piece of music, as well as how you can perform it. If you're a musician or just curious about Johannes Brahms, then this video is for you! 00:00 I. Allegro ma non troppo 12:00 II. Andante ma moderato 21:12 III. Scherzo: Allegro molto 24:24 IV. Rondo: Poco allegretto e grazioso 演奏者 Robert G. Patterson (conductor) https://robertgpatterson.com/ 公開者情報 Robert Patterson https://robertgpatterson.com/ 演奏者 Riverside Wind Consort Saundra D'Amato, Joey Salvalaggio, oboe Rena Feller Friedman, Nobuko Igarashi, clarinet Samuel Compton, Jill Wilson, horn Leyla Zamora, Michael Scott, bassoon 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽六重奏曲第1番変ロ長調作品18は、ヨハネス・ブラームスが1860年に作曲した弦楽六重奏曲である。ブラームスが27歳の年に作曲され、若々しく情熱的な曲風で知られている。 作曲の背景 ブラームスは弦楽四重奏曲の分野では、ベートーヴェンの残した16曲の重圧により、40歳になるまで曲を発表することができなかったが、弦楽六重奏曲においては、古典派の巨匠たちに同様の曲種がなかったという気安さから、若くしてこの第1番変ロ長調を残すことができた。またヴィオラやチェロを好み、重厚な響きを好んだブラームスは、2本ずつにふえたヴィオラ・チェロの声部を自在に書くことにより、厚みのある響きや陰影豊かな叙情性を表現することに成功している。 シューベルトが最晩年に残したチェロ2本の弦楽五重奏曲の、重厚で深い表現から影響を受け、弦楽四重奏にヴィオラ・チェロを追加するという着想を得たともいわれる。 編曲版 作曲の同年にブラームス自身によって第2楽章がピアノ独奏用に編曲され(「主題と変奏」)、クララ・シューマンの誕生日にプレゼントされた(1927年出版)。全曲の編曲としては、作曲者による四手ピアノ版、弦楽六重奏曲第2番とともに編曲したテオドール・キルヒナーによるピアノ三重奏版がある。 曲の構成 第1楽章 Allegro ma non troppo、変ロ長調 第2楽章 Andante ma moderato、変奏曲、ニ短調 第1ヴィオラから始まる力強くロマンティックな旋律(譜例)は有名である。変奏曲ではロマンティックな音楽が堰を切ったように自在に展開される。ルイ・マル監督の映画『恋人たち』で用いられていることでも知られる。 第3楽章 Scherzo. Allegro molto - Trio. Animato、ヘ長調 第4楽章 Rondo. Poco Allegretto e grazioso、変ロ長調 演奏時間 35分ほど 編成 第1・2ヴァイオリン 第1・2ヴィオラ 第1・2チェロ Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ヨハネス・ブラームス 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ブラームス #弦楽六重奏曲第1番 #作品18 #JohannesBrahms #StringSextetNo1 #Opus18

ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36
In this video, we're going to take a look at Johannes Brahms' String Sextet No. 2 in G major, Opus 36, composed in 1864–65. This sextet is a beautiful work, and is ideal for performances by a chamber orchestra or viola consort. Learn more about this composition in this video, and see how it can be played on your instrument by following the accompanying audio. After watching this video, you'll have a better understanding of this beautiful sextet and be ready to give it a try! 00:00 I. Allegro non troppo 14:54 II. Scherzo: Allegro non troppo 22:34 III. Poco adagio 32:37 IV. Poco allegro 演奏者 Borromeo String Quartet (string quartet) https://www.borromeoquartet.org/ 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 演奏者 with Liz Freivogel (viola) and Daniel McDonough (cello) 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 備考 Recorded 2006 Nov. 5 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽六重奏曲第2番ト長調作品36は、ヨハネス・ブラームスが1865年に作曲した弦楽六重奏曲。同編成の弦楽六重奏曲第1番作品18と並んで親しまれている。 作曲の経緯 第1番の作曲から第2番の作曲まで 1860年に弦楽六重奏曲第1番を完成させ翌年に出版した後、ブラームスは1862年に、ハンブルクからウィーンに旅行に出かける。そこで、批評家エドゥアルト・ハンスリックをはじめとする多くの人々と親交を結び、その年からウィーンに定住する。その翌年には、ウィーン・ジングアカデミー(ドイツ語版)の指揮者に就任した。その後、ジングアカデミーの指揮者は1864年に辞任するものの、ブラームスはその後もウィーンにとどまり作曲活動を続ける。弦楽六重奏曲第2番はこのような最中で作曲された。 この曲のスケッチは1855年にまでさかのぼることができる。この年から、ブラームスはたびたびクララ・シューマンに宛てた手紙の中でこの曲の一部を披露している。作曲が本格的に行われたのは1864年からのことであり、その年の内に第3楽章までの作曲を完了した。全曲の作曲は、遅くとも翌年の7月までには完了した。ブラームスは、友人のヘルマン・レヴィに宛てた7月26日付け手紙の中で、この曲の四手ピアノ用の編曲が完了したことを伝えている。 出版は、紆余曲折を経てジムロック社から1866年4月に行われた。この時出版されたのは、総譜、パート譜、四手ピアノ用の楽譜であった。初演は、同年10月にアメリカのボストンにて、メンデルスゾーン五重奏団演奏会にて行われた。ヨーロッパ初演は11月にチューリヒで、ウィーン初演は1867年にそれぞれ行われている。 いわゆる「アガーテ音型」について この曲の作曲の際に必ず持ち上がる問題が、ブラームスのかつての恋人アガーテ・フォン・ジーボルト(Agathe von Siebold, 江戸時代に来日したシーボルトの親類)との関係である。ブラームスは、デトモルトの宮廷ピアニストを務めていた1858年にゲッティンゲンにて大学教授の娘だったアガーテと知り合い、恋愛関係に陥る。彼女はきわめて美しい声の持ち主で、ブラームスは彼女が歌うことを想定した歌曲を作曲している。しかし、1859年にアガーテから婚約破棄を伝えられ、この恋愛は終わることとなる。 前述のように、弦楽六重奏曲第2番のスケッチは遅くても1855年から始まっている。ブラームスは、この曲のうちにアガーテへの思いを断ち切る決意を秘めた伝えられている。その根拠として挙げられるのが、第1楽章の第2主題終結部に現れるヴァイオリンの音型である。この音型は、イ-ト-イ-ロ-ホという音であるが、ドイツ語音名で読み替えるとA-G-A-H-Eとなる。これは、アガーテの名(Agahte)を音型化したものだ、といわれている。また、ブラームス自身が「この曲で、最後の恋から解放された」と語った、とも伝えられたということも相まって、ブラームスの友人で彼の最初の伝記作家となったマックス・カルベック(Max Kalbeck, 1850-1921)以来、有名な逸話として伝えられている。 しかし冷静に考えるならば、この逸話にはいくつかの疑問点が浮かび上がる。その第1に、果たしてこの音型は本当にアガーテを音型化したものなのか、という点である。ブラームス自身はこの音型について何も語ってもいないし、ドキュメントも残していない。ということは、この音型がアガーテを音型化したものであるということに対して、反論する証拠がないと同時にそれを裏付ける証拠もないわけである。また、作曲時期についても、この逸話が第1番の作曲時期(1860年)ならば納得できようが、果たして失恋(1859年)と第2番の作曲時期(1864年~1865年)との間にこれほどの隔たりがあるものか、という点が疑問として残る。さらに言うならば、カルベックの記述に対して、ブラームスの作品をあまりにも詩的に解釈しすぎているのでは、という批判が存在するのも事実である。この逸話については、カルベックの記述がすべての源であるということをあわせるならば、その信憑性についてはもう少し慎重を期すべきである。 編成について ヴァイオリン 2、ヴィオラ 2、チェロ 2 前作と同じ編成である。 構成 以下の4楽章からなる。 第1楽章 Allegro non troppo ト長調、ソナタ形式による。ヴィオラのさざ波のような音型にいざなわれるように、ヴァイオリンに息の長い第1主題が現れる。この主題は途中で変ロの音や変ホの音をとるため、ト短調のような印象を与える。やがて楽器を加えながら高揚していき、チェロに伸びやかな第2主題が現れる。この第2主題がヴァイオリンにより繰り返されたその最後に、結尾として例の「アガーテ音型」が登場する。展開部は、さざ波の音型を基盤としながら、主に第1主題を中心に展開していく。この展開がひとしきり終わった後に、緩やかに再現部へと入っていく。 第2楽章 Scherzo, Allegro non troppo - Trio, Presto giocoso ト短調、複合三部形式による。主部はハンガリー風の2拍子のスケルツォ。中音域以下がピチカートをする中、ヴァイオリンが愁いを帯びた主題を提示する。トリオではト長調の3拍子に変わり、それまでの憂いから解放されたように明るい旋律となる。中間部では持続音の間に活発なメロディが挟まる。その後主部が戻ってくる。そして、第1部のコーダをアニマートで処理しこの曲を終わる。 第3楽章 Poco adagio ホ短調、変奏曲形式による。主題と5つの変奏からなる楽章で、変奏曲作曲家ブラームスの手法が光る楽章。主題はヴァイオリンに現れるが、伴奏が2連符と3連符によって同時進行する形をとっており、かなり複雑なテクスチャーを築いている。ハンスリックはこの楽章について「主題のない変奏曲」と評している。最後は同主調のホ長調で静かに終わる。 第4楽章 Poco allegro ト長調、ソナタ形式による。9/8拍子のリズムに乗って16分音符の細かいパッセージによって始まる。クレッシェンドして高揚した後、ヴァイオリンによって静かに第1主題が現れる。この主題を扱いながらフォルテになると、ヴァイオリンのオブリガートを伴って、チェロに第2主題が現れる。これは高音で伸びやかに歌われる。展開部は比較的短く、第1主題を断片的に扱いながら転調を繰り返す。やがて再現部に戻るものの、再現部は幾分簡略化されている。コーダは長く、第1主題を元に気分を高揚させていき華やかに曲を結ぶ。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ヨハネス・ブラームス 『弦楽四重奏曲』再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zMdO7fTwSqHJWzWkfwzO4_ ヨハネス・ブラームス 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ブラームス #弦楽六重奏曲第2番ト長調 #作品36 #JohannesBrahms #StringSextetNo2 #Opus36

ブラームス:ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83(Konzert für Klavier und Orch ester Nr.2 B-dur op.83
In this video, we'll be going through the second movement of Johannes Brahms' Piano Concerto No. 2 in B♭ major, Op. 83. This movement is full of excitement and excitement, and is sure to leave you eager to hear the whole concerto! If you're a fan of classical music, then you'll love this video! In it, we'll be going through the second movement of Johannes Brahms' Piano Concerto No. 2 in B♭ major, Op. 83, and that's sure to get your Classical music fix! 00:00 I. Allegro non troppo 15:59 II. Allegro appassionato 24:00 III. Andante 35:48 IV. Allegretto grazioso (P)ヴィルヘルム・バックハウス カール・ベーム指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1939年録音 Wilhelm Backhaus (Con)Karl Bohm The Staatskapelle Dresden Recorded on 1939 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヨハネス・ブラームスのピアノ協奏曲第2番変ロ長調作品83(ドイツ語表記:Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-dur op. 83)は、初期の作品であるピアノ協奏曲第1番より、22年後に書かれたピアノ協奏曲。交響曲第2番やヴァイオリン協奏曲と並ぶ、ブラームスの成熟期・全盛期の代表作であり、最も有名な作品のひとつでもある。 ブラームスの作曲の師匠エドゥアルト・マルクスゼンに献呈された。 経緯および初演 初めてのイタリア旅行にインスピレーションを得て1878年に作曲が開始され、ウィーン近郊のプレスバウムに滞在中の1881年に完成された。この間にヴァイオリン協奏曲の作曲に集中していたため、2回目のイタリア旅行から帰国後一気に書き上げた。イタリアで受けた印象を基に書かれているため、ブラームスにしては明るい基調で貫かれている。楽曲構成上はピアノ・ソロが単独で自由に奏するカデンツァ的な部分は無いとも言え、ソリストの超絶技巧の見せびらかしとしての協奏曲という従来の協奏曲観からは意図的に距離をとった作品であるが、それにもかかわらず、この作品が現実に要求する桁外れの難技巧は、多くのピアノ奏者や教師をして「最も難しいピアノ曲の一つ」と呼ばせてもいる(ちなみに記録によればブラームスはこの曲を自らの独奏で初演しており、ブラームス自身のピアノ演奏の技術の高さがうかがえる)。 ピアノ協奏曲第2番の一般初演は、1881年11月9日、ブラームス自身の独奏、アレクサンダー・エルケルの指揮によりブダペストのRedoute(建物の名称が1865年に変わり、現在も音楽ホールとして使われているヴィガドー(ハンガリー語: Pesti Vigadó))で行われた。不評だったピアノ協奏曲第1番と異なり、この作品は即座に、各地で大成功を収めた。ブラームスはその後、ドイツ、オーストリア、オランダでこの作品の演奏会を繰り返し開き、そのうちの幾つかはハンス・フォン・ビューローによって指揮された。 構成 一般的に古典派、ロマン派以降の協奏曲は3楽章から構成されるが、この作品は交響曲のようにスケルツォ楽章を備えた4楽章からなる。 第1楽章 Allegro non troppo 変ロ長調、4/4拍子、ソナタ形式。 第2楽章 Allegro appassionato ニ短調、3/4拍子のスケルツォ、複合三部形式。スケルツォ入りの協奏曲としては、アンリ・リトルフの5曲の「交響的協奏曲」、フランツ・リストのピアノ協奏曲第1番という先例がある。 第3楽章 Andante 変ロ長調、6/4拍子、複合三部形式。この楽章からトランペットとティンパニは使用されない。ヴァイオリン協奏曲第2楽章のオーボエのように、主題提示をピアノではなくチェロ独奏が行う。 第4楽章 Allegretto grazioso - un poco piu presto 変ロ長調、2/4拍子、ロンド形式。 楽器編成 独奏ピアノ、フルート2(ピッコロ持ち替え1)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2(第2楽章まで)、ティンパニ1対(第2楽章まで)、弦五部。 演奏時間 約50分(各18分、9分、14分、9分)。 エピソード ブラームスがその完成稿のコピーを送った友人、外科医兼ヴァイオリン奏者のテオドール・ビルロートはこの作品を、その規模の大きさにもかかわらず「ピアノ小品集」と表現した(ビルロートはこれ以前にブラームスから弦楽四重奏曲第1番、第2番を献呈されている)。実は、ブラームス本人もこのような逆説的な表現をわざと使っていたようである。ピアノの弟子であり、相談相手でもあったエリーザベト・フォン・ヘルツォーゲンベルクへ宛てた手紙の中で、ブラームスは長大で劇的な第2楽章を「小さなスケルツォ」と呼んだ。同様に、陽気な交響曲第2番(1877年)の時には、出版社に「堪えがたいほどに悲痛な作品である」と伝え、さらには「楽譜は葬式の黒枠を入れて印刷して欲しい」と申し出たという。 ヨハネス・ブラームス再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxeAouJeYyTV9dZCtwp3n4 #ブラームス #ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 #作品83 #PianoConcertoNo2 #JohannesBrahms

ブラームス:ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品40
In this video, we'll be playing Johannes Brahms' Horn Trio in E♭ major, Op. 40. This beautiful piece is full of beauty and lyrism, and is a must-listen for all fans of classical music. If you're a fan of classical music, then you need to check out this video. We'll be playing the Horn Trio in E♭ major, Op. 40, by Johannes Brahms, and it will be impossible not to be impressed. This piece is full of beauty and lyrism, and is a must-listen for all fans of classical music. 00:00 I. Andante - Poco più animato II. Scherzo: Allegro - Molto meno allegro - Allegro III. Adagio mesto IV. Finale: Allegro con brio 公開者情報 Blagomira Lipari, Lauren Becker, Rob Auler 演奏者 Lauren Becker (horn), Blagomira Lipari (violin) Rob Auler (piano) 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 LaVeck Concert Series, May 16, 2015 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品40は、ヨハネス・ブラームスが作曲した室内楽曲で、ホルン、ピアノ、ヴァイオリンのための三重奏曲である。ブラームスは、ホルンに代えてヴィオラを用いることを認めている。 概要 ブラームスは多くの室内楽曲を作曲しているが、ホルンを使用した室内楽曲はこの作品のみである。1865年の5月にバーデン=バーデンで作曲が始められた。バルブを持たないナチュラルホルンのストップ奏法で演奏することを意図して作曲されている。作曲者の友人であったホルン奏者アウグスト・コルデス(August Cordes)を想定して書かれたのではないかとの推測がある[2]。初演は同年の11月28日にチューリヒで、ブラームスのピアノと2人の友人によって行われた。 アダージョ・メストの第3楽章は、同年の2月2日に母が76歳で世を去ったため、母を追悼する気持ちを込めて書き上げている。また第3楽章の主題には、ドイツの古いコラール『愛する神の導きにまかすもの』("Wer nur den lieben Gott lässt walten")が用いられ[要検証 – ノート]、より重厚な対位法で書かれているが、これは母の死に直接関係していることが窺われる。 同じ編成の曲として、ハンガリーの作曲家ジェルジ・リゲティが1982年に作曲したホルン三重奏曲(英語版)がある。この曲には『ブラームスを称えて』という副題が付けられている。 構成 全4楽章から構成され、バロック時代の教会ソナタを思わせる楽章配置で、ソナタ形式は終楽章のみ用いられていることも特徴。演奏時間は約30分。 第1楽章 アンダンテ 変ホ長調、4分の2拍子。 第2楽章 スケルツォ(アレグロ) 変ホ長調、4分の3拍子。 中間部の主題は1853年に作曲したピアノ曲「アルバムのページ Albumblatt」にさかのぼる。この曲はゲッティンゲンの音楽監督だったアルノルト・ヴェーナーのアルバムから2010年に発見され、翌2011年に初演された。これはブラームスの曲では、確認されている限り現存する最古の作品である。 第3楽章 アダージョ・メスト 変ホ短調、8分の6拍子。 第4楽章 アレグロ・コン・ブリオ 変ホ長調、8分の6拍子。 #ブラームス #ホルン三重奏曲 #作品40 #HornTrio #Op40 #JohannesBrahms

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a
00:00 Theme: Chorale St. Antoni: Andante 02:03 Variation 1: Andante con moto 03:24 Variation 2: Vivace 04:27 Variation 3: Con moto 06:19 Variation 4: Andante 08:39 Variation 5: Poco presto 09:36 Variation 6: Vivace 10:57 Variation 7: Grazioso 13:56 Variation 8: Poco presto 15:10 Finale: Andante ( - 19:10 ) 演奏者ページ University of Chicago Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 公開者情報 Chicago: University of Chicago Orchestra 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 備考 Performed 25 April 2009, Mandel Hall. From archive.org. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 《ハイドンの主題による変奏曲》(ハイドンのしゅだいによるへんそうきょく、ドイツ語:Variationen über ein Thema von Haydn)は、ブラームスが1873年に作曲した変奏曲。《ハイドン変奏曲》の略称や、《聖アントニウスのコラールによる変奏曲》の別称でも親しまれている。先に2台ピアノ版(作品56b)、次に管弦楽版(作品56a)が完成した。 主題 ブラームスは1870年に、友人でウィーン楽友協会の司書、カール・フェルディナント・ポールから、当時はハイドン作とされていた《ディヴェルティメントHob.II.46》の写譜を示された。その第2楽章は「聖アントニウスのコラール」と題されていた。ブラームスが変奏曲の主題に用いたのがこれである。 近年の研究によって、ディヴェルティメントそのものがハイドン作でないか(イグナツ・プライエル作という説がある)、ディヴェルティメントがハイドン作であっても主題であるコーラルはハイドン作のものではなく、古くからある賛美歌の旋律を引用したものと考えられているため、最近は《聖アントニウスのコラールによる変奏曲》と呼ぶ向きも見られるが、一般には《ハイドン変奏曲》との呼称が定着している。 楽曲構成 Orchesterwerke Romantik Themen.pdf 主題 Andante 変ロ長調 序奏はない。10小節単位の楽節構造が特徴的な主題で始まる。すべての変奏は、ほぼ例外なく、主題の楽節構造に従っている。和声構造については、あまり厳密に従ってはいない。各変奏ははっきりした性格づけがされ、いくつかの変奏は、古い時代の音楽形式や作曲技法が使われている。 第1変奏 Poco piu animato 変ロ長調 弦が中心で、対位法的な進行を見せる。 第2変奏 Piu vivace 変ロ短調 木管が付点リズムの特徴的なメロディを奏でる。 第3変奏 Con moto 変ロ長調 やはり木管が中心だが、のびやかである。 第4変奏 Andante con moto 変ロ短調 オーボエとホルンのゆったりしたメロディが、二重対位法で進行する。 第5変奏 Vivace 変ロ長調 スケルツォ風の軽快な変奏。 第6変奏 Vivace 変ロ長調 ピツィカートの上で、ホルンとファゴットがリズミカルにメロディを奏でる。 第7変奏 Grazioso 変ロ長調 フルートの哀愁漂うメロディを、弦が引き継ぐ。 第8変奏 Presto non troppo 変ロ短調 不気味に動き回る弱音弦の上に、木管が陰鬱な調べを乗せる。非常に不満足な形で終止して終曲に続く。 終曲 Andante 変ロ長調 壮麗なパッサカリアで、これ自体がバッソ・オスティナートによる一種の変奏曲である。コラール主題を引き継いだ5小節単位のパッサカリア主題は19回変奏され、クライマックスでコラール主題が再呈示される。 #ブラームス,#ハイドンの主題による変奏曲,#SaintAnthonyVariations,#VariationsonaThemebyHaydn,#Op56

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.77
00:00 I. Allegro non troppo - Cadenza - Tempo I 23:25 II. Adagio 32:36 III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto 演奏者ページ Michel Schwalbé (violin) Orchestre de la Suisse Romande (orchestra) Ernest Ansermet (conductor) 公開者情報 Lausanne: Radio Suisse Romande, 1964. Reissue Schattdorf: Gagnaux Collection 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 Recorded December 9, 1964. Victoria Hall, Geneva 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 (Violinkonzert D-Dur) 作品77は、ヨハネス・ブラームスが1878年に作曲したヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲である。 概要 ブラームスは幼時からピアノよりも先にヴァイオリンとチェロを学び、その奏法をよく理解してはいたが、最初の、そして唯一のヴァイオリン協奏曲を書き上げたのは45歳になってからだった。これは、交響曲第2番の翌年という、彼の創作活動が頂点に達した時期にあたり、交響的な重厚な響き、入念な主題操作、独奏楽器を突出させないバランス感覚、いずれもブラームスの個性が存分に表現された名作となった。本作品は、ベートーヴェンの作品61、メンデルスゾーンの作品64と並んで3大ヴァイオリン協奏曲と称されている。 この作品を聴いたシベリウスは、その交響的な響きに衝撃を受け、自作のヴァイオリン協奏曲を全面的に改訂するきっかけとなった。構成、各主題の性格などベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲の影響が強い。 一方チャイコフスキーは、メック夫人へ宛の手紙で、この曲について「私の好みに合わない」「詩情が欠けているのに、異常なほどに深遠さを装ってみせる」と酷評している。 同年に発表されたチャイコフスキーの作品35と並び、超絶技巧を要求する難曲である。 作曲の経緯 1877年9月にバーデン=バーデンでブルッフのヴァイオリン協奏曲第2番をサラサーテが演奏するのを聴いた時が作曲動機であるとされている。1878年イタリア旅行の帰りに、避暑地ペルチャッハに滞在し、ここで本格的にヴァイオリン協奏曲の作曲を行った。同年8月21日付けのヨアヒム宛の手紙では、ヴァイオリン協奏曲のパッセージについて相談している。また翌日の手紙には協奏曲は4つの楽章からなる作品であると書いている。これに対してヨアヒムからは、スコアがないと判らないがとしながらも、独奏パートについての助言が届いた。さらにヨアヒムはブラームスの元を訪れ、この曲について議論をしている。10月中旬にヨアヒムは、ブラームスを説得し、翌1879年のライプツィヒでの新年のコンサートでこの曲を初演することを決めた。11月になってブラームスは、中間の2つの楽章を破棄し、新たな緩徐楽章を書いた。ブラームスがリハーサルのためにスコアとソロ・パートの楽譜をベルリンのヨアヒムに送ったのは12月12日になってからだった。 ヨアヒムは、この作品のために様々な助言を与えたが、ブラームスはそのすべてを受け容れたわけでなく、このために2人の関係はこのあとぎくしゃくしたものになった。 初演 1879年1月1日 ライプツィヒ・ゲヴァントハウスにて、ヨーゼフ・ヨアヒムの独奏、ヨハネス・ブラームス指揮のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により演奏された。 当初ブラームスはライプツィヒでの初演に反対した。それは20年前にこの地で行ったピアノ協奏曲第1番の演奏会が惨憺たる大失敗(拍手をしたのは3人だけだった)に終わった記憶によると言われている。ヨアヒムの熱心な説得により行われたヴァイオリン協奏曲の初演は、今度は大成功で、音楽批評家からも絶賛された。この初演の1週間後にはブダペストで、さらに翌週にはウィーンで、いずれもヨアヒムの独奏により演奏され、好意的に受け容れられた。 楽器編成 独奏ヴァイオリン、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4(2楽章で3番ホルンと4番ホルンがtacet)、トランペット2(2楽章でtacet)、ティンパニ(2楽章でtacet)、弦楽五部 演奏時間 約40分 作品の内容 第1楽章 Allegro non troppo ニ長調、ソナタ形式。冒頭からゆったりとした第1主題(譜例1-1)がヴィオラ、チェロ、ファゴットにより演奏され、オーケストラが力強く提示する。オーケストラによる第2主題の提示がないまま弦楽器群がマズルカ風のリズムを力強く奏すとコデッタとなり流れるように下降して、そのまま第2提示部へ入る。独奏ヴァイオリンが情熱的な音で演奏に加わり第1主題をオーケストラと歌い交わす。オーケストラによる提示部で披露された動機が回想されるうちに独奏ヴァイオリンが優美な第2主題(譜例2)を奏でる。これが第1ヴァイオリン、ヴィオラに引き継がれ再びコデッタが現れ、総休止で提示部が終わる。 展開部はオーケストラのトゥッティによる第1主題で始まり、これまでに登場した動機を次々に活用し、入念に変形・組み合わせしてブラームスの美質を存分に味わえる。また独奏ヴァイオリンには9度、10度という幅広い音程での重音奏法が要求されている。これについてヨアヒムが「よほど大きな手でないと難しい」と修正を提案したのを拒絶している。ここではブラームスらしく弦楽器群とティンパニによる激しいトレモロと木管楽器の分散和音にのって独奏ヴァイオリンが重音奏法で演奏を続け更に音楽は力を増して再現部に入る。やはりトゥッティによる第1主題で始まり、提示部の主題を順番に再現し、オーケストラによるトゥッティで力強く締めくくってからカデンツァとなる。 ブラームスはカデンツァを書いていないため、この協奏曲は多くのヴァイオリニストがそれぞれのカデンツァを書いており、その種類が多いことでも知られている。主なものに、初演者のヨアヒム、フリッツ・クライスラー、レオポルト・アウアー、アドルフ・ブッシュ、ヤッシャ・ハイフェッツらのものがあるが、やはり圧倒的にヨアヒムかクライスラーのものが演奏される。カデンツァの後は第1主題に基づくコーダで独奏ヴァイオリンが静かに奏でるが、徐々に速度と力を増しながら力強く結ばれる。 第2楽章 Adagio ヘ長調、三部形式。管楽器による合奏で始まり、オーボエが美しい主題(譜例2)を奏でる。サラサーテがこの作品の出版譜をブラームスから贈られながら、それでも演奏しない理由として「オーボエが旋律を奏でて聴衆を魅了しているというのに、自分がヴァイオリンを持ってぼんやりそれを眺めていることに我慢がならない」と語ったと言われる魅惑的な旋律である。独奏ヴァイオリンがこの旋律を引き継ぎ装飾的に奏でた後、経過句に入り中間部へ移る。中間部はヴァイオリンが憧れを切々と訴える「ヴァイオリンによるコロラトゥーラのアリア」と評される部分である。主部に戻ると再びオーボエが旋律を歌うが、時折中間部の動機が聞こえ、平穏のうちに終わる。 第3楽章 Allegro giocoso,ma non troppo vivace - Poco più presto ニ長調、変則的なロンドソナタ形式。前楽章とは打って変わってジプシー風の力強い主題で、独奏、トゥッティと何度か繰り返される。第1主題(譜例3)はブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番に似た3度の重音奏法の熱狂的な主題で、この楽章の重要なモチーフである。第1副主題は独奏ヴァイオリンが8度音程の重音で奏でる上行音型。続くロンド主題の後の第2副主題は2拍子と3拍子を組み合わせリズムに変化を持たせた主題。この主題を操作して行くうちやがて第1副主題が再現される。再び冒頭主題が戻ると続いて対位法的なカデンツァとなる。これにオーケストラが順次加わって行き結尾へと移る。ポコ・ピウ・プレストのコーダはトルコ行進曲風のリズムをチェロが刻み、独奏ヴァイオリンが主題を変形した旋律を演奏するが、やがて管楽器が第1副主題を暗示する。最後は低弦がピッツィカートを奏する上で独奏ヴァイオリンが主要主題による和音を静かに奏で、八分休符をはさんで力強く終わる。 #ブラームス,#johannesbrahms,#violin,#ヴァイオリン協奏曲,#Op77

ブラームス:8つの小品 作品76
00:00 1. Capriccio in F♯ minor 03:34 2. Capriccio in B minor 06:56 3. Intermezzo in A♭ major 09:53 4. Intermezzo in B♭ major 12:53 5. Capriccio in C♯ minor 16:03 6. Intermezzo in A major 20:15 7. Intermezzo in A minor 24:28 8. Capriccio in C major 演奏者ページ Felipe Sarro (piano) 公開者情報 Felipe Sarro 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 8つの小品(8 Klavierstücke)作品76は、ヨハネス・ブラームスが作曲したピアノのための性格的小品集。 概要 交響曲第2番の作曲から1年後、1878年の夏頃に、ヴェルター湖畔の避暑地ペルチャッハ(英語版)で作曲された。なお、第1曲の初稿のみ1871年に書かれている。第2曲がイグナーツ・ブリュルによって1879年10月22日に先行して初演されており、全曲の初演は10月29日にベルリンでハンス・フォン・ビューローによって行われた。ビューローはその後もこの曲集を愛奏したと伝えられている。出版は1879年春に行われた。 『ワルツ集』の独奏版以来、13年ぶりに出版されたピアノ独奏曲となった。マックス・カルベックは、ブラームスがこの頃ロベルト・シューマンやフレデリック・ショパンの作品の校訂を行ったことをピアノ曲への回帰と関連付けている。和声が晦渋になり作品が内向的になっていく、ブラームスの「後期」への入口にあたる作品[1]とも言われる。 楽曲構成 4曲の間奏曲と4曲の奇想曲を含む。全曲を通した演奏時間は27-28分程度。初版では1-4曲、5-8曲の2巻に分けて出版されていた。 第1曲 奇想曲 嬰ヘ短調 ウン・ポコ・アジタート、Unruhig bewegt(落ち着かずに、動きをもって)。6/8拍子。三部形式。1871年9月13日のクララ・シューマンの誕生日に贈られたとされる。中間部において下降アルペジオに乗って寂しげな旋律が奏でられ、上行アルペジオを中心にした両端部がそれを挟む。中間部を回想する短めのコーダが続き、嬰ヘ長調で終止する。 第2曲 奇想曲 ロ短調 アレグレット・ノン・トロッポ、2/4拍子。複合三部形式。スタッカートを中心にした軽快な作品で、演奏機会は多い。中間部はピウ・トランクイロとなって、なだらかな旋律も現れる。 第3曲 間奏曲 変イ長調 グラツィオーゾ、Anmutig, ausdrucksvoll(優美に、表情豊かに)。4/4拍子。二部形式。セレナード風の書法で、シンコペーションを伴った旋律を歌う。 第4曲 間奏曲 変ロ長調 アレグレット・グラツィオーゾ、2/4拍子。三部形式(中間部は主部の展開)。単一の伴奏音形と内声のEs音が執拗に保持される。曲調は優雅ではあるが、和声はかなり複雑に書かれ不穏さをにじませている。 第5曲 奇想曲 嬰ハ短調 アジタート・マ・ノン・トロッポ・プレスト、Sehr aufgeregt, doch nicht zu schnell(きわめて興奮して、しかし速すぎずに)。6/8拍子。A-B-A'-B'-A"の拡大された三部形式。分厚く書かれた活動的な作品で、曲集の中でも規模が大きい。3/4拍子と6/8拍子が共存するリズム法が特徴的。 第6曲 間奏曲 イ長調 アンダンテ・コン・モート、Sanft bewegt(穏やかに動きをもって)。2/4拍子。複合三部形式。無言歌風の穏やかな作品で、2:3のクロスリズムが用いられる。 第7曲 間奏曲 イ短調 モデラート・センプリーチェ、2/2拍子。A-B-C-B-Aのアーチ形式。比較的大きな場面転換が見られるが、各部は二度下降+二度上行の動機(交響曲第2番の基本動機と同一)で統一されている。 第8曲 奇想曲 ハ長調 グラツィオーゾ・エド・ウン・ポコ・ヴィヴァーチェ、Anmutig lebhagt(優美に、活動的に)。6/4拍子。広い音域を使うピアニスティックな作品。 #brahms,#ブラームス,#johannesbrahms,#8つの小品

ブラームス:ドイツ・レクイエム 作品45
00:00 1. Selig sind, die da Leid tragen 09:15 2. Denn alles Fleisch 23:13 3. Herr, lehre doch mich 32:49 4. Wie lieblich sind deine Wohnungen 37:43 5. Ihr habt nun Traurigkeit 44:11 6. Denn wir haben hie 55:55 7. Selig sind die Toten 1. 第1曲 幸いなるかな、悲しみを抱くものは 2. 第2曲 肉はみな、草のごとく 3. 第3曲 主よ、我が終わりと、我が日の数の 4. 第4曲 万軍の主よ、あなたの住まいは 5. 第5曲 このように、あなた方にも今は 6. 第6曲 この地上に永遠の都はない 7. 第7曲 今から後、主にあって死ぬ死人は幸いである 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ドイツ・レクイエム(ドイツ語: Ein deutsches Requiem)作品45は、ドイツの作曲家ヨハネス・ブラームスが作曲したオーケストラと合唱、およびソプラノ・バリトンの独唱による宗教曲。1868年に完成し、翌年1869年初演された。全7曲で構成され、歌詞はドイツ語。 通常レクイエムはカトリック教会において死者の安息を神に願う典礼音楽のことであり、ラテン語の祈祷文に従って作曲される。しかし、ハンブルクで生まれ、ウィーンで没したブラームスはルター派信徒であるため、ルター聖書のドイツ語版の文言から、ブラームス自身が選んだ旧約聖書と新約聖書のドイツ語章句を歌詞として使用している。 これは、メンデルスゾーンが1840年に作曲した交響曲第2番『讃歌』ですでに行われた手法である。 また、演奏会用作品として作曲され、典礼音楽として使うことは考えられていないのが大きな特徴として挙げられる。ブラームス自身も、「キリストの復活に関わる部分は注意深く除いた」と語っている。 ポリフォニーが巧みに活かされた作品であり、初期作品ピアノ協奏曲第1番の第3楽章にも見られるようなバロック音楽、特に大バッハやハインリヒ・シュッツ(シュッツも、「ドイツ・レクイエム」を作曲している)の影響が顕著に見て取れる。また第1曲の旋律が全曲にわたり用いられており、楽曲構成にも統一が意図されている。 なお、この曲の理解者で1868年に一部演奏を担当した指揮者カール・マルティン・ラインターラーは、ブラームスの詞の選択に納得がいかず、ヘンデルの『メサイア』のソプラノによるアリア「私は知る、私を贖う者は生きておられる」を挿入した。 作曲の経緯と初演 この曲は1857年頃から書かれ始めた。この曲が構想されたきっかけは、1856年に自らを世に出してくれた恩人ロベルト・シューマンが死去したことにあったと言われている。1857-59年には早くも現在の第2楽章を完成させるが、そこからは進まなかった。しかし、1865年、ブラームスの母が死去し、これが彼に曲の製作を急がせることとなった。 まず、初演2年前の1867年12月1日、作曲されていた第1曲から第4曲までのうち、最初の3つの楽章の試演が、ヨハン・ヘルベックの指揮によりウィーン楽友協会で行われたが、演奏がうまくいかず聴衆の罵声を浴びて失敗した。エドゥアルト・ハンスリックもこの時、皮肉を込めた批評を書いている。しかしブラームスは諦めることなく作曲を続けて、第6曲と第7曲を書き上げ、初演1年前の1868年4月10日、ブレーメンで第5曲を除く全曲を自らの指揮で演奏し、成功を収めた。これにより、ブラームスは35歳にしてドイツ屈指の作曲家としての地位を確立した。その直後の4月28日、ラインターラーの指揮で再演され(上述)、5ヶ月後の9月17日、チューリッヒで8月までに完成した第5曲がフリードリヒ・ヘーガーの指揮で演奏された。 この5ヶ月後の1869年2月18日、カール・ライネッケ指揮のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により7曲全曲が初演された。この作品のユニークな特色の一つに、この初演以前に、上述のような部分的に作曲した楽章の分だけ演奏されてきた遍歴を持つことが挙げられる。 編成 演奏者ページ University of Chicago Orchestra (orchestra) 演奏者 Kimberly Jones (soprano), Jeffrey Ray (baritone) University Chorus, Motet Choir, Members of the Rockefeller Chapel Choir James Kallembach (conductor) 公開者情報 Chicago: University of Chicago Orchestra 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 From archive.org. Performed 30 May 2010, Mandel Hall. #brahms #requiem #brahmsthe boy #johannesbrahms brahms #thebestofbrahms