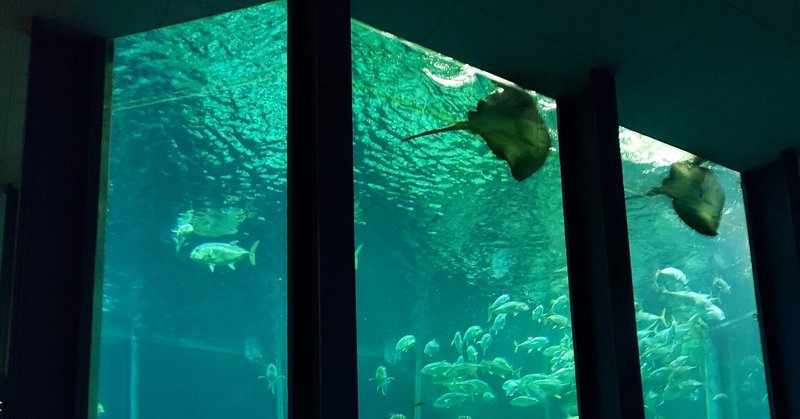
今の闇~抗がん剤から1年~
2021年6月1日、私は初めて抗がん剤を身体に入れた。ddECという、2週間に1度の投与を4クールやる治療だった。
4月に手術を終え、抗がん剤治療を開始するまで、受精卵凍結による妊よう性温存治療をしたり、術後病理診断で最終的なステージが決まったり、記事にできそうな区切りはたくさんあった。
本当なら、1年経つ毎に書いていくつもりだった。のに。
妊よう性温存治療について書くべき日付が巡ってきたとき、私の手は止まった。
私は文章を書くことが好きだし、特技の一つだと自負してもいる。書くときは読んだ人を引き込むつもりで書いている。
この言い回し、この比喩、うん、伝わるな……という気持ちの良い自己満足に浸りながら書いている。
でも、妊よう性温存治療、そして術後病理診断について書こうとすると、私の頭は真っ白というか、テレビの砂嵐のようになってしまった。
育児が忙しいせいだと思った。
でも、初めて抗がん剤を打った日付を迎えた夜、まったく眠れずに息子と夫の寝息に焦りを感じている中で、何故書けないのか、その理由が突然形を持って現れた。
妊よう性温存治療から先のできごとには、1年経っても尚、「過去の物語」として整理できない想いがあるからだ。他人に差し出せるような形にできないくらい、まだ生々しく、辛さや恐怖、苦しみが私の中にわだかまっている。
だから今回は、読み手を意識せず、備忘録のような感じで思い付くままに書き散らしたい。
まず妊よう性温存治療。
初めてがんセンターに行き、まだ癌だと確定する前に書いた問診票で、私は妊娠の希望があるという欄にチェックした。たぶん癌だったら、諦めてくださいと言われるだろう。でも、一応希望を伝えておかないと、何の断りもなく妊娠できなくなる治療をされるかもしれない……がん治療について何の知識もなかった私は、こんなことを考えながらチェックを付けた。「諦めてくださいと言われる」そんな簡単な話ではないなんて知らなかったから。そして、妊よう性温存治療というものの存在さえ知らなかったから。
癌だとわかった日、主治医はこちらの方が痛々しくなるくらい同情しつつも、冷静な彼らしく事務的に様々な情報を一気に私に叩き込んだ。妊よう性温存治療もその一つだった。
「まだ若いから生理が戻る可能性は充分ある。でも、抗がん剤をやってホルモン療法をやって、5年やるとしてもその間に卵子はどんどん劣化する。ダウン症のリスクを考えても若い今の卵子を残した方がいい」
妊よう性温存治療の説明に続けて、主治医はこのように自身の見解を述べた。
私は今後の妊娠について、2人目について、どう考えているか、なぜ希望するか、すぐに正直に話した。実を言うと、この話を聞けば主治医が妊よう性温存治療を「止めてくれる」と思っていた。
「あの…私は一人いるだけで充分なんです。でも、うちは母子家庭一人っ子同士の夫婦で、この先息子には従兄弟すらできないと思うと、兄弟はいた方がいいかなって。だから妊娠希望に丸付けました。だけど一番は生き残ることなので…妊娠が癌に悪影響ならやめます」
「まぁ…何を取るかですね。後悔しない選択をしてください」
そりゃそうだ。そうしたいから今相談してるのだ。月並みな返答に憤りそうになったとき、主治医が続けた。
「親として子供のためには何としても生き残らなければいけない」
主治医はいつもの聞き取りづらいくぐもった声が嘘のように、力強く断言した。自然と背筋が伸びた。この言葉は、以来今でもずっと、私の癌治療の指標であり、支えになっている。
主治医は続けた。
「あと50年生きるとして、後悔しないように、どう生きたいかです」
この時、私は一度目の前の主治医のことをシャットダウンした。そうしなければ泣いてしまいそうだった。
「生き残ること」「長く生きること」それらを諦めた上で延命していくのが癌治療だと思っていた。癌である自分はもう、「将来」なんて考えてはいけないのだろうと思っていた。でもせめて、息子の記憶に残るまでは…それが私の切実な想いだった。でも主治医は生き残らなければいけないと言い、私の50年後を見据えている。生きたいと思っていいと知ることが、告知されたばかりの私にとってどれだけ励みになったかは計り知れない。
が、それはそれとして、主治医の言葉を総合するに、やはり妊よう性温存治療は勧めないということだろうな、とも思った。
だからこそ、この直後の「提携しているレディースクリニックを紹介しますね」という主治医の言葉には拍子抜けした。
そんな、迷いの中で行った妊よう性温存治療だった。
そして今でも、その迷いは消えない。それにはいろんな理由がある。
一つは、莫大なお金がかかったこと。凍結する受精卵の数にも寄るが、私はトータルで80万近くかかった。補助金の制度を利用して半分ほどが戻ったが、それでも、もし私が2人目を授かれなかったら40万はドブに捨てたことになる。
もう一つは、本当に2人目を望むべきか、ずっと答えがでないということ。妊娠年齢を考えて、私のホルモン療法は5年という予定になっている。しかし、私の癌の悪性度を考えたら10年やった方が安心である。これが主治医の言う「何を取るか」の話になると思うのだが、仮に2人目を授かったとして、もしその後すぐに癌が再発して死んでしまうことになったら…息子はどう思うのだろう。兄弟と頑張ろうと思うだろうか。それとも、お母さんが死ぬんだったら兄弟なんか要らなかったと思うだろうか……
そして最後に、私たち夫婦仲の問題もある。私たち夫婦は気が合うし、仲がいい。しかし、そこに男女関係はない。そうなってから2年以上過ぎている。私は、受精卵を凍結しつつも、自然妊娠ができたらいいなとどこかで思っていた。お金の問題と矛盾するが、でもその方が…どんな夜に彼もしくは彼女が自分達家族のもとに舞い降りてきてくれたのかがわかっている方が、なんとなく素敵だなという、年甲斐もない夢見勝ちな想いがあった。しかし、ホルモン療法が終り、生理が戻り、どんなに健康な女性に近づいたとしても、たぶん私が自然妊娠することはもうない。そんな夫婦仲になってしまった。そんな二人が、本来なら授かりようもない命を授かっていいのか。人工的かどうかの是非というより、性愛がなければ命は生まれないのが本当なのに、それがない二人の間に命が生まれていいのかという迷いがある。そうして生まれた子は、夫婦が愛し合った結果ではなく、私が現代医療の恩恵を受けた結果でしかないんじゃないか。たとえ不妊治療の末で人工受精や体外受精に及んだとしても、そこに夫婦二人の男女の愛があるなら自然妊娠と変わらない尊いできごとだと思う。でも、夫婦がもう男女としては愛し合っていないのに、そこに子が生まれるのは……?私にはそんな、感傷的な迷いがずっとある。
妊よう性温存治療をしたからこそ、私は「2人目」というワードに敏感になった。ママ友が妊娠するのが怖い。息子の検診で妊婦を見るのが怖い。芸能人の第二子誕生が怖い。私の中に、そんな妬み嫉みうずめく地雷原が生まれてしまった。
妊よう性温存治療を振り返ると、そんな地雷たちがカタカタと音を立てる。
妊よう性温存治療を終えて一週間もしないうちに、術後病理診断が出た。
術前の診断では、私はステージ1だった。でも癌の悪性度がちょっと気になるから、たぶん抗がん剤はするでしょう…そんな話だった。抗がん剤をすることへのショックや拒否感はなかった。嘔吐恐怖症で、悪阻のときは吐きたくないがために拒食になり、飢餓状態だと診断された私である。抗がん剤にもとにかく吐くイメージがあったが、何故かやりたくないとは思わなかった。生きられれば何でもよかった。「親として生き残らなければならない」私自身がそう思うようになっていた。
気がかりなのはステージであった。病理診断が出る前、私は素直な恐怖を主治医に訴えた。
「ステージが上がるのが心配です。2cm超えたら上がるんですよね?18㎜だからギリギリじゃないですか」
「面でなく、立方体で考えてください」
理系に疎い私は黙った。一気に働きが悪くなった私の思考回路などお構いなしに主治医は続けた。
「面で2ミリ3ミリ大きくなったところで、あまり変わらない。そりゃ1cmと3cmだったら違うだろうけど。ステージも、便宜的に分けなきなゃいけないからただ区切ってるだけです」
ただ区切ってるだけ。頭の悪い私はそこだけを信じて少し安心することにした。
そんなやりとりがあったものの、この日まで何度も検索魔になった私には、ステージ1とステージ2の5年生存率、10年生存率の違いが頭にこびりついていた。初めてのPET検査の結果の日ほどではないが、がんセンターに向かう私の喉はカラカラで、何もないのに何かを嚥下しようとして吐き気を誘っていた。
診察室に入ると、いつもの飄々とした主治医だった。
「傷見せてごらん」
カーテンが引かれるのを目で追いながら、これは大丈夫そうだぞ?と安堵した。
「うん、問題ないね。じゃ、戻って」
椅子に戻ると、主治医はホチキス留めの資料を机上に差し出した。
「……!」
息を呑んだ。動揺を悟られないよう、身体を固くした。
私のステージは、1から2aに上がっていたのだ。
それでも、そこは覚悟してきていた。18㎜だったのだ。たった2ミリなんて誤差だから、こうなる可能性はあった。私の腫瘍は結局、24㎜だった。
そんなことよりも、癌の増える力を表すki67という数値が、術前では20~30%と聞かされていたのに60%に上がっていた。さらに癌の悪性度を表すグレードも、2から3に上がっていた。
あぁ、私の癌は、「まぁ助かるだろう」という類いのものではないのだ。手術までの、治ろうとするヤル気、高揚感が消し飛んだ。
その後の主治医との会話は、あまり覚えていない。放っておいたらかなり危険な癌であるということ、一方で治療の効果が望めるタイプでもあるということ、だから抗がん剤で徹底的に叩くということ、若いからハードな治療を選ぶということ…そんな話だった。あの日別れた右乳が、青緑に染められて輪切りにされた写真を突然何の前置きもなく見せられたけど、何の感慨もなかった。その写真を主治医が「カツサンドみたい」と形容したけれど、それが適当かどうか判断する力も残っていなかった。付き添いの夫も、珍しく顔を曇らせていた。
この頃には私はTwitterの闘病アカウントをフル活用していた。入院のときも、妊よう性温存のときも、思ったことを書き散らしては、同じ病と闘う先輩に励まされ、賑やかな癌患者ライフを送っていた。
術後病理診断の結果を受けて、「最悪でした」と呟いた。ステージが上がったこと、ki67が上がったこと、グレードが上がったこと、リンパ転移はなかったこと…もうどんな文面だったか覚えていないが、事細かに書き散らして嘆いた。
たくさんの人が励ましてくれた。同じような悪性度の人が何人もコメントをくれた。ki67が高いのは抗がん剤が効きやすいということを教えてくれる人、見えるものは取り切ったんだと安心させてくれる人もいた。
そして、ある人からもらった「リンパ転移がなくてよかった!」という言葉に、私の涙腺は決壊した。嬉しさからではない。何も考えず悲嘆の言葉を吐き続けた自分の幼さが情けなかった。
その言葉をくれたのは、きらちゃん(仮名)だった。
彼女はとにかく明るい子で、どんな人にも物怖じせず「タメ口でいこうよ!」と飛び込んですぐに仲良くなってしまうような人だった。Twitterを始めて、私が初めてタメ口で話すようになったのもきらちゃんだった。
きらちゃんは当時、いくつかの遠隔転移が発覚しステージⅣになったばかりだった。きらちゃんがどんな思いで私に「よかった」と言ってくれたのか。想像しようにも自分のことばかりに必死になっている私にはわからなかった。ただただきらちゃんに「よかった」と言わせた自分を責めて涙が止まらなかった。
それから四日後。私のTwitterのお手紙のマークに印が付いた。滅多にないことだから、驚いて反射的にタップした。
きらちゃんからのDMだった。
RONIちゃんこんばんは!
いきなりDMごめんね。
これからの抗がん剤不安でしかないよね。わたしもめちゃめちゃに不安だったし逃げてえええって思いながら治療してる(笑)
わたしでよければなんでも話聞くし答えられるものはそのまんまで答えるのでとりあえずLINE教えときます。嫌だったら全然無視してもらって大丈夫よん。
こんな文面に、LINEのIDが添えられていた。
嗚咽するほど泣いた。逆の立場なら、こんなに優しく明るく、手を差し伸べることができただろうか。私なら絶対に、「まだ再発転移したわけじゃないのに騒ぐなよ」と冷ややかな目を向けていた。きらちゃんの底知れぬ優しさが眩しくて何も見えなくなりそうだった。ただただ、子供のようにわんわん泣いた。
それからきらちゃんとはいろんな話をした。髪が抜けてきたらどんなシャンプーを使えばいいのか、安くて可愛いウィッグはどうやったら買えるのか、抗がん剤の吐き気止めがどれほど進化しているのか……。それだけじゃない。学生時代の話、ハマっているテレビ番組、好きな芸能人、家族の愚痴、そんな、病気とは関係ない話を画面いっぱいの長文をいくつも連ねて送り合った。
学生時代の部活動が同じだったり家庭環境が似ていたりしたのもあって、きらちゃんとの話は尽きなかった。癌じゃなくても絶対仲良しの友達になれたと思ったし、SNS上の友達じゃなくてちゃんと普通の、生身の友達になりたいと思った。春になったらピンクのウィッグで上野にお花見に行こうよ、そんなことを言い合った。
きらちゃんとのLINEは、私が抗がん剤を終え、きらちゃんが発熱する抗がん剤を始めた辺りで途切れた。
Twitterではきらちゃんは相変わらず明るくて、なんだかいつもちょっとした懸賞に当選していた。
そんな投稿も、2月の終わりに突然止んだ。短い短いLINEを送ったら、既読だけがついた。
そして春が来た。私は一年検診を無事に終え、再びきらちゃんにLINEをした。
最近どうしてる?春になったから桜も見たいな。
そんな文面だった。
1週間後、きらちゃんのお母様から、きらちゃんのLINEを通して、きらちゃんの訃報が届いた。
1ヶ月前に、きらちゃんは旅立ってしまったということだった。
Twitterのみなさんには、私から訃報を伝えた。
私でいいのか迷ったけれど、たくさんの人がきらちゃんを気に掛けていたから、お母様の了承を得て伝えた。きらちゃんにはいっぱい趣味があったから、きっと趣味を通して私よりも仲良くしていた人がたくさんいただろうけど、伝えさせていただいた。
私の闘病は、きらちゃんがレールを敷いてくれた。何にもわかってなかったけれど、きらちゃんが、大丈夫大丈夫と、面白おかしく導いてくれた。
きらちゃんが、いつも明るくて笑わせてくれたから、きらちゃんの病状が重いのはわかっていたはずなのに、絶対、普通の友達になれる日が来ると信じていた。こんな素敵な人が、奪われていいわけがないと信じていた。
つらいとか、怖いとか、そんな思いを見せないままフッと姿を消したきらちゃん。誰のことも傷付けないきらちゃんらしいお別れだった。
なんの光も見えない、と最近よく思う。
抗がん剤中はド派手なウィッグをしたり30越えてカラコンにハマったり、身体の苦しさはあったけれど心は元気だった。
今私は、日常生活を送れている。家事も育児も、ホルモン療法の副作用と闘いながら人並みにやっている。
でも。
心はとぷんと、そこの見えない泥水に沈んだまま顔を出さない。光が消えてしまったから。
告知や手術から1年が経ち、癌を振り返るつもりでいた。
でも癌は振り返るものではなかった。まだ私は癌にとらわれている。癌の只中にいる。
生きたいと願いながら、暗闇はそう遠くないと、冷ややかな覚悟をすることもある。
これが今の私の、とりとめなく、正直で、苦しい闇である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
