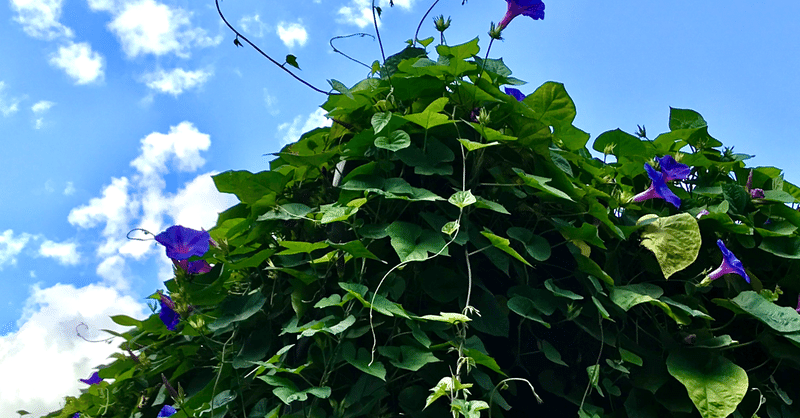
あなたに私は絡みつく 第53話
第53話 欧介
「見合い……」
「断ったけど。…びびった」
「………」
「焦りすぎなんだよ…そんなこと想像したこともない」
律はビールの代わりにジンジャーエールを飲んだ。そうとう昨夜のことを気にしているらしい。
叔父さんから持ちかけられた見合い話で苛々して呑んだのか。
俺は二本目のビールを開けながら、尋ねた。
「でも…叔父さんもそんなこと言い出すなんて、どうしたんだろうな」
「……母さんが」
「え?」
「……俺が、いつか結婚するときに蓄えておきたいって、仕事増やしたらしくて」
「まさか…それで倒れた?」
「…うん。で、叔父さんが早く結婚して安心させてやれって…」
「そうなんだ…」
「俺の気持ちそっちのけで、わけわかんねえし」
なるみさんの気持ちも、叔父さんの気持ちも、俺にはよく分かる。普通と違う、と言われるからこそ、普通のことがよく理解できてしまう。
でも今それを言ったら、十中八九、律はキレる。
「でも、いーんだよ。これはとりあえず解決したんだから」
多分解決なんかしていない。叔父さんは律に会う度、見合い話をもちかけるだろう。でも話したくないオーラ全開の律は、これ以上説明する気はなさそうだった。
ジンジャーエールをまるでビールのように飲み干すと、律が言った。
「…欧介さん」
「ん?」
「このタイミングで聞いていいのかわかんないんだけど…」
「…なに?」
「東京であったこと、聞きたい」
「………」
律は俺が何か言うのを待っていた。これも、律の悪酔いの原因のひとつか。
「あんまり、聞いて楽しい話じゃないと思うけど…」
「でも聞かないほうが、変な想像して苦しいから」
聞きたかったのを我慢していた律の、覚悟が見えた。俺はビールの缶を置いた。そして隣に座っていた律を手招きして、自分の前に座らせた。
後ろからハグして、頬にキスをした。
「欧介さん?」
「こうしてないと、話せなさそうだから…」
今、必要なのは律だけだと確認しながらじゃないと、聞いている方も話す方も辛い内容だ。
わかった、と言って律は俺に背中を預けた。
芦沢は18歳の俺を拾った。高校を卒業してすぐ、ゲイストリップをやっていた俺に本気で踊ってみないかと声をかけてきた。
最初は好みだったから、というだけの理由でついていった。飽きたら辞めればいいくらいの軽い気持ちで。
ところが、俺は芦沢と、ポールダンスの面白さにはまり、気がつけばどっちからも離れられなくなっていた。
既にいくつか事業を起こして成功していた芦沢は、そのころからモン・サン・ミッシェルを作ることを計画していた。
芦沢は俺に一流のトレーナーを付け、ポールダンサーとしての実力をつけさせた。
同時に自分の恋人として何不自由ない生活を与えた。
が、当時の俺に声をかける男は後を絶たず、俺は芦沢の目を盗み、たくさんの男と関係を持った。
「芦沢にバレて、一ヶ月彼のマンションに監禁された。そのあとの方がもっとやばかったけど…」
「そのあと…?」
俺はその時、芦沢が自分を愛しているのではなく、執着しているのだということを初めて知った。
恐怖を感じた。
逃げ出してもすぐ見つかって連れ戻され、芦沢のもとで暮らすうちに、最初に感じた恐怖は麻痺し、芦沢の言うことだけが正しいと思うようになってしまった。
ただ、踊っている間だけは楽しかった。
無心で踊るうちに、技術がついて、気が付けば世界ランクに名を連ねるレベルに達していた。
そして、初めてヨーロッパで行われる世界的なコンクールに出場することになった前日、俺は急激に気づいた。
もし世界一になったら芦沢は俺をどうするだろう?
自慢の恋人として、専属ダンサーとして一生彼のもとで踊るのか?
もし失敗したら?
用済みで捨てられる?そんなことになったら、俺は次に、何をして生きていけばいいんだ?
自分の意志で生きていなかった俺は、芦沢という男に寄生していただけで、次のことなど何も考えていなかった。
むしろ、考えていなかったのではなく、考えることを禁じられていたのだと思う。
俺だけを見ろ。
俺のために踊れ。
俺にふさわしくいろ。
お前の価値は俺が決める。
お前の幸せは俺が決める。
お前の人生は俺の為にある。
毎日それを植え付けられて麻痺していた頭が、急にクリアになった瞬間だった。
そのコンクールの当日、俺はパスポートとチケットだけを持って、芦沢から逃げた。日本に着いても東京には戻らず、地方に住む姉に連絡して匿って貰った。
律は、黙って聞いていた。
芦沢の名前が出ると、無意識に身体が緊張するのがわかった。
律の手を握った。強い力で握り返してきた。
「どうして…逃げ出したのに、また東京に戻ったの」
律は低い声で、尋ねてきた。おそらくこれは律が一番聞きたかったこと。
俺は律を抱きしめる腕にさらに力を入れて、言った。
「律に会って……幸せ過ぎて…律との未来を想像するのが怖くなって。律にはもっと、明るい未来があるんじゃないかと思った。俺といても…何も産まれるものはないし…」
「………」
「そう思ってた時に、モン・サン・ミッシェルのリニューアルのことで芦沢から連絡があって。一時的でいいから、戻ってきてほしいって言われたんだ」
芦沢は、最初、翌年のリニューアルオープンのために、と言った。しかし、蓋を開けてみれば、オープン予定は二年後だった。
「……馬鹿だった。あの狡猾な芦沢の裏を読めなかった。俺はここで暮らす五年の間に、あの男の独特のやり方を忘れてたんだ。気づいたときには手遅れだった。…でも、ひとつだけ、律に分かってほしいことがある」
律は顔だけ振り返り、横目で俺を見た。俺は言った。
「どんなに時間がかかっても、ここに帰ってくるつもりだった」
「……もし、モン・サン・ミッシェルで俺に会わなくても?」
俺はうなづいた。律は俺のハグを解いて、向き直ってから言った。
「もし、帰ってきたとき、俺が、誰かとつき合っていたり、結婚していたらって思わなかったの」
「何度も……思ったよ」
「そうなっていたら、どうするつもりだったの」
「たぶん…ただの隣に住む人に戻ったかも」
律の顔が曇った。怒っている。ごつん、と額をぶつけてきた。
「……いつも欧介さんは、そうやって自分が引く準備ばっかりする」
「……ごめん。でも、ただのお隣さんでも、律のそばにいられれば、それでいいと思ってたんだ」
「……やっぱり、いくじなしだ」
「うん。でもね、律」
「……でも?」
「きっと律は、俺を待ってるって、どこかで信じてた」
律と目が合う。きれいなアーモンド型の、黒目がちの瞳。嘘がつけなくて、思ったこと全てがそこに映し出される。
男を好きになってしまったことに、理由を探しもせず、怯みもしない。
何年経っても、くすまない律。
「……んだよ、それ……自信あんのかないのか、どっちだよ」
「……どっちかな」
「欧介さん」
「ん?」
「芦沢さんを……好きだった?」
俺が芦沢に初めて会った年齢と、律が初めて俺に会った年齢は同じ18。
人を疑う術を知らない時代の俺は、確かに芦沢が好きだった。
律のように、澄んだ瞳は持っていなかったけれど。
俺は律の頭を抱き寄せ、唇を合わせた。
「もう、律しか見えてないから……心配するな」
律の手が、俺の背中を力一杯掴んだ。痛いぐらいに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
