『和香様の座する世界』雑感
祖父が現世を去ったために天涯孤独の身となった主人公は、唯一の親類であり、いまは海外に居住する叔母が所有していた廃社に、寝所をもとめて転がりこむ。そこにあったのは、荒れ果てた本殿、人気の無い住宅兼社務所、打ち棄てられた井戸であった。これでは浮浪者とかわりないと、我が身の不幸を嘆きつつ境内で呆然としていた彼は、突如として謎の時空に取り込まれる。
そこは水の滴る地下洞窟なのだが、伏見稲荷のごとき千本鳥居が林立している。あまりに非現実的なことで、本能的な危機感を抱きながらも、彼は一歩を踏み出す。するともはや、なにかに憑かれたかのように、歩みを止めることができなくなる。
すべての鳥居をくぐり終えた先に、蝋化した、若い女の死体がある。その頭は禍々しい大刀で貫かれ、巨石に磔にされている。大刀によって上顎よりも上部が破壊されており、女の表情をうかがい知ることは出来ない。
ここで選択肢があらわれる――刀を抜くべきか、抜かざるべきか。この選択は、磔にされた女が頭のなかに直接語りかけてくる、怨念めいた声として示される。
この時点では霊力をもたない彼が彼女の声を聞くことができたのは、鬼見というよりも、おそらくは運命の力だったのだろう。主人公はこれが〈封印〉であると理解し、女への憐憫を抱く。彼女はこのような無残な仕方で磔にされ、封印され、人草には計り知れぬ長き時を耐え忍んできた。どのような事情があったにせよ、このままにはしておけない。
そして彼は霊力ではなく、物理的な力でもってこの大刀を抜く。すると封印が解け、女の形をした何かが動き出し、彼を襲う。彼は腕を食いちぎられ、あわてて千本鳥居へと逃走する。女だったものは、彼を捕食しようとしている。彼は髪の毛を引きちぎり、自分の爪を噛みちぎって捨て、それをおとりにして逃げようとする。しかし、間に合わないとわかる。
どこから現れたのか、それとも彼ともともと一体化していたものなのか、彼は「下側が大きく湾曲した」弓を発見する。ご都合主義ではなく因果的な必然によって、彼はいままでの人生で触ったこともない弓に矢をつがえ、射る。矢は怪物に命中し、主人公は打ち棄てられた境内の、古井戸の前に戻ってくる。
おそろしい夢を見ていたのだと自分を納得させかけたとき、古井戸のなかから、S子も著作権侵害を訴えかねない勢いで、さきほどの怪物が現れる。
しかし、もはや主人公は恐怖を抱かない。その理由は具体的には説明されない。ただ、なぜかここ(廃社の境内)は自分の世界、自分が根を生やした土地であると知っている。また、さきほど食いちぎられたはずの腕も、爪も元通りになっている。かつて通っていたが、祖父の死のために授業料を支払うことができなくなり、退学した学園で身につけた柔道をもちいて、彼はこの女の化け物を打ち倒す。技ふたつで女は倒れる。
襲われたとはいえ、これではただ女を昏倒させただけではないかと冷静になった主人公は、新たな住まいである社務所兼住宅へと彼女を運び込む。しばらくすると女が目覚め、奇妙な言葉をつぶやく。腹を空かせている様子なので、グラスに入った水を渡すと、二音節の、耳慣れないが、しかしどこか懐かしい感じのする言葉を、女はつぶやく。人語を解するのかと近づくと、まだ主人公をかじろうとするので、彼はあわてて女に柔術をかける。昏倒しているあいだにインスタント・ラーメンをつくり、目覚めたところでそれを差し出す。彼女は食べはじめる。言葉は通じないが、そのおいしさに感動していることがわかる。その姿は、ありていに言って、とてもかわいい。
異文化コミュニケーションの第一歩は駅前留学ではなく、言語の交換である。そのために主人公は、社務所に転がっていたコルクボードを用いて、文字と音と指示対象を交換しようとするのだが、女はそのコルクボードまでをかじる始末である。さもありなんという豪胆さだが、あきれ果てた主人公はすべてを忘れて就寝することにし、祖父が支払っていてくれたおかげでまだ通る電気のことを思い出し、女にテレビの使い方を教えてから、別室で眠る。
翌朝目覚めて女のところへ行くと、驚くべきことに、女はすでに新しい言葉――現代語を覚えている。主人公のことを「人草」と呼び、腹が空いているからおまえを食わせろと襲いかかる。しかしながら、長年の封印によって力が出ない。彼女はまたしても柔術によってうち伏せられる。その後、主人公はインスタント・ラーメンをもういちど作る(昨晩とは違う味)。すると彼女はそれをおいしそうに味わい、非常にすばらしい味であり、神であるわたしを迎えるのにふさわしい馳走であると発言する。
これが若香様降臨の顛末である。以後、主人公は興味に突き動かされ、アルバイトで稼いだ金の一部を削って、この現実離れした基地外……じゃなかった、神を社務所にかくまうことになる。徐々に現れてくる彼女の神的スーパーパワー(五階建ての建物のてっぺんにジャンプして飛び乗ったり、彼に鬼見の力を授けたり)にあてられて、ワカと名乗るこの女が、神としか形容しようのない存在であることを、主人公は知る。

よのためひとのためにつくさしめたまへと かしこみかしこみももうす……。
神が去り、現世が人草の世となったことを悟った和香様は、かつて彼女を封印せしめた天津神どもとの戦争の禍根をきっぱり忘れて、彼女の妹の捜索を主人公に頼む。鬼見の目を与えられた主人公は、夜ごとに日本列島の夢を見、そこにちりばめられた星空のような霊魂を見分していく。ひときわ禍々しいものがあって、これが和香様の妹神、ルルハ様である。つつがなく封印が解除され、インスタント・ラーメンによる懐柔によって廃社に二柱が揃うが、気性の荒い妹神は、天津神どもへの募る恨みを忘れていない。神というよりは妖怪に近い魑魅魍魎どもが跋扈し、神の気配が絶えて久しい現世で、彼女は復讐の炎を胸にいこらせたまま雌伏の時を過ごすことになる。

三種の神器ってどこにあるの? っていう話からの東京都千代田区の流れ。名前を言ってはいけないあの人。
とまあ、これが『和香様の座する世界』の序盤、邪神姉妹降臨編のあらすじである。あとのことは各々プレイして楽しむがよい。ここからはおきまりの印象批評、というよりそれにも満たない雑感である。九尾狐編、酒呑童子編、ぬらりひょんの娘婿編、綿津見のまぼろし編といった中盤のストーリーアークは、いずれも良くまとまっている。ふつうの神なら捨て置くにちがいない現世の瑣事におもしろがって介入しまくり、ワンパンでラスボス級の怪異を吹っ飛ばすことができる二柱を祀っている主人公/書き手は、かなり早い段階で少年漫画的パワーインフレを行わないことを決定したようだ。

大丈夫です、この作品が神話(それ自体がパロディー)なので……
確かに、われわれには和香様がついているのだから、目標を達成するだとかしないだとかいった話題は、すべて瑣事となる。いわば読者が和香様を信仰して同一化することで神の視点を獲得し、ごくふつうのプロットが「人草」の次元のものとなるのである。これによって人草と妖怪どもの、ふつうの物語であれば胸熱な努力や画策がすべて茶番となるのだが、その茶番感をただ単に虚仮にするのではなく、往年のパロディ・テキストで機知の笑いに転化した作家の手腕がすばらしい(作家は筒井康隆を師と仰いでいる)。
とはいえ、神は孤独である。この孤独を想像することは難しいが、終盤に登場した天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)の、あまりにもピントのぼけた会話から、それを読み取ることは可能である。『古事記』の第一行目の書き出しに登場して以来まったく出番のないこの神は、われわれの世の神社本庁のホームページに記載されている国生み神話にさえ登場しない。その理由を、自分の作ったものに関心がないからだと主人公に代弁させる作家もまあまあ孤独だが、閑話及第。
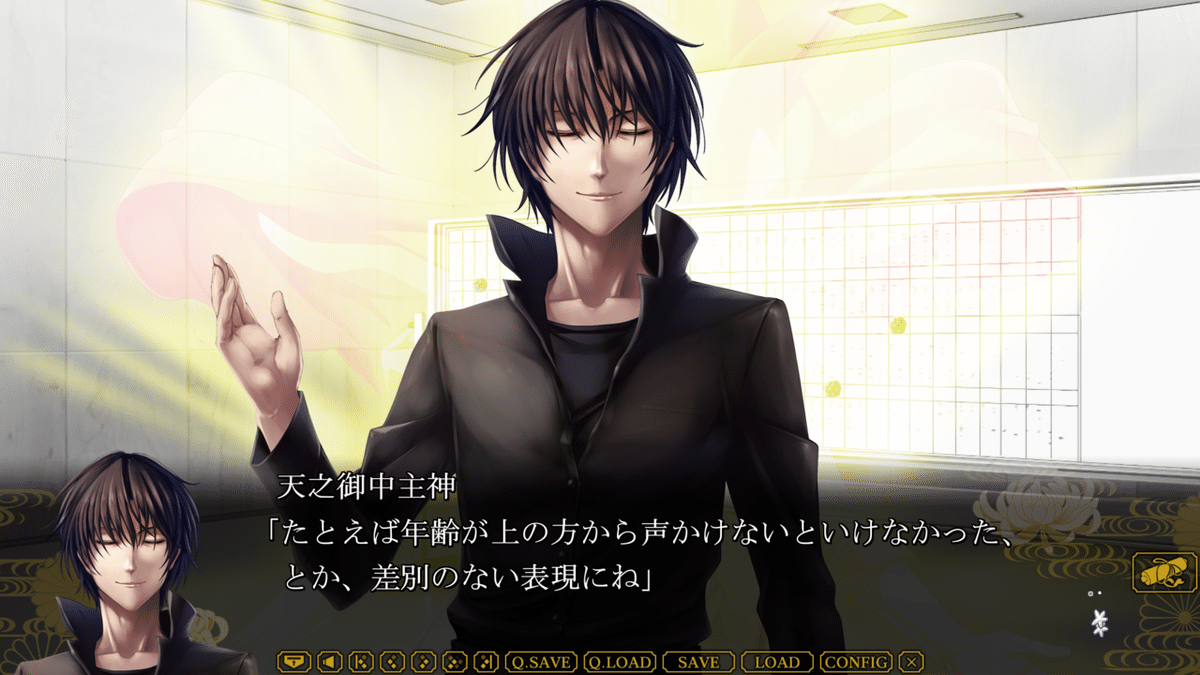
神なのでポリコレの気持ちがわからない。
実際のところ、すべての神/人草はこの作品で描かれた天之御中主神のような孤独さを、いくらか分有していると思う。たった百年で主人公に死なれてはこまると困惑する和香様は例外中の例外だが、いろんな作品を浮気につまみ食いする筆者のような神/人草は、つねに多くを知ろうとするその態度そのものが、世界への仁義にもとることに気づいているはずだ。その後悔をいくらかでも果たそうとして筆者はこうして筆をとる(飯を食ったのであれば働かねばならない)のだし、あらゆる創作の行為(読書も含む)は自ずからそうである。
では、神であること、この孤独、この後悔をどのようにして晴らすべきか? 驚くべきことに作家は、日本神話における最大の未解決問題――水蛭子の物語をみずから追記することで、現世的な動機(そもそもどうして和香様はそんなに現世のことに関わるの?)と、神話の採録(恵比寿信仰)を同時にやってのけている。そりゃあ生まれて間もないときに親に捨てられたら悲しいだろうし、流れ着いた先ですてきな人たちがいたら嬉しいだろう。そういう当然の感覚を神話に戻すのには、じつはかなりの想像力(妖力)を要する。
人間の情念が霊であり、現代に伝わる神話はすべて霊を失った空蝉である。しかし、この作家のような才能ある者が空蝉に霊を吹き込むことによって、神話はあらためて「再演」され、読者の心に刻まれ、続いていくのだ。あらゆる物語には類型がある。その類型の存在に嫉妬するのではなく、友として引き立てることで、われわれの世は続いていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
