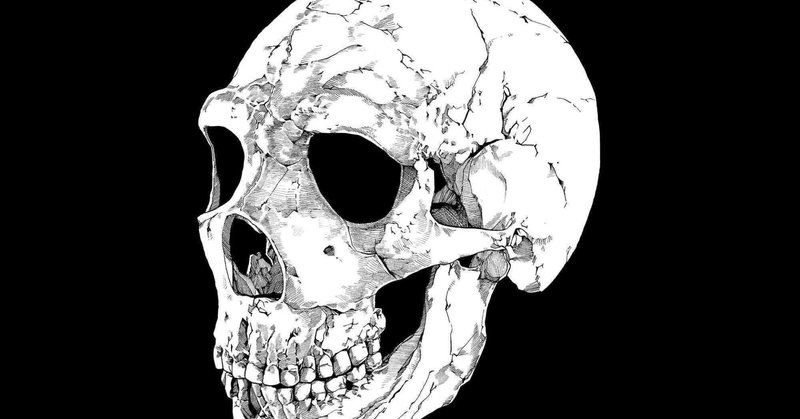
🎶ところがある晩、「チェロキー」でいろいろ試していると、旋律にそこの和音よりもずっと高い位置にある音程を使って、それに合う和音に置き換えてみれば、今まで頭の中で鳴っていた音を、実際に演奏できることに気づいたんだ。
きになる曲をリストアップしとくとりあえず
ガイコツというのはメロディーの骨子の意味で使っているみたい。坂本さんの曲では戦メリとラストエンペラーが同じガイコツと言うことになるそう
Em+ドみたいなことらしい。宇多田ヒカルにもあると
でユーミン サビのかけてゆくところ
そしてワインレッドの心と昭和の名曲が続く。忘れそうな思い出をそっと抱くところ
冒頭の音域についてはチャーリーパーカーがチェロキーについて言っているので、バップみたいなおかしな音楽にはそういう発見や気づきがあったかもしれない。
その頃、年がら年中同じような和音進行で演奏することに、全くあきあきしていた。そこできっと何か別のやり方があるはずだと、いつも考えていたんだ。時々、頭の中でそのやり方が鳴ってくるのだが、演奏してみるとうまくいかない。ところがある晩、「チェロキー」でいろいろ試していると、旋律にそこの和音よりもずっと高い位置にある音程を使って、それに合う和音に置き換えてみれば、今まで頭の中で鳴っていた音を、実際に演奏できることに気づいたんだ。私はすっかり元気になったよ。
しかし印象深いのは後発の人が言う行き詰まりだ。誰かが見た金脈は、誰かにとっての暇つぶしになるが、創始者は飽き飽きしている。
バップはクリエイティブなものだったのだ。メロディック・ライン全体のコンテクストは、正確に組み立てられた数多くのフレーズとして分解することができ、そのフレーズのそれぞれに新しいアイデアが込めてあり、ほかのフレーズとおたがいにどのようにでも組み合わせてつかうことができるし、コード構成が、クロマティックであろうと、ダイアトニックであろうと、どの曲のなかにでも組みこんでつかうことができる。一種のジグソーパズルに喩えることができるだろう。何百通りもの組立方があり、出来上がってくる絵はそのたびに違い、その絵の性格は、出来上がる度にお互いに一つ一つまったく違っている、というようなジグソーパズルだ。<br />しかし1949年には、すでにバードは、このような音楽イディオムのなかで自分が表現すべきことはみんな表現しつくしてしまった、と私に語っていた。レニー・トリスターノ
譜面書き起こしたりする気にはならなかったが、youtubeの世の中になって手軽に感じることができるガイコツ
お願い致します
