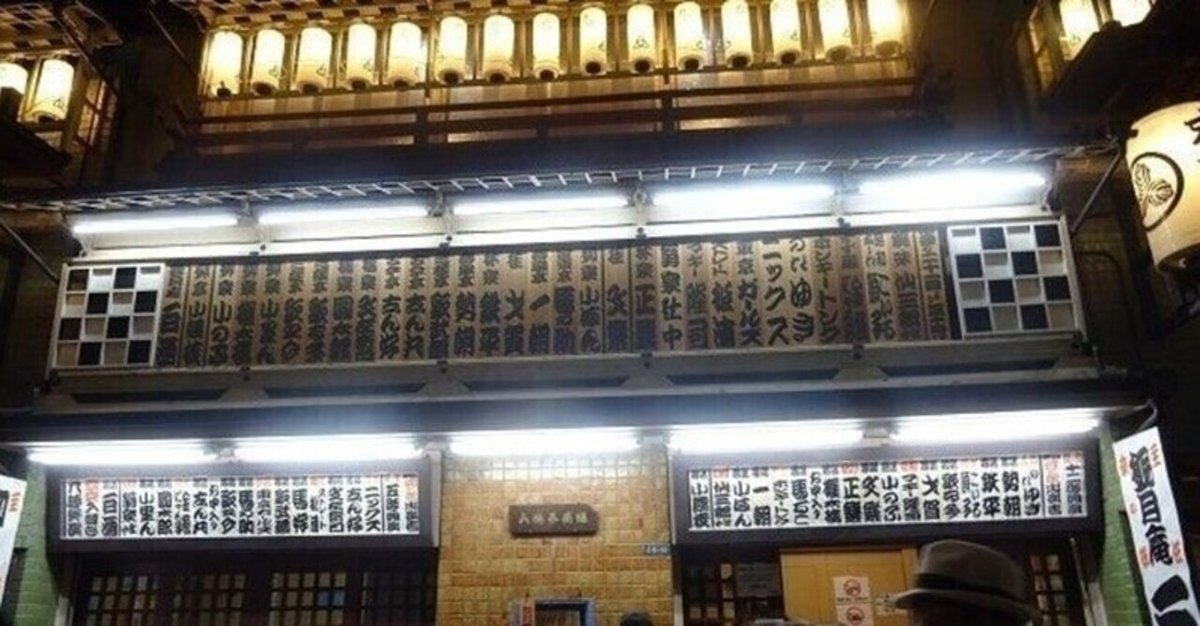
落語形式で考えよう;報道されてる品質不祥事はマネジメントシステムで防げるってホント?
【第十回】 マネジメントとは
大家さん 「あ、そうだ、10年以上前にもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら、って小説が人気になったのを覚えてるかい?」
熊さん 「なんか前に聞いたような気がしやすが・・・・。」
大家さん 「野球部のマネージャーなんてユニフォームの洗濯とか玉拭きなぞの雑務をこなして野球部を助けることと思われていたンだがな、マネージャーになった川島みなみってぇ女子高生が、たまたまドラッカーの書いたマネジメントという本を本屋で読んで、部の意識改革を進め、甲子園を目指すというストーリーだったんだ。」
熊さん 「そのドラッカーとかいう人はどんな人ですかい?」
大家さん 「ドラッカーさんてぇのはアメリカの経営学者でな、マネジメントってぇ本を書いて日本でも人気が出て、マネジメントの父なんて呼ばれているんだよ。」
熊さん 「ちょっと待っておくンなさいよ、そのドラッカーさんは、やっぱ会社経営ってのはマネジメントだといってンですか?」
大家さん 「経営ってのはアドミニストレーションといってな、運営という意味なんだよ。会社の運営という目的のために社長がやらなければならないことがマネジメントだとドラッカーさんは言っている。」
熊さん 「ふーん、分かったようで分かんねえなぁ。」
大家さん 「会社が成果を挙げて、株を買って資本を出してくれている投資家の期待に応えるのが運営だ。会社ってぇのは人の集りでできてるだろう、このためには、財源や土地や技術や人などの経営の資源を投入して会社の目的を達成することが必要でな、そのためにまず会社の目的を明確にして、役員の考え方を揃え、従業員の努力を調整しなっくっちゃならないと言ってるンだ。」
熊さん 「社長だけが一人でハッチャキになったってダメだっていうことだよな。」
大家さん 「だがな、ドラッカーさんのすごいところは、会社の中でマネジメントが必要なのは社長だけではないよ、会社の中にはいろいろな部署を作っているはずだから、それぞれの部署で同じようにマネジメントをし、しかも、それを会社全体の目的に合わせなけりゃならん、と言ってるンだ。」
熊さん 「なるほど、一部の正解は全体の正解でないかも知れないぞ、って訳ですか。」
大家さん 「ドラッカーさん自身はマネジメントシステムという言い方をしてなかったようだがね、個々の部署のマネジメントはお互いに関係しながら社長のマネジメントに組み込まれる必要があるから、全部でシステム化することは勧めていたらしい。」
熊さん 「マネジメント・・システム、って訳ですか。」
大家さん 「うん、そう。それと、ドラッカーさんは、マネジメントの相手として会社の事業利益だけじゃなく、お客や社会の信用を得ることなど、会社として必要なことを取り上げることができることいっていたし、会社だけではなく人の集合の組織でマネジメントの考え方を使えるとも言ってたんだ。」
熊さん 「日本でよく言われるボトムアップの考え方とずい分違っているみていだな。」
大家さん 「うん、マネジメントではトップダウン的な考え方が中心だ。」
熊さん 「トップダウンっていうとワンマンな社長を連想するけど・・・。」
大家さん 「いやいや、トップの考え方をマネジメントシステムを通して段階的に展開していく考え方だから、ワンマン経営とは違うんだ。」
熊さん 「企業の運営のためのマネジメントというと、利益の確保みたいなことを考えるンでしょうな?」
大家さん 「いや、それだけじゃなくってな、企業の運営はお客や社会の信頼を得なけりゃやっていけないだろう?だから、いろんなテーマで、お互いが矛盾を抱えないようにそれぞれのマネジメントも必要になるって訳なんだ。」
熊さん 「標準や規格としてマネジメント、マネジメントシステムを取り扱ったものはなかったのですかい?」
大家さん 「日本の規格にはなかったんだけど、ISOという国際標準化機構の作った標準にあるので、この次来たときはその話をしてみよう」
熊さん 「なんかむつかしそうだけど、大家さんなら分かり易く言ってくれると期待してますンで、よろしく!」
(次回に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
