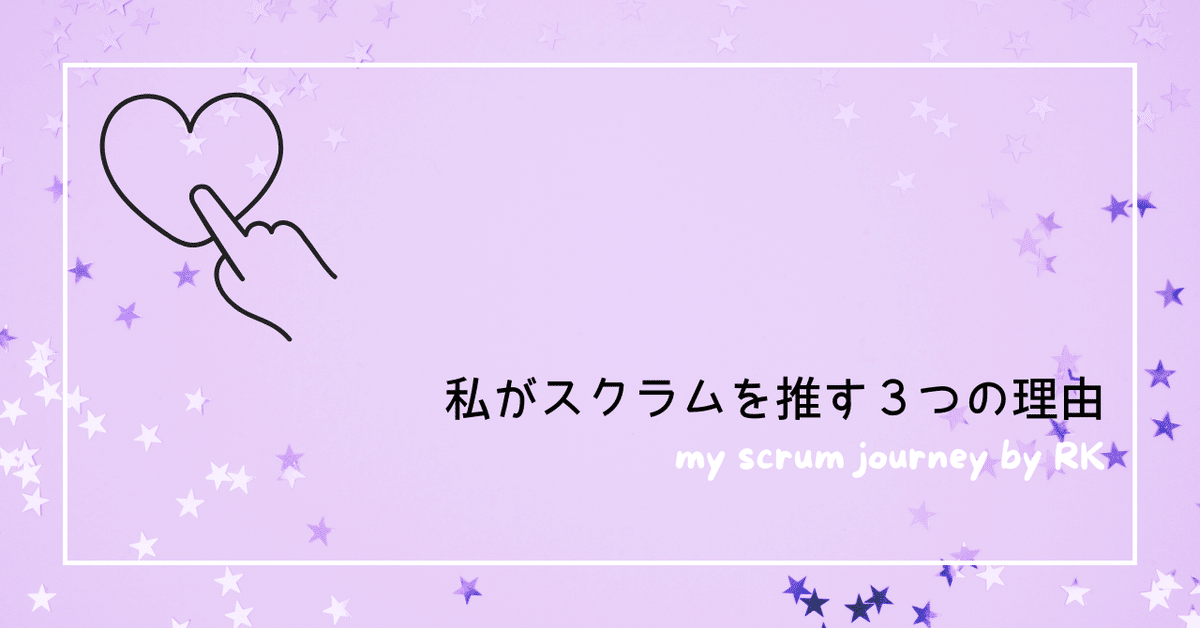
私がスクラムを推す3つの理由
アジャイルはひとりでも始められるし、ひとりでも実践できる。
でも、1人より2人、2人より3人、チームでスクラムできると、もっと良いことがある。
今回は、スクラムで得られる自由や安心に着目して、最近感じたことをベースにスクラム推ししてみる。
1. サイロの中の孤独からの開放
専門性の高い仕事を専門性の高い個人に割り振るのは、作業効率が良い。多くの組織で一般的に行われている方法でもある。
しかし、この割り振りは、負荷分散や技術継承・ノウハウ蓄積の観点からはいけていない。局所的な効率の最適化は、業務のサイロ化のような状況を生み出す一因にもなっている。
サイロ化は高効率に見えるが、人的・時間的リソース負荷の平準化を阻害する。そして、何より、孤独だ。どんな高度な専門家でも、誰かと相談したいときくらい、ある。絶対。
スクラムでは多能工を前提とし、課題は全員で共有して、全員でやっつける。お団子サッカー上等。全員が自分ごととして課題を捉えるために、コミュニケーションも密になり、そのうち、チーム成熟度が上がって、パス回しもうまくいくようになるハズ。もちろん、メンバーも日々のコミュニケーションや研鑽を通じて、お互いにスキルアップする。
コミュニケーションをしっかり取らないと進まない、スクラムのそんなしくみが、私はすき💛
ペアプロやモブプロも、すきなプラクティスのうちのひとつ。
実は、私のモブプロのイメージは、蜂球に近い。1人の熱量では足りない時も、発熱役・保温役など各ロールでスクラムを組んでやっつける。
もっとも、モブプロで余命が縮まることはないと思うけど。
2. 泥沼感あるいは迷走感からの開放
ステップバイステップ。一口サイズに切る。1段ずつ踏みしめながら、確認しながら、進む。
遠いゴールに向けてひた走っていると、いつまでたってもたどり着かない気がしてくることがある。でも、1段ずつ、1歩ずつのマイルストーンを刻むと、その分、ゴールに向かっている実感が得られる。実際に、1段ずつ、1歩ずつ進んだ後ろには、道ができている。そして、目指す先のゴールが動いても、新しいゴールに向けてマイルストーンを刻みなおせばよい。
定期的に道やマイルストーンをふりかえったり、時にむきなおったりするアジャイルプラクティスは泥沼感や迷走感を払拭する好機なので、私はすき💛
3歩進んで2歩下がるのと、1歩進むのとは、経験が違う。2歩下がった分があるとすれば、また、新たな2歩分のバックログを積めばよい。その新たなバックログは、新たなゴールに向かっているハズ。
3. カンペキな計画という幻想からの開放
カンペキな計画というのは、すべての要件が確定して変化しないような開発では、実現可能だ。カンペキな計画を立て、計画通りに遂行する。しかもコストを抑えて。日本の高品質の製造業を支えてきたのは、この手法であり、確定的な仕様定義ができる限りは最強といっても過言ではないと思う。この世界線では、変更は悪でしかない。
しかし、ビジネス環境の変化を含め、要件・要求が変化しうる状況では、カンペキな計画というのは幻想の中にしかない。そんな状況には、カンペキな計画より、変更耐力が高い計画の方が親和する。
なお、確定的な世界線においても、要件への理解に対して、ステークホルダの間で、ある種のブレ・ズレが生じるリスクは常にある。同じ定義書を見ても、企画部門、開発部門、品質保証部門などの関係者が揃って同じ完成形を思い描くとは限らない。顧客側と同じものを思い描くのはもっと難しいかもしれない。動くものを見て、触ってみて、初めて違和感や齟齬や本当にほしかったものに気がつくこともある。
アジャイルプロセスでも、ドキュメンテーションは重要だ。でも、ドキュメントに落としきれない要件は、どんなシステムにも存在しうる。
リポジトリやプロダクトバックログ・タスクボードの状態から、進捗を常に共有する。動くもので見せる。そして、要求とアウトカムのギャップを確認する。ギャップがあれば、必要に応じてバックログを更新していく。そうやって、ギャップを微調整しながら進む。
荒ぶる四天王QCDSに対抗するカンペキな計画という幻想から解放され、現実的なQCDとSを常に真剣に模索し続けるためのスクラムのプロダクトバックログのしくみや考え方が、私はすき💛
プロダクトバックログは、上の方のアイテムだけでもReadyReady(計測可能・一意に判定可能な受け入れ条件が完全に定義されていて、技術的・環境的にも(ヒト・モノ・カネ的にも)着手可能な状態になっているような状態)にするのは大変なことだ。そもそも、いくつもある重要なプロダクトバックログアイテムを最適な順序に並べるのも簡単ではない。けれど、これらのようなReadyReadyにする努力やコミュニケーションは、ギャップを埋める方向に私たちを導いてくれる。
まとめ
私がアジャイルを好きな理由、スクラム推しの理由について、スクラムで得られる自由や安心に着目して、3点挙げた。チームで仕事を進める幸せ、進んでいる実感を得られる幸せ、ゴールをタイムリーに更新して共有できる幸せが、アジャイル・スクラムにはあると思う。
アジャイルやスクラムの手法を「正しく」適用するには、スキルも要るし骨の折れることも少なくない。けれど、アジャイル・スクラムの適切な運用で、(私を含めて)多くの人が幸せな開発ライフを送れるようになることを、切に願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
