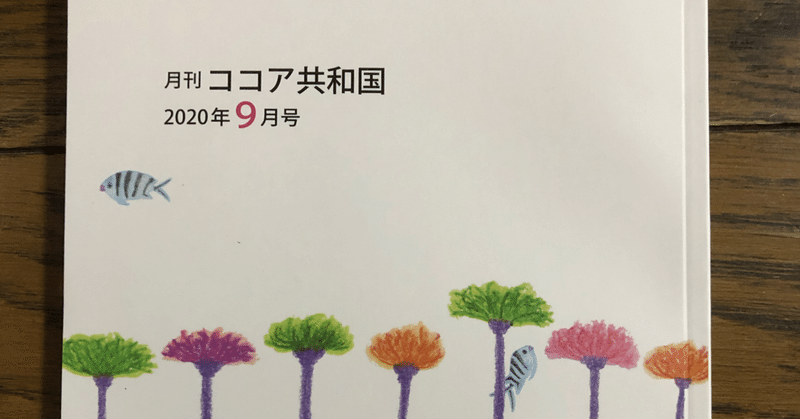
ココア共和国9月号やながわの感想②
詩のなかの「わたし」は現実社会の私とイコールか?
②では①で予告のとおり、佐々木貴子さんの「嘘八百屋⑥」について。
「一読者として、読みたがり屋の「わたし」が著者であり、書きたがり屋の「佐々木貴子」に何かしらを書いてもらい、それを読んで楽しむスタイル」
驚いた。佐々木さんと梁川のスタイルはまったく同じだ。このスタイルについて、詩友と論じたことがこれまであまりなかった。他の方は、わたしとは違うのではないか、そんな気がして今まで秘密にしていた。(謎)
わたしは「自分のかくもの」を好んで読む傾向がある。詩友のなかには手放した(発表した)詩を一度も読まない、という方もおり、わたしが「自分のかいたもの」を楽しんで読んでいることが知れたら「なんて恥ずかしいやつ!」とか、「自己愛者!」と罵られるのではないかと今まで言えずにいた。それは、「発話者」と「著者」がイコールだとする思考からくる「自己愛」であり、わたしの場合(エッセイを読むかぎりにおいて、佐々木さんも)イコールではないから全然不思議なことではないのではないかい?という気がしてきた。詩のなかのわたしは、わたしがかいているとはいえ、わたしではないからだ。
佐々木さんがエッセイの中でかかれている「随分、苦労されているのですね」等の詩への感想、梁川も幾度となく言われてきた。「会うと明るいのに、詩に闇がある」や、「そもそもこれはおはなしなのですか?おはなしだとすれば詩ではないですね」など。梁川の詩を細かく解説するつもりはないが、その時わたしは生意気にも「おはなしでも詩でもどちらでもいいです」と答えた気がする。詩を現実に体験したものを語る手段だとすると、このように言われるのは尤もだ。しかし、それが「詩」なのだとしたら梁川は「おもしろくない」のだ。体験したことだけを書くのであれば「詩」でなくてもいい。これは単に梁川の趣味の問題である。ありのままを書くほうが好きなのであれば、それでいいと思う。
要は「見たこともないものを、見たい」この、好奇心が梁川の詩への想いの全てで、自分で書けないのであれば、「梁川にかかせたかった」一行を誰かがかいたものを読みたい、単純にそれだけだ。たとえば、猛烈に梁川が心を奪われた数行がある。
「通路、が塞がれ、身長ほどにしか、心が/ない、日のなかで恐怖の種がわれる。蛍光灯/で焼けしなないか、ソファで溺れないか、/窓で迷わないか、/わたしは、だれなのか」川原「杉本真維子/裾花」より
文字を打ちながら、文字通り打ち震えた。改行も、読点も、含めて、このような世界を差し出してくれること、それが自分であるか自分でないか、どちらでもよいのだ。「わたしは、だれなのか」で、詩集を持つ手がふるえ、唸り、捻れ、平伏す。明らかに、読む前のわたしには想像できなかった世界が広がっている。溺れるはずのない場所で溺れることを畏れること、そのことがこれほど心を震わせるとは。
ところで「発話者=著者」に関連して、詩の虚偽や妄想について。佐々木さんのお父さまは、ご存命にも関わらず、詩の中では何度も亡くなりお墓の中だそうだ。思わず、ぷぷぷと笑ってしまった。わたしは自分を殺したり、病気で死なせたりしてきたが、父親が詩に出てこないことに、ふと気付いた。家人もだ。わたしの詩のなかで、男は「おとこ」でしか登場しない。このへんはなぜなのか自分でもよく分からない。いない姉も登場しない。梁川の詩は、佐々木さんの詩に比べて閉じているのかもしれない。それはとても「つまらない」まったくもって「おもしろくない」
梁川の詩は妄想が多いので、どこからが現実でどこからが夢で、どこからが空想なのか、その切間が自分でもよくわからない。詩をかきはじめて、思わぬものたちが勝手に指先を動かして、かいている。あれ、こんなところに着地したのね、そんな俯瞰したわたしがいるのだ。明らかに、それはあまりに他力本願、あなたはどこと繋がっているの?問うても、梁川は笑っているだけなのだ。ただ最近、思うところがあり、推敲の際に「わたし以外の読者」を気にかけるようになった。「わたし」だけを楽しませればよいのでは日記と同じではないか。そんな読み手の存在を意識することで詩はどう変わるのか。小さく閉じてしまわないかを危惧している。
脱線してしまった。虚偽について。すこし前に、第57回短歌研究新人賞受賞作「父親のような雨に打たれて」が実際には存命な父親の死を題材としたことに対して、「短歌における虚偽」が話題になった。「短歌では虚偽をかいてはいけない。かくのであればそれなりの強度が求められる」様々な批評の多くが、このようにかかれていた。短歌は57577という定型の韻文であるゆえに制約がある(らしい)この作品が選考委員や読者を騙したか否かで、議論が巻き起こっていた。
詩は、虚偽をかいてもいいか、駄目だとすれば虚偽を妄想とすればよいか、駄目だと言われたところで梁川はかくのだけれど。ああ、もうほんとやめよう、と一昨年思ったものの、また戻ってきてしまうほどに詩は魅力のあるものだから。
ココア共和国には、入国審査がない。誰もが入国できる。これは詩ではありません、おはなしです、お帰りください、などと言われることのない、伸び伸びとした可能性に満ちた「わたし」(←著者でない)が走り回っている。その言葉たちが、梁川の欲しい一行をつぶやいてくれますように、そんな思いでページをめくっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
