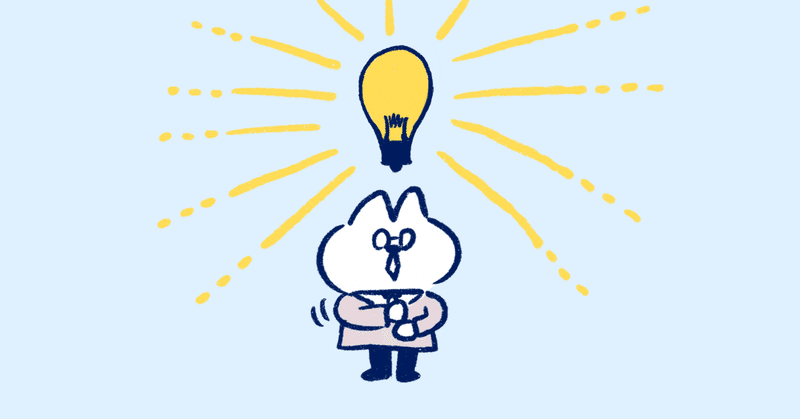
小学生の子どもに「家で英語を勉強させたい」という友人にどうアドバイスをするか
小学生の子どもをもつ友人から、「子どもに英語のテキスト何かやらせたいんだけど、おすすめある?」と聞かれました。英語に関する教材は、子供向けから大人向けまで本当に様々で、本屋にいっても、インターネットで検索しても、なかなか選びきれないですよね。私も経験があります。この記事では、中学校の英語教員の経験から、彼女にアドバイスした小学生向けの英語教材やその選び方のポイントについて書きます。
① どんな英語力を目標にするか
その子が中学校の授業や高校受験で困らないようにしてあげたいのか、海外留学等を視野に入れて、世界を相手に戦っていけるような英語力をつけさせてあげたいのか、そのゴール地点によって、子どもの英語教育にかけるお金や時間は当然変わってきます。
前者であれば、正直申し上げて、今の親の世代がしてきたような英語の勉強をイメージしてあげれば、何を与えたらよいかが想像できると思います。たしかに、東京都で高校受験にスピーキングが導入されたり、高校入試の長文の量が以前よりはるかに多くなったりと、変化はみられているように思います。ただ、中学校の現場は、依然として基礎的な単語や英文法を身につけさせ、正しく英文を読んだり、書いたりすることに重きをおいていると思います。定期テスト、高校入試で重きをおかれているのが、読み書きだからです。ゴールがそこなので、それに向かって授業を進めるのが当然のことです。
小学校での英語教育がはじまり、入学してくる生徒たちは、英語を聞いたり発音することに慣れています。自分の口から英語を話すことに、あまり抵抗がなく、自己紹介程度の簡単な英語はしっかり小学校で経験してから入学してくるのです。これは、小学校の現場の先生方の、努力の賜物と思います。教科書にあるデジタル教材を使い、イラストや音、動画をたくさん使いながら英語の音に触れさせてくださったことには、感謝しかありません。
(以前、中1生に東京書籍の検定教科書『NEW HORIZON』のデジタル教材に入っている、ネイティブスピーカーが子音や母音を発音する動画を見せて、「これ小学校でも見た~!」と言われたときには驚きました。小学校の先生!すばらしい!)
ただ、小学校で英語の音に慣れてきた中1は、中学校で文字の壁にぶつかります。今まで発音してきたはずの英語を文字で書きあらわすことは、とても難しいだと気付くのです。その壁に対するケアや対策が、今の中学校での授業に足りない部分の1つかもしれない、と考えています。昔と違って、小学校で触れてきたからこそ感じる、大きな挫折。今までとったこともないような悪い点数を単語テストでとってしまい、涙する子もいるのです。
ですので、小学校のうちに何か教材をという友人には、簡単な英語の書き取り教材をすすめました。やみくもに中学校の先取りをさせるのはつまらないですが、親がサポートしてあげるのは悪いことではありません。現状、学校現場ではそこまで手が回らないと思うからです。ちなみに、仕事で外国籍児童の補助についたこともありますが、そのカナダ出身の児童も英語のスペリングが間違っていることがありました。どんな言語でも、読み書きについては、やはり何らかの練習、訓練が必要ということです。
・『6年生英語の文』くもん出版
こちらの5,6年生向けのものは、内容がほぼ中1で授業で使うようなワークの最初の方と同じレベルです。
・『ドリルの王様 英単語』新興出版社啓林館
こちらは内容を一部ダウンロードでき、無料で使うことができます。英語にカタカナがふってあるところが難点です。しかし、本当に苦手意識がある子もいますので、助けになることもあります。
・"My Book Of Rhyming Words" Kumon Publishing
ちなみに、海外で使われている公文のワークも、音の指導でとても参考になります。ライミングやアリタレーションなど、日本の英語指導では触れない音の指導を強化すると、これからの子どもたちの英語の学び方、会話する力に変化が出るのではないかと思います。
② 英語の音についての知識はマスト
子ども向けの英語教室もたくさんあると思いますが、フォニックスのような英語の音と文字の関係について指導してくれるところだと、中学校に入ってからも英語に苦労することが少なくなるように思います。前述したとおり、中学校に入って、英単語をテストで書くということは、日本語環境で育ってきた子どもたちにとって大きな壁となります。中学生に「先生、英語って何なん?ローマ字と違うん?」と聞かれたこともあります。英語の発音とスペリングの関係は、日本語とは大きく異なります。読まない文字や、同じ文字でも単語によって読み方が変わるなんてことは、今まで英語に触れてこなかった子にとっては、意味不明なわけです。
もちろん、中学校でも入学当初にフォニックス教材を使用することも増えてきたように思います。たとえば、光村図書の検定教科書『Here We Go』では、教科書の最初に英語の音に関するページが多く盛り込まれています。
ただ、なかなかそこにじっくり取り組めないのが現状です。教科書のボリュームは増え、内容をこなしていくことに精一杯になります。さらに、新年度明けの学校では、学級開きや身体測定、春に体育祭をやるのであれば行事の準備など、本当にバタバタしています。気がついたら定期テストと言うことも多いので、ゆっくりフォニックスをやる時間もなく、教科書を進めて試験範囲を確保しなくてはなりません。そのような実状を考えると、小学生のうちにゆっくりフォニックスに取り組むことはおすすめできます。
・『小学生のフォニックス1』mpi松香フォニックス
フォニックス教材は最近たくさんのものが出ていますから、親御さんやお子さんが気に入ったものを使うとよいと思います。youtube やダウンロードできる無料教材も多々ありますが、コースブックのようになっていると、自宅で取り組みやすく、次に進んだ!という達成感をお子さんが感じられると思います。こちらの会社さんの教材では、『Active Phonics テキスト』というものを中学1年生に使ったことがありました。
そして紹介しておきたいのが、フォニックスの前段階となる音素認識についてふれている書籍です。英語は日本語に比べると音が本当に多いので、私たち日本語話者には聞こえない、聞き慣れないような音がたくさんあります。フォニックスはもちろん、英語の音と文字の関係について学ぶよい教材です。ただ、それも万能ではなく、フォニックスのルールにはあてはまらない例外も多い、ということも覚えておかなくてはなりません。
私の考えでは、マザーグースや英語の手遊び、絵本のような、音で遊ぶような経験をできるだけたくさんさせてあげたほうが、結果として受験や資格取得として英語を学ばなくてはならなくなったときにも、音を頼りに脳にインプットされやすくなるのでは、と考えています。もちろん、なかなか一般的な小学校や中学校では難しいことですので、興味がある方は読んでみてください。英語の早期教育には様々な考えがありますが、このようなやり方であればもっと広まってもいいと思っています。
・リーパーすみ子『アメリカの小学校ではこうやって英語を教えている―英語が話せない子どものための英語習得プログラムライミング編』
・アレン玉井光江『小学校英語の教育法』大修館書店
③ 世界で戦っていく英語を身につけさせたいなら時間と熱意は必要
①で書いた目標のうち、世界で戦っていけるような英語力を身につけさせたいなら、それなりの時間と熱意、ときには投資も必要と思います。ただ、小学生の子どもには、もしかしたら英語以外にやりたいこともあるかもしれません。英語に時間もお金も投資するということは、それなりの犠牲も伴うように思います。前述したような英語の音、基本的な読み書きに継続的に取り組めば、基礎となる英語の力はつくように思います。日本は、母語で高等教育まで受けることができ、社会人になってお金も稼げるような恵まれた国です。子どものうちに詰め込んで疲弊させるのではなく、ずっと英語を学び続けられるような海外に対する好奇心、日本をでて世界中の学生たちと学んでみたいという挑戦する心を育ててあげることを望みます。
それを踏まえたうえで、斉藤淳先生が立ち上げられたjprepという英語塾は大変興味深いものです。斉藤先生は英語教育について本も書いていたり、南相馬市の外国語教育のアドバイザーにもなったりと、自身の経験を日本の英語教育のために生かそうと活動しておられます。その姿勢や考え方に学ぶものがありますので、興味がある方は一度読んでみてはいかがでしょうか。本のタイトルはキャッチ―ですし、塾の料金等をみると相当なものですが、それだけの豊かな英語教育を、日本中の子どもたちが受けられるようになったら、と願ってやみません。少しでも実現していけたらと思います。
・斉藤淳『10歳から身につく 問い、考え、表現する力 ぼくがイェール大で学び、教えたいこと』NHK出版新書
・斉藤淳『ほんとうに頭がよくなる 世界最高の子ども英語』ダイヤモンド社
今日は、以下の3つのポイントにそって、英語教員を経験した私が、英語を勉強させたいという友人にしたアドバイスについて書きました。
① どんな英語力を目標にするか
② 英語の音についての知識はマスト
③ 世界で戦っていく英語を身につけさせたいなら時間と熱意は必要
日本語に加えて英語も話せる、2つの言葉を高いレベルで操るということは、決して簡単なことではないと思います。日常会話ならともかく、ビジネスの現場や海外大学で学ぶといったような高度な英語が必要とさせる場合には、それなりの時間と努力が必要です。
ただ、大人でも尻込みをするような長文に果敢に向き合う中学生を見ていると、学びに向かう姿勢というのは本当にすばらしいなと感じます。英語の発音について指導しても、楽しんで、面白がってチャレンジできるのが子どものよいところです。これからもずっと学び続けられるように指導することが、中学校の先生の役目だとも思います。
小学生の保護者の方で、子どもさんの英語教育に関心がある方は多いと思います。小学校や中学校はもちろん万能ではありませんが、デジタル教材等、昔はなかったよい教材を使える環境も整ってきています。英語に関しては、お子さんに身につけさせたい力で、学校では足りないと思うところがあるでしょうから、そこをプラスしていくというスタンスでいくと、うまくいくのではないかなと思いました。
何かの参考になれば嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
